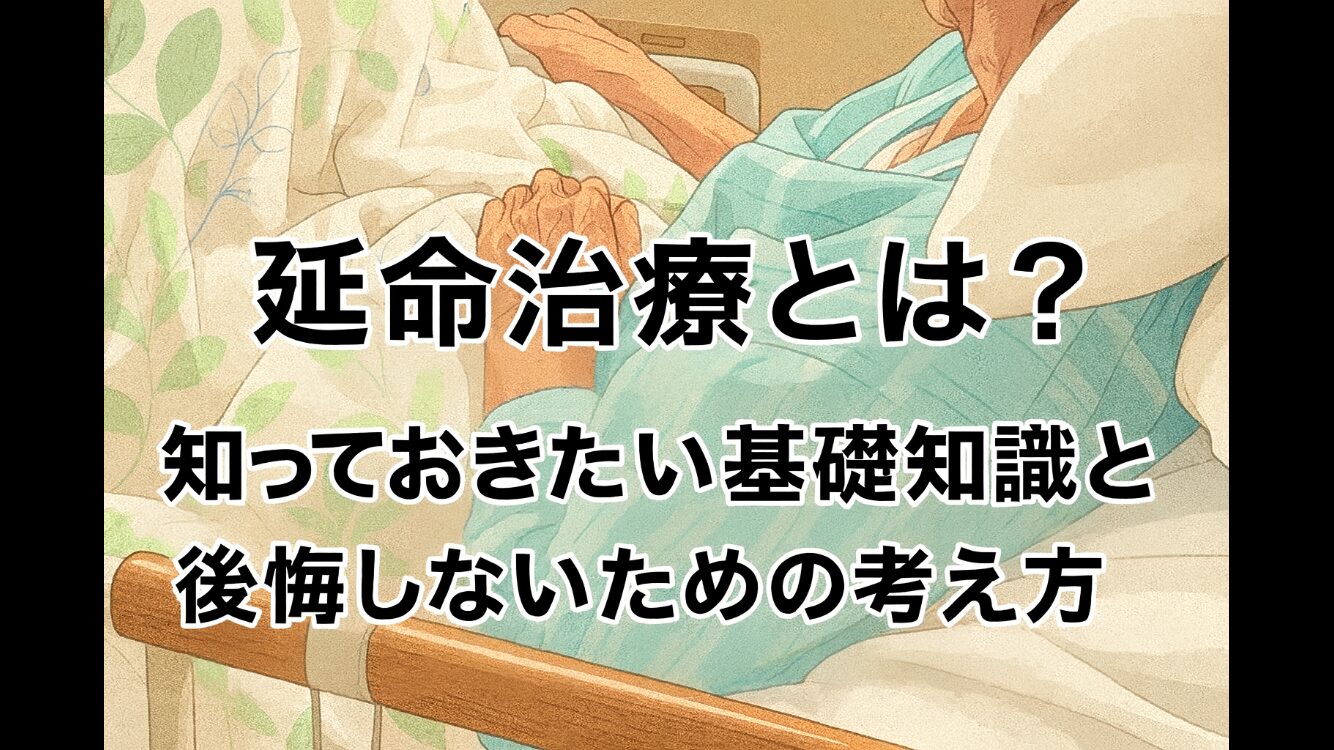
延命治療とは? 知っておきたい基礎知識と後悔しないための考え方
はじめに 高齢化が進む日本では、病気の治療だけでなく最期をどう迎えるかが大切なテーマになっています。 特に延命治療は、突然選択を迫られることが多く、家族が迷ったまま判断してしまうケースも少なくありません。 「延命治療って […]
続きを読む 延命治療とは? 知っておきたい基礎知識と後悔しないための考え方本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
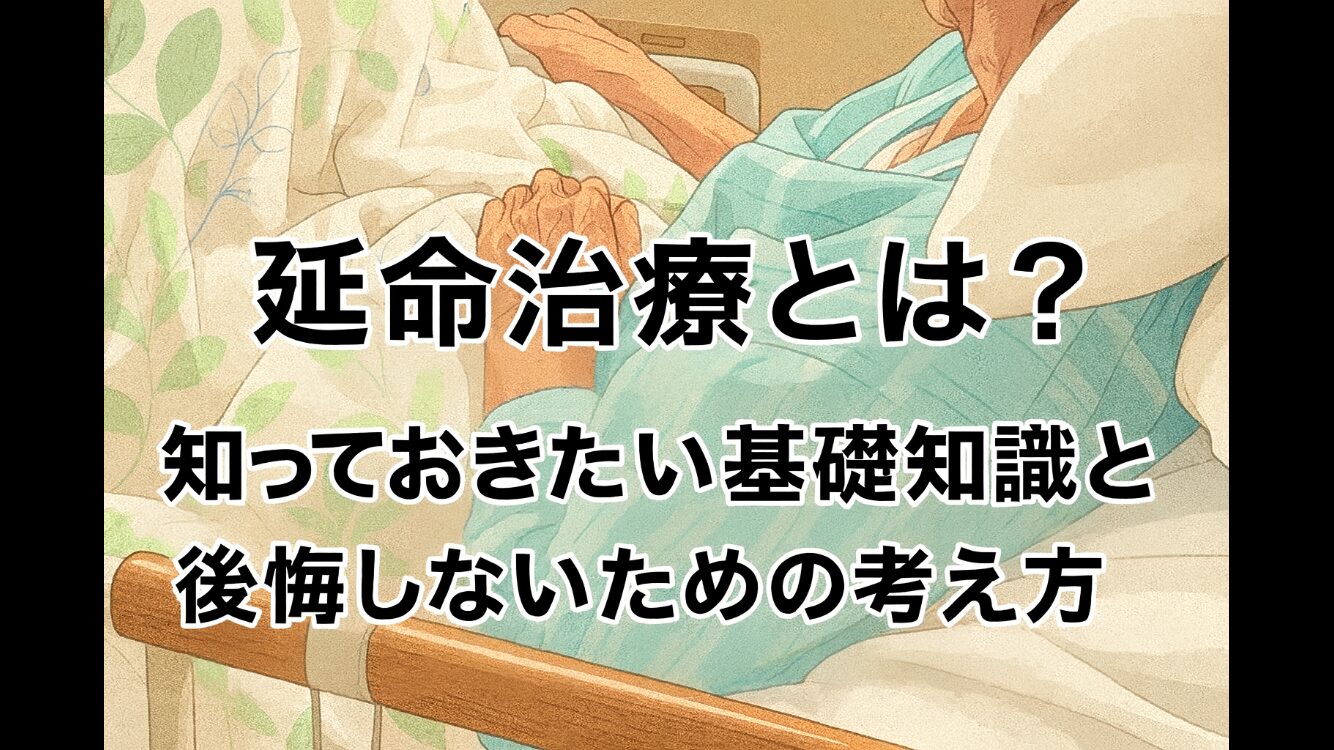
はじめに 高齢化が進む日本では、病気の治療だけでなく最期をどう迎えるかが大切なテーマになっています。 特に延命治療は、突然選択を迫られることが多く、家族が迷ったまま判断してしまうケースも少なくありません。 「延命治療って […]
続きを読む 延命治療とは? 知っておきたい基礎知識と後悔しないための考え方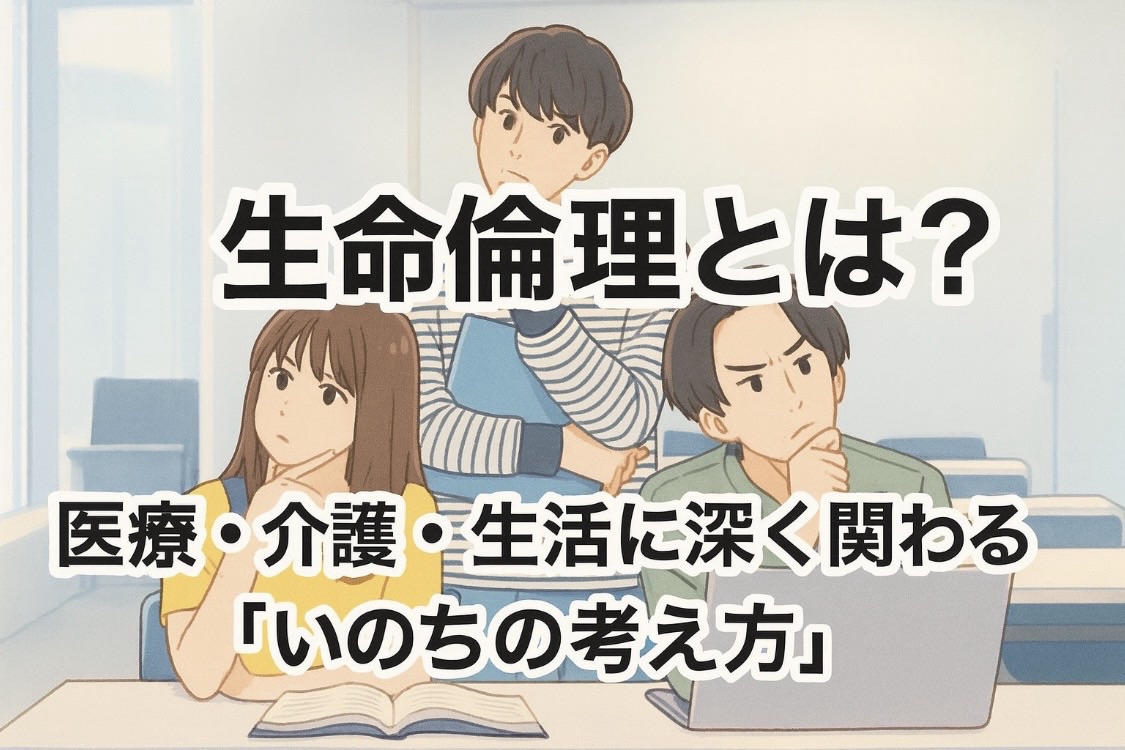
はじめに 医療技術が大きく進歩し、寿命が延び、社会が多様化した現代では、 「いのち」や「健康」をどう扱うべきか という問いに向き合う場面が増えています。 たとえば、 ・延命治療を続けるべきか ・親の介護でどのように意思を […]
続きを読む 生命倫理とは?医療・介護・生活に深く関わる「いのちの考え方」
はじめに 福祉や医療の現場では「PT・OT・ST」という言葉を耳にすることがあります。これらは専門職の略称であり、リハビリテーションや生活支援には欠かせない存在で、ともに国家資格を持つ専門職が担っています。 今回の記事は […]
続きを読む リハビリの専門職PT・OT・STとは? それぞれの国家資格の役割を分かりやすく解説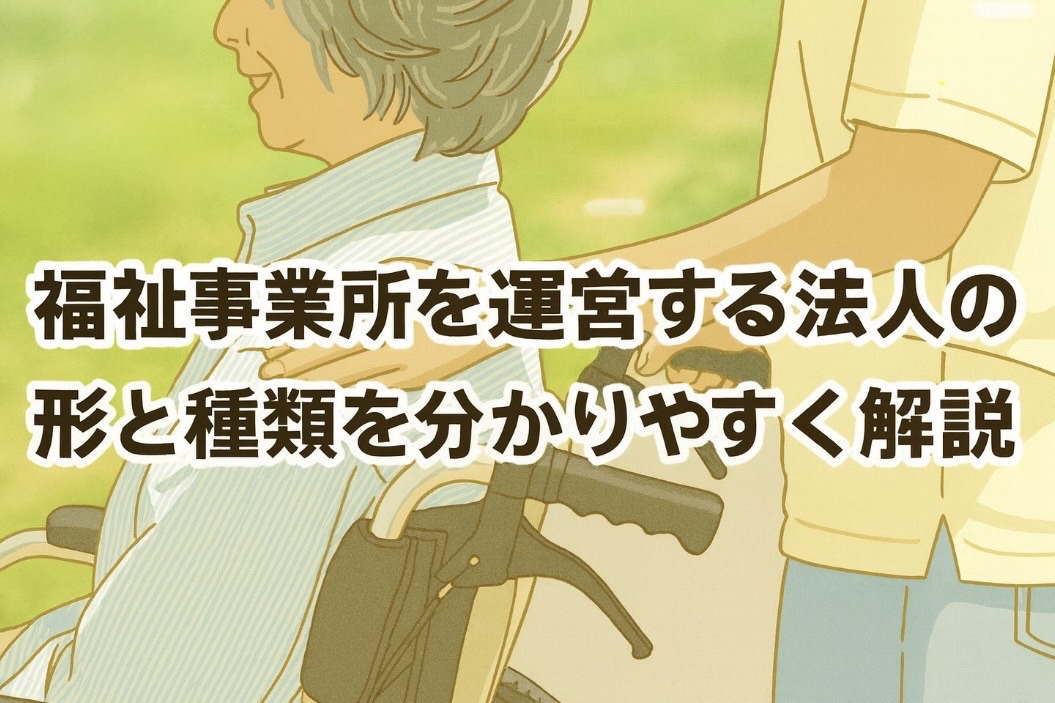
はじめに 福祉サービスを利用するとき、「どんな法人が運営しているか」まで気にする方は、決して多くありません。 しかし実際には、法人の形はサービスの安定性や地域との繋がり、利用料などに静かに影響しており、利用者の暮らしの背 […]
続きを読む 福祉事業を運営する法人の形と種類をサービスを分かりやすく解説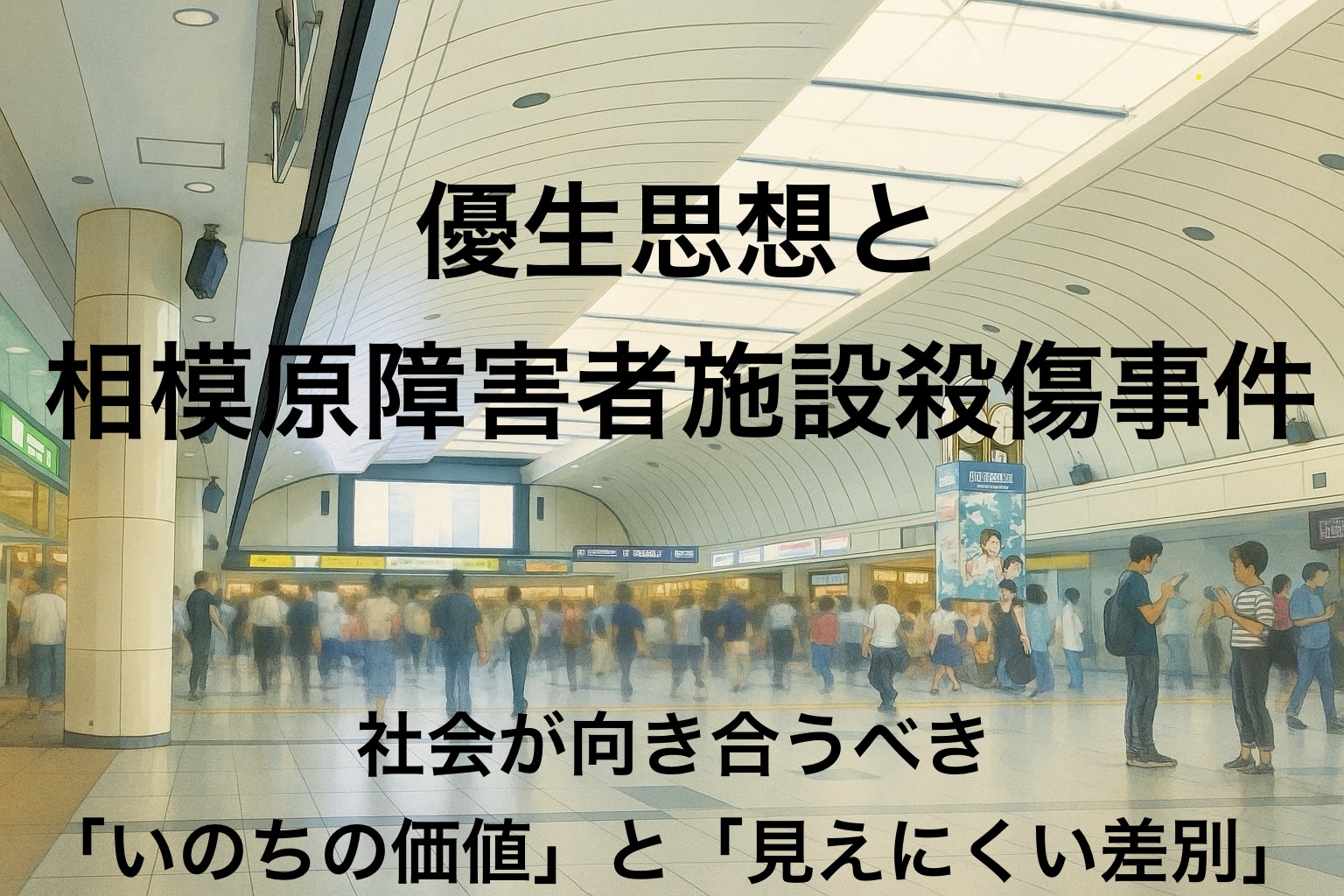
はじめに 2016年7月、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起こった殺傷事件(相模原障害者施設殺傷事件)は、19名の尊い命が奪われ、26名以上が負傷した日本の戦後最悪の大量殺人事件として深く刻まれています […]
続きを読む 優生思想と相模原障害者施設殺傷事件 〜社会が向き合うべき「いのちの価値」と「見えにくい差別」〜
はじめに 心はいつも頑張っている 人付き合いや仕事、家族との関わり、健康の不安、将来の心配…。 私たちは生活の中で、言葉にならないストレスや不安と向き合う場面がたくさんあります。 そんなとき、心は黙って負担を受けるわけで […]
続きを読む 防衛機制とその種類を分かりやすく解説 〜心理学の知識を身につけて人間関係やストレスに対処する〜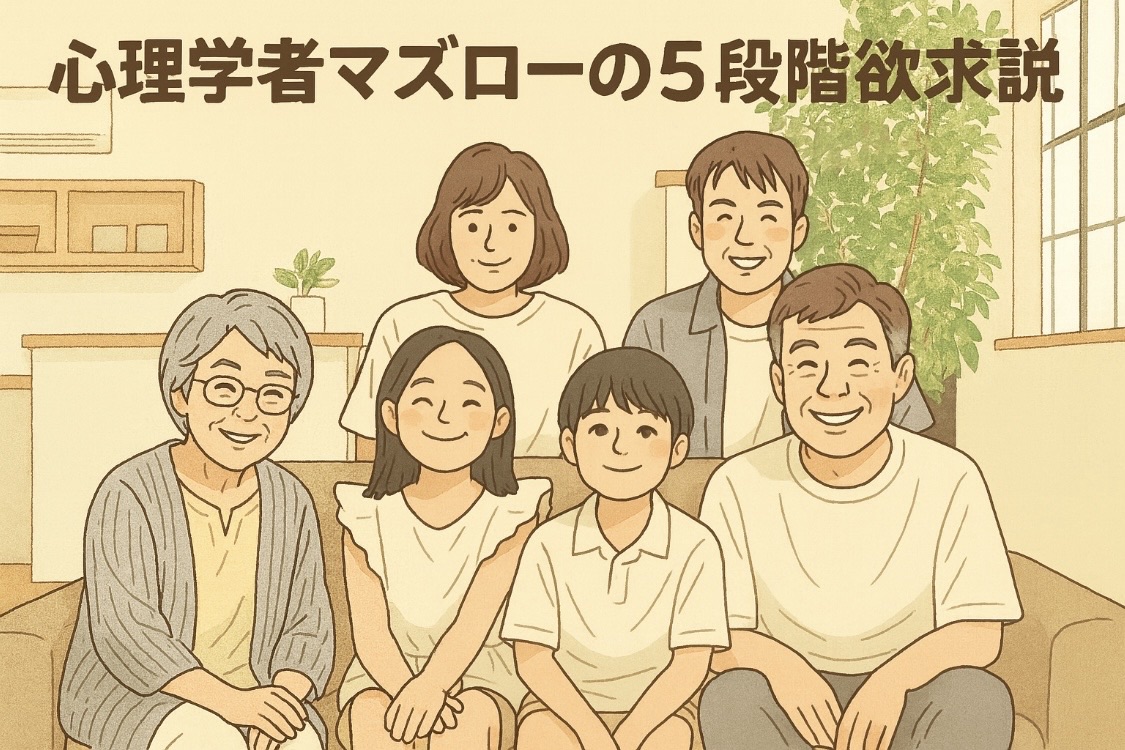
はじめに 人は誰しも、生きる中でさまざまな満たされたい感覚を抱きます。安心したい、つながりたい、認められたい、自分らしく生きたいといったように、日々「何かを求める」存在です。 介護や福祉、育児、子育て、教育のみならず、私 […]
続きを読む 心理学者マズローの5段階欲求説 〜介護・福祉・育児・子育て・教育者必見〜
はじめに てんかんという言葉を聞いたことはありますでしょうか? てんかん以外に、発作、てんかん発作、などと呼ばれたりすることもあります。 これは脳の神経が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作が繰り返される病気で、世界 […]
続きを読む てんかん発作ってなに?基礎知識と語源に隠された歴史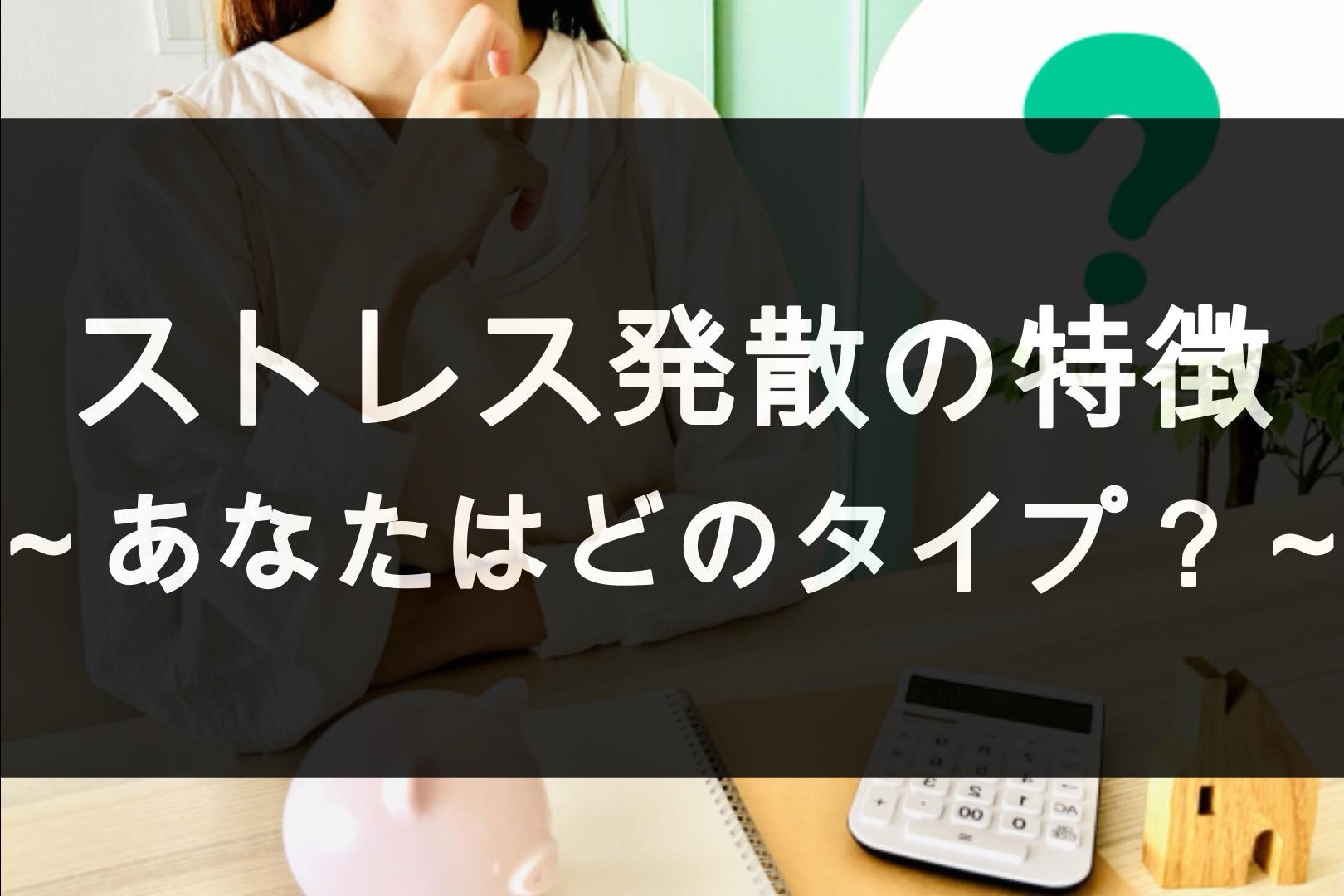
はじめに 人は、強いストレスを受けた時、そのストレスというエネルギーをどんな形であれ外側に向けて発散したり、内側で処理したりといったようにしていく体の機能が備わっています。 そして、その反応の方向性には、攻撃性を伴うもの […]
続きを読む ストレス発散の特徴 〜あなたはどのタイプ?〜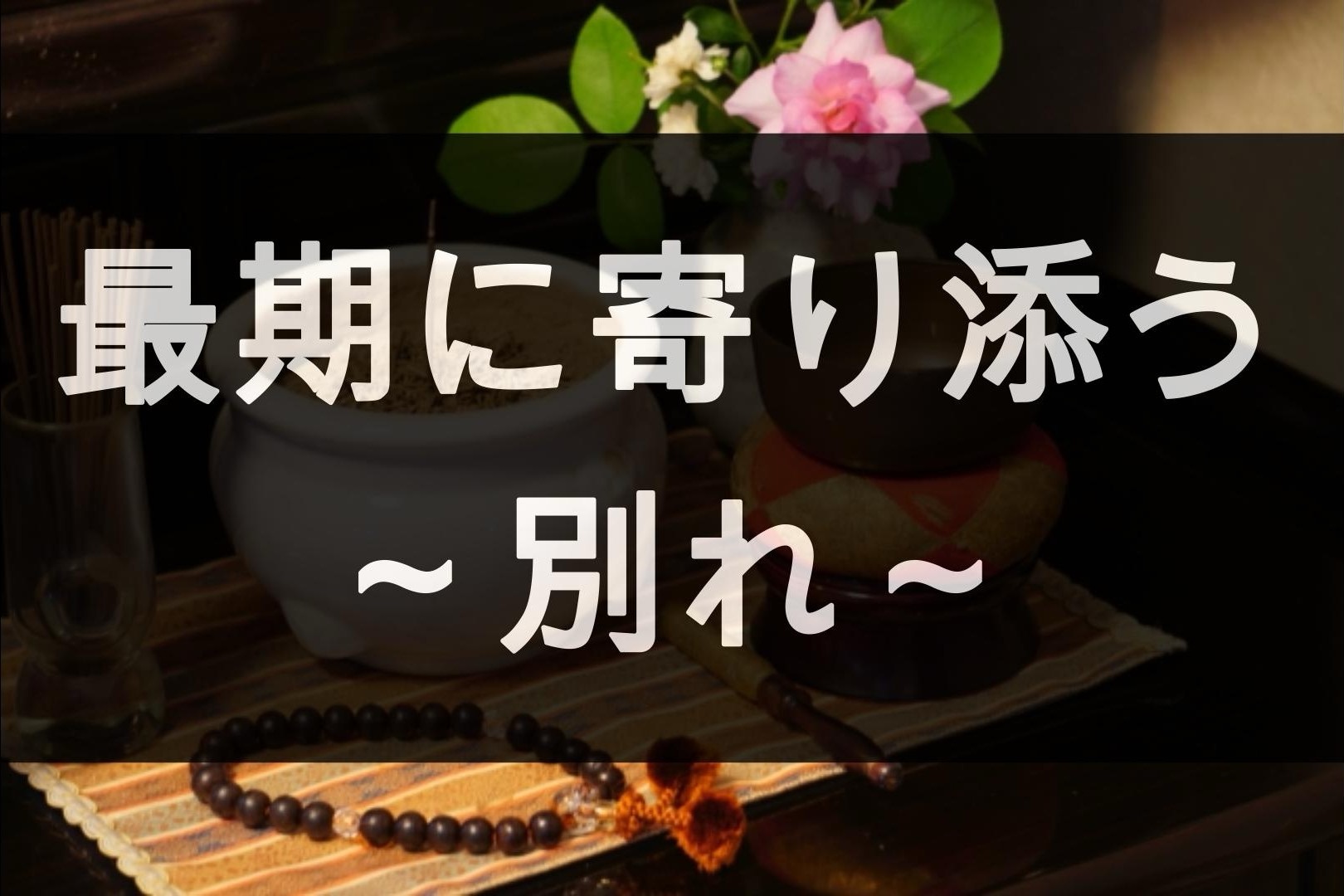
はじめに 福祉の仕事をしていると、日々の暮らしの中でたくさんの出会いがあります。利用者さんとの何気ない会話や、ご家族とのやり取り、地域の方々との関わり。その一つひとつが積み重なっていくうちに、気がつけば仕事を超えて大切な […]
続きを読む 最期に寄り添う 〜別れ〜