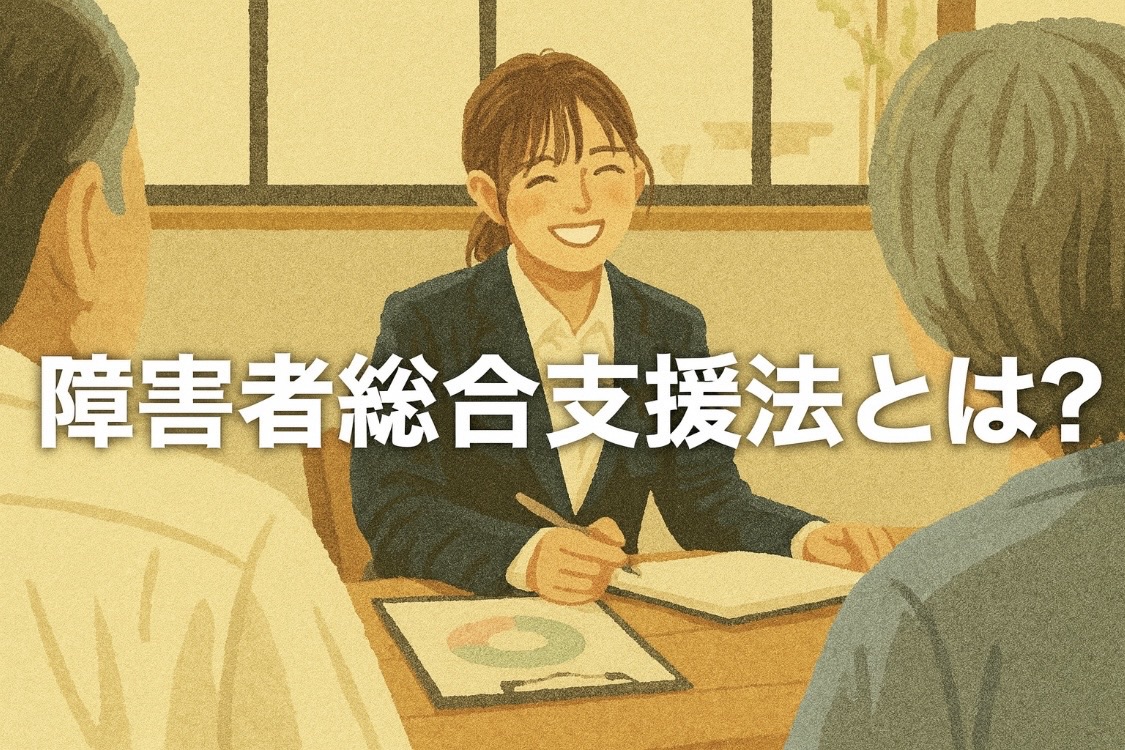
障害者総合支援法とは?〜利用者・家族が知っておきたい制度の仕組み・目的・サービス内容の基礎知識を解説〜
障害者総合支援法について、目的・利用できる支援サービス・手続きの流れ・課題までをわかりやすく解説。利用者・家族・支援者が正しく学べる基礎知識まとめ。 はじめに 障害のある人が地域でその人らしく生活していくためには、日常生 […]
続きを読む 障害者総合支援法とは?〜利用者・家族が知っておきたい制度の仕組み・目的・サービス内容の基礎知識を解説〜本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
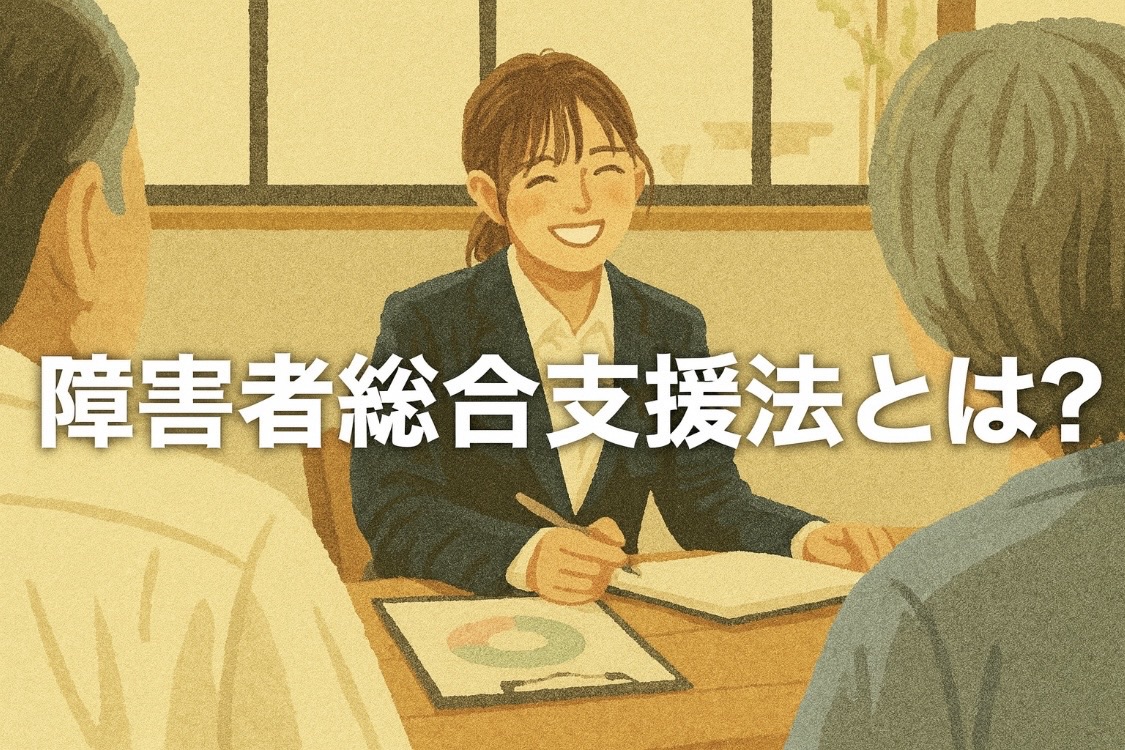
障害者総合支援法について、目的・利用できる支援サービス・手続きの流れ・課題までをわかりやすく解説。利用者・家族・支援者が正しく学べる基礎知識まとめ。 はじめに 障害のある人が地域でその人らしく生活していくためには、日常生 […]
続きを読む 障害者総合支援法とは?〜利用者・家族が知っておきたい制度の仕組み・目的・サービス内容の基礎知識を解説〜
障害者自立支援法とは何かをわかりやすく解説。措置制度から契約制度へ転換した背景、支援サービスの仕組み、制度の意義と課題まで丁寧に整理しています。 はじめに 日本の障害福祉制度は、この20年で大きな転換期を迎えました。その […]
続きを読む 障害者自立支援法とは?〜措置から契約へ変わった背景と、日本の障害福祉がどう進歩したのかをわかりやすく解説〜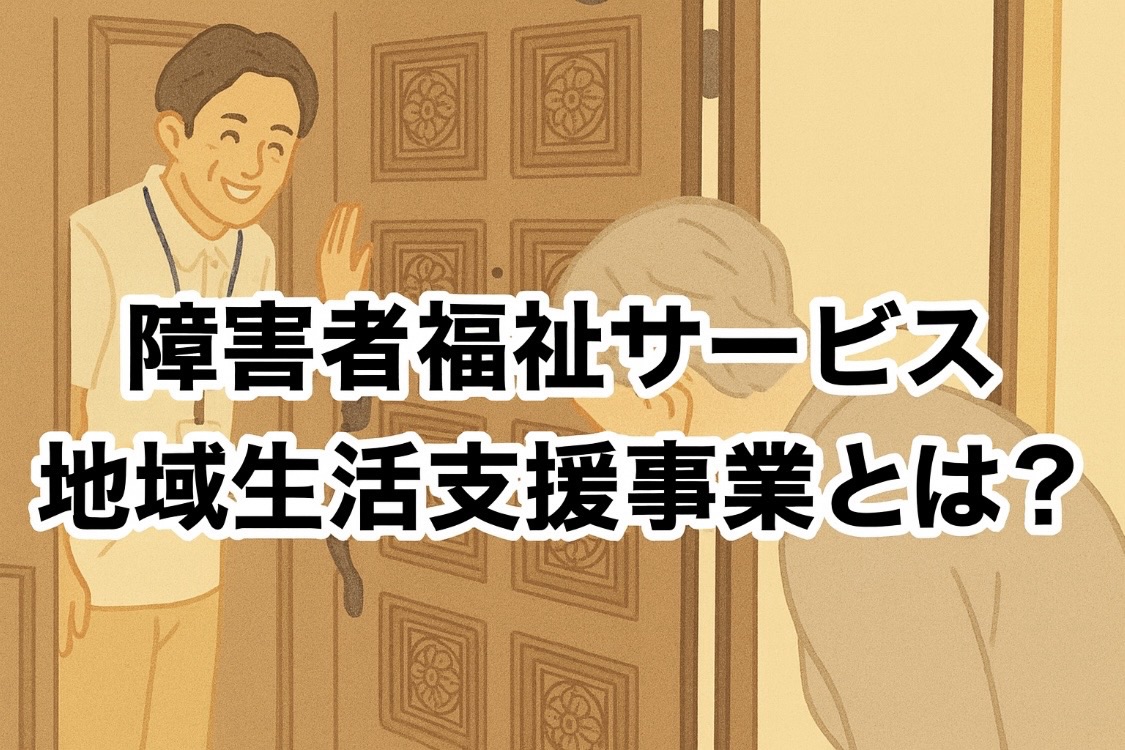
この記事では、障害者福祉サービスについて、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門 […]
続きを読む 地域生活支援事業とは? 自治体が行う身近な福祉支援をわかりやすく解説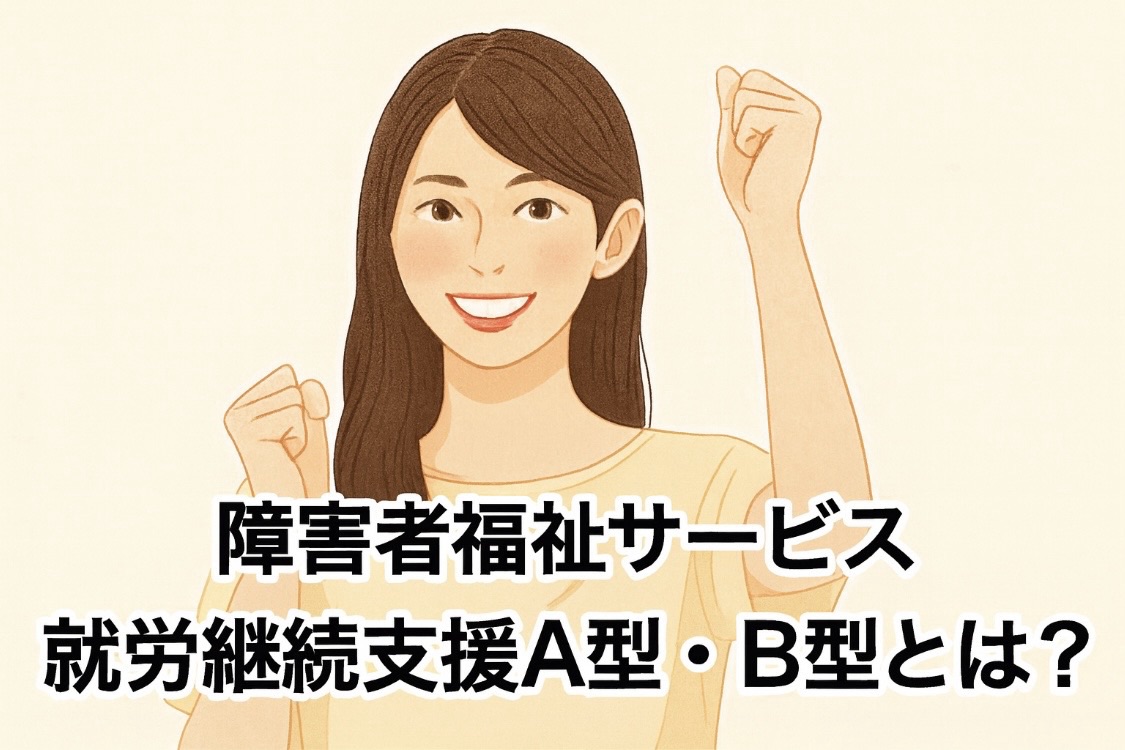
就労継続支援A型・B型の違いや特徴を、雇用契約の有無・収入の仕組み・働き方のポイントをわかりやすく解説。初めての方でも制度の選び方が理解できます。 はじめに 障害のある人が「働きたい」という気持ちを実現するための仕組みと […]
続きを読む 就労継続支援A型とB型とは? 雇用契約の違いから見る「働く支援」の役割を徹底解説
就労移行支援とは何かを初心者にもわかりやすく解説。対象者・支援内容・メリット・利用の流れまで、一般企業で働く力を身につけたい人のための福祉サービスを詳しく紹介します。 はじめに 就労移行支援(しゅうろういこうしえん)は、 […]
続きを読む 就労移行支援とは? 一般企業で働きたい人の就職準備をサポートする支援をわかりやすく解説
権利擁護とは何かを初めて学ぶ方へ。福祉の現場で大切にされる考え方や、本人の権利を守る仕組みをやさしい言葉で解説した記事です。 はじめに 福祉の現場では、「支援」だけでなく、本人の権利を守ることが欠かせません。 しかし、 […]
続きを読む 福祉における権利擁護とは?わかりやすく解説 仕組み・制度・現場の課題まで徹底解説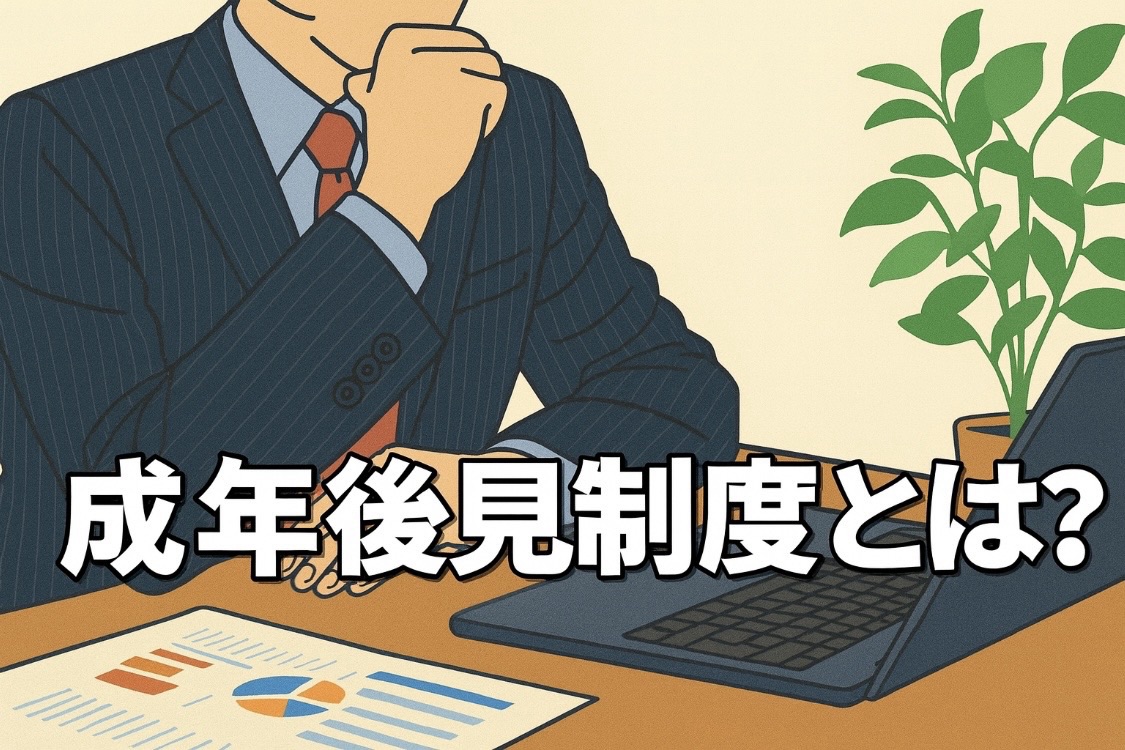
認知症・障害などで判断が不安な人の財産管理や契約を支える成年後見制度の基本、仕組み、手続き、費用まで丁寧に紹介。安心して暮らすためのポイントも解説。 はじめに 障害や高齢による認知症の進行などにより、 ・大切な契約を本人 […]
続きを読む 成年後見制度とは?仕組み・種類・費用をやさしく解説 認知症や障害のある方の財産管理に備える完全ガイド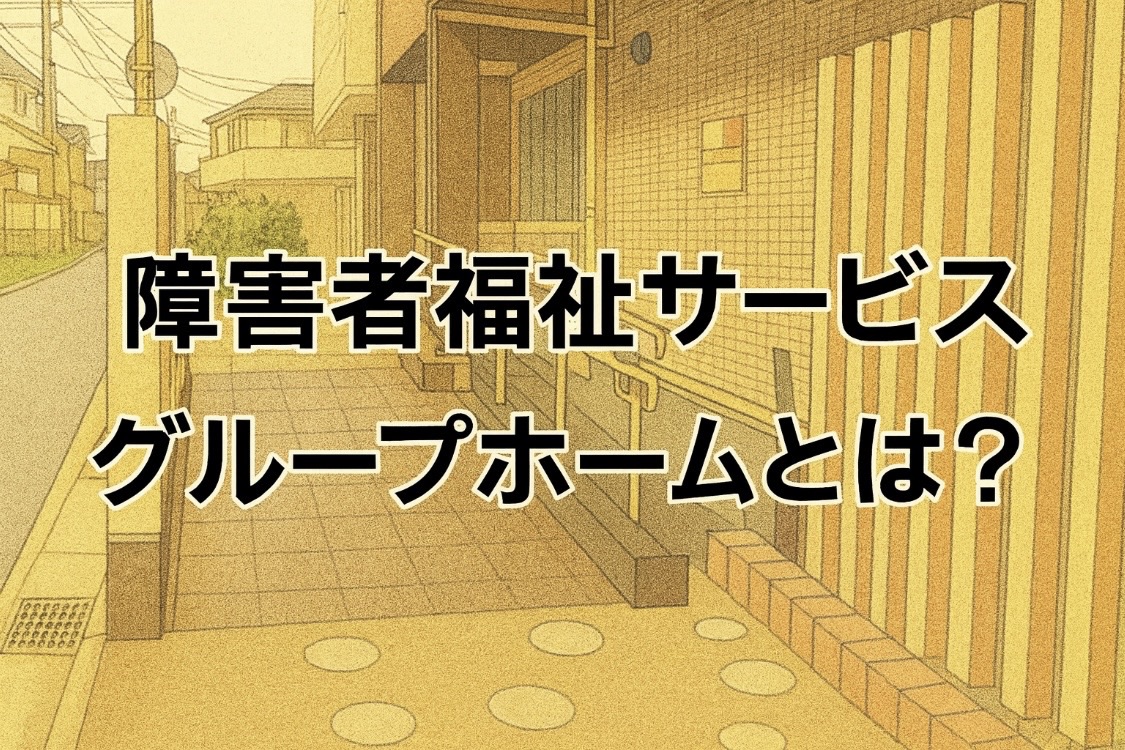
はじめに 障害のある人が、地域の中で安心して暮らし続けるために欠かせないのが「住まいの支援」です。 その中心的な役割を担っているのが グループホーム(共同生活援助) であり、地域生活を支える仕組みとして全国的に整備が進ん […]
続きを読む 障害者福祉サービスのグループホーム(共同生活援助)とは?〜地域で自分らしく暮らすための住まいと支援をわかりやすく解説〜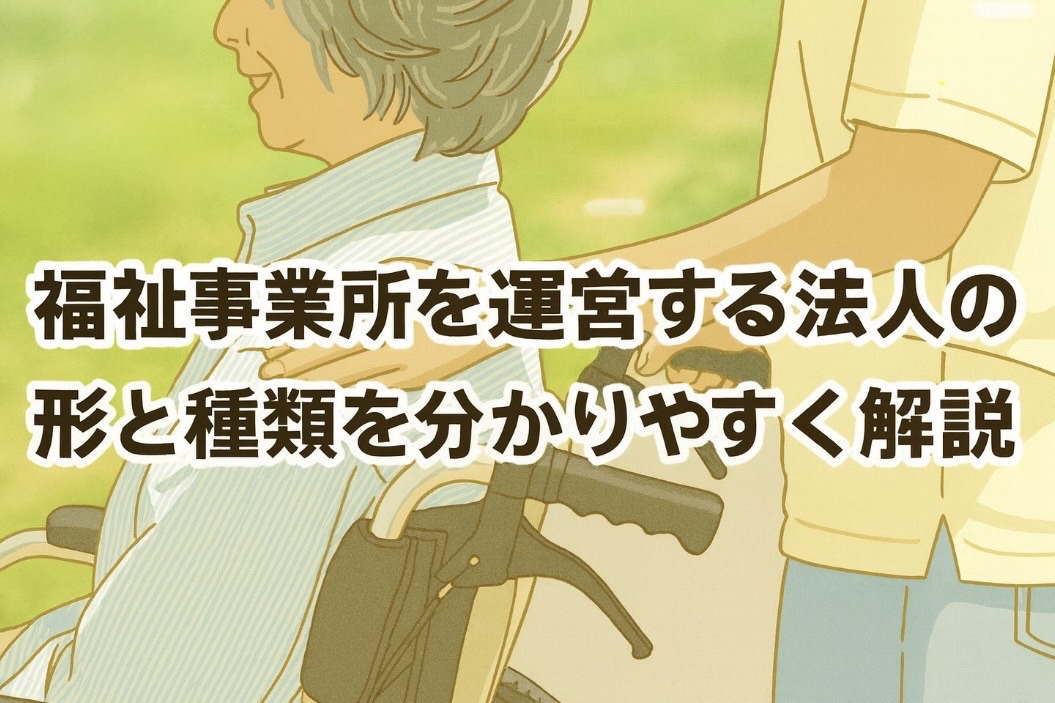
福祉事業を運営する法人形態の違いをわかりやすく解説。社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人・株式会社それぞれの特徴や選び方を、実務視点で整理します。 はじめに 福祉サービスを利用するとき、「どんな法人が運営しているか」ま […]
続きを読む 福祉事業の法人形態とは?|社会福祉法人・NPO・一般社団・株式会社の違いをわかりやすく解説