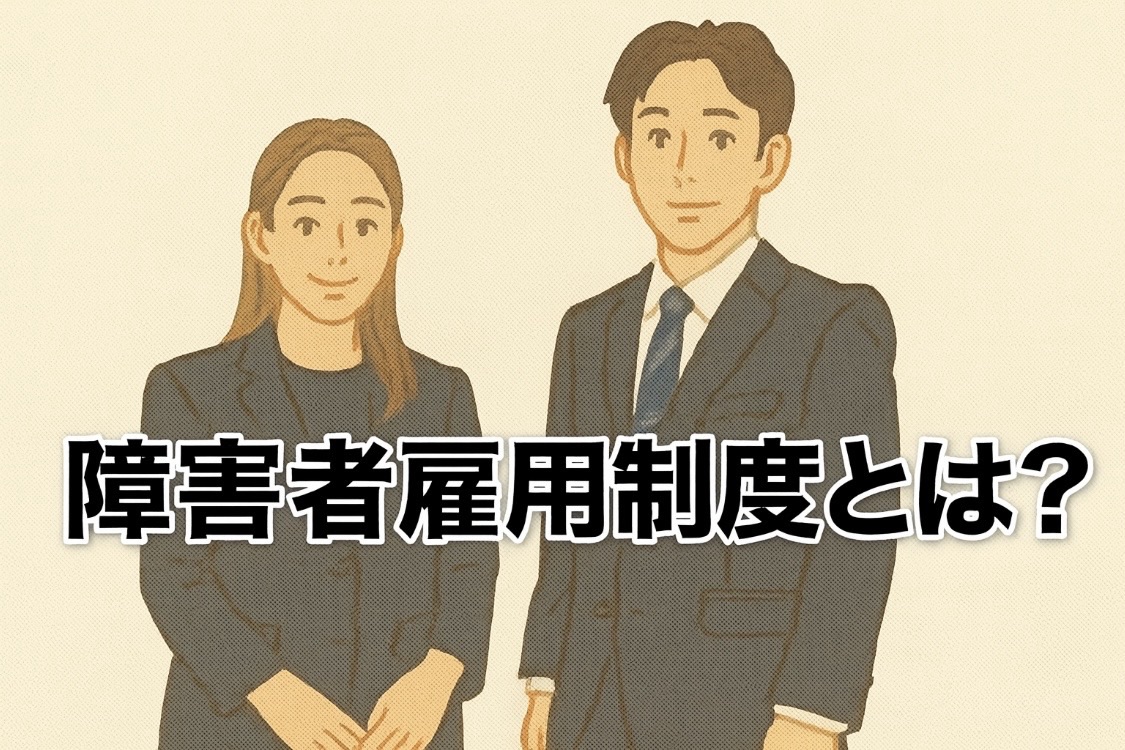
障害者雇用制度とは? 仕組み・目的・企業の取り組みをわかりやすく解説
障害者雇用制度とは何かを、仕組み・目的・企業の義務やメリットまでわかりやすく解説。これから制度を知りたい方や、雇用を検討する企業担当者にも役立つ入門ガイドです。 はじめに 障害者雇用制度は、障害のある人が社会の一員として […]
続きを読む 障害者雇用制度とは? 仕組み・目的・企業の取り組みをわかりやすく解説本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
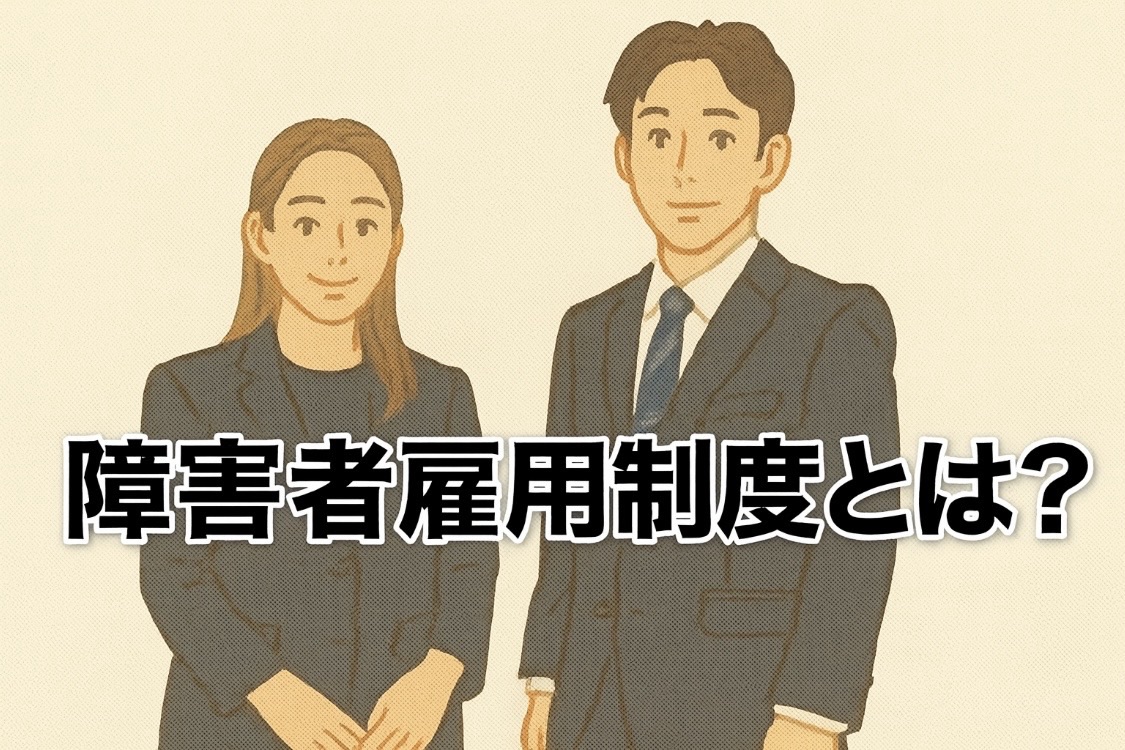
障害者雇用制度とは何かを、仕組み・目的・企業の義務やメリットまでわかりやすく解説。これから制度を知りたい方や、雇用を検討する企業担当者にも役立つ入門ガイドです。 はじめに 障害者雇用制度は、障害のある人が社会の一員として […]
続きを読む 障害者雇用制度とは? 仕組み・目的・企業の取り組みをわかりやすく解説
この記事では、サービス等利用計画について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門 […]
続きを読む サービス等利用計画とは? 役割・作り方・相談支援専門員との連携までわかりやすく解説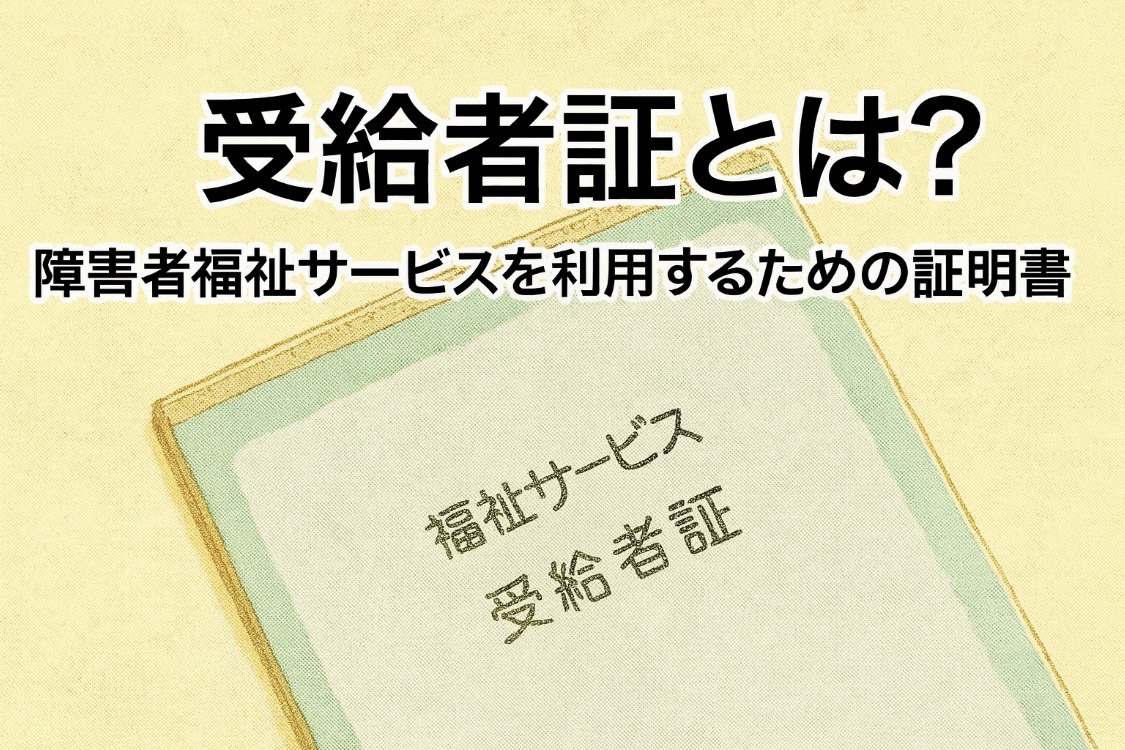
この記事では、受給者証について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相談 […]
続きを読む 受給者証とは?〜障害福祉サービスを利用するための大切な証明書をわかりやすく解説〜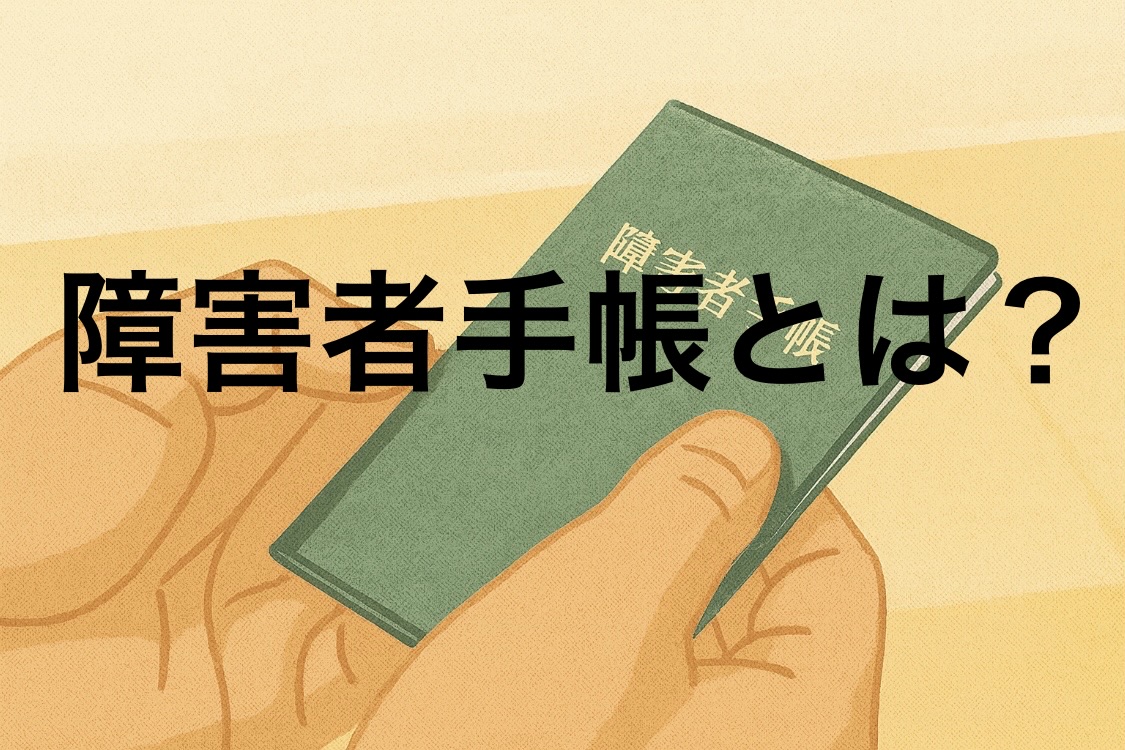
この記事では、障害者手帳について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相 […]
続きを読む 障害者手帳とは?種類・取得方法・メリットをわかりやすく解説
重度訪問介護とは何かをわかりやすく解説。対象となる人、支援内容、利用条件、他サービスとの違い、利用の流れまで福祉現場の視点で丁寧にまとめています。 はじめに 重度訪問介護は、重い障害のある人が「自分らしく生きる場所」とし […]
続きを読む 重度訪問介護とは? 24時間に寄り添い、地域で生きる力を支える総合的な在宅支援
居宅介護(ホームヘルプ)の基本を丁寧解説。支援内容(身体介護・家事援助・通院介助)、利用条件、流れ、他サービスとの違い、費用・活用のコツまで初心者にも理解しやすい解説です。 はじめに 障害があっても、自宅という「自分らし […]
続きを読む 居宅介護(ホームヘルプ)とは? 自宅での生活を支える大切な支援をわかりやすく解説
障害福祉サービスの「生活介護」を基礎から丁寧に解説。対象者、支援内容、1日の流れ、メリットまで、これから利用を考える本人・家族・支援者に役立つ情報を網羅します。安心して日中を過ごすための支援の全体像がわかる解説記事。 は […]
続きを読む 生活介護とは? 内容・対象者・メリットを徹底解説 初めてでもわかる日中活動支援の基礎
障害福祉サービスの「施設入所支援」とは何かを、対象者・支援内容・利用の流れ・費用・グループホームとの違いまでわかりやすく解説。24時間体制で安心の暮らしを支えます。 はじめに 障害者福祉サービスの中でも、暮らしの場そのも […]
続きを読む 施設入所支援とは?〜24時間体制で生活を支える入所サービスをわかりやすく解説〜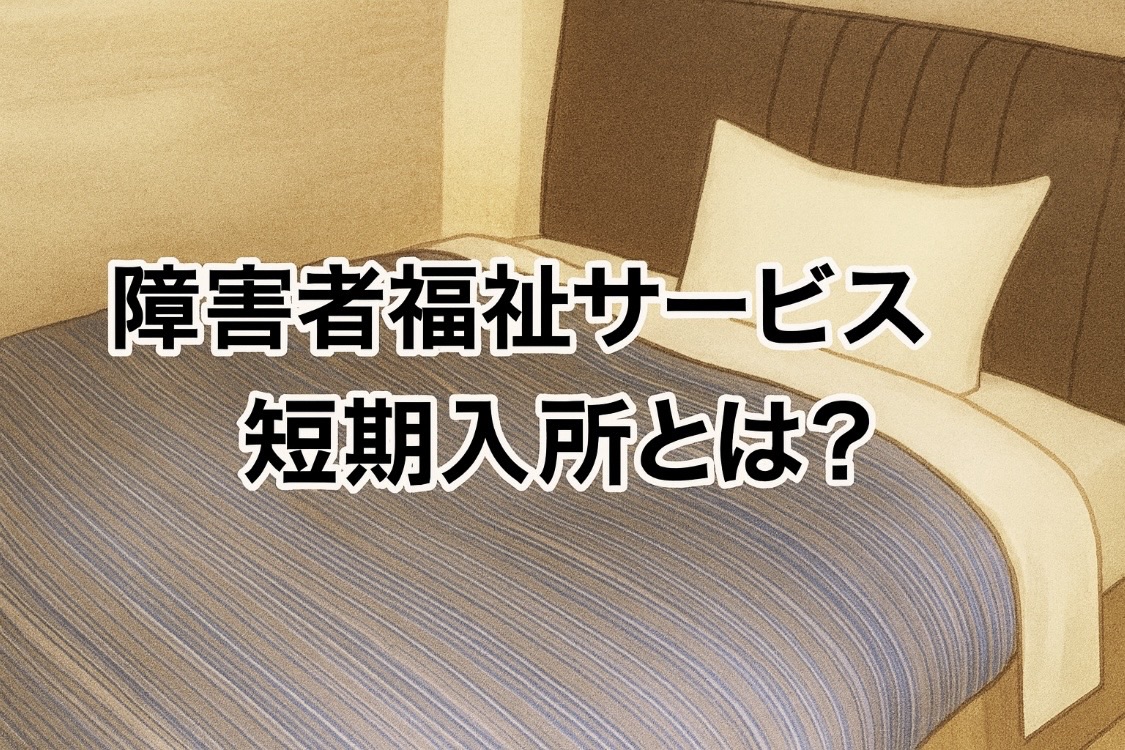
障害者福祉サービスの短期入所(ショートステイ)について、対象者・介護型・医療型の違い、支援内容、メリット、利用の流れまでを初心者にもわかりやすく解説。家族の負担軽減や生活の幅を広げる大切な制度を丁寧に紹介します。&nbs […]
続きを読む 短期入所(ショートステイ)とは? 役割・利用の流れ・支援内容をわかりやすく解説
この記事では、障害者福祉サービスについて、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門 […]
続きを読む 障害者福祉サービスとは? 種類・利用の流れ・選び方までを分かりやすく解説