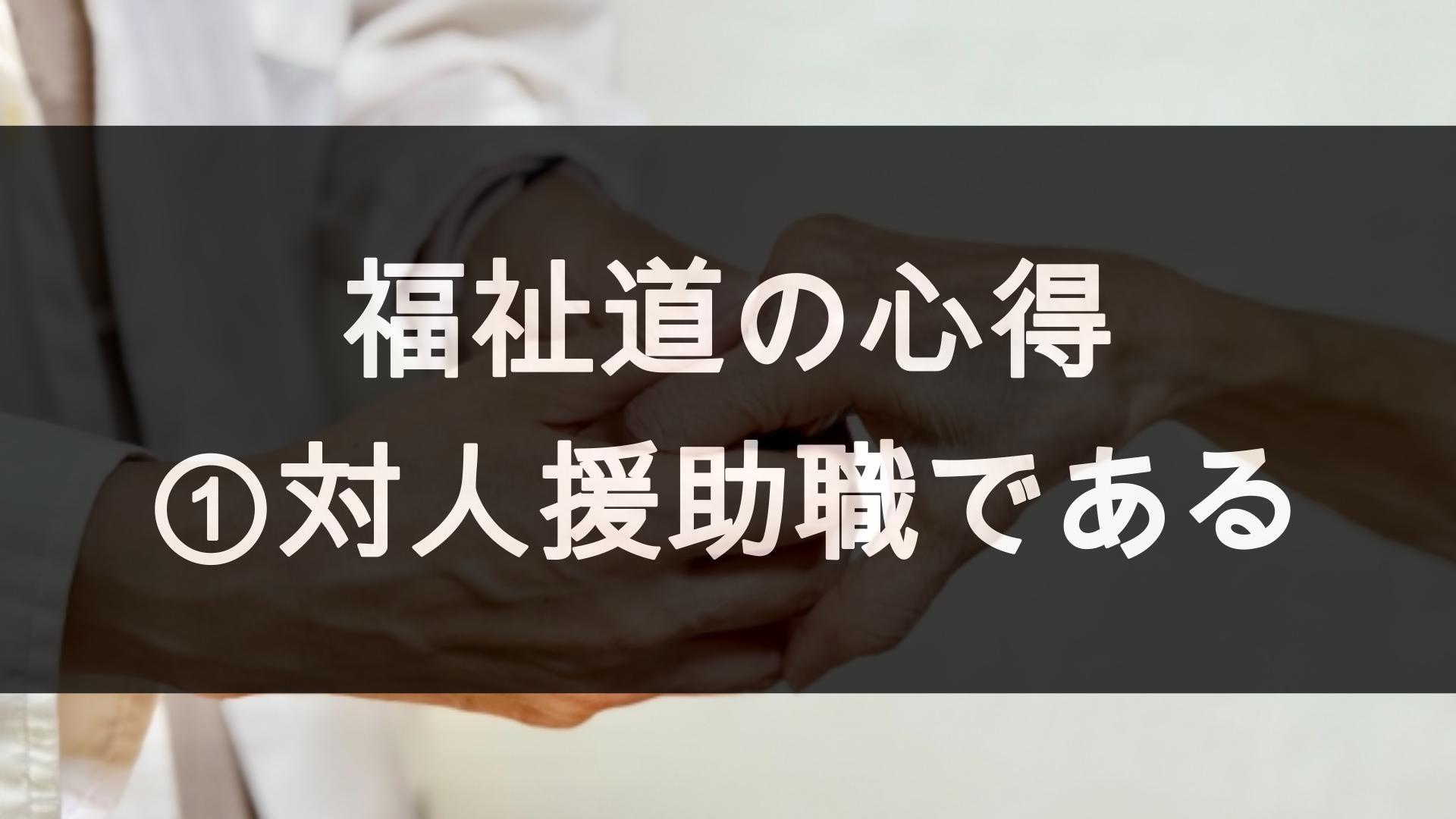福祉道の心得②「エッセンシャルワーカーである」
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 福祉道の心得②「エッセンシャルワーカーである」本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです

はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 福祉道の心得②「エッセンシャルワーカーである」