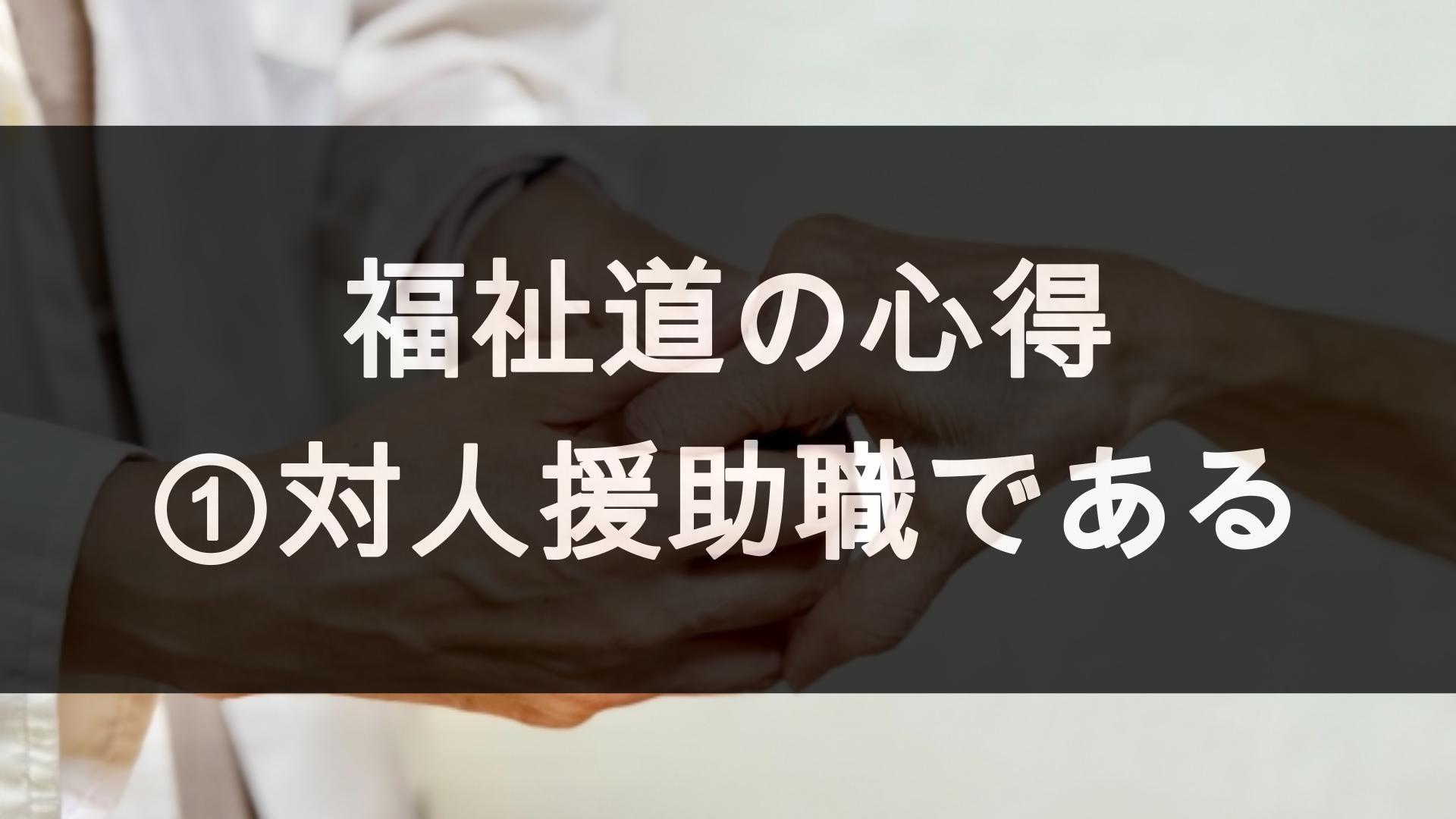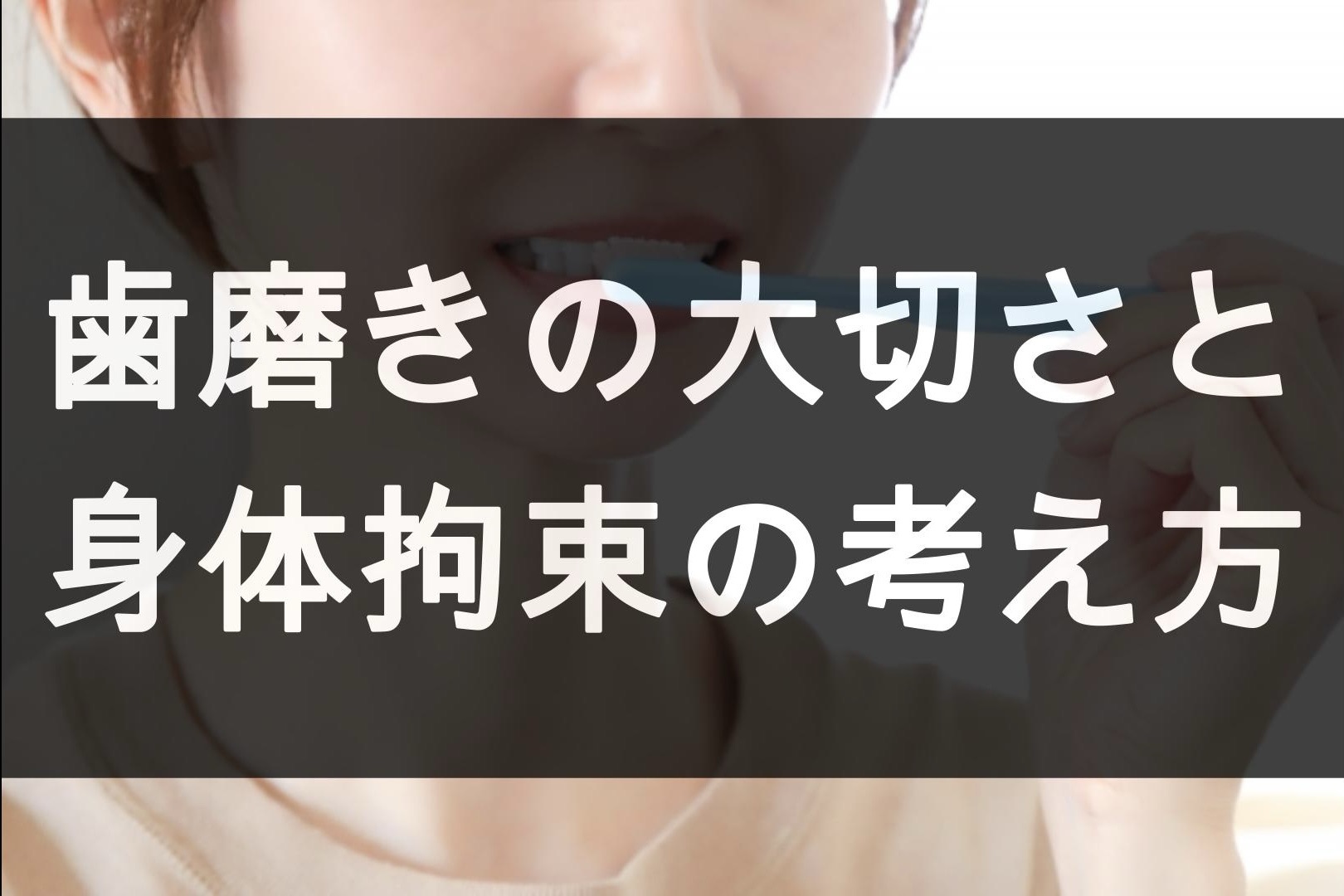
歯磨きの大切さと身体拘束の考え方
はじめに 「歯を磨くことなんて、毎日の当たり前の習慣」と思っていませんか? 私自身もそう思っていましたが、歯医者さんに行ってみると意外な虫歯の数に驚かされた経験があります。さらに、福祉の現場で出会った障害のある方の歯磨き […]
続きを読む 歯磨きの大切さと身体拘束の考え方本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
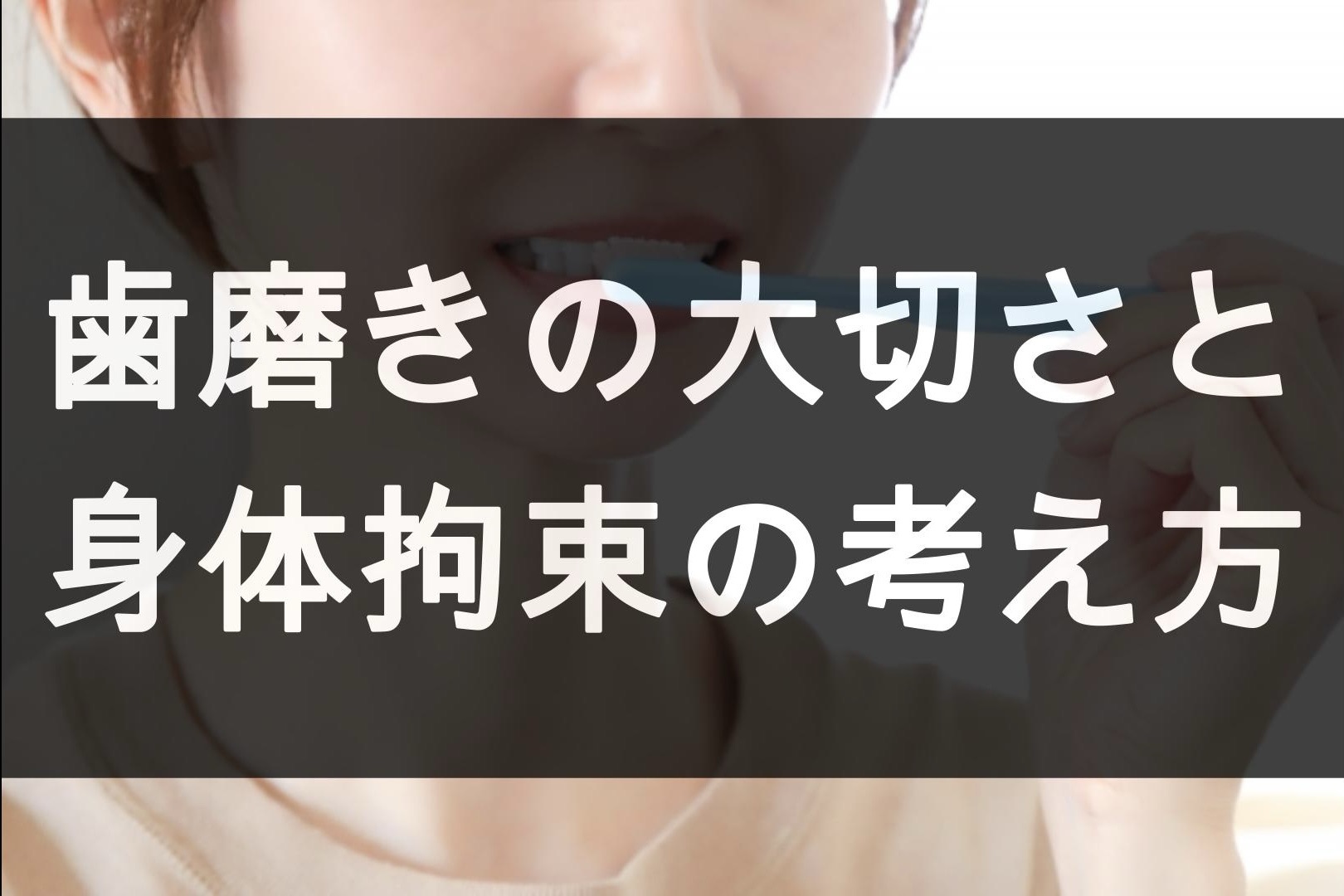
はじめに 「歯を磨くことなんて、毎日の当たり前の習慣」と思っていませんか? 私自身もそう思っていましたが、歯医者さんに行ってみると意外な虫歯の数に驚かされた経験があります。さらに、福祉の現場で出会った障害のある方の歯磨き […]
続きを読む 歯磨きの大切さと身体拘束の考え方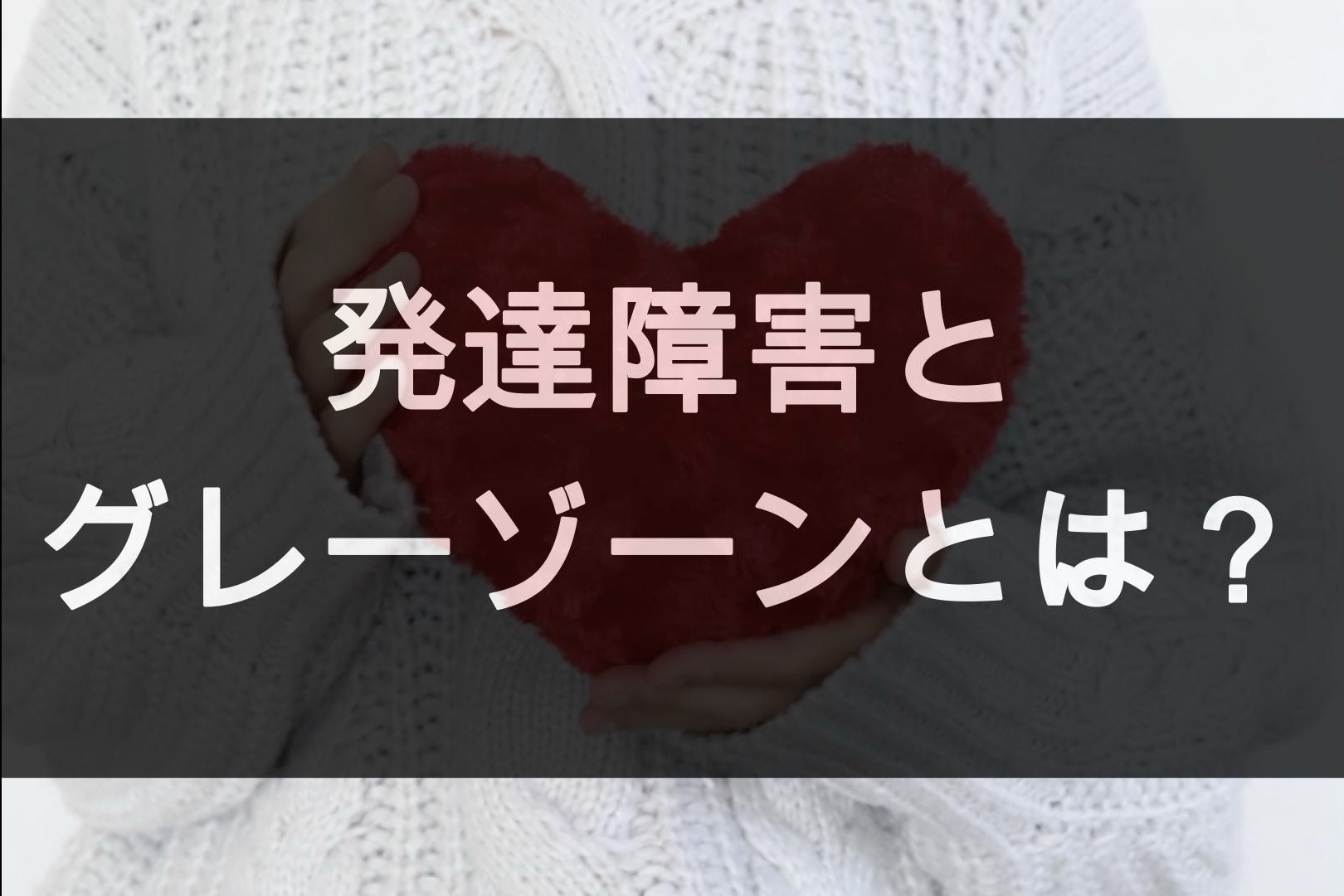
はじめに 近年、発達障害やADHD、ASD(アスペルガー)、高機能自閉症、グレーゾーンといった言葉をよく聞くようになってきました。 これらは広義で発達障害と呼ばれいて、生まれつきの脳の発達の特性によって、社会生活やコミュ […]
続きを読む 発達障害とグレーゾーンとは?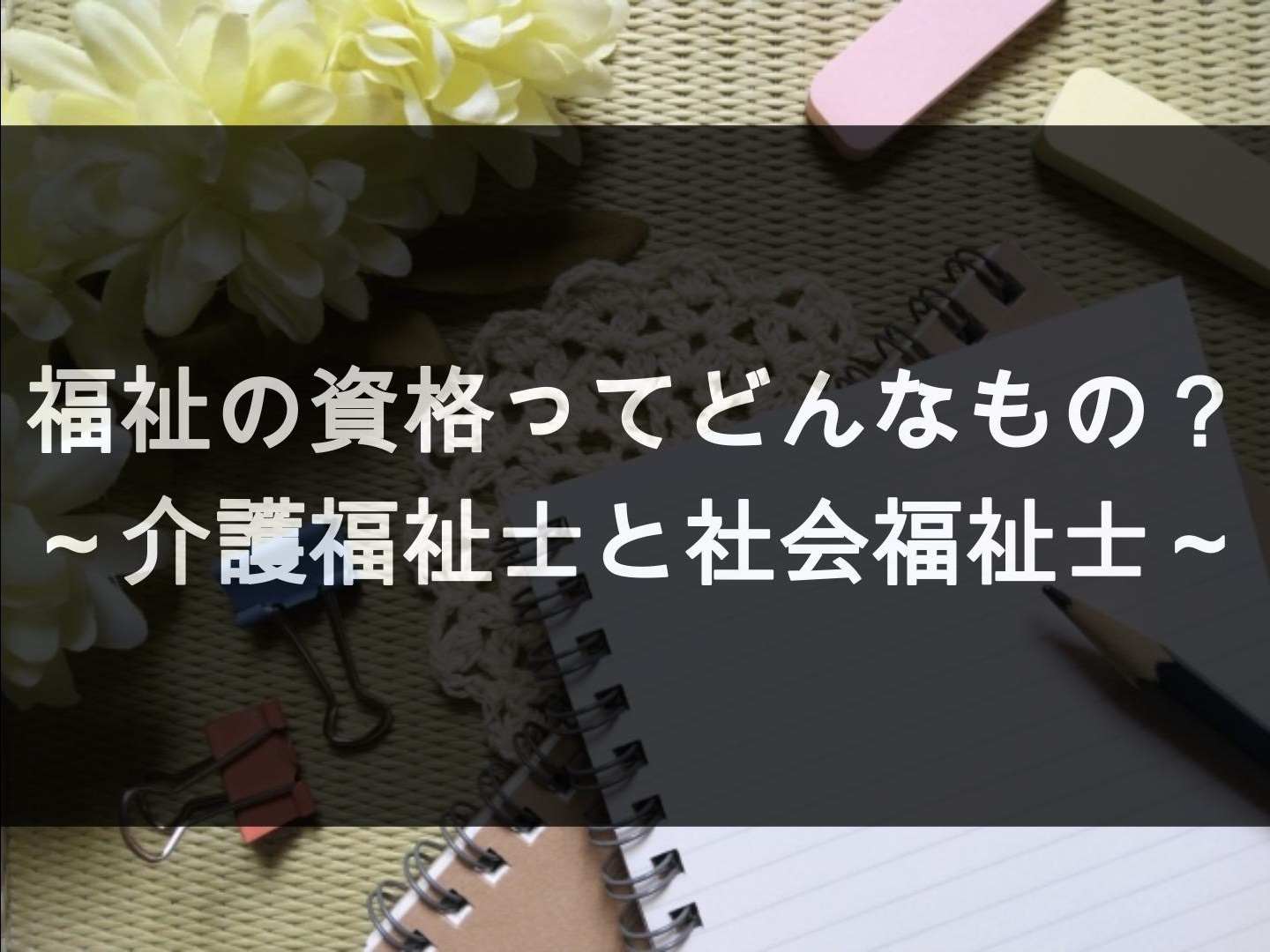
はじめに 今回は福祉領域の代表的な資格としてよく言われる介護福祉士と社会福祉士についてお話ししていきたいと思います。 福祉の仕事をする上では、このような専門の資格を持っていると、採用の面で有利になるといったように社会的信 […]
続きを読む 福祉の資格ってどんなもの? 〜介護福祉士と社会福祉士〜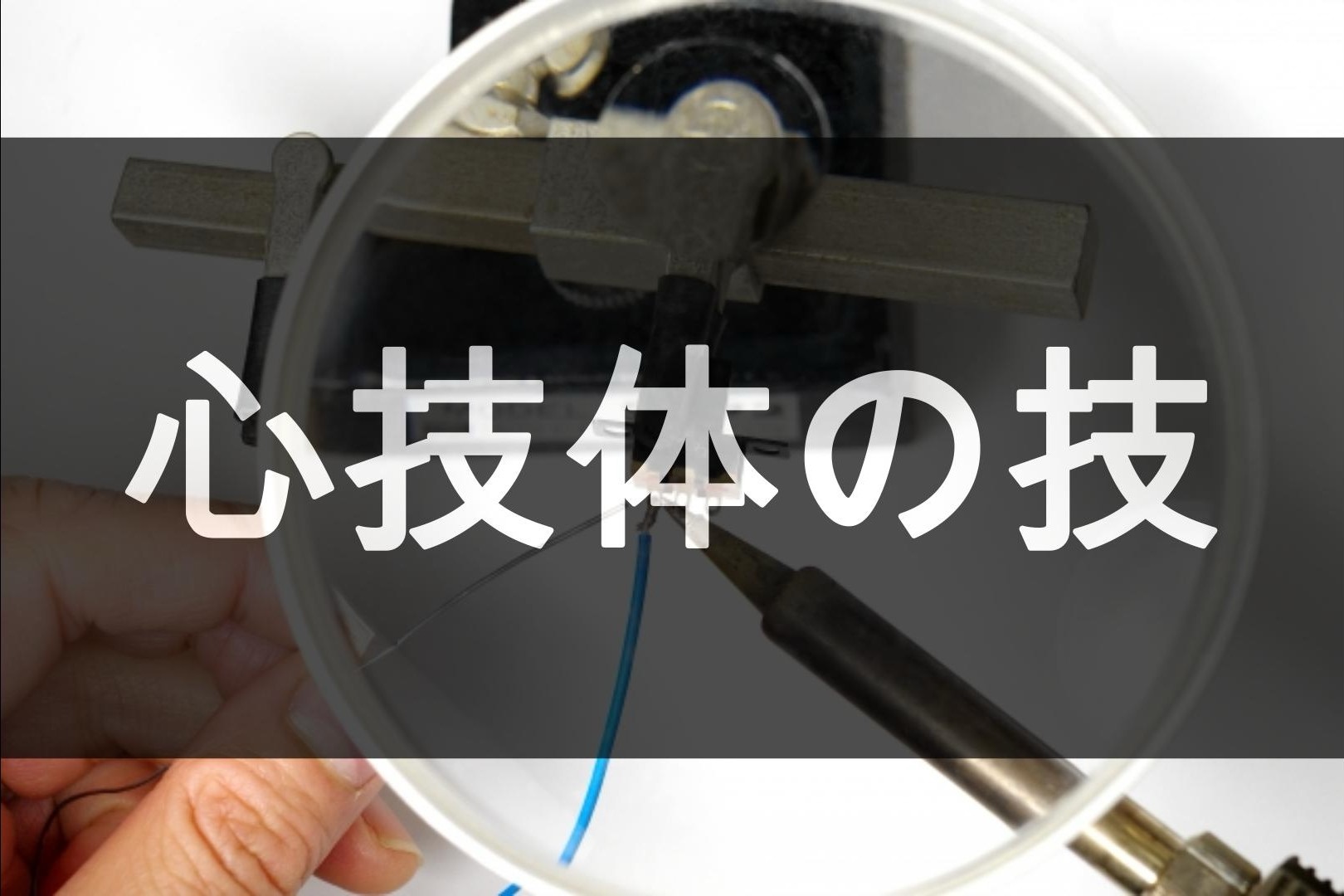
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 心技体の技について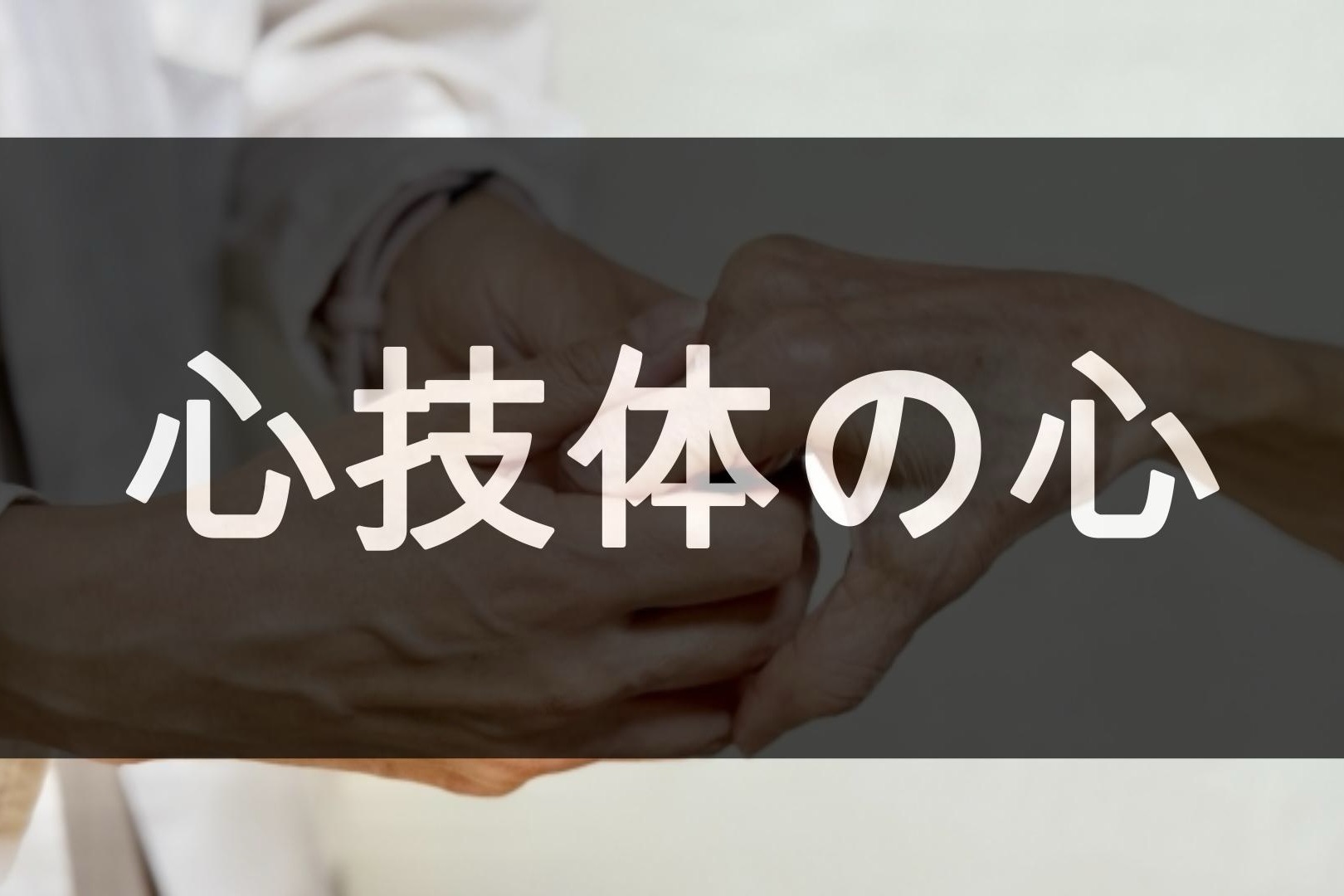
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 心技体の心について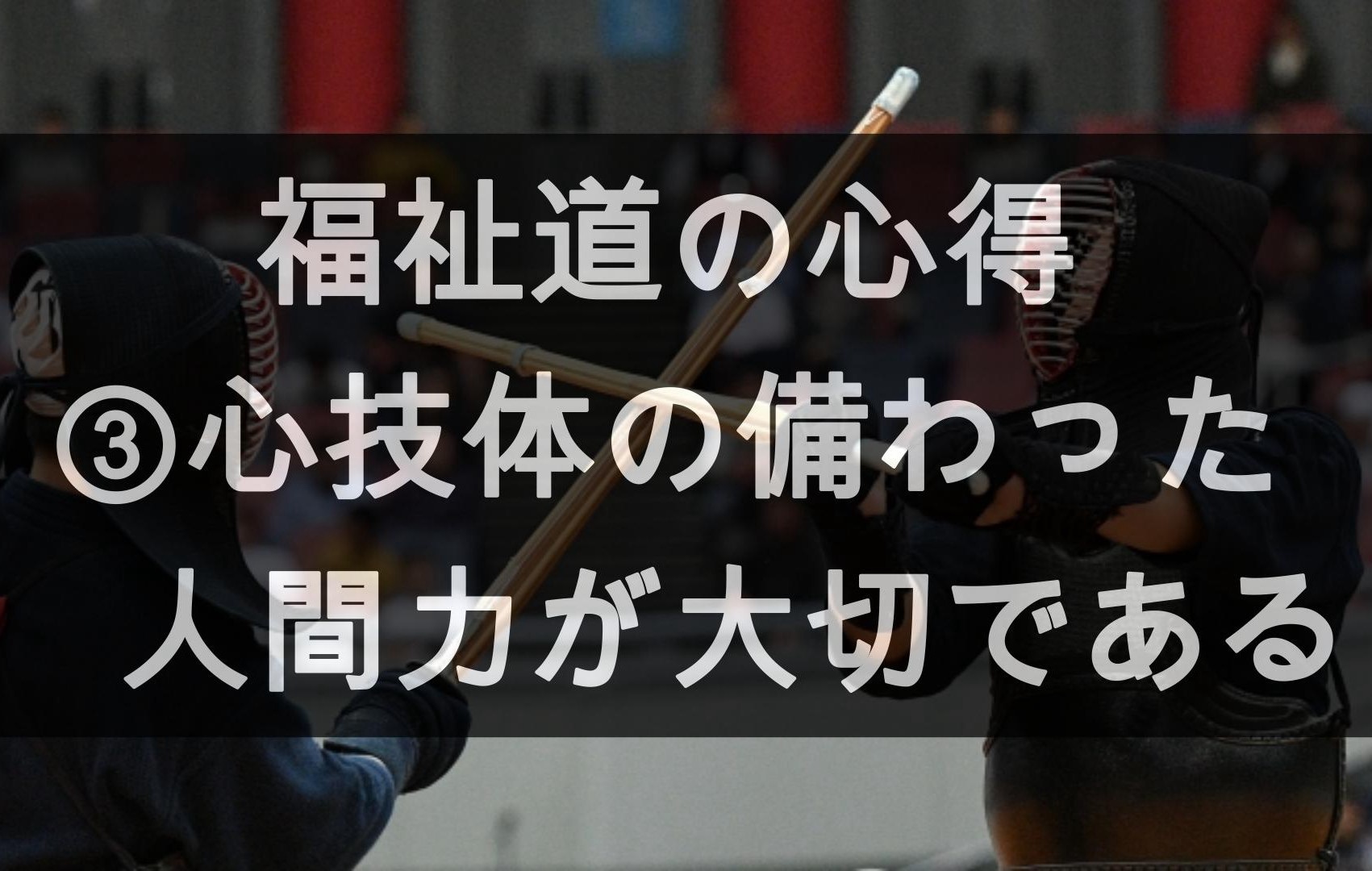
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 福祉道の心得③「心技体の備わった人間力が大切である」
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 福祉道の心得②「エッセンシャルワーカーである」