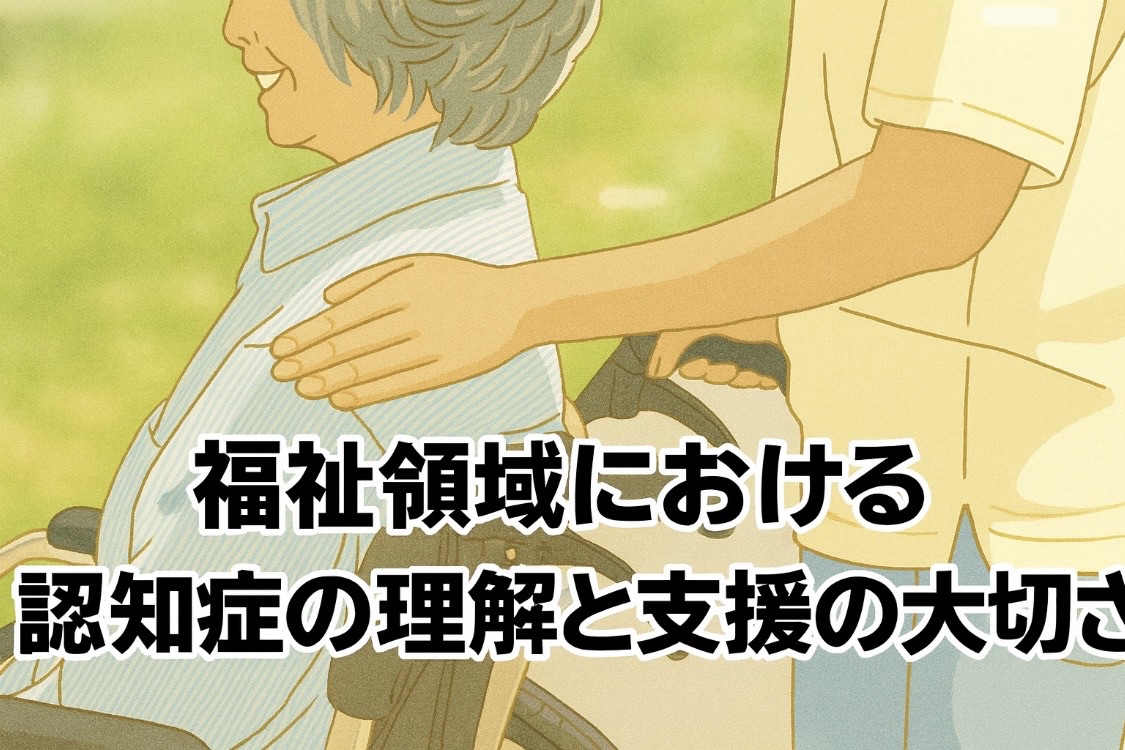
福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜
はじめに 日本では高齢化が加速し、認知症の人は年々増え続けています。 家族の誰かが認知症と診断される、職場の利用者に認知症の症状が見られる──こうした場面は決して特別ではありません。 しかし、認知症は「記憶障害だけの病気 […]
続きを読む 福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
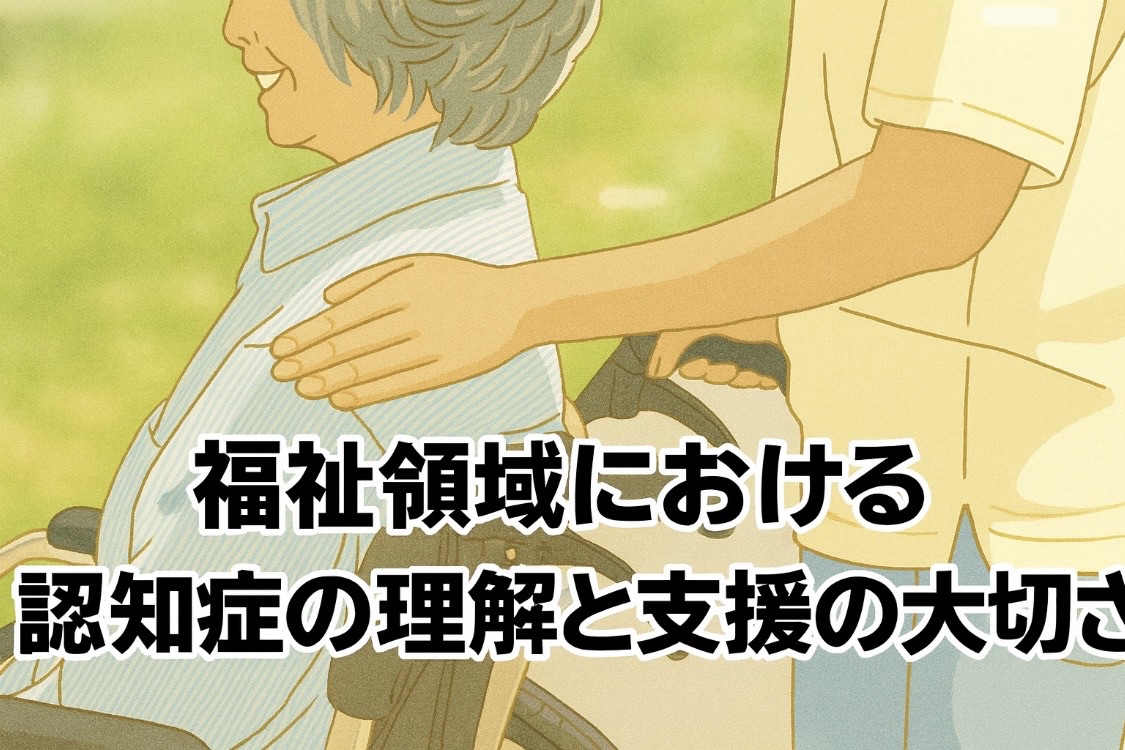
はじめに 日本では高齢化が加速し、認知症の人は年々増え続けています。 家族の誰かが認知症と診断される、職場の利用者に認知症の症状が見られる──こうした場面は決して特別ではありません。 しかし、認知症は「記憶障害だけの病気 […]
続きを読む 福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜
この記事では、知的障害・身体障害・精神障害についてを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相談ください。 […]
続きを読む 知的障害・身体障害・精神障害とは?基礎からわかりやすく解説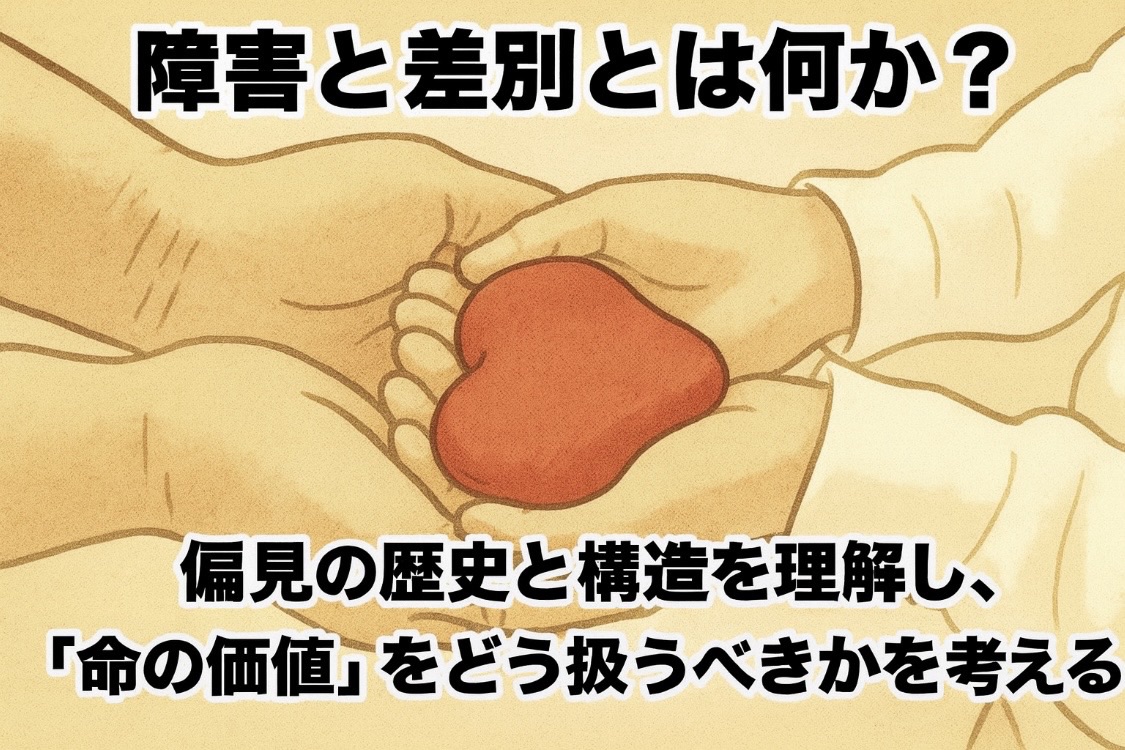
はじめに 優生思想と生命倫理から読み解く現代社会の課題 現代社会は「共生」「多様性」「インクルージョン」といった言葉が広がりつつあります。 しかし、障害のある人が日常生活で直面する差別や偏見は、決して過去の話ではありませ […]
続きを読む 障害と差別とは何か? 偏見の歴史と構造を理解し、「命の価値」をどう扱うべきかを考える
はじめに 医療や介護、保育などの人との距離感が近い対人援助の現場では、体調管理を常に念頭に置いておかなければなりません。 職員一人ひとりが自分自身の健康を守り、免疫力を維持していくことが、利用者さんへの安心・安全な支援に […]
続きを読む 免疫力アップ 〜お勧めのセルフケアとチームで促すラインケア〜
はじめに てんかんという言葉を聞いたことはありますでしょうか? てんかん以外に、発作、てんかん発作、などと呼ばれたりすることもあります。 これは脳の神経が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作が繰り返される病気で、世界 […]
続きを読む てんかん発作ってなに?基礎知識と語源に隠された歴史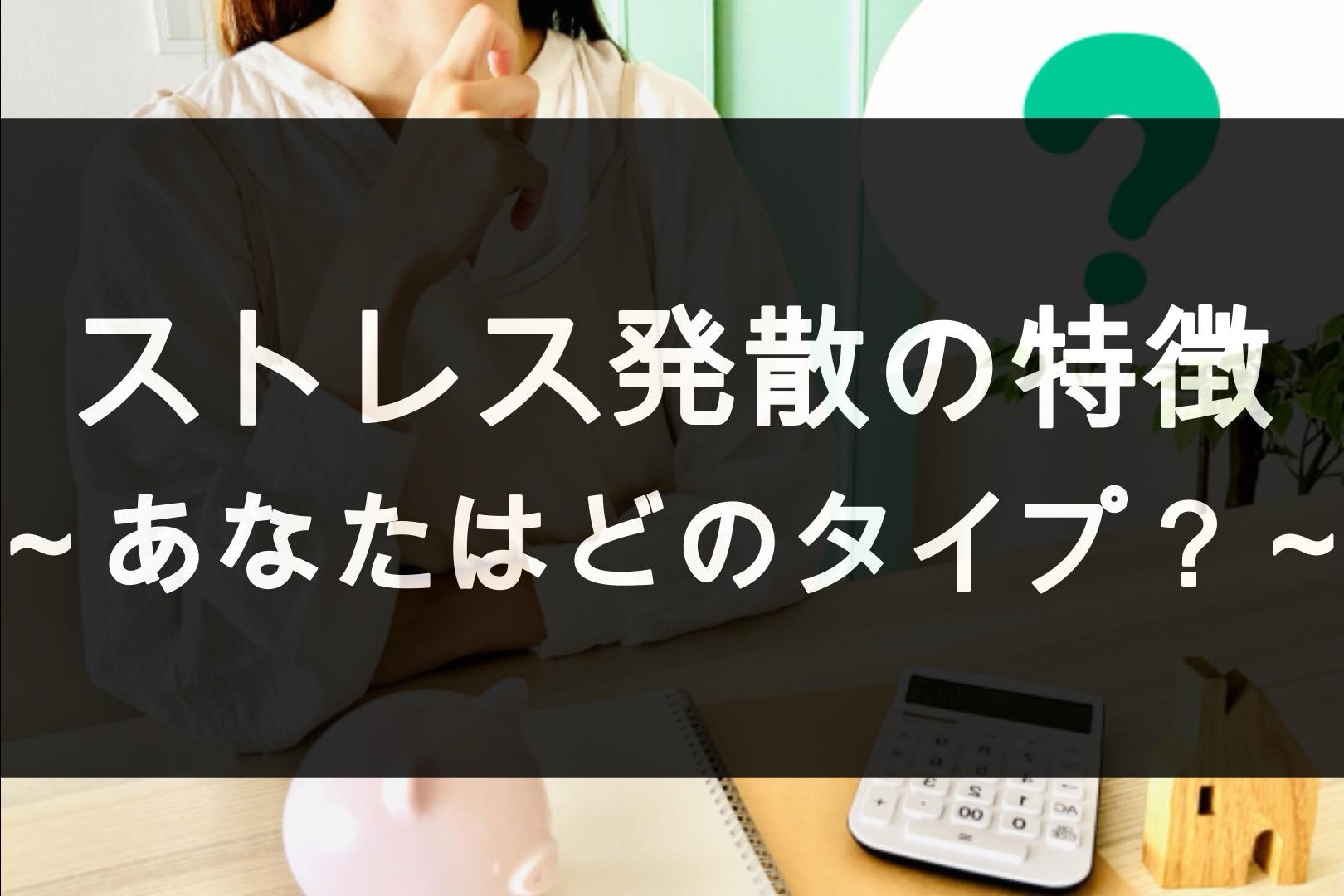
はじめに 人は、強いストレスを受けた時、そのストレスというエネルギーをどんな形であれ外側に向けて発散したり、内側で処理したりといったようにしていく体の機能が備わっています。 そして、その反応の方向性には、攻撃性を伴うもの […]
続きを読む ストレス発散の特徴 〜あなたはどのタイプ?〜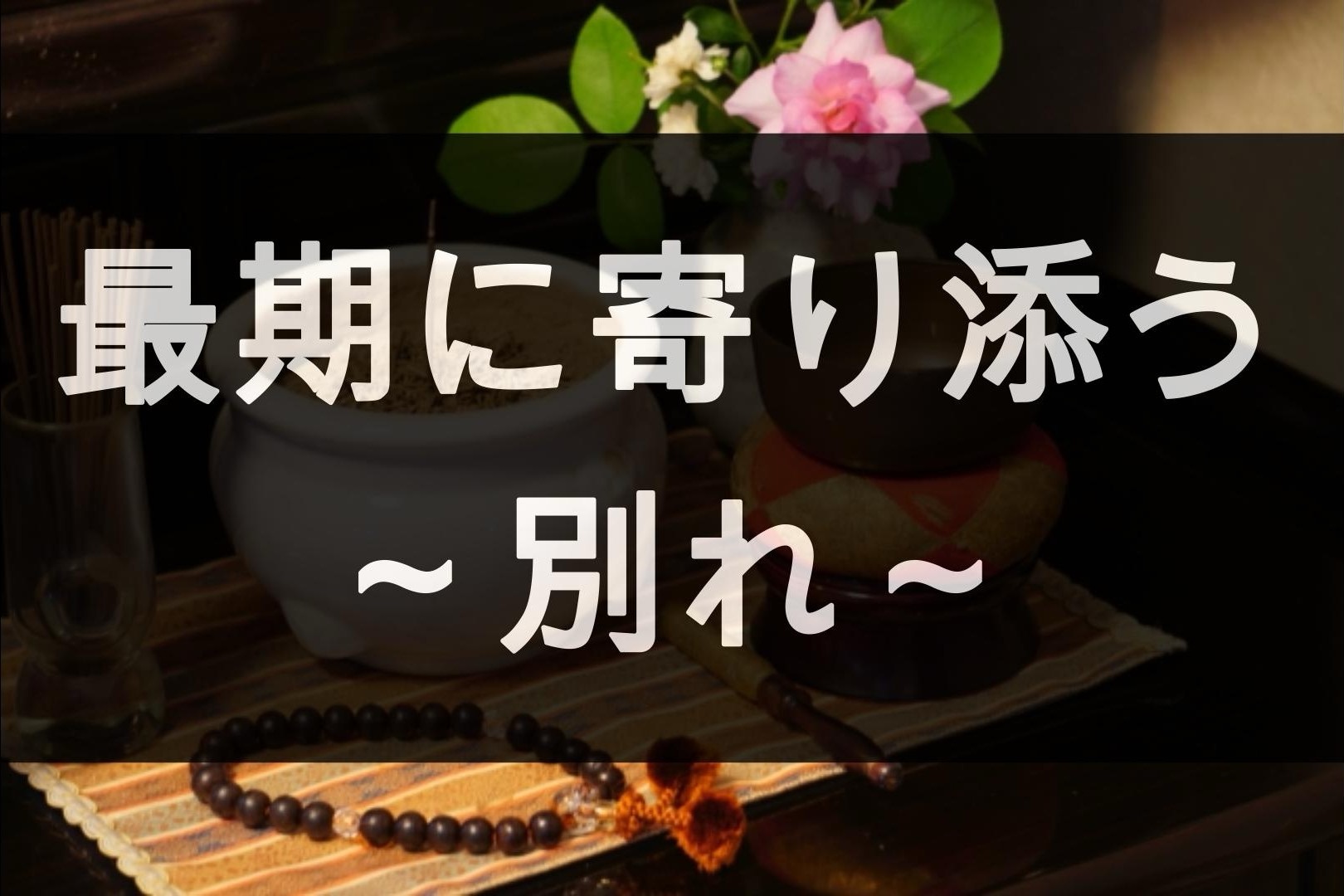
はじめに 福祉の仕事をしていると、日々の暮らしの中でたくさんの出会いがあります。利用者さんとの何気ない会話や、ご家族とのやり取り、地域の方々との関わり。その一つひとつが積み重なっていくうちに、気がつけば仕事を超えて大切な […]
続きを読む 最期に寄り添う 〜別れ〜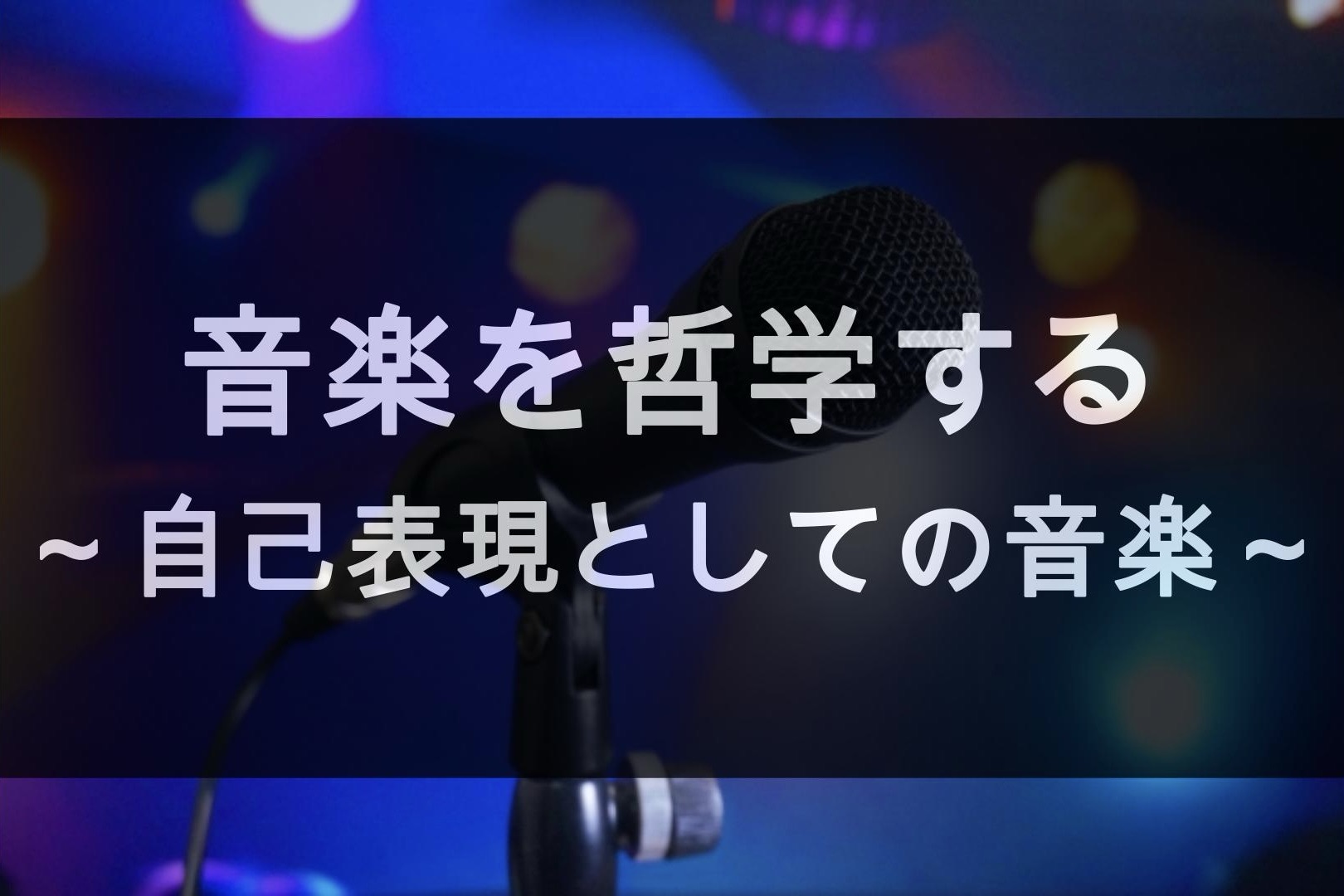
私は大学時代、文学部哲学科の専攻で、ギリシャ哲学や生命倫理などを中心に学ぶことが多かったです。今回はそこで学んだことをまとめた論文『音楽を哲学する 〜自己表現としての音楽〜』を取り上げさせて頂きます。 3万字を超える論 […]
続きを読む 『音楽を哲学する 〜自己表現としての音楽〜』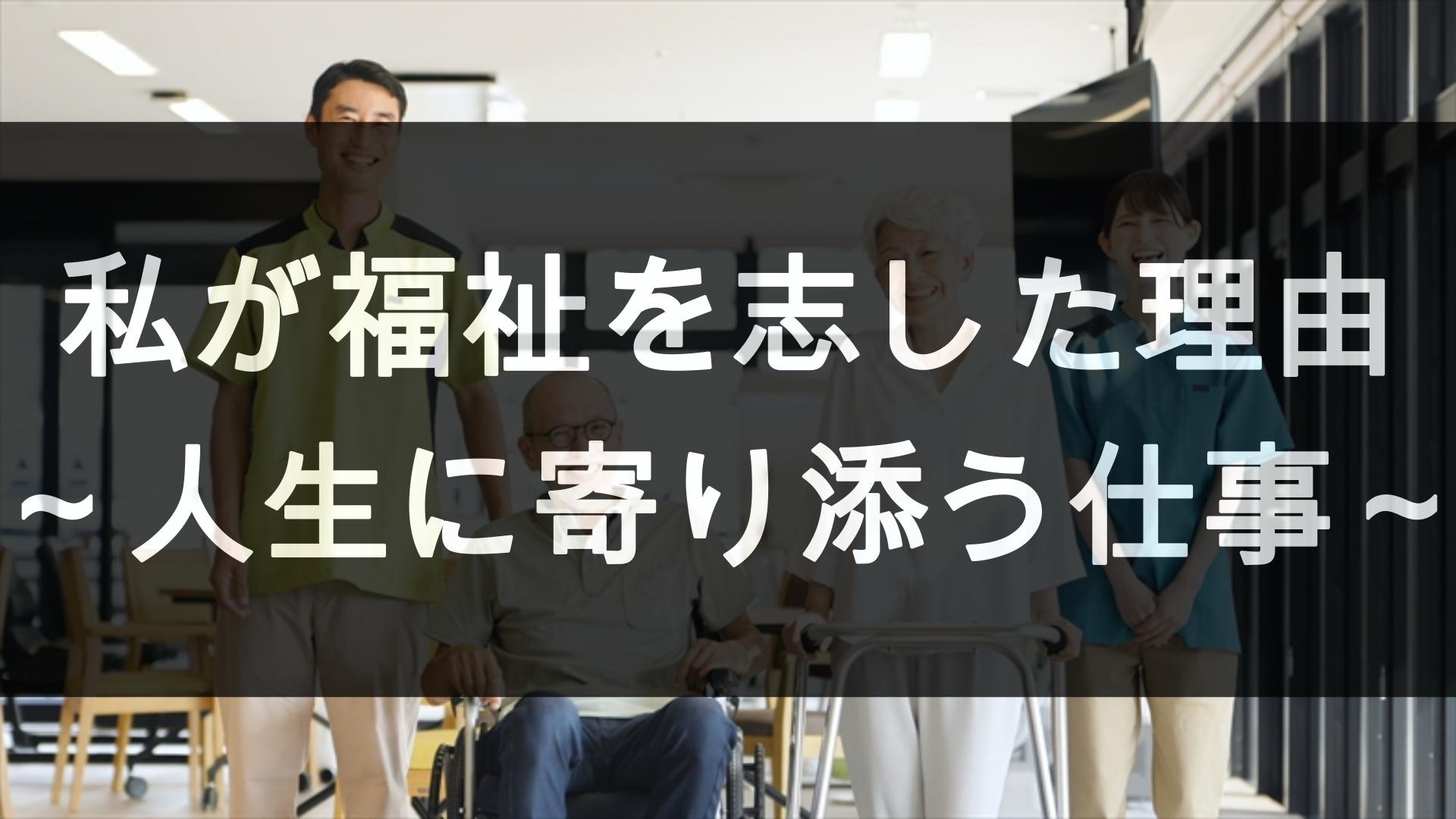
仕事との出会い 私は社会福祉法人の生活介護事業所に勤めていました。そこには、重度の肢体不自由と知的障害が重複している方々が通所されています。詳しい自己紹介はこちらの記事よりご覧ください。 仕事との出会いのきっかけは、私が […]
続きを読む 私が福祉職を志した理由 〜人生に寄り添う仕事〜
自閉症とは? 自閉症(自閉スペクトラム症:ASD)とは、発達障害の特性のひとつであり、 人とのコミュニケーションや社会的な関わり方、行動や興味の偏り に特徴が見られます。かつては「自閉症」「アスペルガー症候群」などと分け […]
続きを読む 自閉症支援の奥義