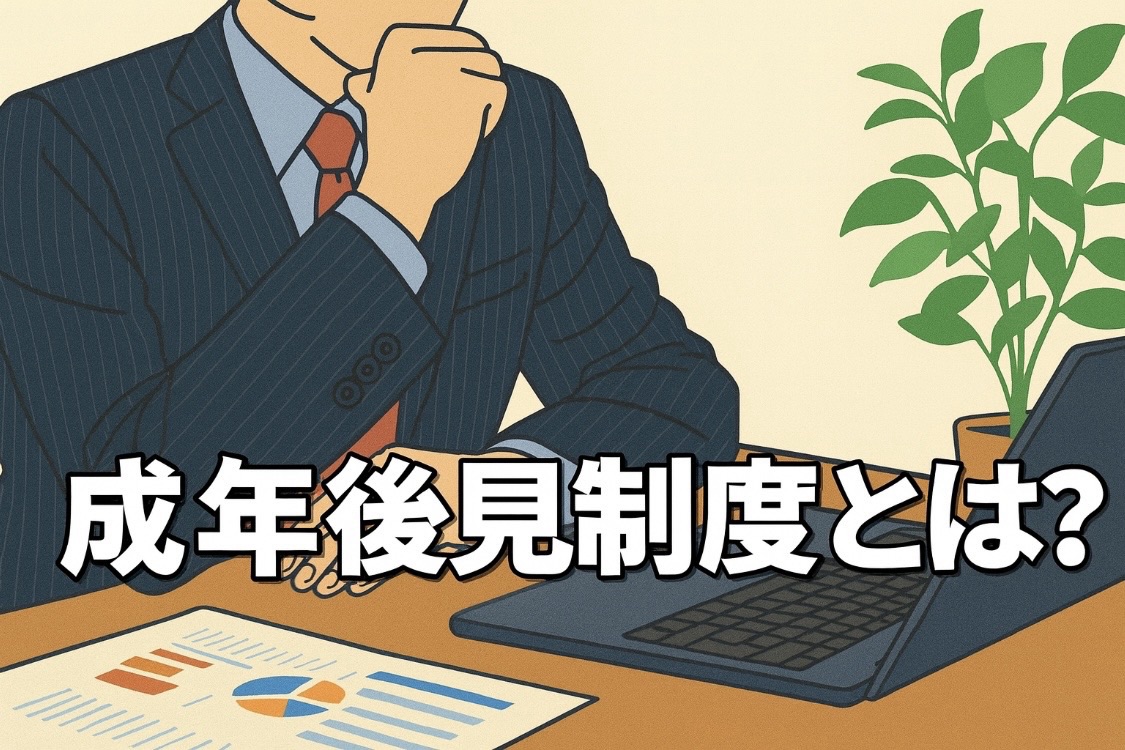
成年後見制度とは?仕組み・種類・費用をやさしく解説 認知症や障害のある方の財産管理に備える完全ガイド
はじめに 障害や高齢による認知症の進行などにより、 ・大切な契約を本人だけで判断するのが難しい ・詐欺や悪徳商法の被害が心配 ・お金の管理をどうしたらよいかわからない といった不安を抱える家族が増えてきました。 こうした […]
続きを読む 成年後見制度とは?仕組み・種類・費用をやさしく解説 認知症や障害のある方の財産管理に備える完全ガイド本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
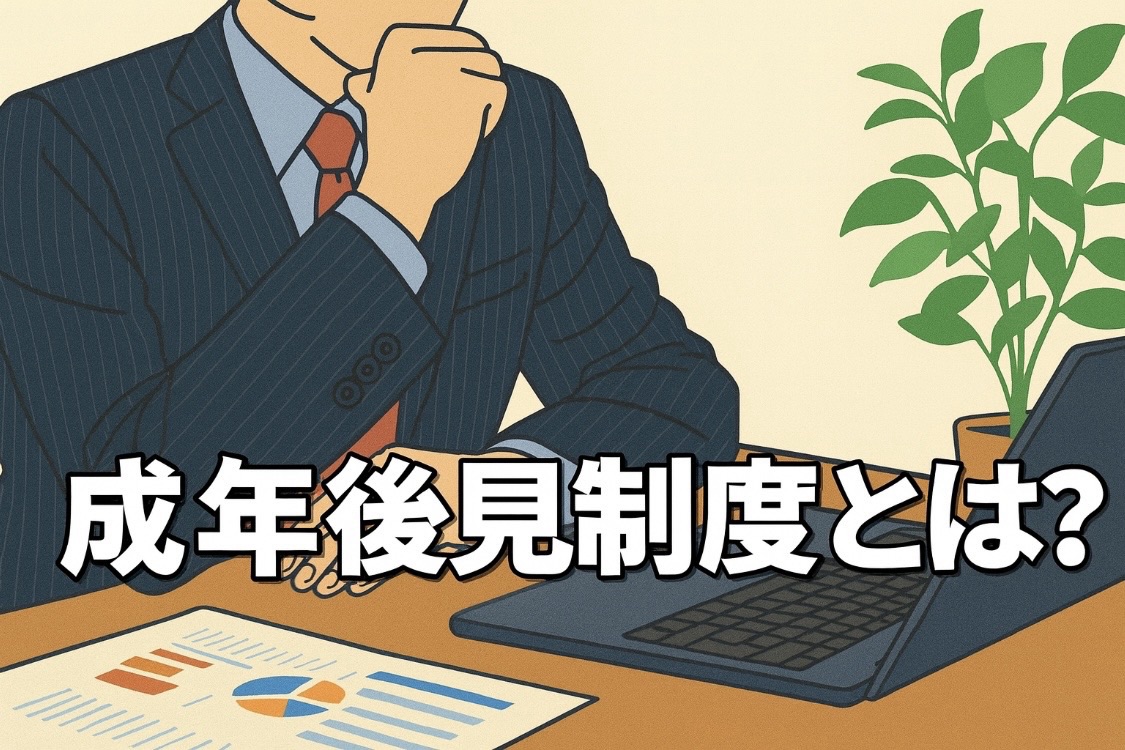
はじめに 障害や高齢による認知症の進行などにより、 ・大切な契約を本人だけで判断するのが難しい ・詐欺や悪徳商法の被害が心配 ・お金の管理をどうしたらよいかわからない といった不安を抱える家族が増えてきました。 こうした […]
続きを読む 成年後見制度とは?仕組み・種類・費用をやさしく解説 認知症や障害のある方の財産管理に備える完全ガイド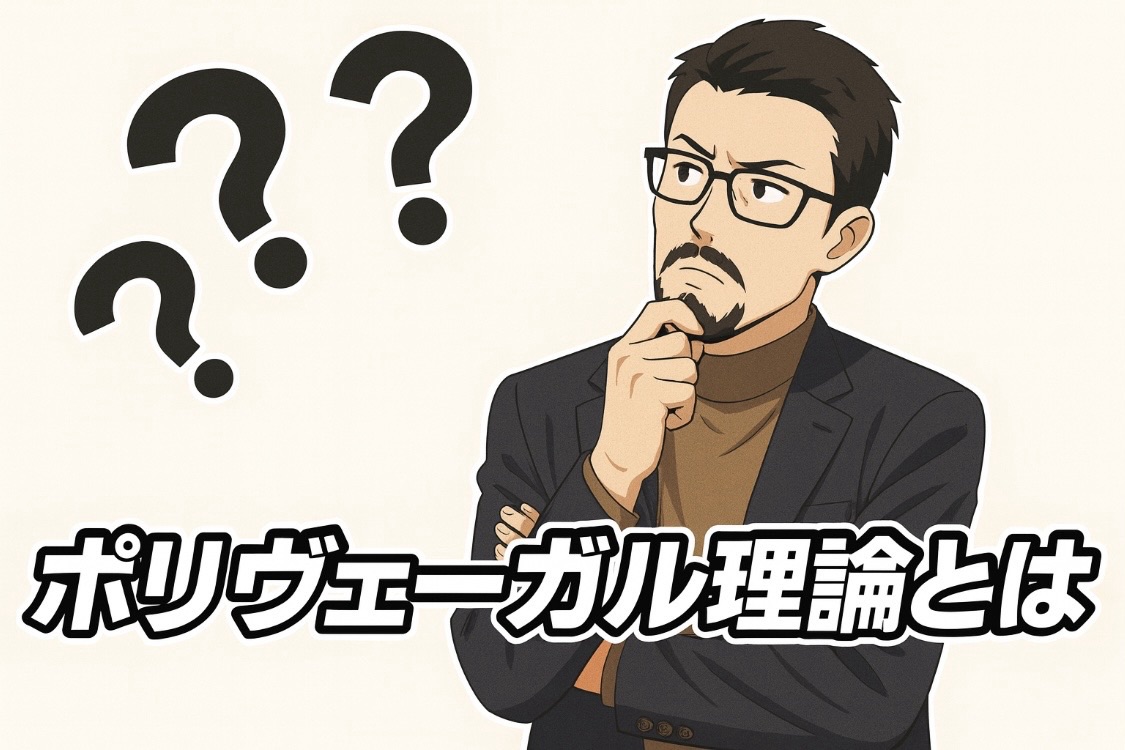
はじめに 「急に体が強張る」 「気持ちは落ち着きたいのに、呼吸が浅くなる」 こうした体の反応は、決して気のせいではありません。 私たちの体は、外の刺激やストレスに対して常に反応し、 その結果として「緊張」「安心」「疲労」 […]
続きを読む ポリヴェーガル理論とは?〜こころと体の安全を理解する新しい視点〜
この記事では、知的障害・身体障害・精神障害についてを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相談ください。 […]
続きを読む 知的障害・身体障害・精神障害とは?基礎からわかりやすく解説
はじめに 摂食(食べる)と嚥下(飲み込む)は、私たちが毎日ごく自然に行っている動作ですが、身体の多くの器官が複雑に連携して成り立っています。 高齢者(認知症含む)の介護、子どもの発達、発達障害、病気や知的・身体・精神障害 […]
続きを読む 【摂食と嚥下】食べる・飲み込む仕組みをわかりやすく解説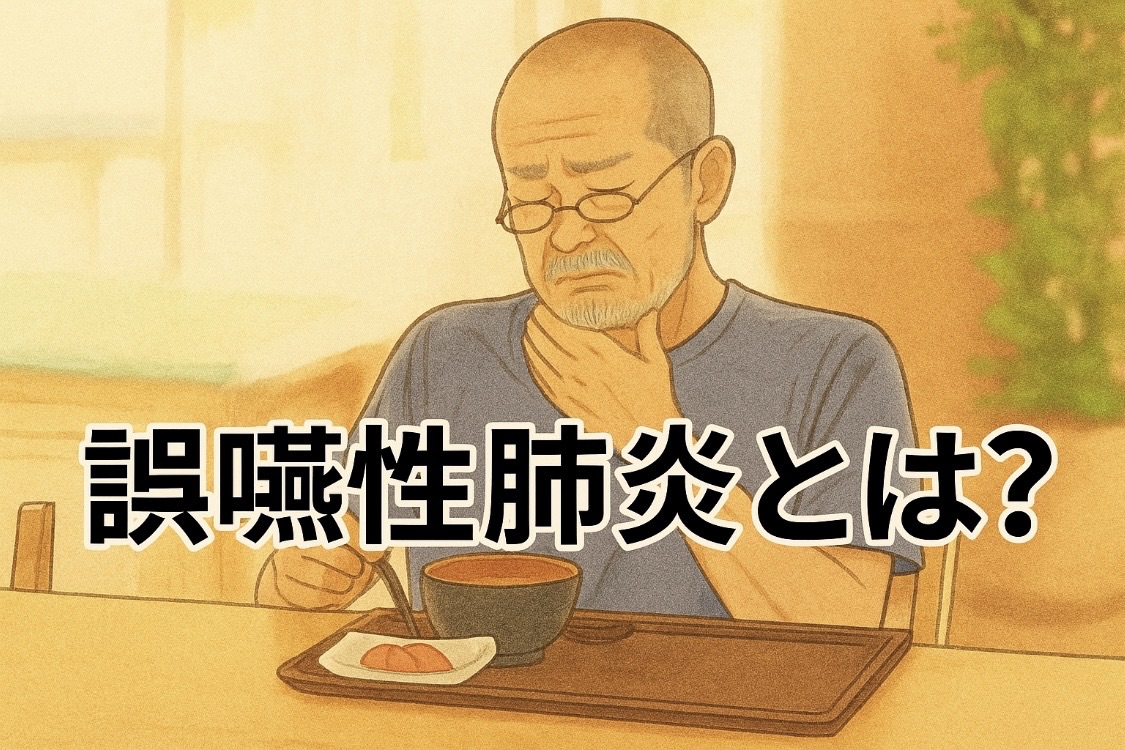
はじめに 誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は、障害のある方や高齢者(認知症含む)の健康リスクとして特に注目される疾患の一つです。 「なぜ誤嚥すると肺炎になるの?」 「むせやすくなってきたけど大丈夫?」 「家庭でできる予防 […]
続きを読む 誤嚥性肺炎とは?原因・症状・予防を徹底解説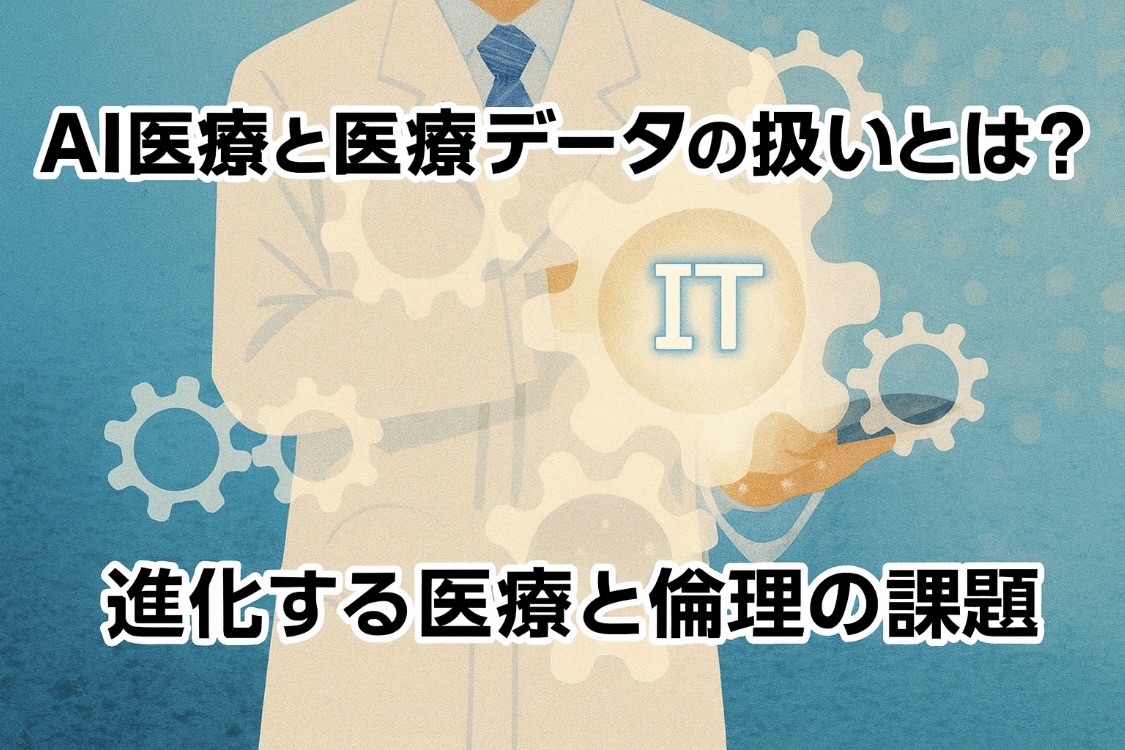
はじめに AI(人工知能)が急速に医療の現場へ広がるなかで、私たちの身体情報・遺伝情報・生活習慣など、さまざまな「医療データ」が分析に利用されるようになっています。 AI医療は、病気の早期発見や、医師の診断補助、手術の安 […]
続きを読む AI医療と医療データの扱いとは?わかりやすく解説 — 進化する医療と倫理の課題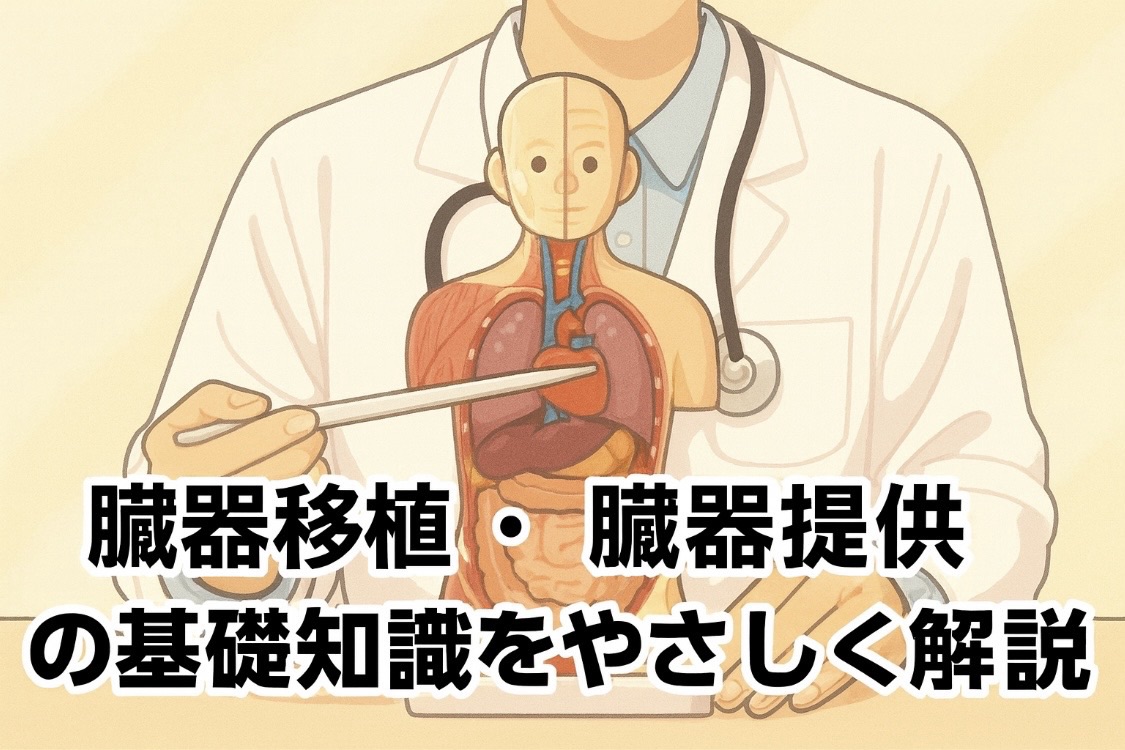
はじめに ― なぜ今「臓器移植・臓器提供」を知る必要があるのか 臓器移植は、重い病気で臓器が働かなくなった人が、新しい臓器を移植することで命を救われる医療です。 近年、医療技術は大きく進歩し、心臓・肝臓・腎臓・肺といった […]
続きを読む 臓器移植・臓器提供の基礎知識をやさしく解説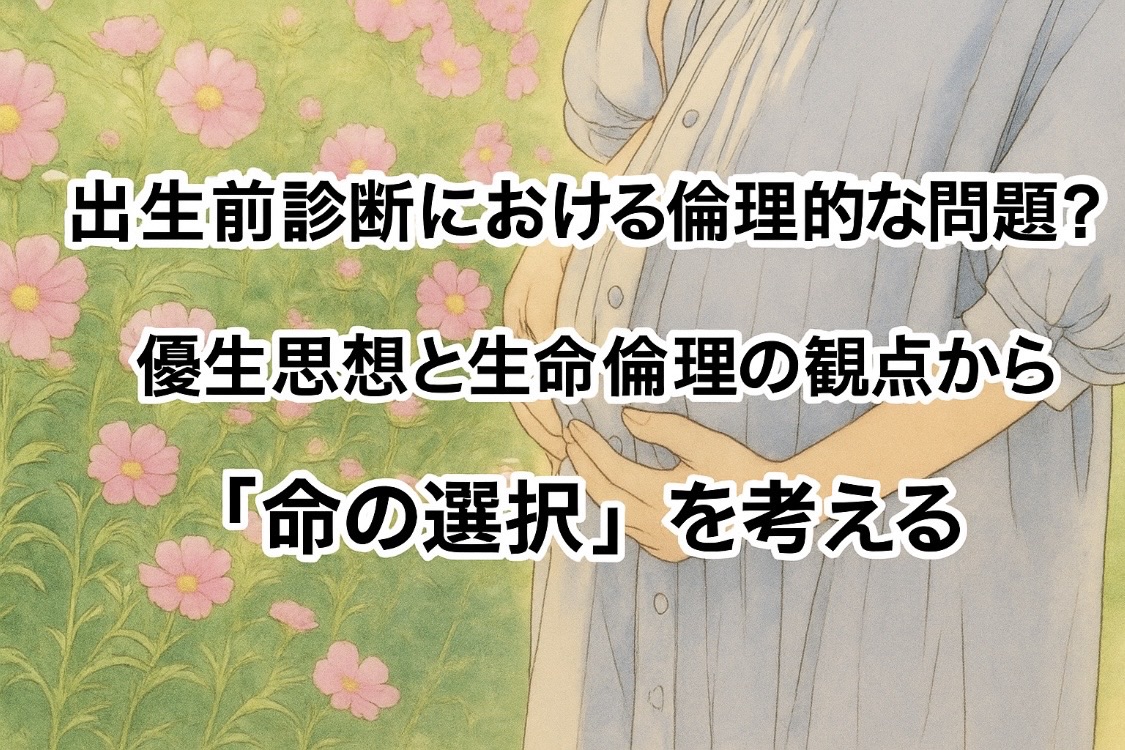
はじめに 出生前診断は、妊娠中の赤ちゃんの状態を詳しく知ることができる医療技術として注目されています。 一方で、この検査は 命をどう受け止めるか”という根源的な問いを突きつけるため、医療・当事者・社会の間で議論が続いてい […]
続きを読む 出生前診断における倫理的な問題とは? ― 優生思想と生命倫理の観点から「いのちの選択」を考える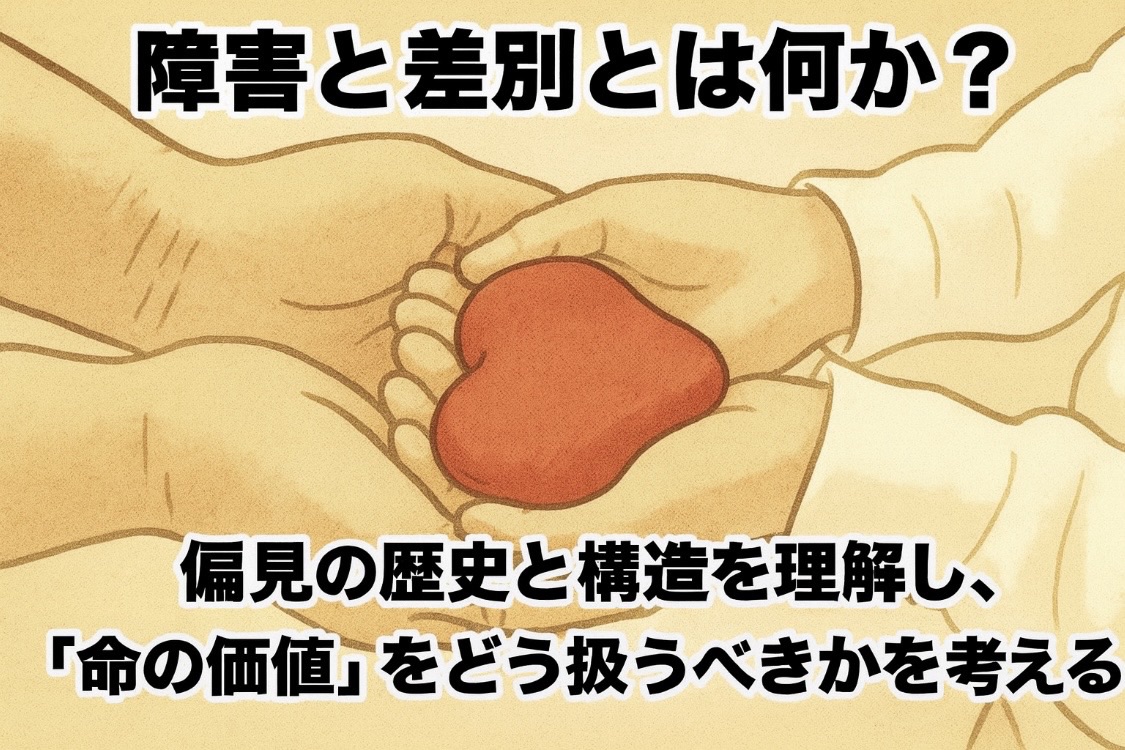
はじめに 優生思想と生命倫理から読み解く現代社会の課題 現代社会は「共生」「多様性」「インクルージョン」といった言葉が広がりつつあります。 しかし、障害のある人が日常生活で直面する差別や偏見は、決して過去の話ではありませ […]
続きを読む 障害と差別とは何か? 偏見の歴史と構造を理解し、「命の価値」をどう扱うべきかを考える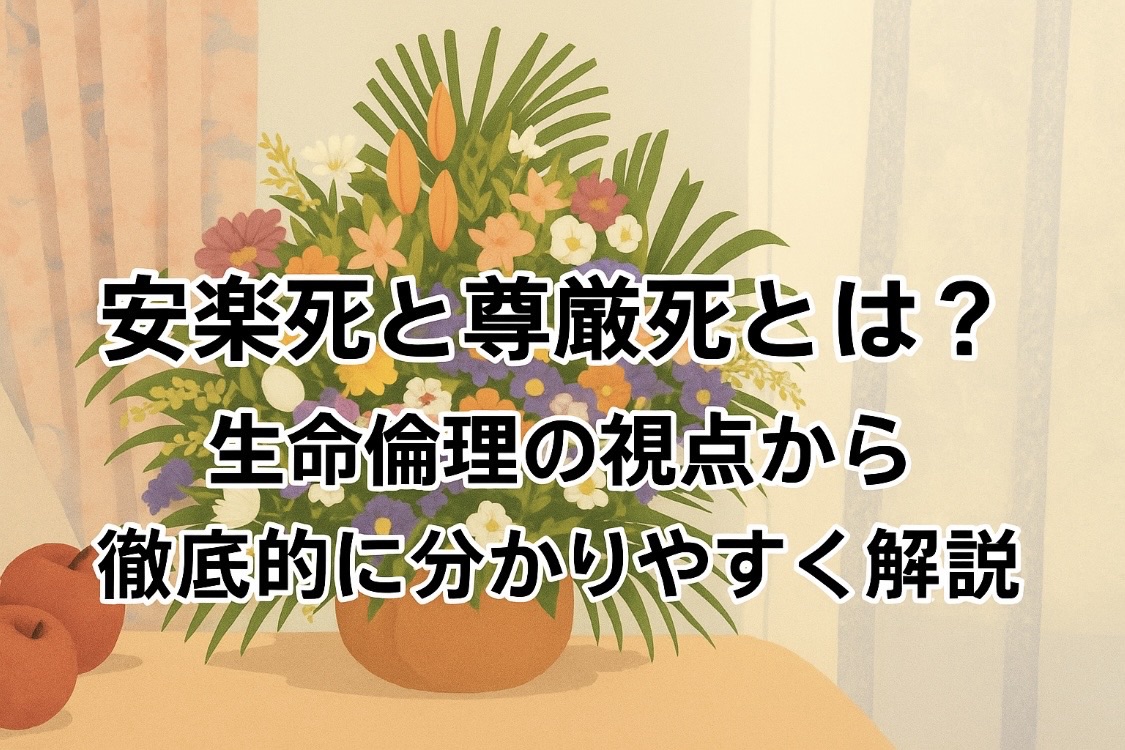
はじめに 近年、安楽死や尊厳死といった言葉が、ニュースやドラマ、SNSなど、さまざまな場面で取り上げられるようになりました。 医療技術が高度化し、延命治療が可能になった一方で、「苦痛を抱えながら生き続けることが本人にとっ […]
続きを読む 安楽死と尊厳死とは? 生命倫理の視点から徹底的にわかりやすく解説