保護中: 理学療法士(PT)の仕事内容と現実とは 〜回復期病院で働いた体験談から見えたリハビリの力と壁〜
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
続きを読む 保護中: 理学療法士(PT)の仕事内容と現実とは 〜回復期病院で働いた体験談から見えたリハビリの力と壁〜本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。
続きを読む 保護中: 理学療法士(PT)の仕事内容と現実とは 〜回復期病院で働いた体験談から見えたリハビリの力と壁〜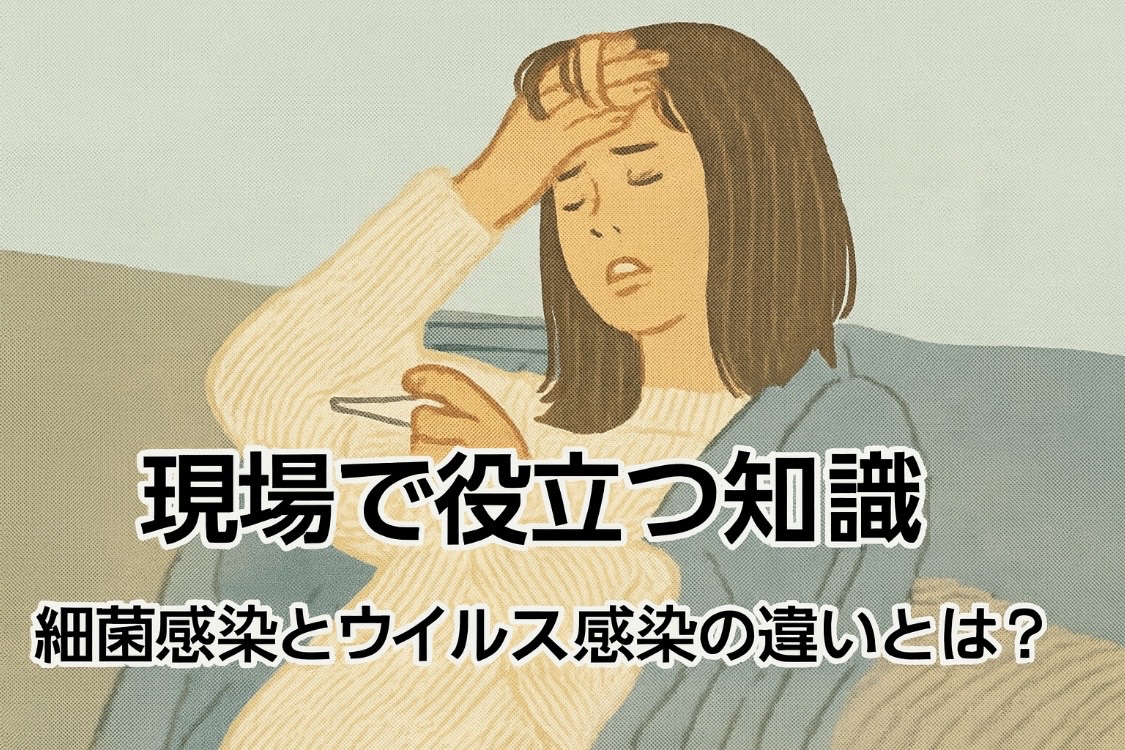
この記事では、細菌感染とウイルス感染について、仕組みや基本的な考え方を、初めて触れる方にも分かりやすく整理して解説します。 内容によっては、地域や状況によって運用・対応が異なる場合があります。実際の利用や判断にあたっては […]
続きを読む 現場で役立つ知識 細菌感染とウイルス感染の違いとは? 血液検査から読み取る判断のポイント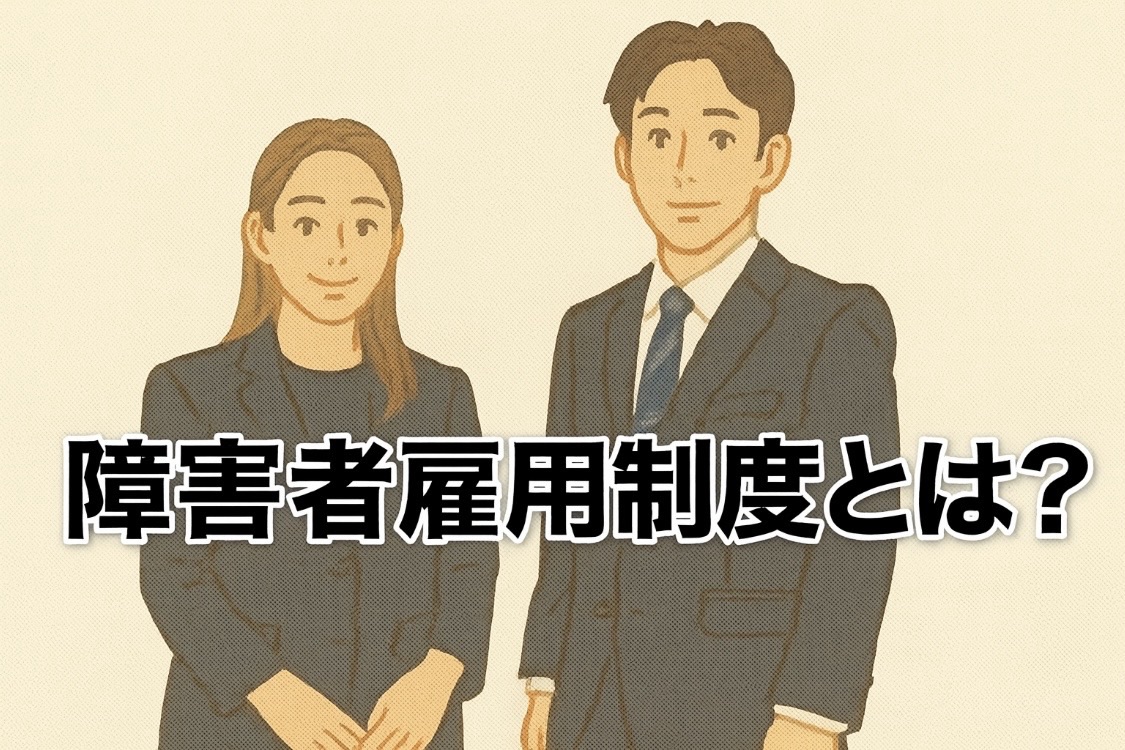
はじめに 障害者雇用制度は、障害のある人が社会の一員として働く機会を確保し、安定した生活を送れるようにするために設けられた仕組みです。 企業や行政が「どれだけ雇うべきか」を法律で定め、働くための環境づくりや支援体制も整え […]
続きを読む 障害者雇用制度とは? 仕組み・目的・企業の取り組みをわかりやすく解説
この記事では、サービス等利用計画について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門 […]
続きを読む サービス等利用計画とは? 役割・作り方・相談支援専門員との連携までわかりやすく解説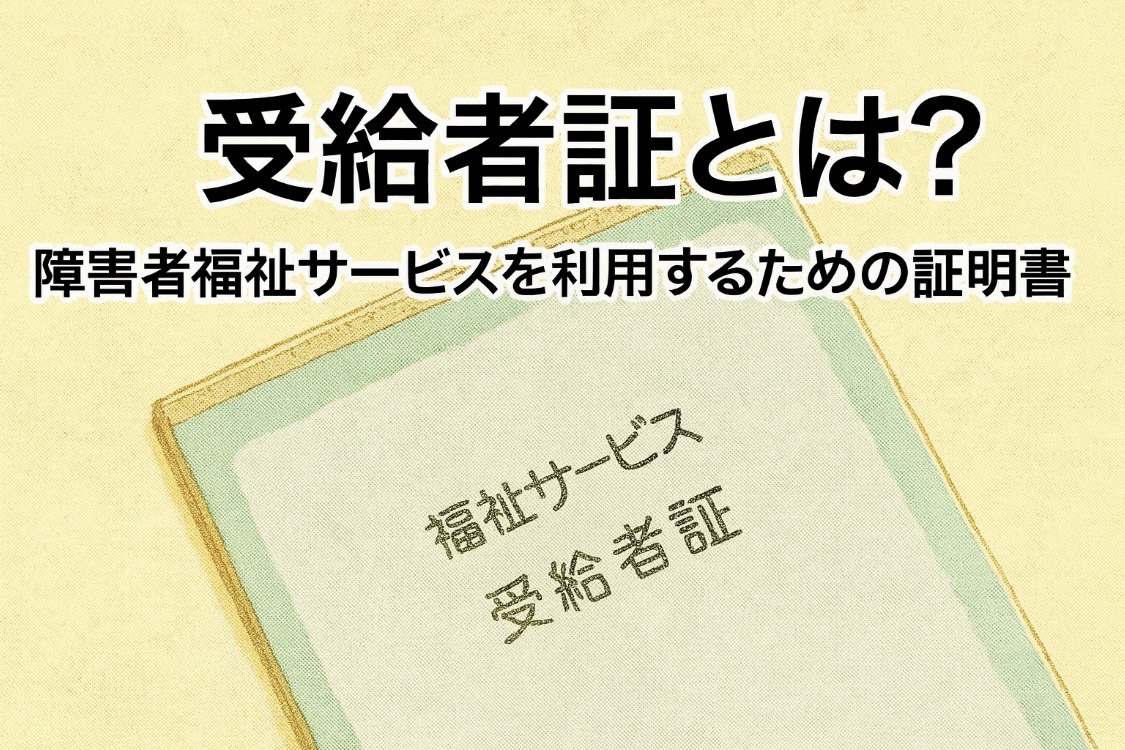
この記事では、受給者証について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相談 […]
続きを読む 受給者証とは?〜障害福祉サービスを利用するための大切な証明書をわかりやすく解説〜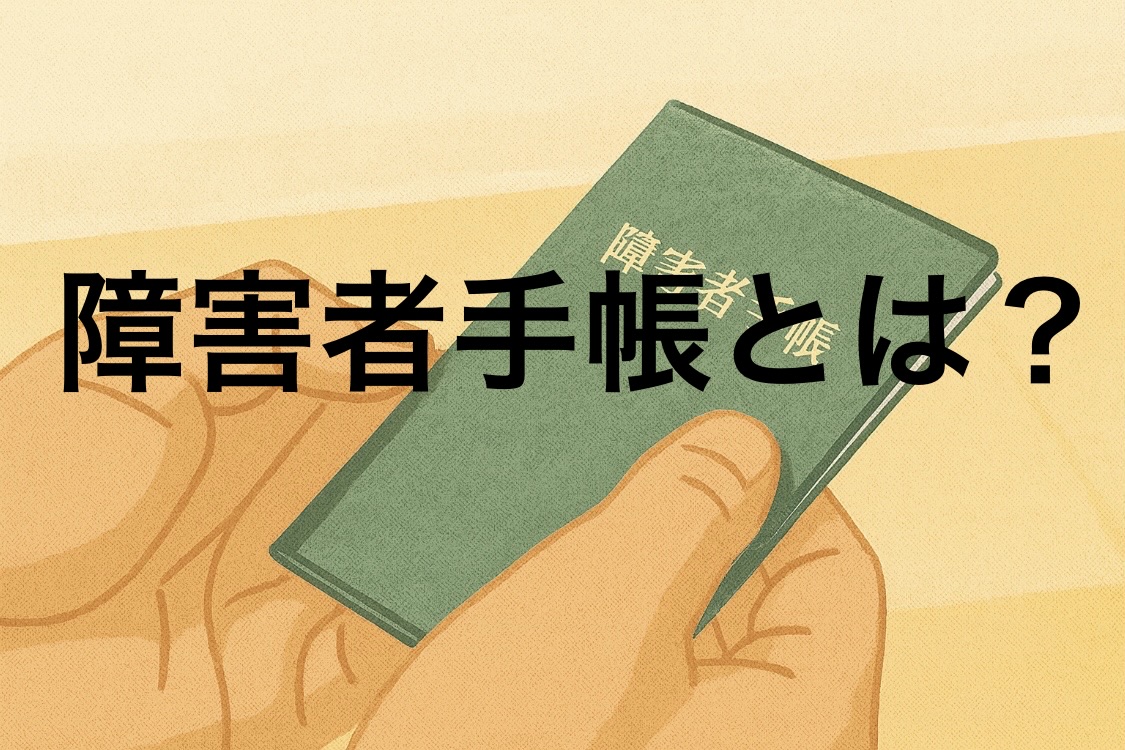
この記事では、障害者手帳について、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門職へご相 […]
続きを読む 障害者手帳とは?種類・取得方法・メリットをわかりやすく解説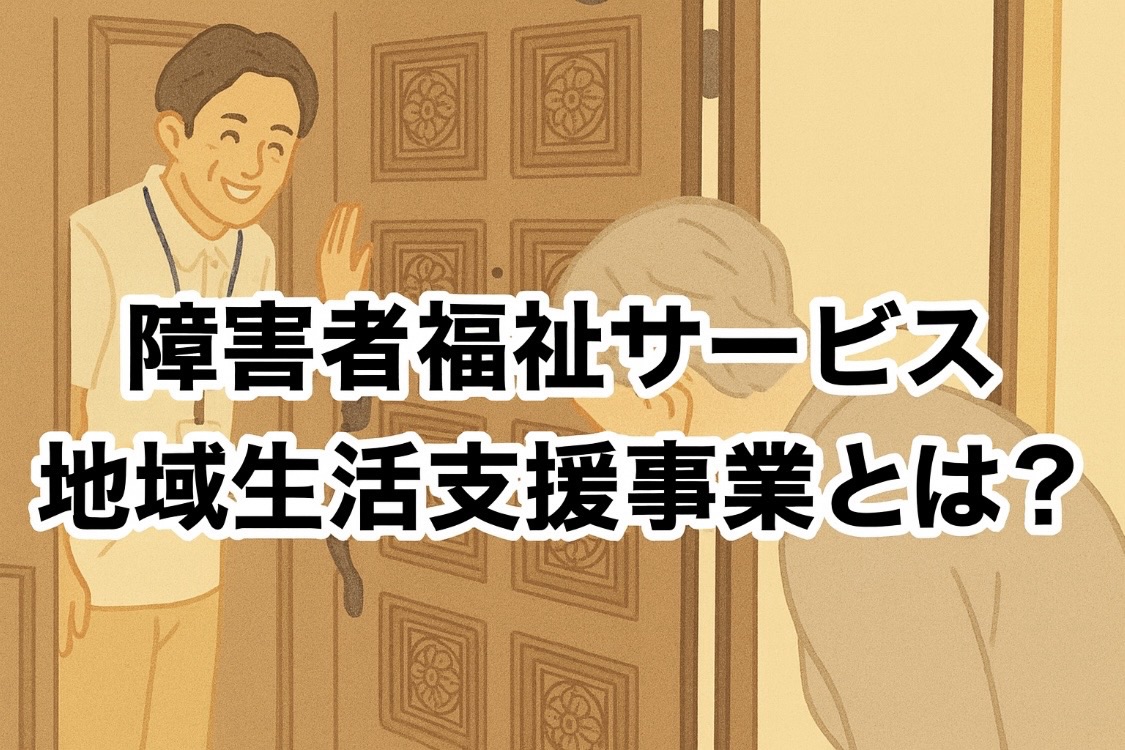
この記事では、障害者福祉サービスについて、制度の目的や仕組み、利用の流れを一般の方にも分かりやすく整理して解説します。 福祉制度は自治体ごとに運用が異なる場合があるため、実際の利用にあたっては、必ずお住まいの自治体や専門 […]
続きを読む 障害者福祉サービスの地域生活支援事業とは? 自治体が行う身近な福祉支援をわかりやすく解説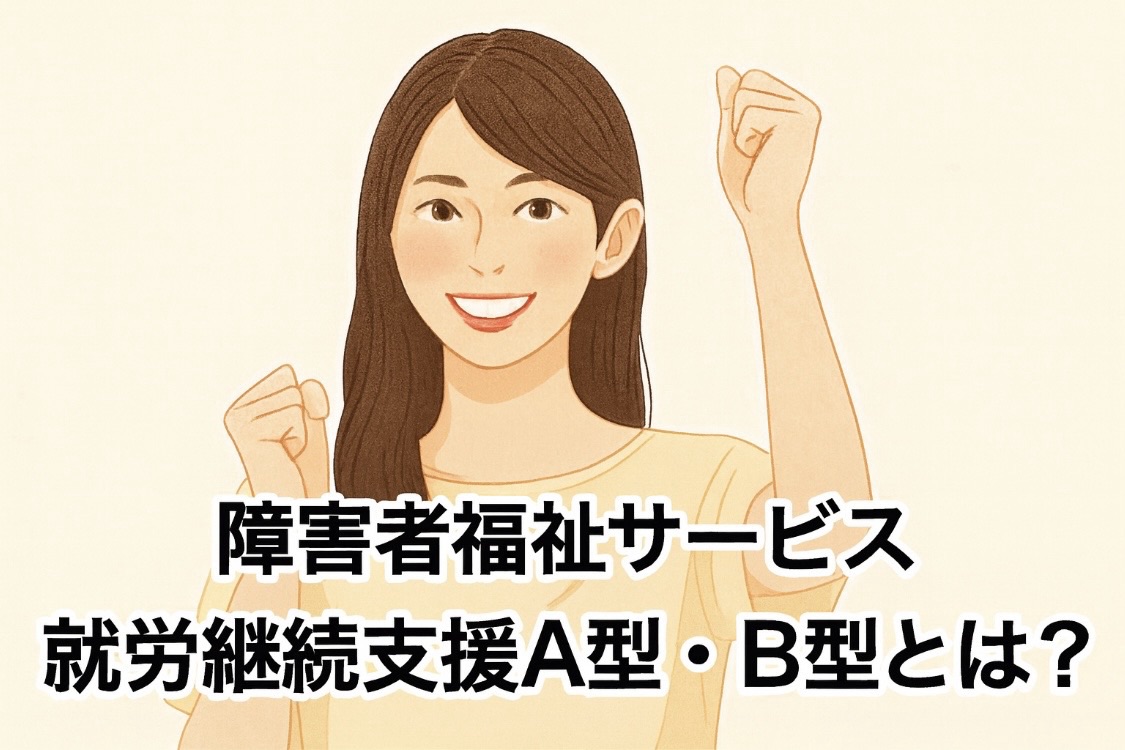
はじめに 障害のある人が「働きたい」という気持ちを実現するための仕組みとして、非常に重要なのが 就労継続支援A型・B型 です。 どちらも障害者総合支援法に基づく福祉サービスですが、働き方・契約・求められる能力・収入などが […]
続きを読む 障害者福祉サービスの就労継続支援A型とB型とは? 雇用契約の違いから見る「働く支援」の役割を徹底解説
はじめに 就労移行支援(しゅうろういこうしえん)は、障害のある人が一般企業での就職をめざすために必要な力を身につけるための福祉サービスです。 「働きたいけれど、自信がない」 「ブランクがあって仕事を続けられるか心配」 「 […]
続きを読む 障害者福祉サービスの就労移行支援とは? 一般企業で働きたい人の就職準備をサポートする支援をわかりやすく解説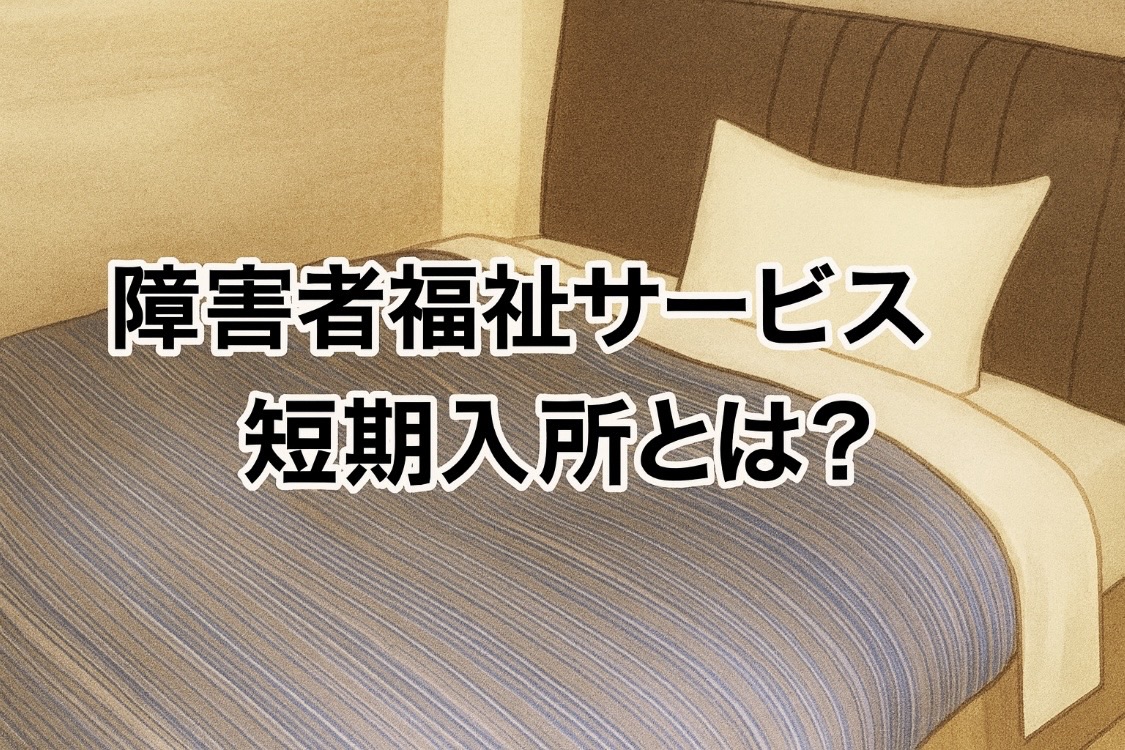
はじめに 短期入所(ショートステイ)は、自宅で生活する障害のある人が、短期間だけ施設に宿泊しながら必要な支援を受けられる障害者福祉サービスです。 家族のレスパイト(休息)や、本人の生活スキル向上・環境調整などさまざまな目 […]
続きを読む 障害者福祉サービスの短期入所(ショートステイ)とは? 役割・利用の流れ・支援内容をわかりやすく解説