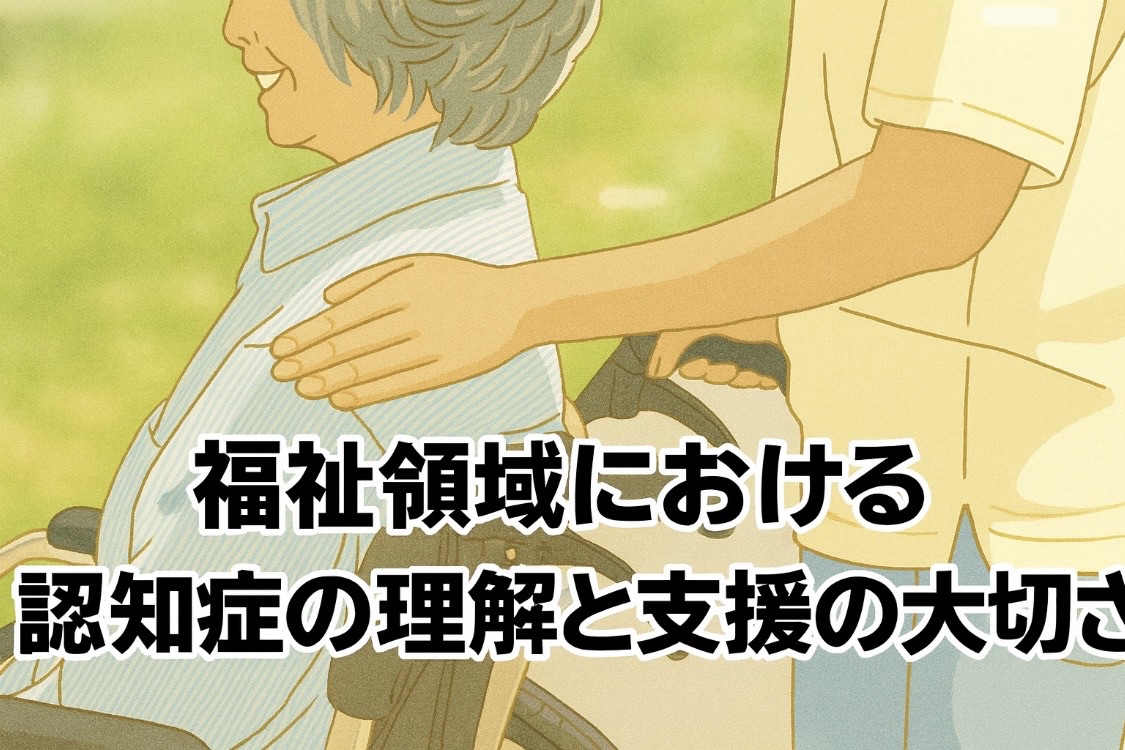
福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜
はじめに 日本では高齢化が加速し、認知症の人は年々増え続けています。 家族の誰かが認知症と診断される、職場の利用者に認知症の症状が見られる──こうした場面は決して特別ではありません。 しかし、認知症は「記憶障害だけの病気 […]
続きを読む 福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです
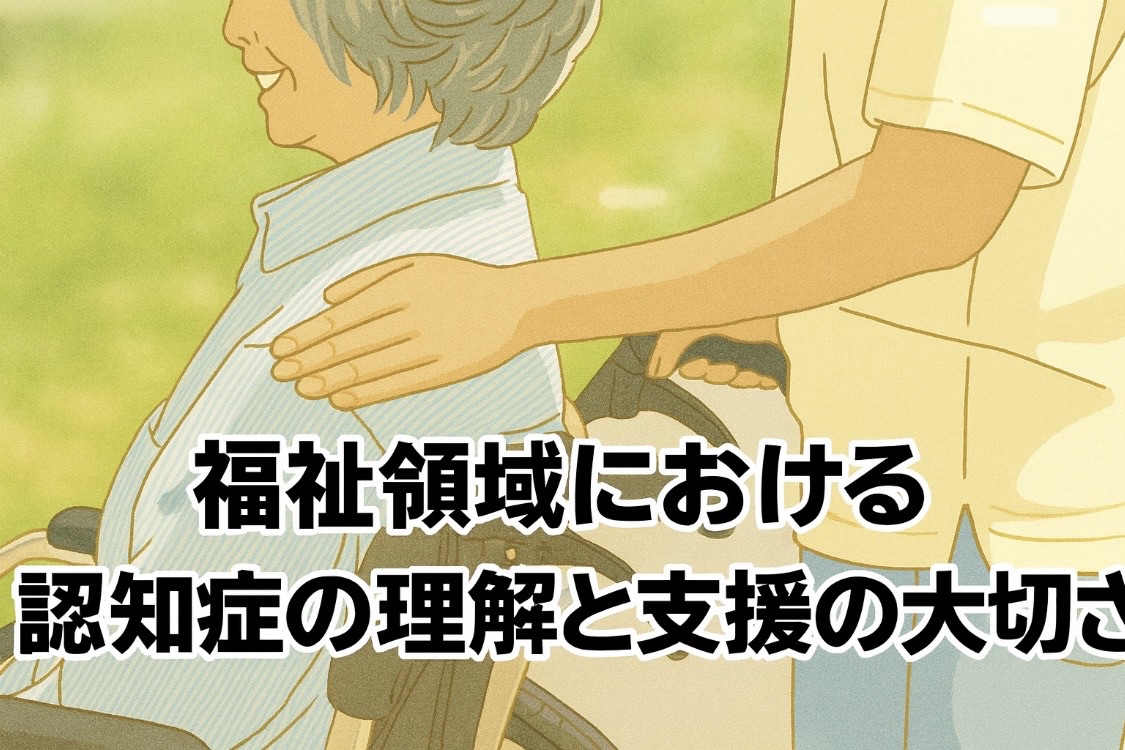
はじめに 日本では高齢化が加速し、認知症の人は年々増え続けています。 家族の誰かが認知症と診断される、職場の利用者に認知症の症状が見られる──こうした場面は決して特別ではありません。 しかし、認知症は「記憶障害だけの病気 […]
続きを読む 福祉領域における認知症の理解と支援の大切さ 〜家族と支援者が知っておきたい基礎知識と向き合い方〜
はじめに 福祉の現場では、「支援」だけでなく、本人の権利を守ることが欠かせません。 しかし、 「権利擁護って具体的に何を指すの?」 「どんな制度があるの?」 と疑問を持つ人も多いかもしれません。 この記事では、福祉におけ […]
続きを読む 福祉における権利擁護とは?わかりやすく解説 仕組み・制度・現場の課題まで徹底解説
はじめに 「人間関係で同じ失敗を繰り返す」 「必要以上に自分を責めてしまう」 「断られることが極端に怖い」——。 このような感覚を抱いた経験はありませんか? その背景には、子どもの頃の経験が今の自分に影響している心の仕組 […]
続きを読む インナーチャイルドとアダルトチルドレンとは? 心の傷と向き合うための基礎知識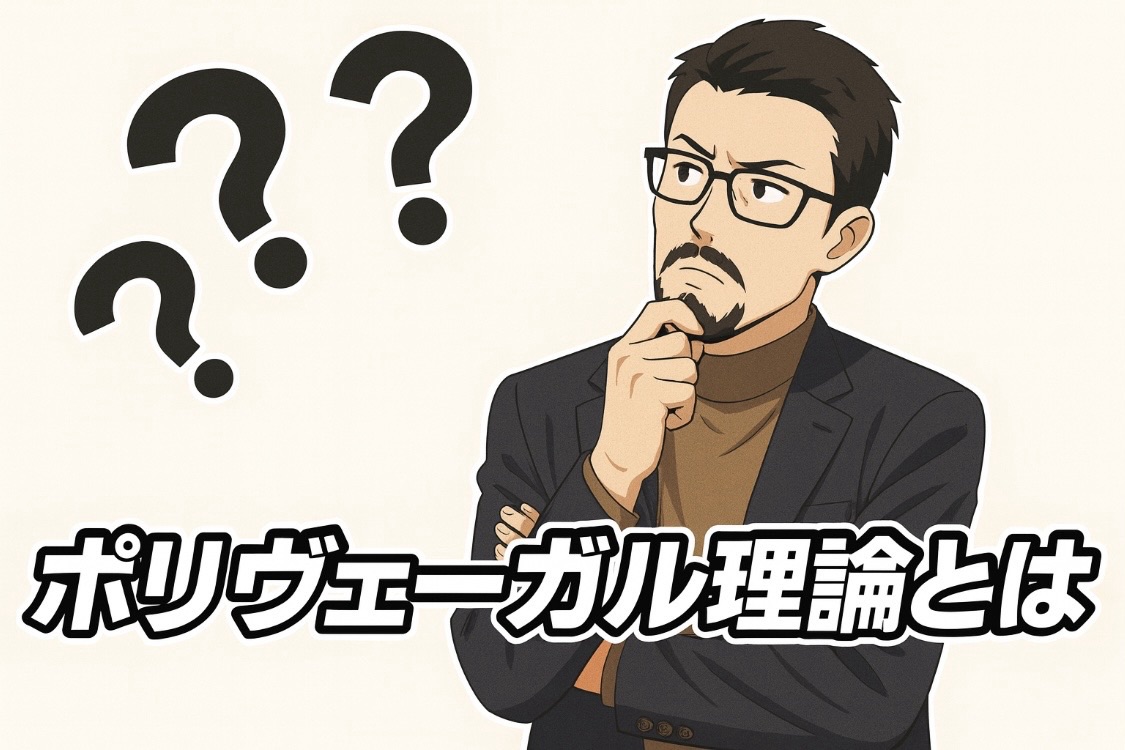
はじめに 「急に体が強張る」 「気持ちは落ち着きたいのに、呼吸が浅くなる」 こうした体の反応は、決して気のせいではありません。 私たちの体は、外の刺激やストレスに対して常に反応し、 その結果として「緊張」「安心」「疲労」 […]
続きを読む ポリヴェーガル理論とは?〜こころと体の安全を理解する新しい視点〜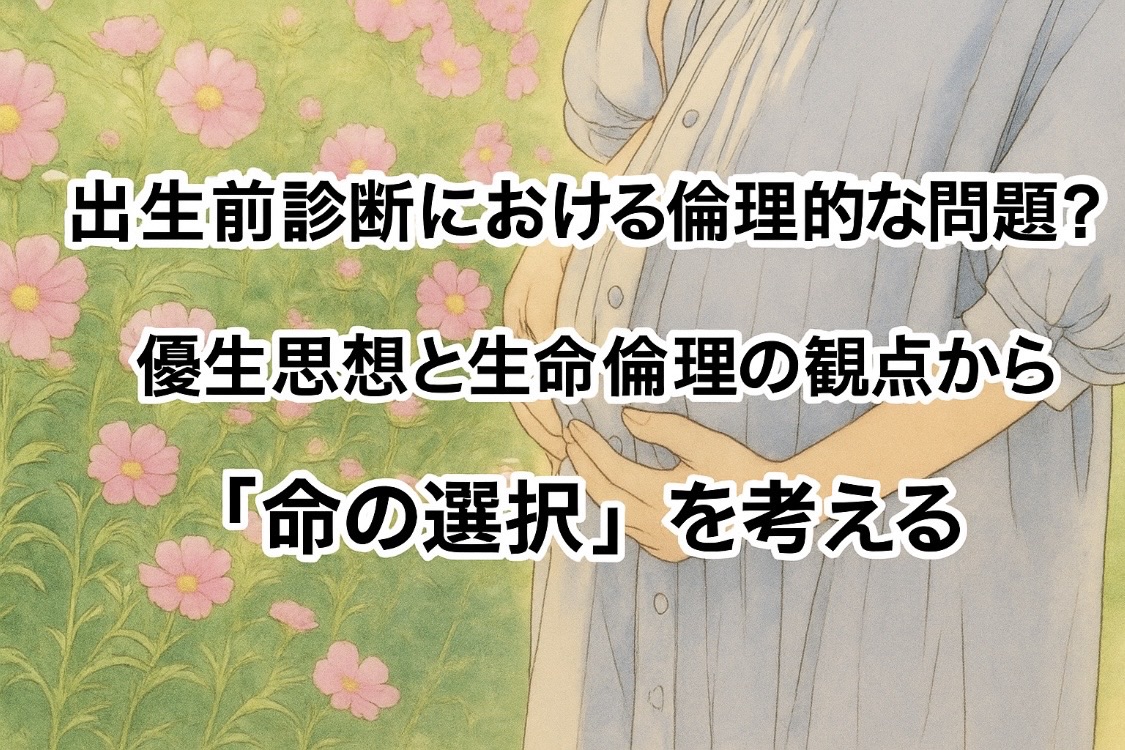
はじめに 出生前診断は、妊娠中の赤ちゃんの状態を詳しく知ることができる医療技術として注目されています。 一方で、この検査は 命をどう受け止めるか”という根源的な問いを突きつけるため、医療・当事者・社会の間で議論が続いてい […]
続きを読む 出生前診断における倫理的な問題とは? ― 優生思想と生命倫理の観点から「いのちの選択」を考える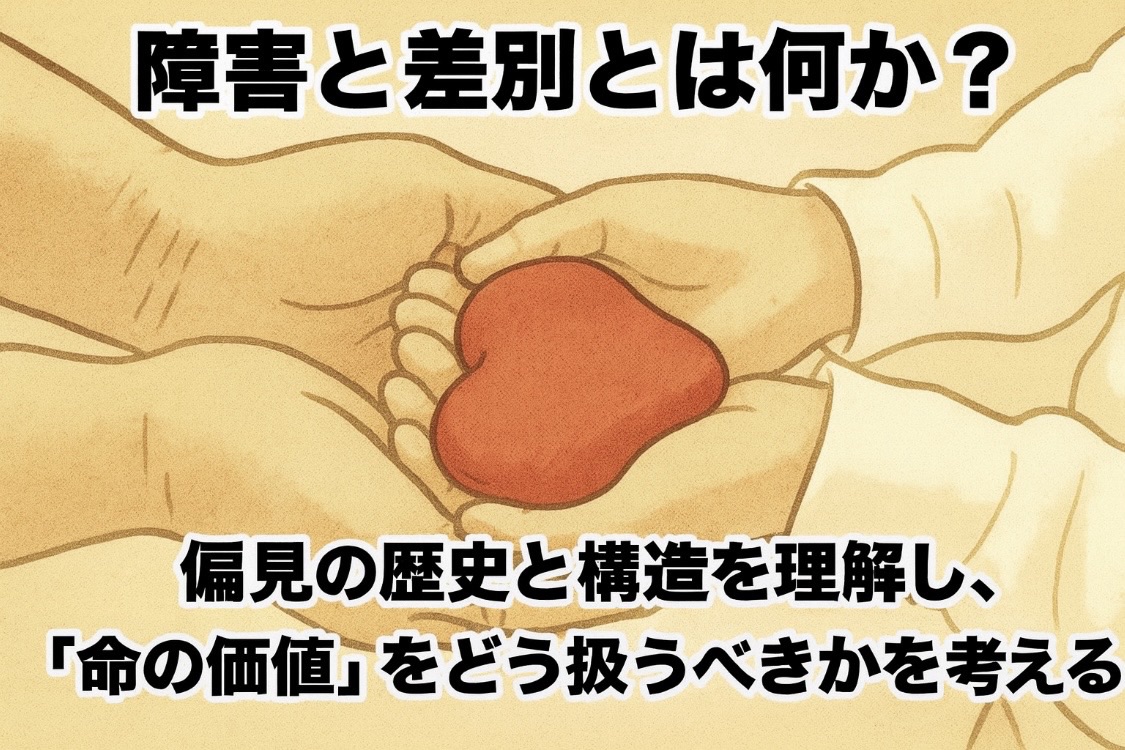
はじめに 優生思想と生命倫理から読み解く現代社会の課題 現代社会は「共生」「多様性」「インクルージョン」といった言葉が広がりつつあります。 しかし、障害のある人が日常生活で直面する差別や偏見は、決して過去の話ではありませ […]
続きを読む 障害と差別とは何か? 偏見の歴史と構造を理解し、「命の価値」をどう扱うべきかを考える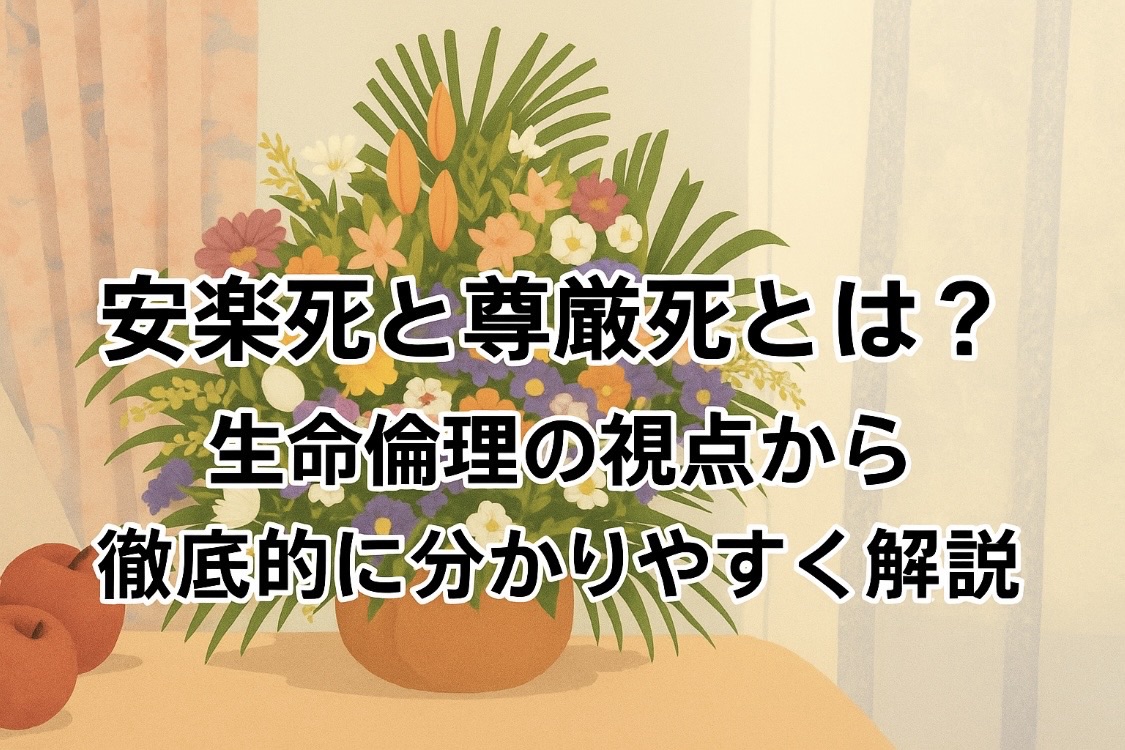
はじめに 近年、安楽死や尊厳死といった言葉が、ニュースやドラマ、SNSなど、さまざまな場面で取り上げられるようになりました。 医療技術が高度化し、延命治療が可能になった一方で、「苦痛を抱えながら生き続けることが本人にとっ […]
続きを読む 安楽死と尊厳死とは? 生命倫理の視点から徹底的にわかりやすく解説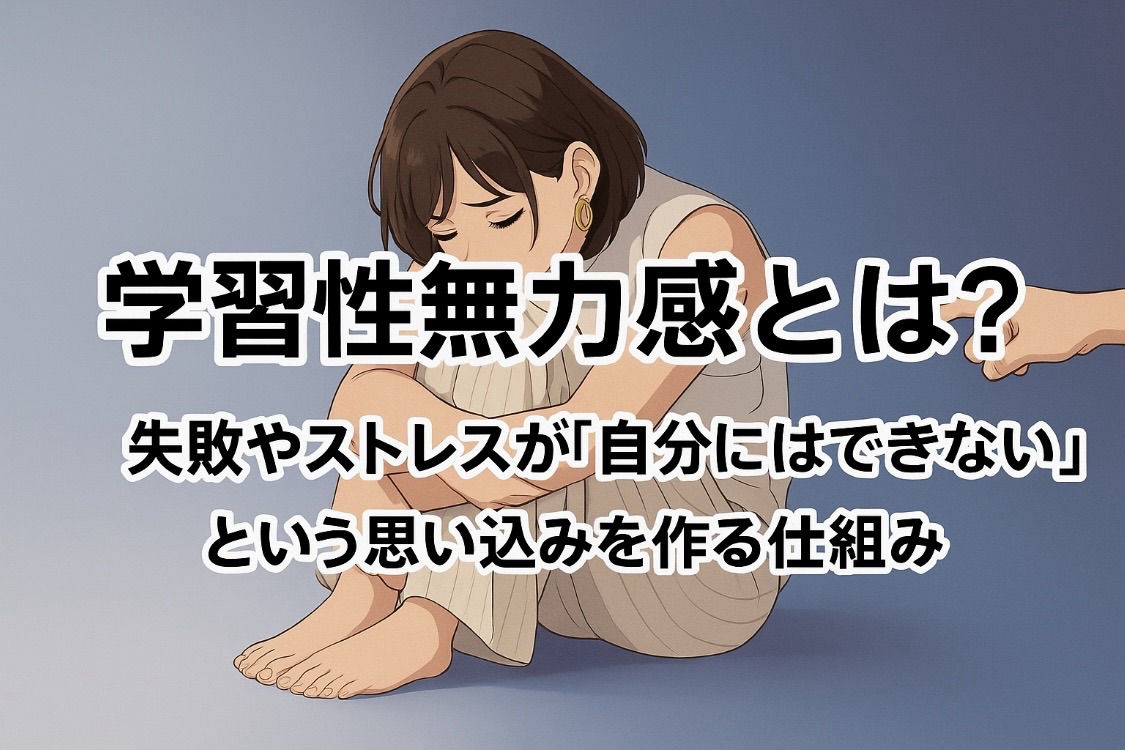
はじめに 「どうせやっても変わらない」 「もう頑張り方がわからない」 「挑戦したいのに、体が動かない」 日常の中で、こんな気持ちになることはありませんか? それは、努力不足でも、性格の弱さでもありません。 心理学では、そ […]
続きを読む 学習性無力感とは?〜失敗やストレスが「自分にはできない」という思い込みをつくる仕組み〜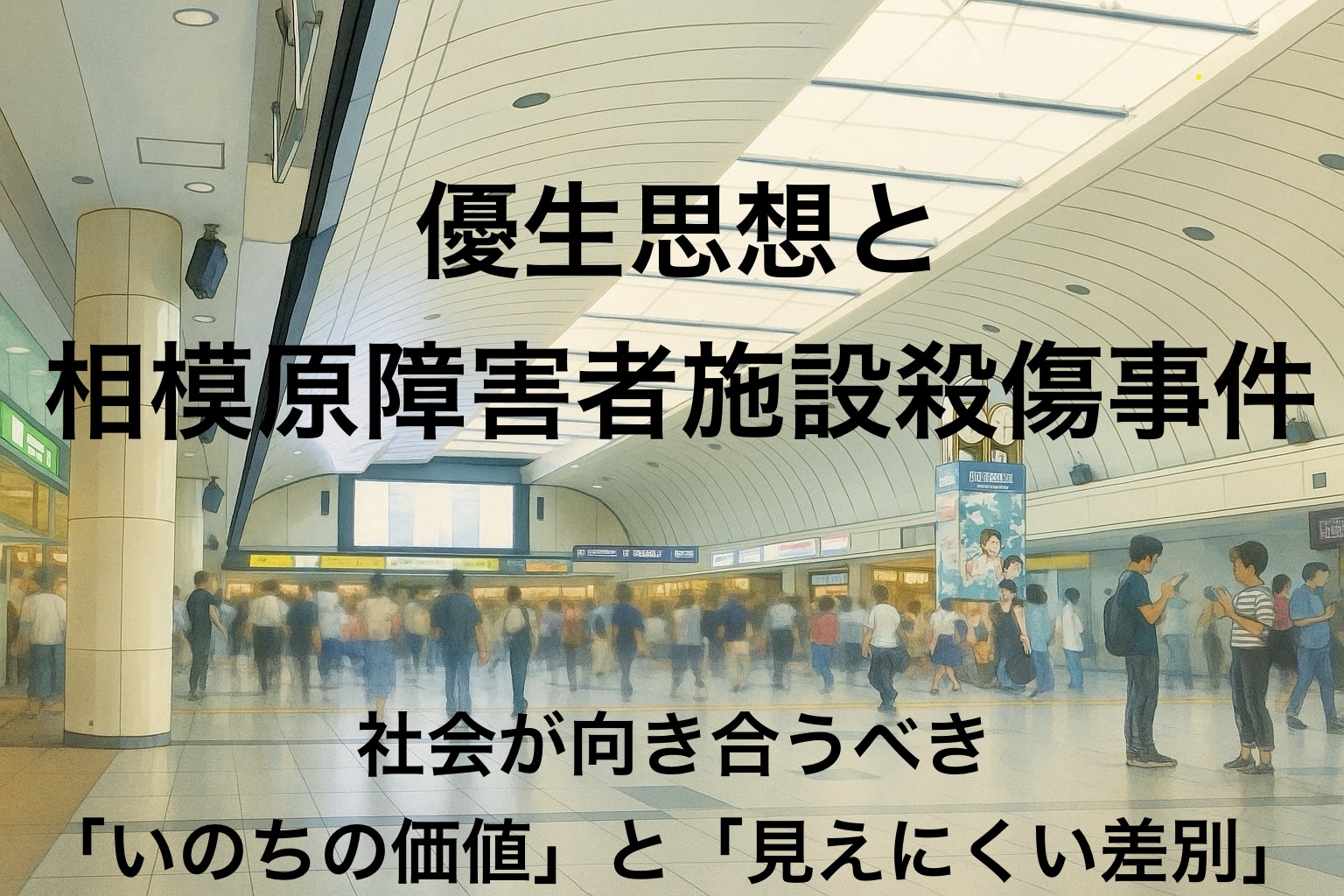
はじめに 2016年7月、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で起こった殺傷事件(相模原障害者施設殺傷事件)は、19名の尊い命が奪われ、26名以上が負傷した日本の戦後最悪の大量殺人事件として深く刻まれています […]
続きを読む 優生思想と相模原障害者施設殺傷事件 〜社会が向き合うべき「いのちの価値」と「見えにくい差別」〜
はじめに 心はいつも頑張っている 人付き合いや仕事、家族との関わり、健康の不安、将来の心配…。 私たちは生活の中で、言葉にならないストレスや不安と向き合う場面がたくさんあります。 そんなとき、心は黙って負担を受けるわけで […]
続きを読む 防衛機制とその種類を分かりやすく解説 〜心理学の知識を身につけて人間関係やストレスに対処する〜