
てんかん発作ってなに?基礎知識と語源に隠された歴史
はじめに てんかんという言葉を聞いたことはありますでしょうか? てんかん以外に、発作、てんかん発作、などと呼ばれたりすることもあります。 これは脳の神経が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作が繰り返される病気で、世界 […]
続きを読む てんかん発作ってなに?基礎知識と語源に隠された歴史本サイトは福祉の現場経験者が一般の方・家族・支援者向けに障害福祉をわかりやすく解説する情報メディアです

はじめに てんかんという言葉を聞いたことはありますでしょうか? てんかん以外に、発作、てんかん発作、などと呼ばれたりすることもあります。 これは脳の神経が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作が繰り返される病気で、世界 […]
続きを読む てんかん発作ってなに?基礎知識と語源に隠された歴史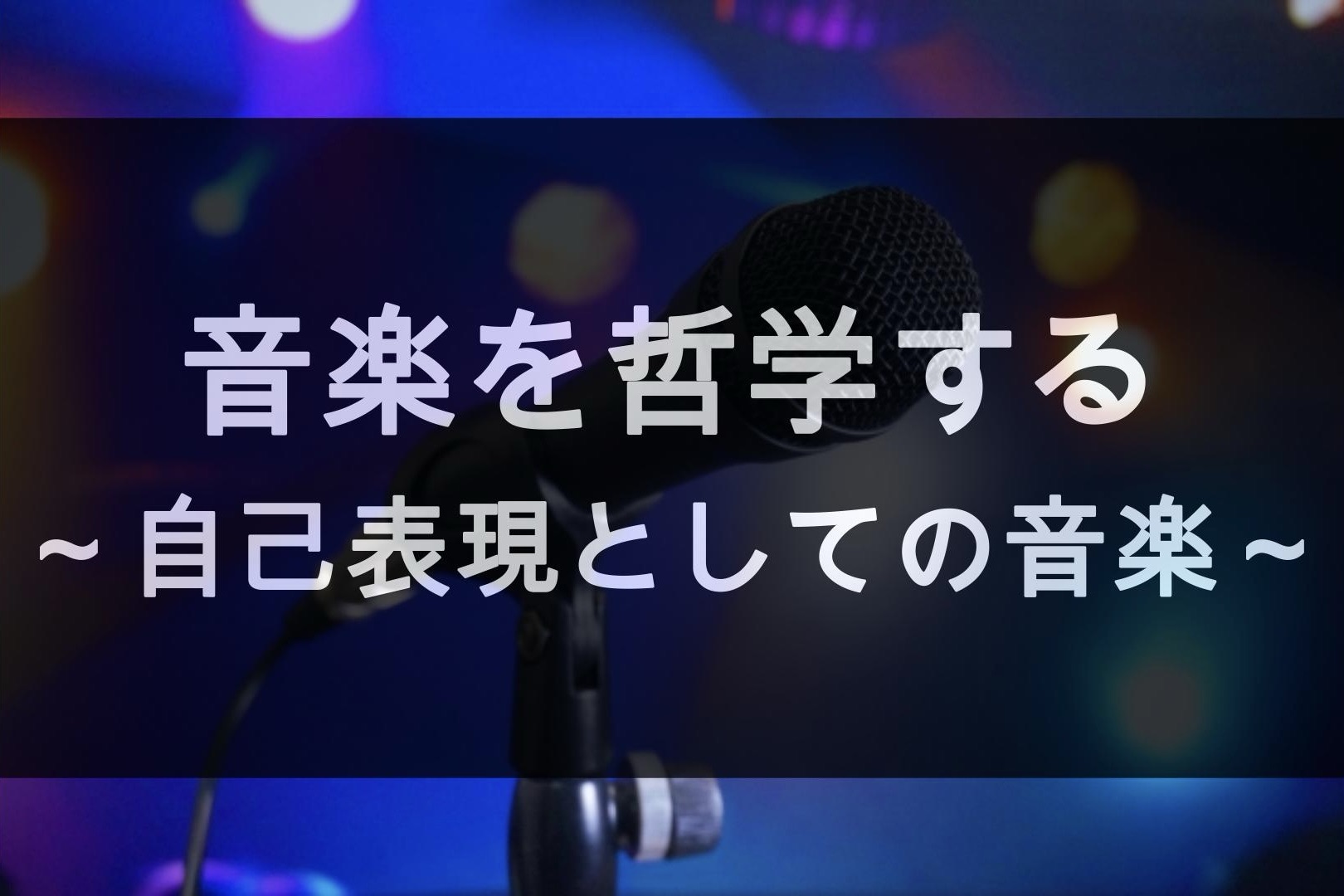
私は大学時代、文学部哲学科の専攻で、ギリシャ哲学や生命倫理などを中心に学ぶことが多かったです。今回はそこで学んだことをまとめた論文『音楽を哲学する 〜自己表現としての音楽〜』を取り上げさせて頂きます。 3万字を超える論 […]
続きを読む 『音楽を哲学する 〜自己表現としての音楽〜』
ダウン症とは? ダウン症(ダウン症候群)とは、21番目の染色体が通常より1本多く存在すること(21トリソミー)によって起こる先天的な特徴です。 日本では約700〜800人に1人の割合で生まれるといわれています。医学的には […]
続きを読む ダウン症支援の奥義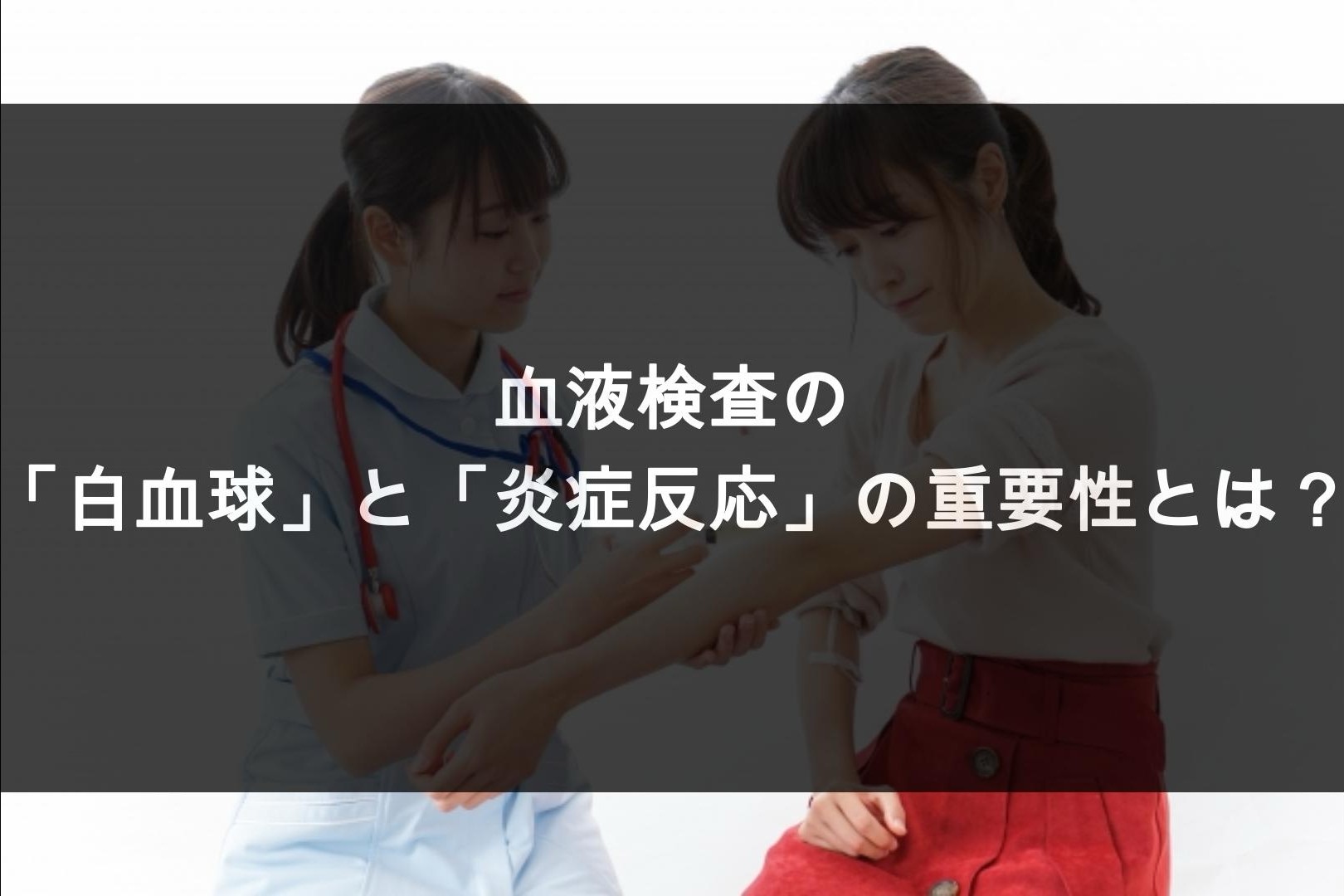
はじめに 福祉の現場では、利用者さんの健康状態を日々観察することがとても大切です。その中でも、病院で行われる「血液検査」の結果を理解することは、体調変化にいち早く気づくための重要な手がかりになります。特に「白血球数(WB […]
続きを読む 血液検査の「白血球」と「炎症反応」の重要性とは?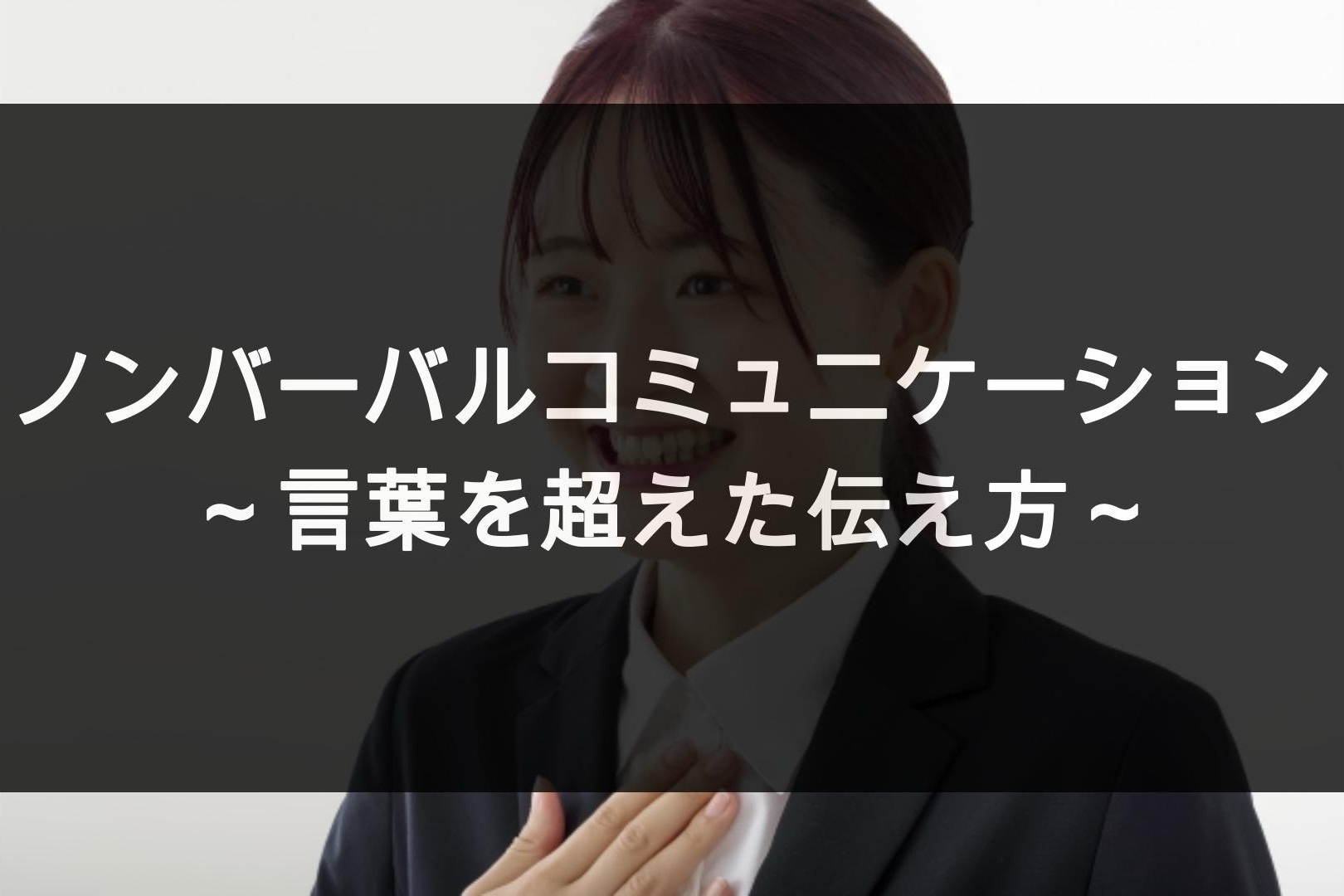
はじめに 今回は「ノンバーバルコミュニケーション」についてご紹介します。 人は言葉だけでなく、身振りや表情などさまざまな方法で気持ちを伝えています。ノンバーバルコミュニケーションについて理解しておくと、福祉だけではなく、 […]
続きを読む ノンバーバルコミュニケーション 〜言葉を超えた伝え方〜
はじめに 仕事や生活、そしてネットの中で、 「自律神経が乱れている」 「自律神経失調症」 「交感神経が高ぶっている」 などといった言葉を聞いたことはありませんか? 今回の記事は、日常生活に深く関わっている自律神経について […]
続きを読む 自律神経について 〜交感神経と副交感神経の切り替えのコツ〜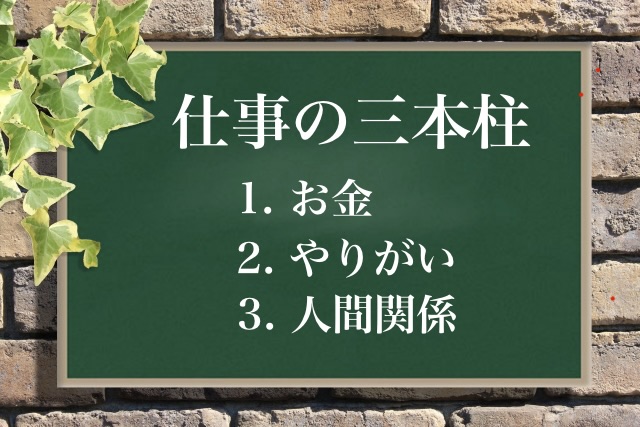
はじめに 私たちが働くとき、その根底にある問いは「何のために働くのか」ということです。単に生活を支えるだけではなく、やりがいを感じ、自分の居場所を持ち、人とのつながりを築くことも大切です。 なかでも、「お金」「やりがい」 […]
続きを読む 仕事の三本柱「お金・やりがい・人間関係」とは?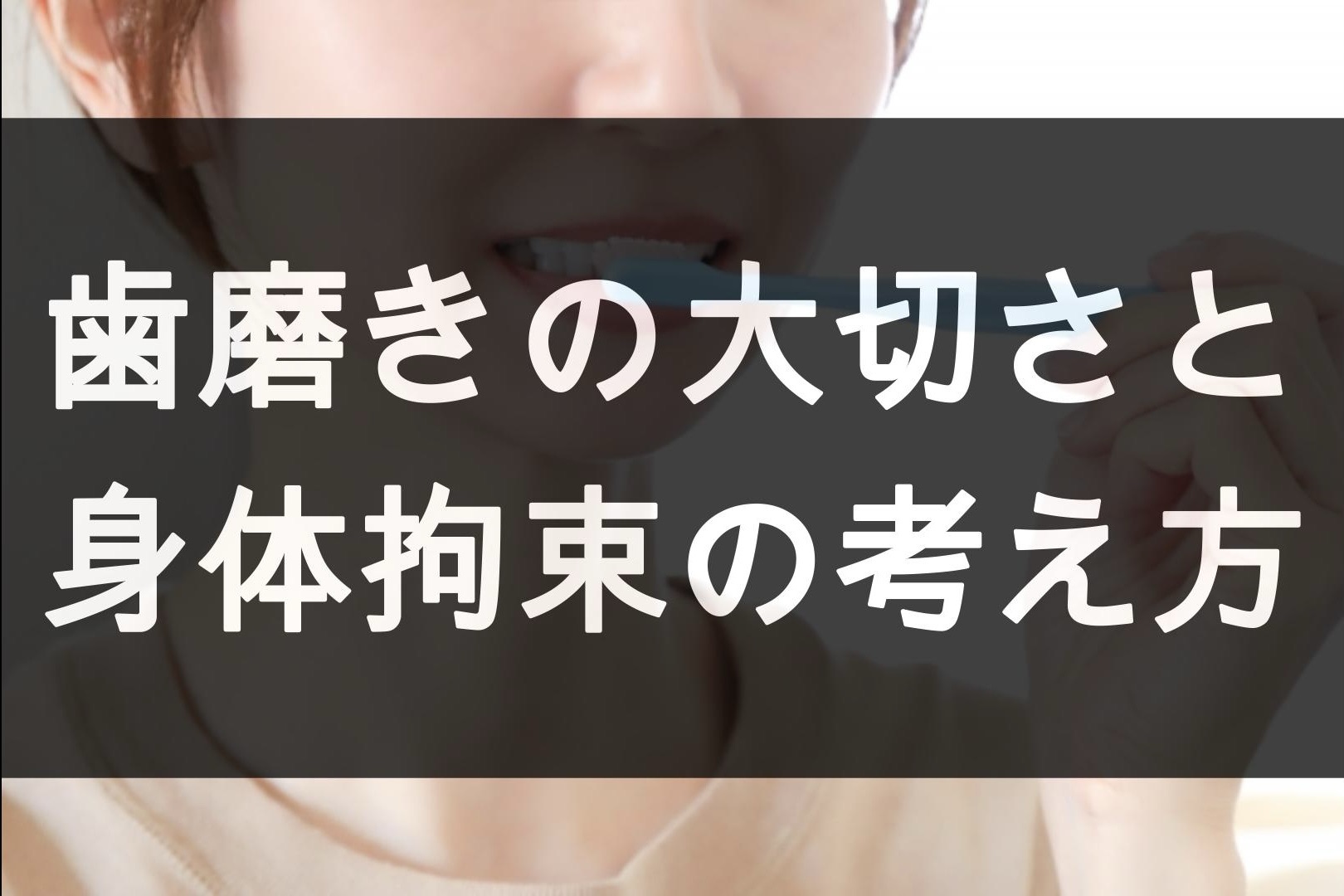
はじめに 「歯を磨くことなんて、毎日の当たり前の習慣」と思っていませんか? 私自身もそう思っていましたが、歯医者さんに行ってみると意外な虫歯の数に驚かされた経験があります。さらに、福祉の現場で出会った障害のある方の歯磨き […]
続きを読む 歯磨きの大切さと身体拘束の考え方
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 心技体の体について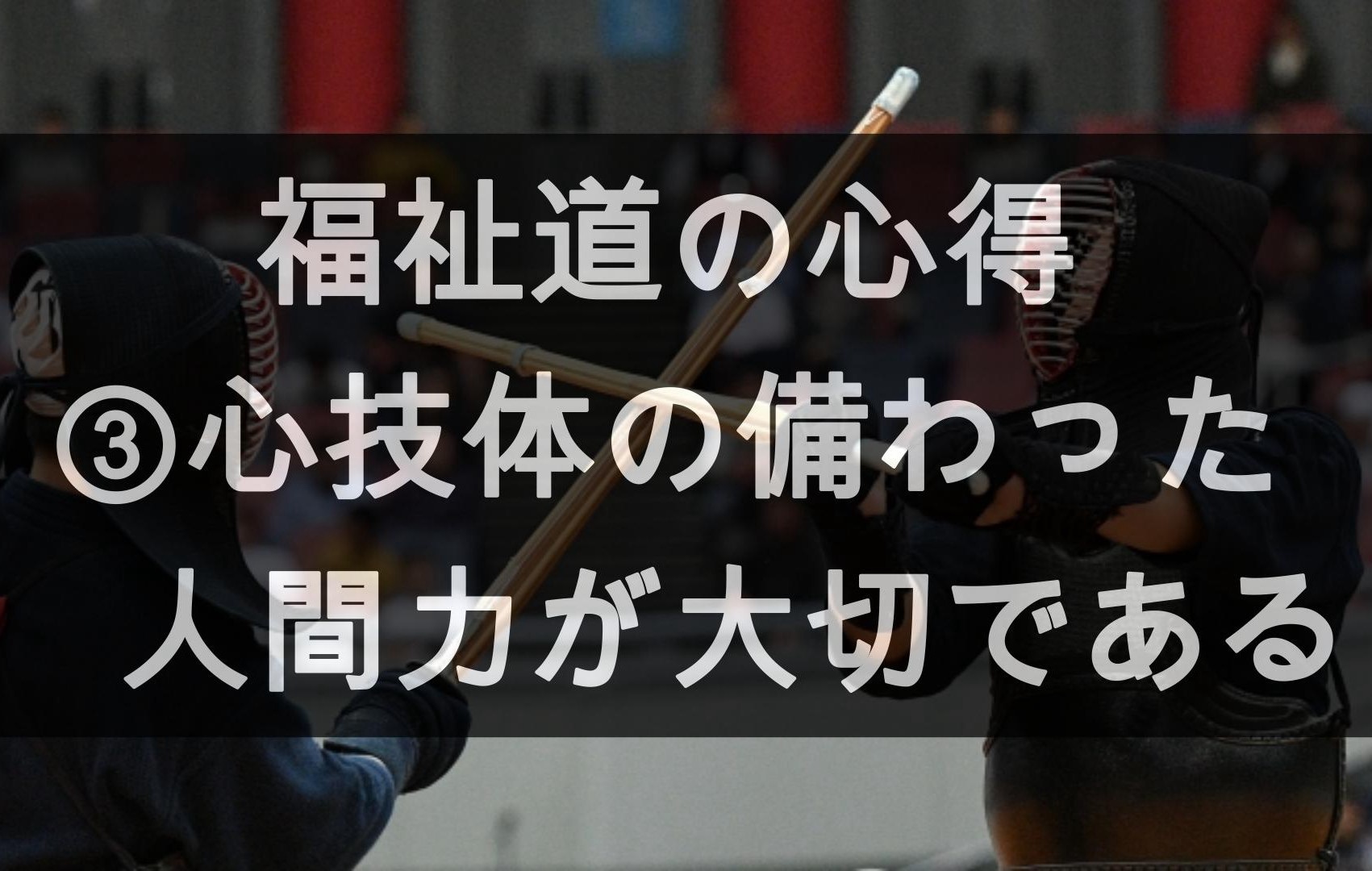
はじめに ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。 ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思ってい […]
続きを読む 福祉道の心得③「心技体の備わった人間力が大切である」