自閉症とは?
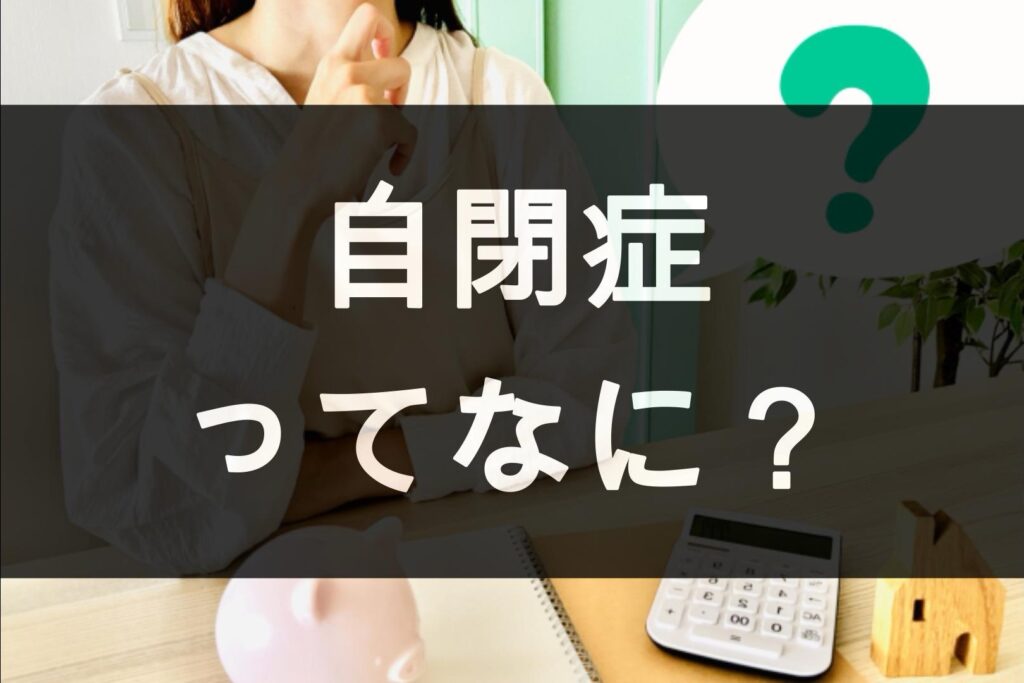
自閉症(自閉スペクトラム症:ASD)とは、発達障害の特性のひとつであり、 人とのコミュニケーションや社会的な関わり方、行動や興味の偏り に特徴が見られます。かつては「自閉症」「アスペルガー症候群」などと分けて呼ばれていましたが、現在は「自閉スペクトラム症」として幅広い特性を含む概念で障害が理解されています。
既にネットや本などで自閉症に関する様々な情報を得ることが出来ますので、今回は私が経験した事例をもとに編み出した行動理論をご紹介したいと思います。
鎖の法則 〜行動と行動とが鎖のように繋がっている〜
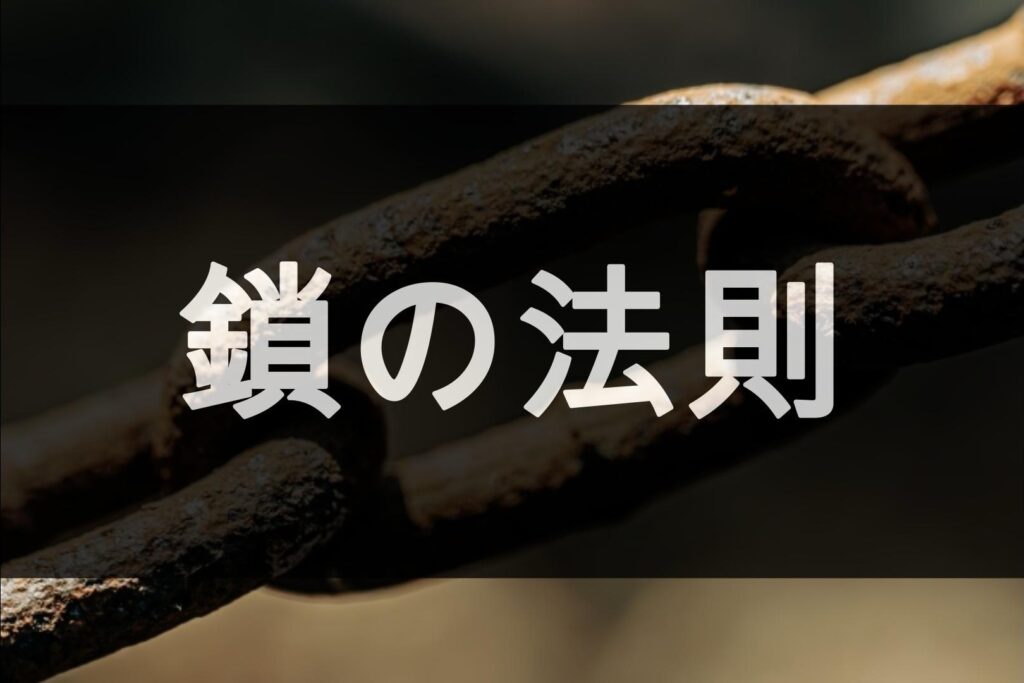
一般的に健常者と呼ばれる人においては、思考や行動にバリエーションがあります。
どういうことかというと…
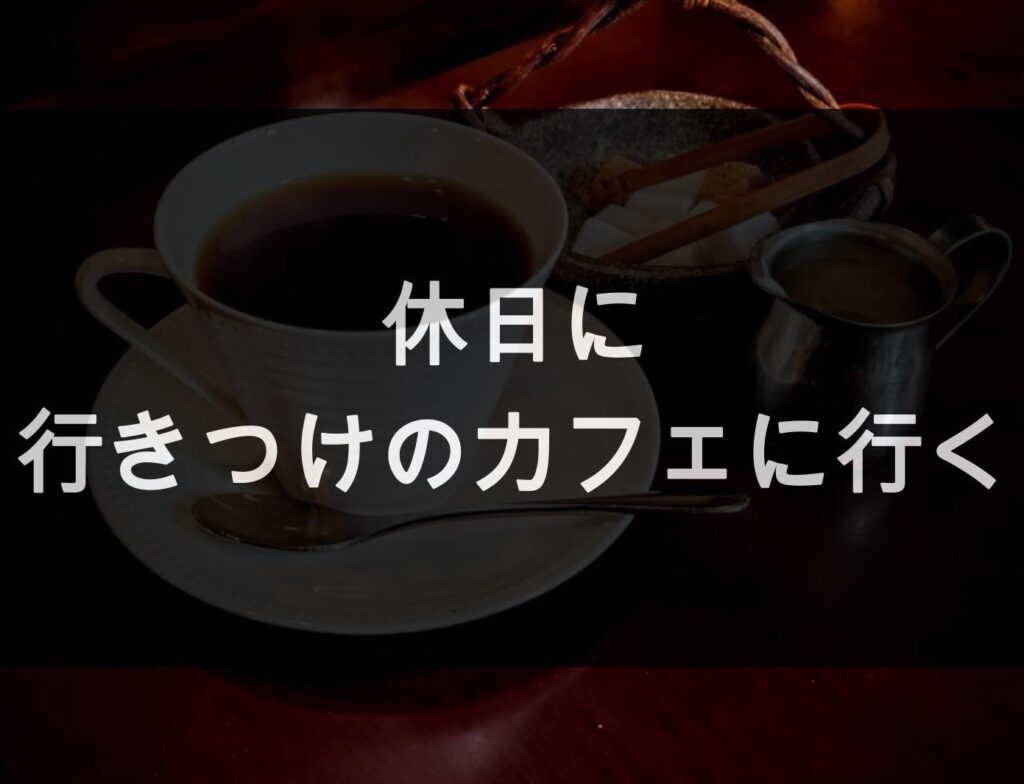
例えば、休日に行きつけのカフェに行こうとしているところをイメージしてみてください。
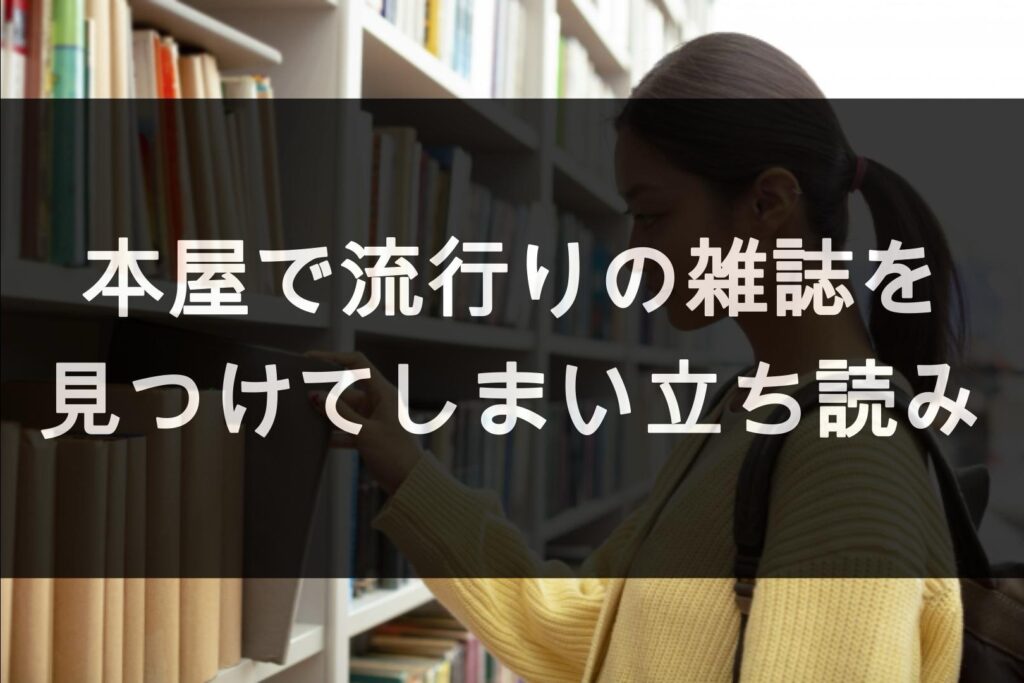
しかし、その道中、本屋で流行りの雑誌を見つけてしまい、10分ほど立ち読みをした後にカフェに向かいました。
このようなケースは、一般的には何の変哲もない「よくあること」と考えられがちです。
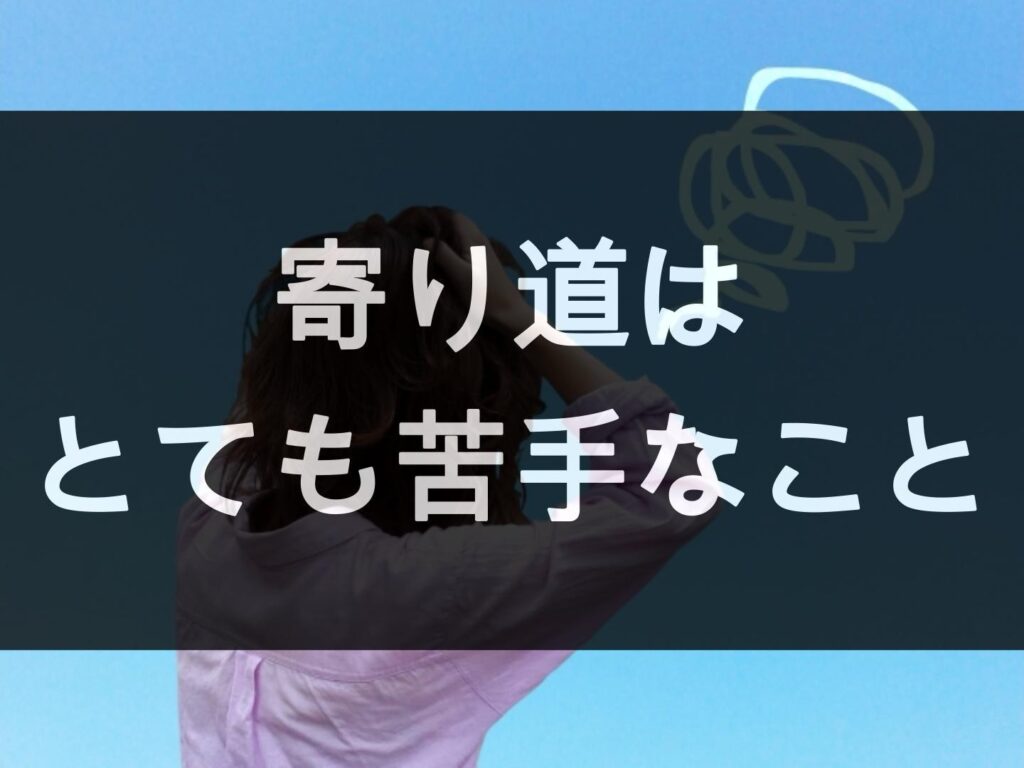
ところが、自閉症もしくは自閉的傾向の強い方にとっては「立ち読みをした」という“寄り道”はとても苦手なことなのです。
そのような本人の日常的に行われる行動の特徴は、「特定の行動をしたと同時に次の行動も決定される」ということなのです。
例えば、今度は、ご家族が利用者さんを車で作業所に送られてきた状況をイメージしてみてください。
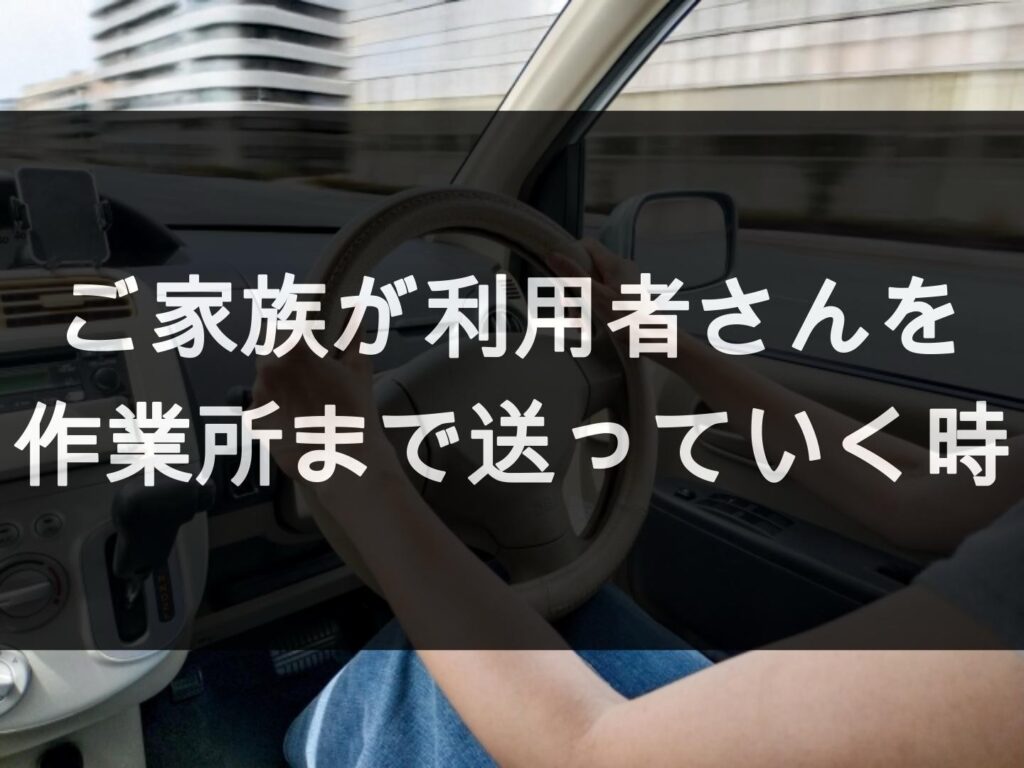
①車を作業所の駐車場に止めると、右後部座席に座っている利用者さんは必ず右後ろのドアを開けて車から降ります。
②玄関で外靴から上履きに履き替え、手を消毒してから作業部屋に入ります。
③鞄をロッカーに入れます。
④ハンガーに帽子と上着(季節に応じて)をかけます。
⑤ロッカーにある鞄からタオルを取り出して首に巻きます。
⑥一旦、ソファに座ります。
⑦お茶を取りに行きます。
⑧ソファに座ってからお茶を飲みます。
⑨お茶を飲み終えたらシンクに空のコップを置きに行きます。
⑩ソファに座ります。
ここまでが利用者さんの一連の行動で、この順番は狂うことなく毎日完璧に繰り返されています。
「①―②―③―④―⑤―⑥―⑦―⑧―⑨―⑩」というように、①の行動をしたと同時に②の行動が決定され、②をしたと同時に③が決定され、その後も連鎖的に行動が繋がっていきます。
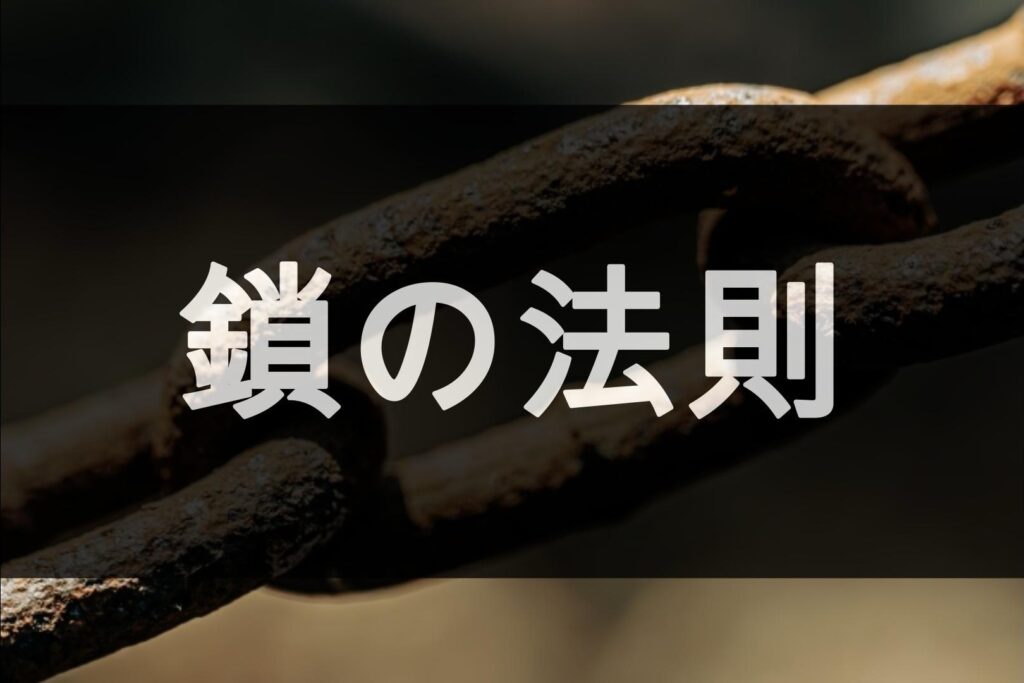
つまりは、まるで鎖のように行動と行動が繋がっているのです。
言い換えると、本人の苦手なことは「行動や思考にバリエーションを持つこと」「自由に選択すること」「想像すること」「変化があること」です。
どういうことかというと…
ロッカーの場所が部屋の外から中に変わった時(ここでいう③)、あるいはコロナ禍に入り感染予防のため玄関で手を消毒することをお願いした時(ここでいう②)に、ピタッと本人の動きが止まり、頭が真っ白になったように困惑する様子が見られました。
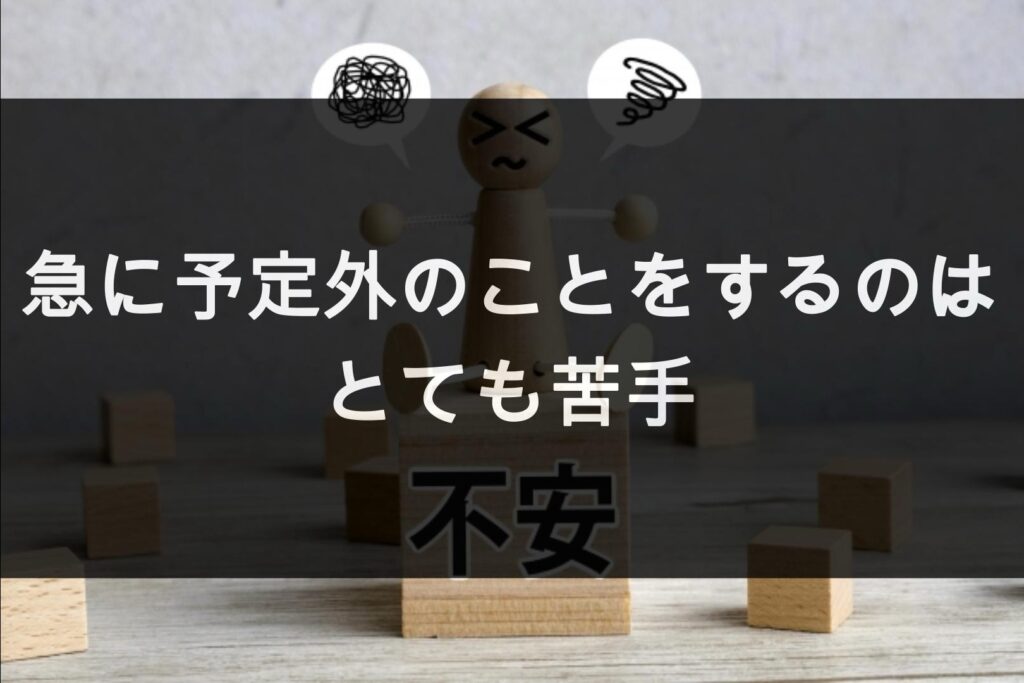
この瞬間こそが、本人が苦手で不安を強く感じる部分なのです。そして頭をリセットするように、はじめの①に戻る行動を取ることがあります。
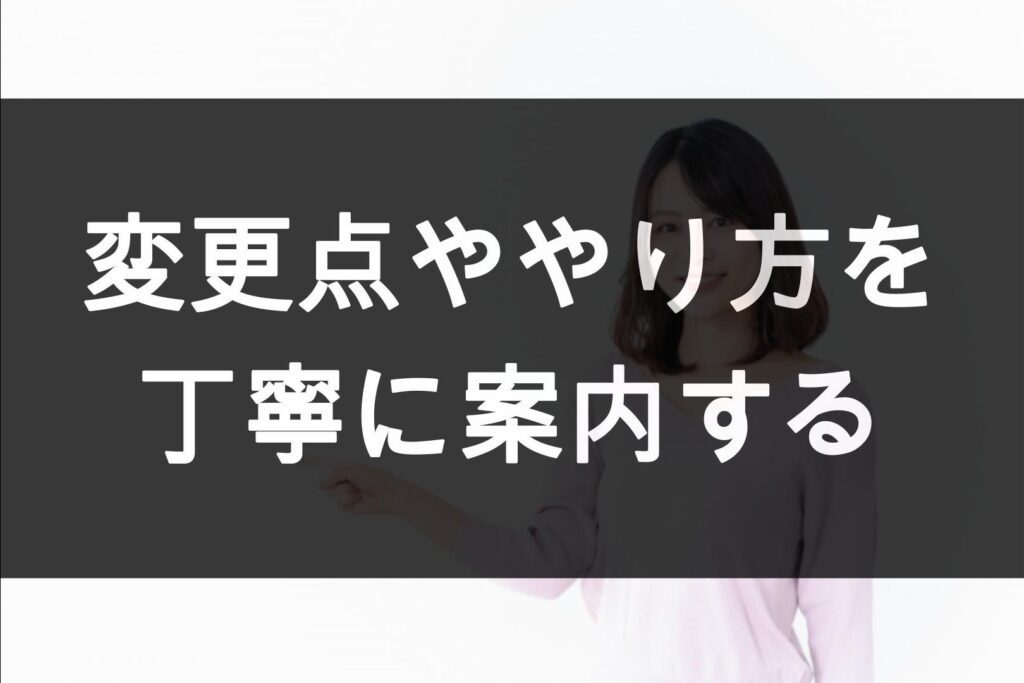
しかし、「今日からロッカーの場所はここに変わりました」や「今日から手の消毒をお願いします」といった具合に、変更点ややり方を丁寧に案内し、それを伝え続けていくと、1週間から1カ月ほど経つ頃には慣れてスムーズに行動できるようになりました。
つまり、「①―②―③―④―⑤―⑥―⑦―⑧―⑨―⑩」という鎖の中に、
「②´」=「消毒をする」という行動の鎖を追加したり、 「新しい③」=「新しいロッカーに鞄を入れる」という行動の鎖に入れ替えるサポート(声かけや指差し)を行ったりすることで、変更への順応が早まり、精神的な負担も軽減されます。
この考え方を活用することで、既存の鎖を組み替えたり、新しい鎖を作ったりすることが可能になります。
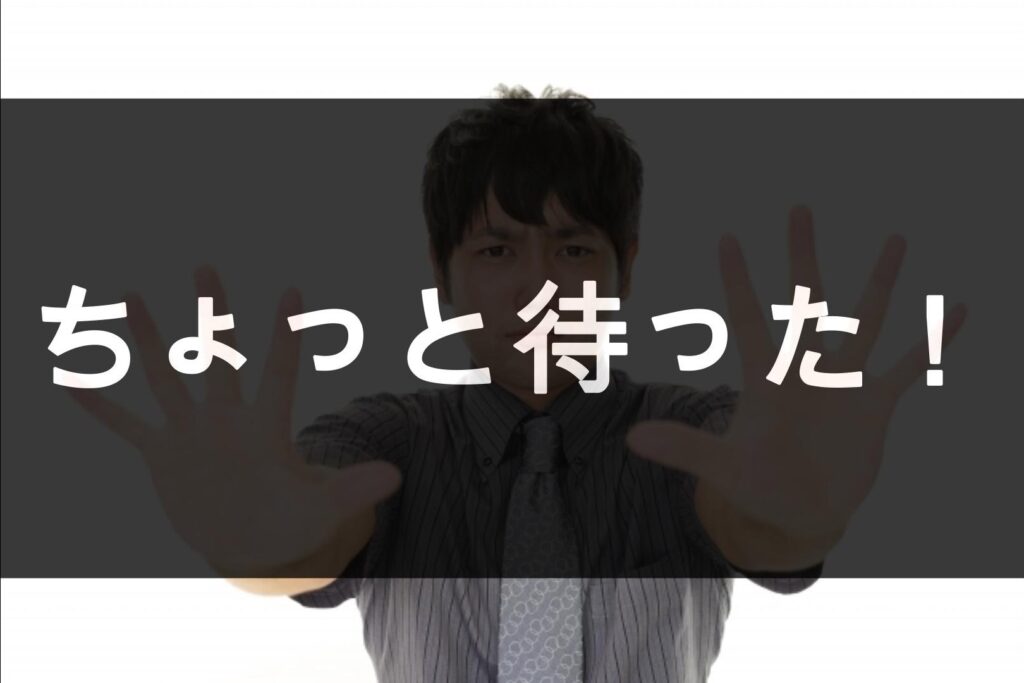
ただし、念頭に置くべきは、この方法を使っても本人にとっては少なからず精神的な負荷が生じるということです。障害の特性上、変化は苦手であるため、日常はできるだけ変化が少ない状態で過ごすことが望ましいです。
しかし、社会生活を送る上ではどうしても変化が伴う場面や、新しいことに挑戦しなければならない場面があります。
そのような場面に積極的に「鎖の法則」を取り入れていくと良いです。
定位置の法則 〜浮き輪があると安心〜
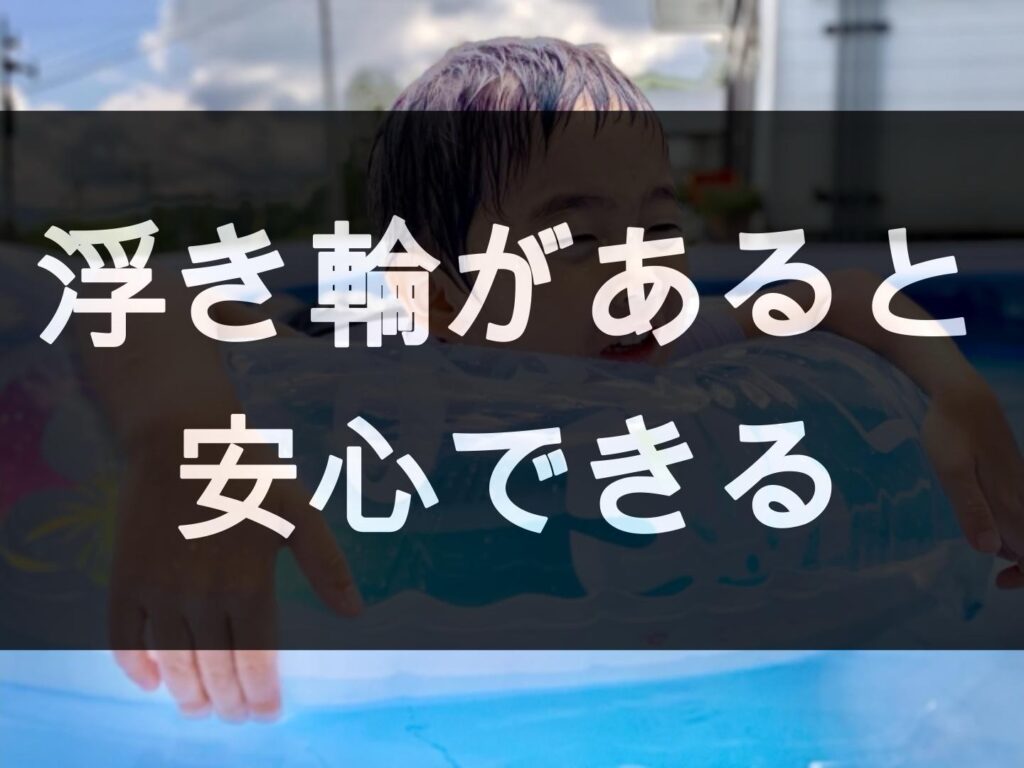
自閉傾向の強い方にとって家で過ごす場所や通所施設で過ごす場所、乗る車の座る場所などといった定位置の有無は非常に重要なことです。
定位置を他の言葉で表すと浮き輪やコックピットとも言えます。そのような特性の強い方は基本的には定位置から柔軟に動くことは苦手であり、定位置が曖昧な状況が続くと心身に大きな負担がかかってしまいます。
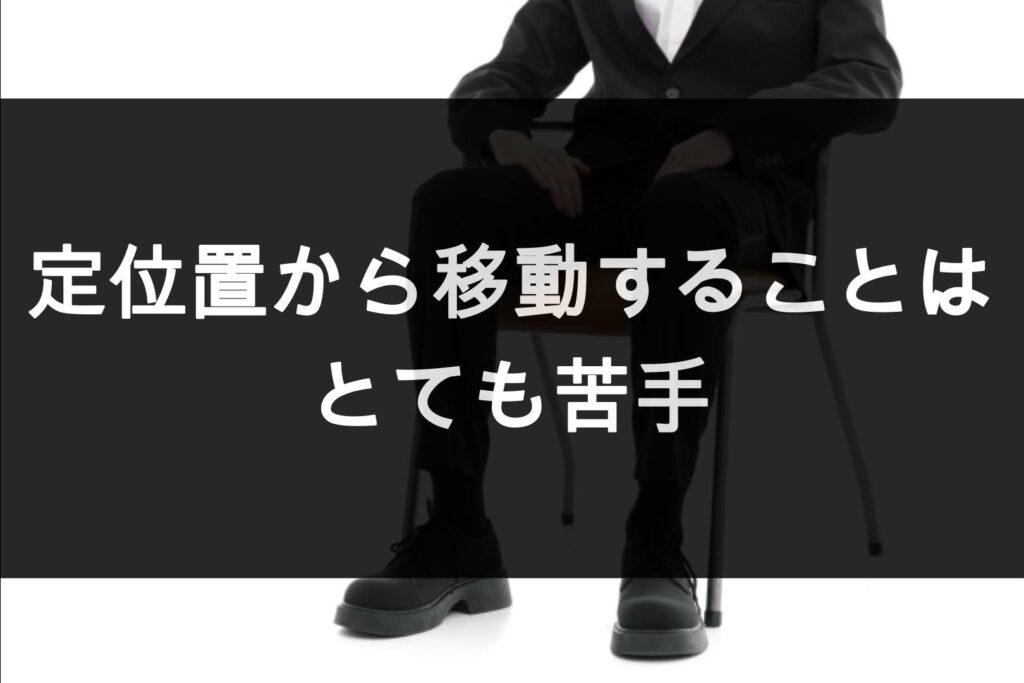
例えば、いつも過ごす部屋の定位置の椅子に座っている利用者さんに別の部屋で作業をするためそこへ移動するようお誘いした際、利用者さんは移動しなければいけないことは分かっていても移動できない時があります。
その理由は、別の部屋での定位置が定まっていないことや、そこで具体的に何を何のためにしなければならないのかが分からないといった背景が考えられます。
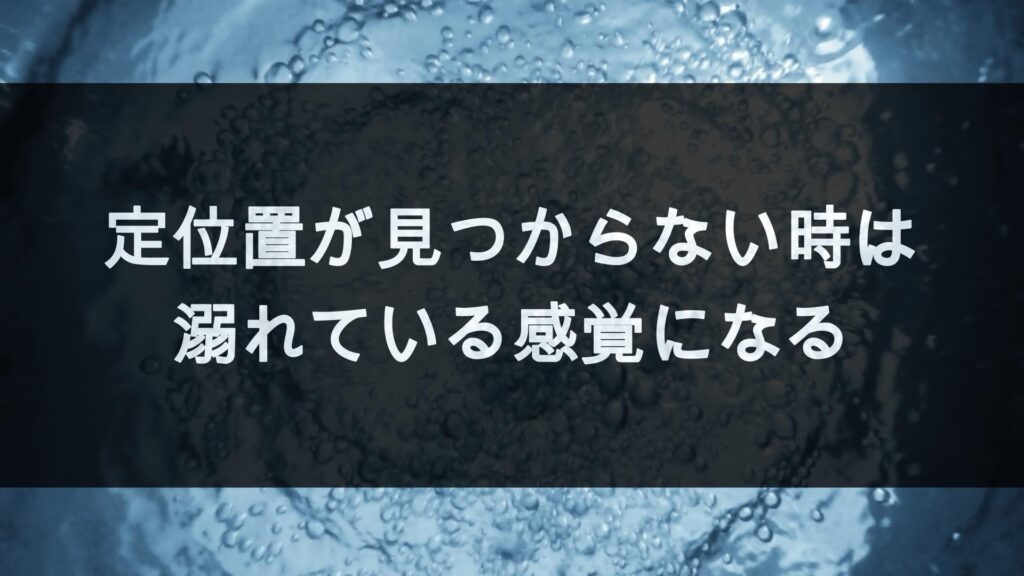
つまりは、いつも過ごす部屋の定位置の椅子(いつも使っている浮き輪)から移動した際、次の場所での浮き輪がないため足が着かず溺れてしまう感覚になるためです。
障害の特性上、オンとオフの切り替えが得意ではないこともありますが、定位置には浮き輪という椅子がある一方で、それ以外の場所は浮き輪がなくなんとも言えない不安を覚えてしまうというのが行動の特徴です。
そのため、椅子(定位置/浮き輪)ごと別の部屋に移動させたり、利用者さんが定位置で活動に参加できる環境を整えたり、活動時間ものを構造化して移動先を固定化する設計にしたり(新たな定位置を作る)、といった工夫が必要です。
これは子供さんでも同じですが、外を出て歩く際、利用者さんは介助者の手を取ったり肩に手を置いたりことがあります。
これは利用者さんにとって介助者が浮き輪(動く定位置)の役割を果たしているためです。利用者さんが介助者の肩から手を離して歩いている時は、「一人で泳ぐことができる状態」と捉えてよいです。
周囲の都合で定位置の椅子から離れることも利用者さんはあまり得意ではありません(尚、食事が好きな方は多いので食事への誘導はスムーズな場合もあります)。
そのため、そのようなちょっとしたイレギュラーな行動をお誘いする際は、椅子に座っている利用者さんに急に声をかけるよりも、トイレからお部屋に戻ってくるタイミング、昼食場所にご飯を食べに向かうタイミング、お部屋から玄関に向かうタイミングなどを活用して、利用者主体での行動の途中に差し込むように誘導するとスムーズに行動に移れます(鎖の法則の応用)。
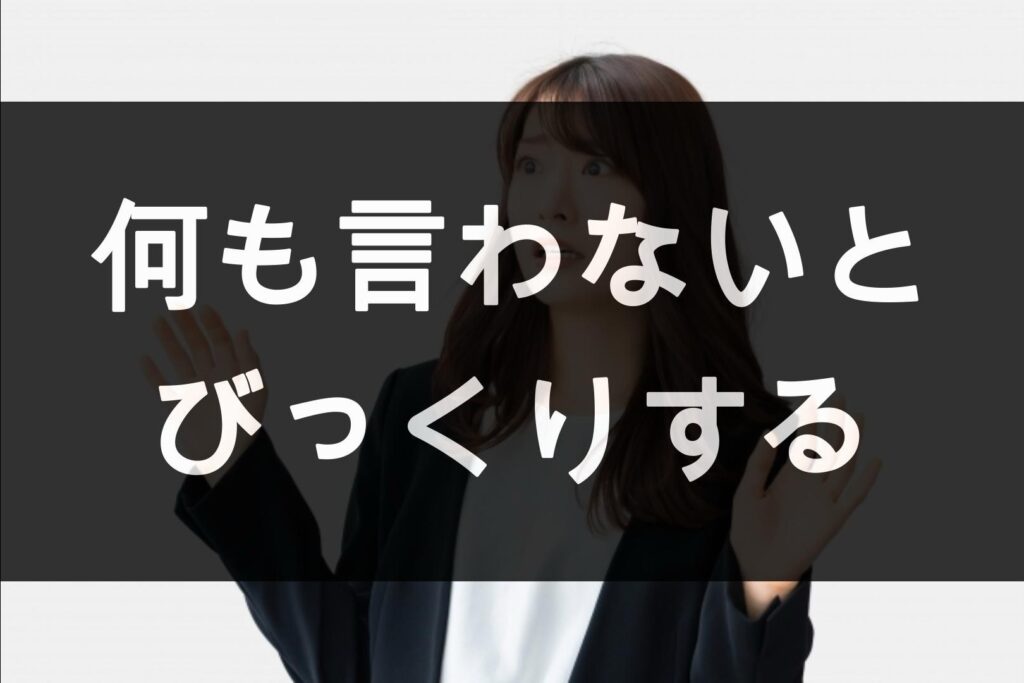
その際、何も言わず突然利用者さんを誘導すると驚いてしまいますので利用者さんに急に伝えるのではなく、
「トイレから戻ってきたら歯磨きしますね」
「ご飯ですよ。(利用者さんが立ち上がったタイミングで)ついでに体重も測りますね」
などといったクッション言葉を添えると受け入れやすくなります。
おわりに
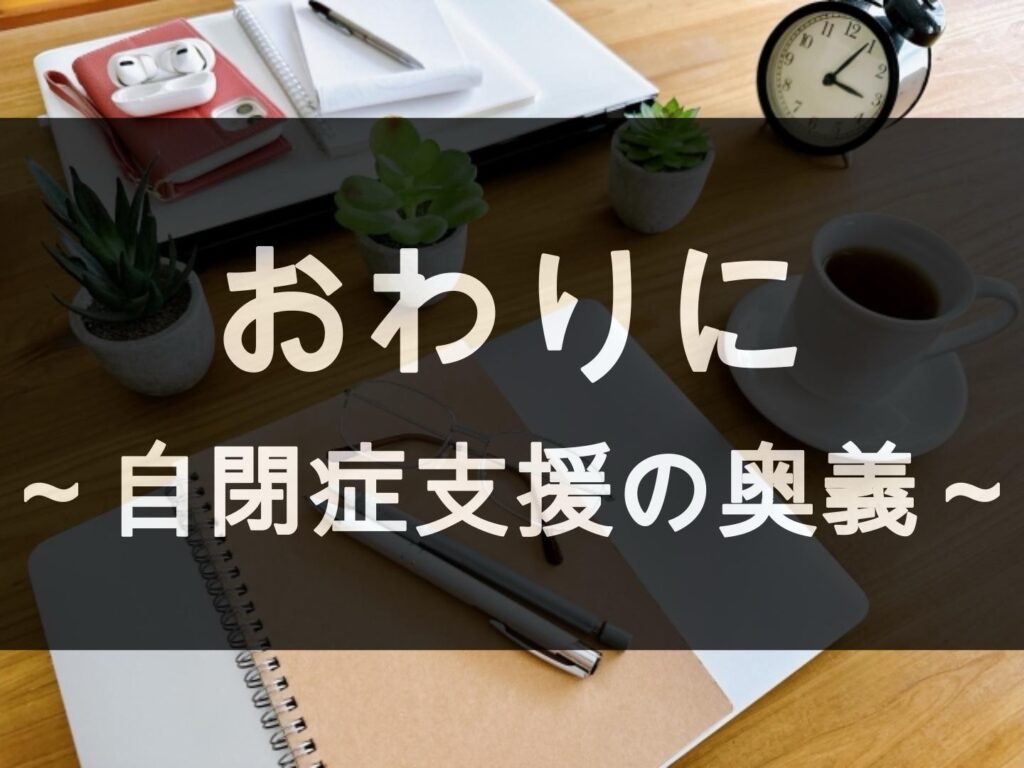
自閉症の方にとっては「行動のつながり」と「安心できる定位置」が大きな支えになります。支援者が鎖の流れを意識して新しい行動を組み込み、定位置を整える工夫をすることで、不安を和らげながら安心して日常を過ごすことができます。
ちょっとした工夫で行動がスムーズになり、本人の笑顔や安心感につながります。日々の支援や関わりの中で、ぜひ意識して取り入れてみてください。

