ダウン症とは?
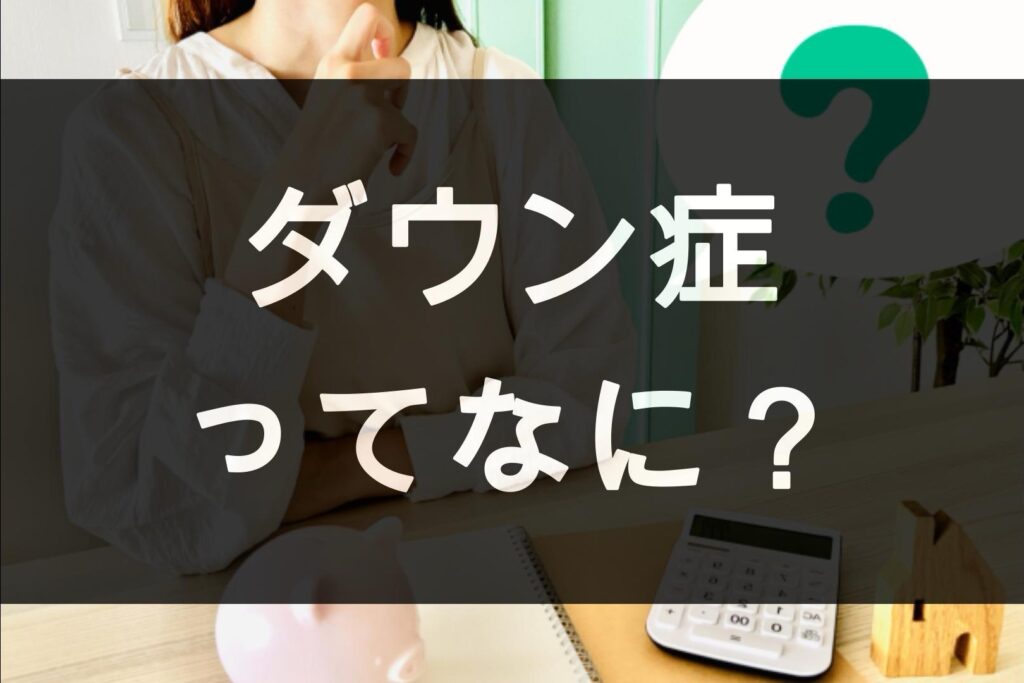
ダウン症(ダウン症候群)とは、21番目の染色体が通常より1本多く存在すること(21トリソミー)によって起こる先天的な特徴です。
日本では約700〜800人に1人の割合で生まれるといわれています。医学的には「障害」と表現されることもありますが、その一方でダウン症のある方たちは、個性豊かな性格や表情を持ち、周囲との関わりの中で多くの魅力を発揮しています。
既にネットや本などでダウン症に関する様々な情報を得ることが出来ますので、今回は私が経験した事例をもとにした行動理論をご紹介したいと思います。
ダウン症的世界観
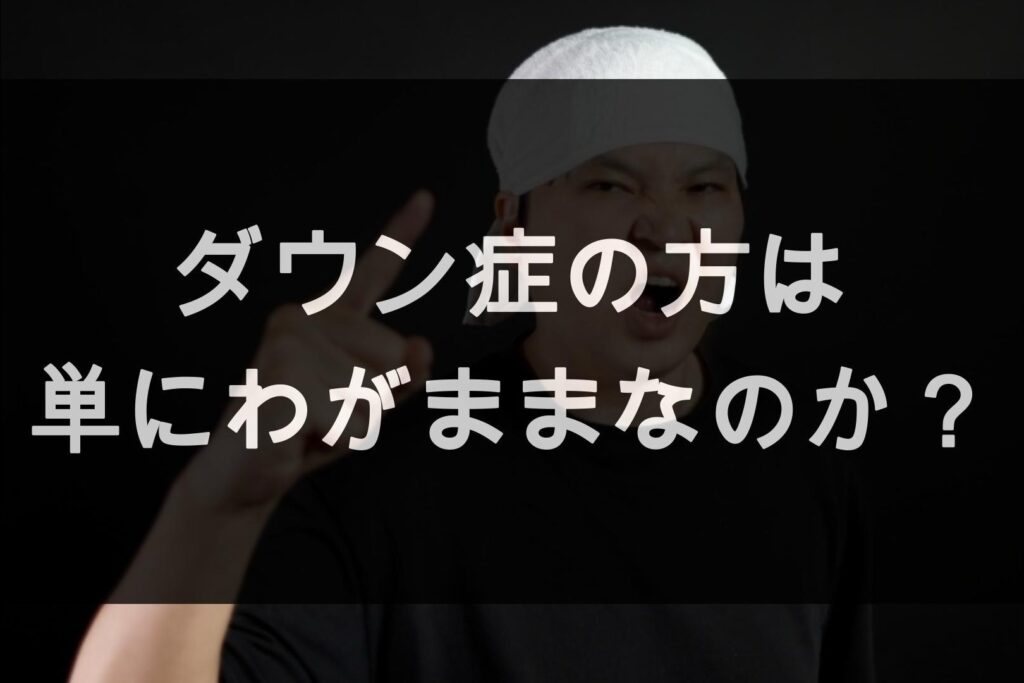
自閉症的世界観は頭の中が真っ白になる傾向が高いですが、ダウン症的世界観はその逆で頭の中が真っ黒、つまりは本人自身で過ごしの流れを明確に決めているという特徴があります。
そのため、本人からの要求が強かったり、本人からの表現に対して周囲が別の提案した際に本人は納得がいかなかったりと、周囲からは頑固やわがままと見られるケースがよくあります。これがダウン症的世界観の方が周囲から誤解されやすい部分であり、社会との障壁となっている部分です。
そのため、本人の世界観に沿った過ごし方を設計して、心身の負担を軽減させていく支援が必要となります。その一方で、社会生活に支障をきたすほどのこだわりの強さが見られた際には支援者側で過ごしの流れを決めさせて頂く(構造化支援)といった工夫も必要になってきます。
タスク完了型
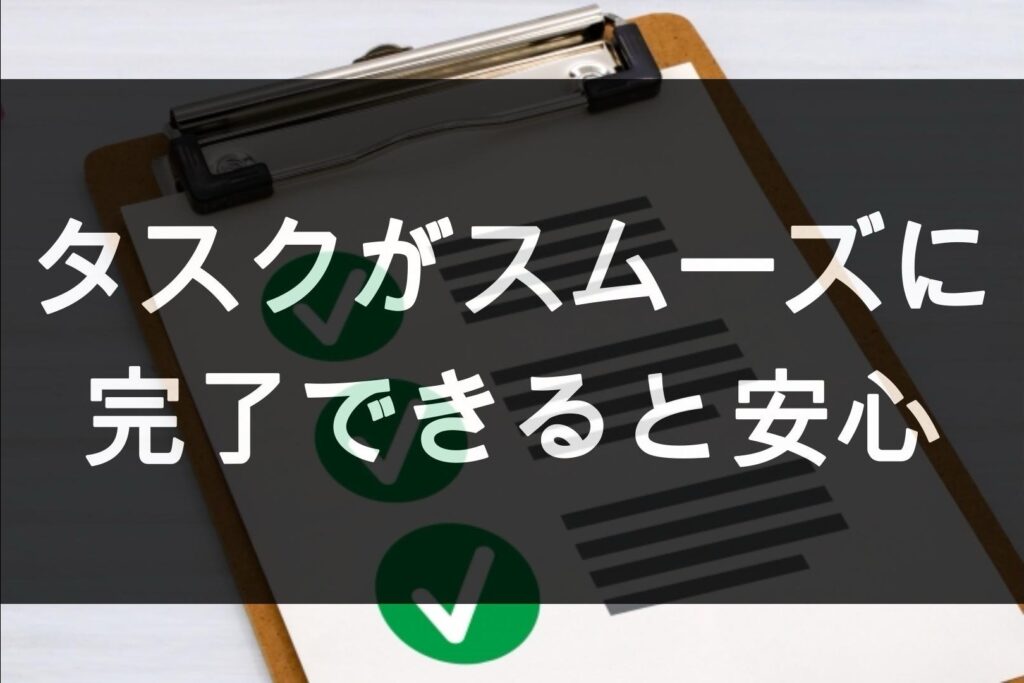
ダウン症的世界観の強い方は、物事をTo Doリストに時系列で羅列したタスクのように認識し、それが達成されないことは受け入れがたく、心身の負担に繋がりやすいです。タスクをスムーズかつ滞りなくクリアしていくことを望まれています。
朝起きた際や作業所に来られた際など何かが始まる前に1日の過ごしの流れ(タスク)を確認しておくことが大切です。
ダウン症の方ではありませんが、その世界観に非常に似ている利用者さんがいらっしゃいましたので、その事例をお話ししたいと思います。
まず、利用者さんが朝施設に通所したら以下の過ごしの流れ(タスク)がありました。
①水分摂取
②トイレ
③午前活動
④トイレ
⑤昼食
⑥歯磨き
⑦トイレ
⑧午後活動
⑨トイレ
⑩水分摂取
このタスクを完了し、身支度が完全に整ったらひと安心して帰宅します。本人と過ごしの流れを一つ一つ確認していった中で分かりましたが、これは本人自身が決めているルールのようで、次の行動に移れないと強い不安に飲み込まれるのだそうです。
認知症リスクの高さ
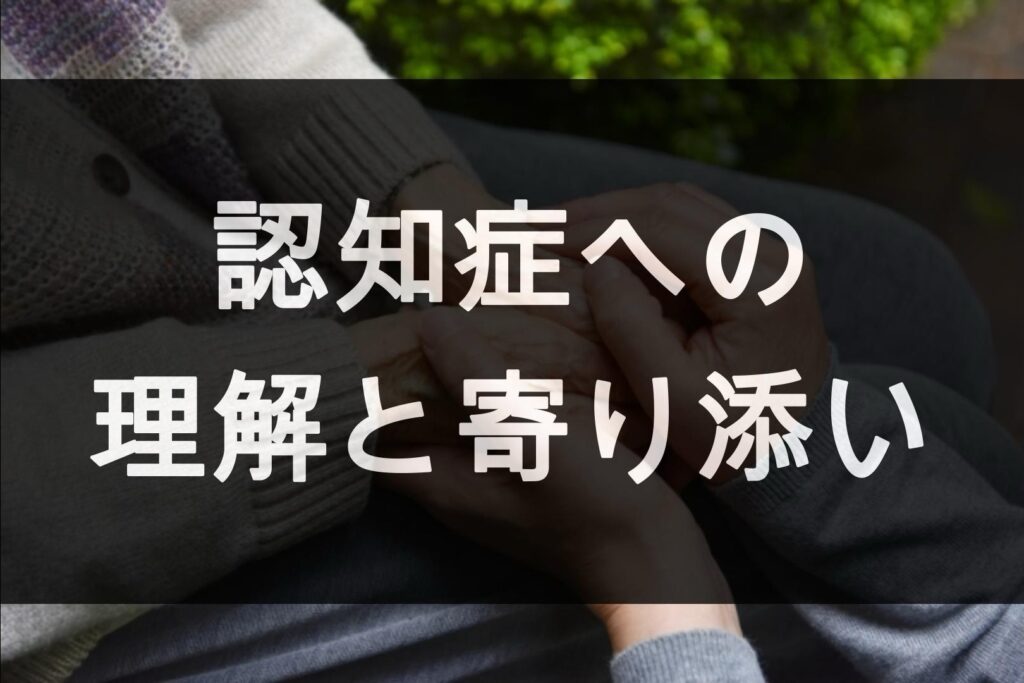
ダウン症のある人は、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高いことが医学的に知られています。その背景には、遺伝的要因が関わっており、一般の人よりも若い年齢(40歳代以降)で認知症を発症しやすい傾向があると言われています。
私が担当するようになった利用者さんは既に50歳を超えていましたが、20歳頃から静かなパニックとも呼ばれる徘徊行動を週に2回(約6時間で治まる)ほどするようになっており、主治医からは認知症はこの時から始まっているのではないかという所見も挙がっていました。
また、ダウン症は知的障害を伴っていることが多いため、認知症の症状の見え方が健常者と異なり、発見までに時間がかかってしまうことがあります。そのため、一般的に言われる認知症の特徴と照らし合わせるだけではなく、いつもの本人の状態を知っている家族や施設の職員などからの情報が判断の材料となります。
心疾患リスクの高さ
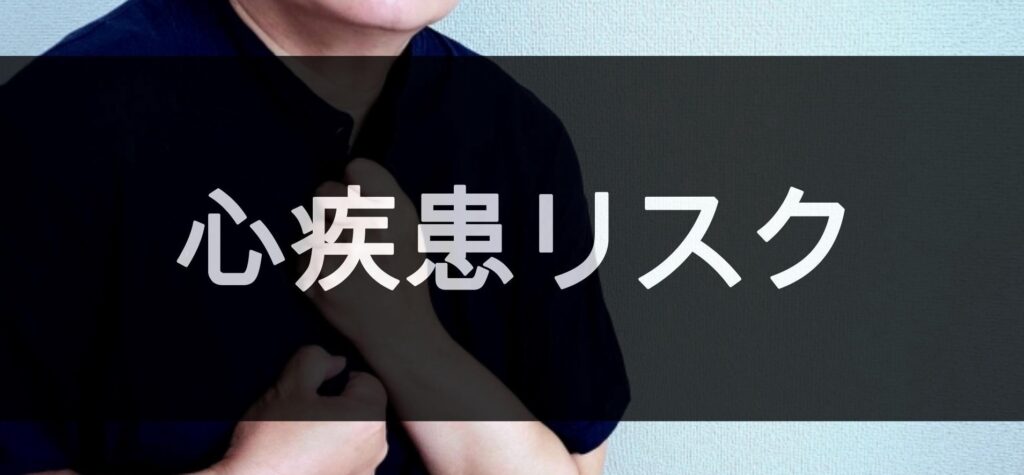
ダウン症のある人は、先天性心疾患(生まれつき心臓に構造的な異常がある状態)を持つ割合が高いことが知られています。日本や海外の報告では、約40〜50%のダウン症児に何らかの先天性心疾患が見られるとされています。 これは一般の新生児と比べて、はるかに高い割合です。
私が担当するようになった利用者さんは既に50歳を超えていましたが、同様に心臓が弱いと昔から言われていました。ダウン症のある方の寿命は短いとも言われていて、高齢の方のケースも稀だと言われていました。
とても活発な利用者さんではありましたが、走って心拍数を上げすぎないようにしたり、生活面でも無理をしすぎないようにしたりといった調整することが大切でした。
そのような経緯もある中で、50歳を超えたあたりから、外を歩いていると息を切らして急に座り込んでしまったり、外を歩くこと自体にプレッシャーを感じていたりするような様子が増えていきました。車椅子を導入し、外に行く際も車椅子を使っていいから歩くのは無理しなくても大丈夫だとお伝えすると快く車椅子に座り、嬉し泣きをされるご様子もありました。
大切なこと
ダウン症のある人の場合、いくつかの背景要因によって突然死のリスクが高まることが知られています。前章でもお話ししたものもありますが、改めてこちらにもまとめています。
主なリスク要因
1.認知症や高齢化との関係
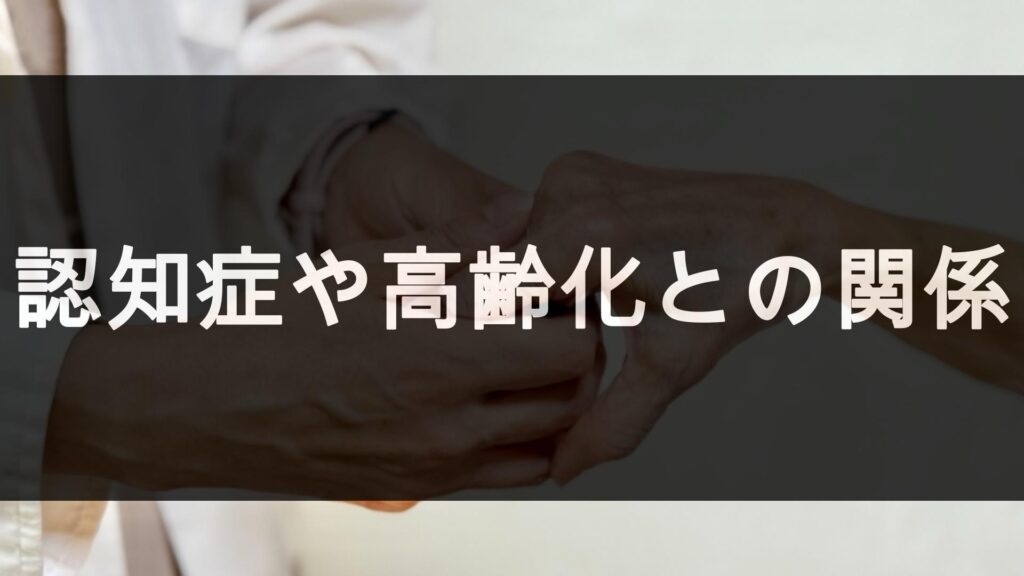
ダウン症の方は40歳以降にアルツハイマー型認知症を発症しやすく、その進行に伴いてんかん発作や全身の健康状態の低下が突然死のリスクを高める要因になることがあります。
2.先天性心疾患
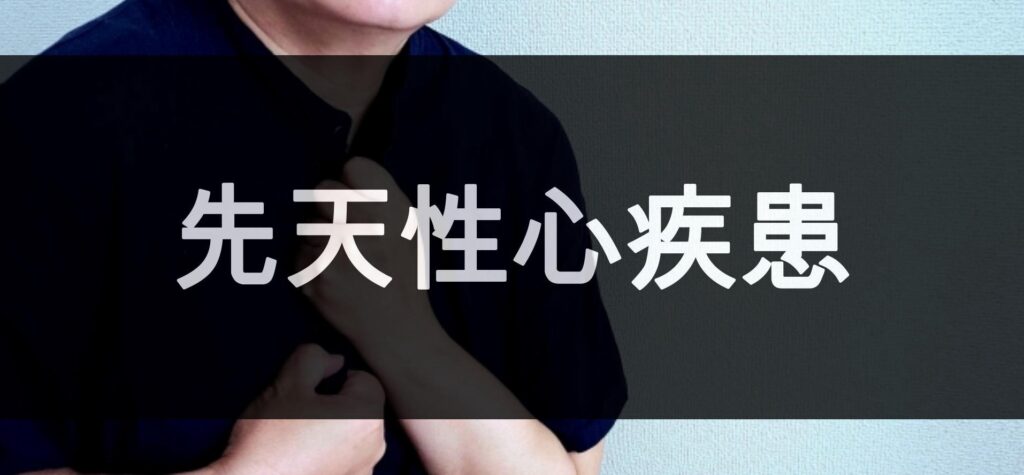
前章でも心疾患リスクの高さについてお話ししましたが、ダウン症の方の約40〜50%に心疾患があり、不整脈や心不全のリスクが伴います。 手術を受けて改善しているケースも多いですが、術後も長期的なフォローが必要です。 不整脈や心停止が突然死につながる可能性があります。
3.睡眠時無呼吸症候群(SAS)
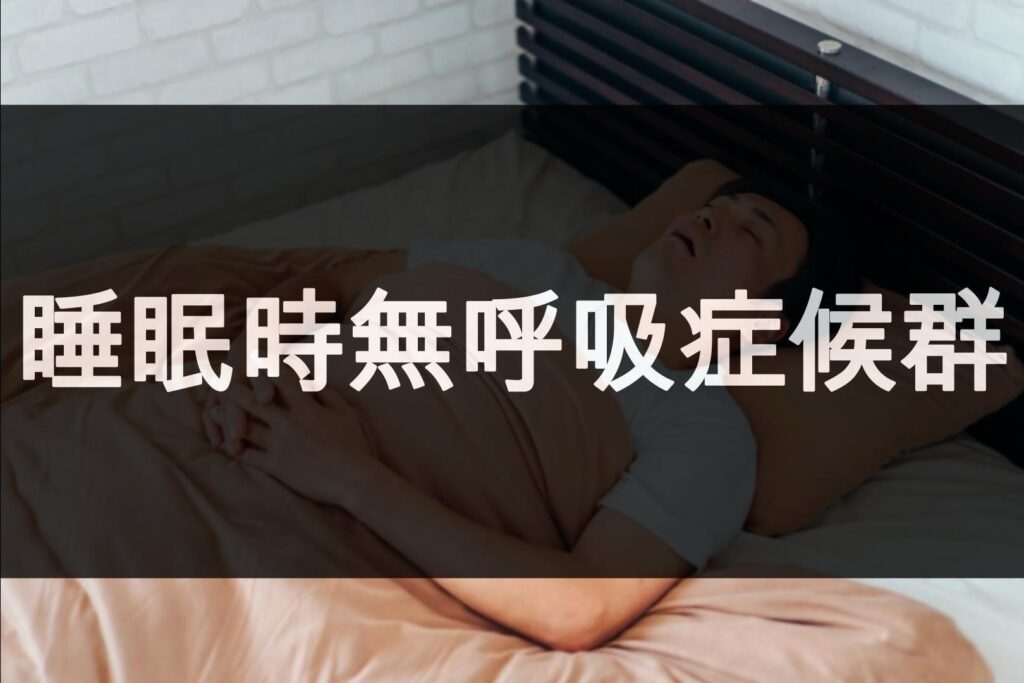
ダウン症の方は気道が狭く、肥満や筋緊張の弱さも影響して閉塞型睡眠時無呼吸症候群が起こりやすいとされています。 重度の場合、夜間の低酸素状態が突然死のリスクにつながります。
4.感染症・免疫の弱さ
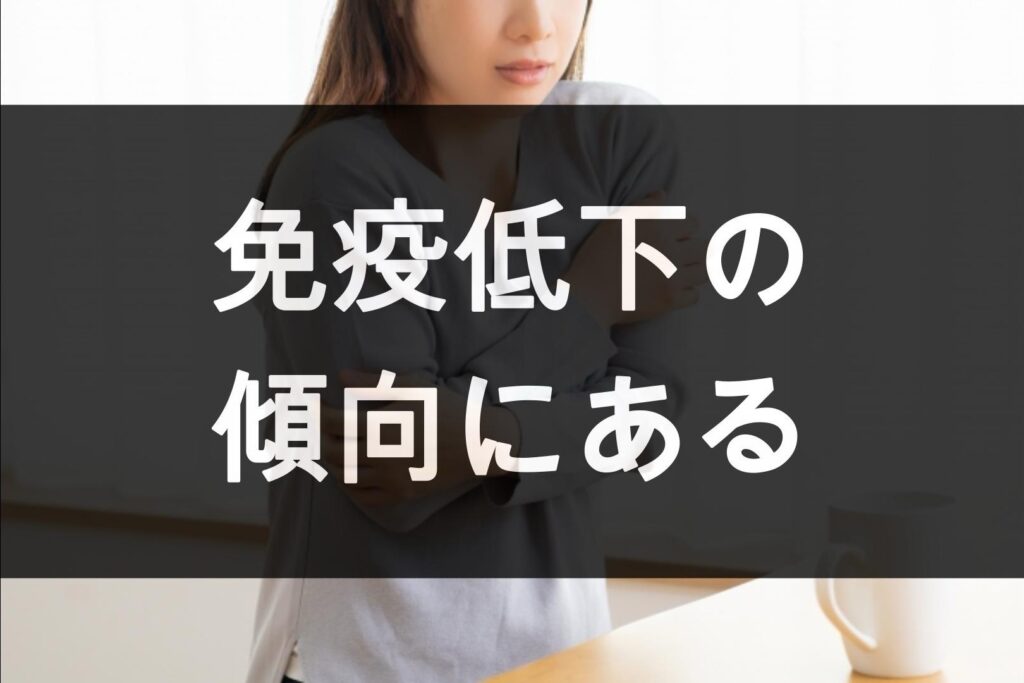
ダウン症では免疫力が低下している傾向があり、肺炎や心筋炎などの重篤な感染症が急激に悪化することがあります。 特に若年期の突然死に関連することがあります。
おわりに
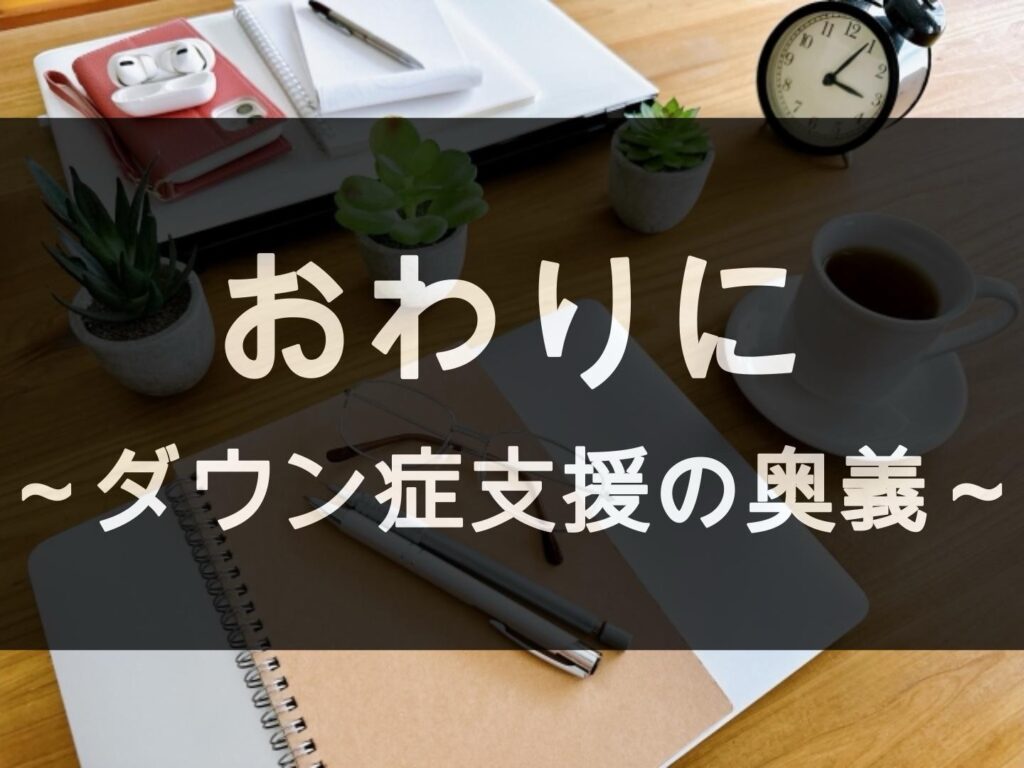
ダウン症のある方は、独自の世界観やこだわりを持ちながらも、多くの魅力を発揮されています。その一方で、認知症や心疾患など健康面でのリスクも高く、日常の支援や生活設計に工夫が求められます。
大切なのは、本人の世界観を尊重しつつ、安心できる環境を整え、必要に応じて医療的な視点や家族・支援者との連携を持つことです。支援者がこうした理解を深めていくことで、本人にとっても、周囲にとっても、より安心で豊かな生活につながっていくのだと思います。

