はじめに

ようこそ、対人援助を学べるバーチャル道場「福祉道」へ。
ここでは、対人援助職と呼ばれる福祉の仕事に10年間携わっていた私の経験から得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思っています。福祉をはじめ、子育てや教育、医療、そしてすべての人間関係に活かせる内容でもありますので、ぜひ習得してみてください!
詳しい自己紹介はこちらの記事に書きましたので読んで頂ければと思います。
福祉道の心得は以下の3つです。

※福祉道の心得の概要はこちらの記事にまとめていますので合わせて読んで頂けたらと思います。
福祉道の心得の3つ目「心技体の備わった人間力が大切である」で言われるように、人間力を磨くには心技体を兼ね備えることが重要です。対人援助職であり、エッセンシャルワーカーでもある福祉の仕事においては、この心技体を整えた状態で臨んでいくことが求められます。
心技体とは
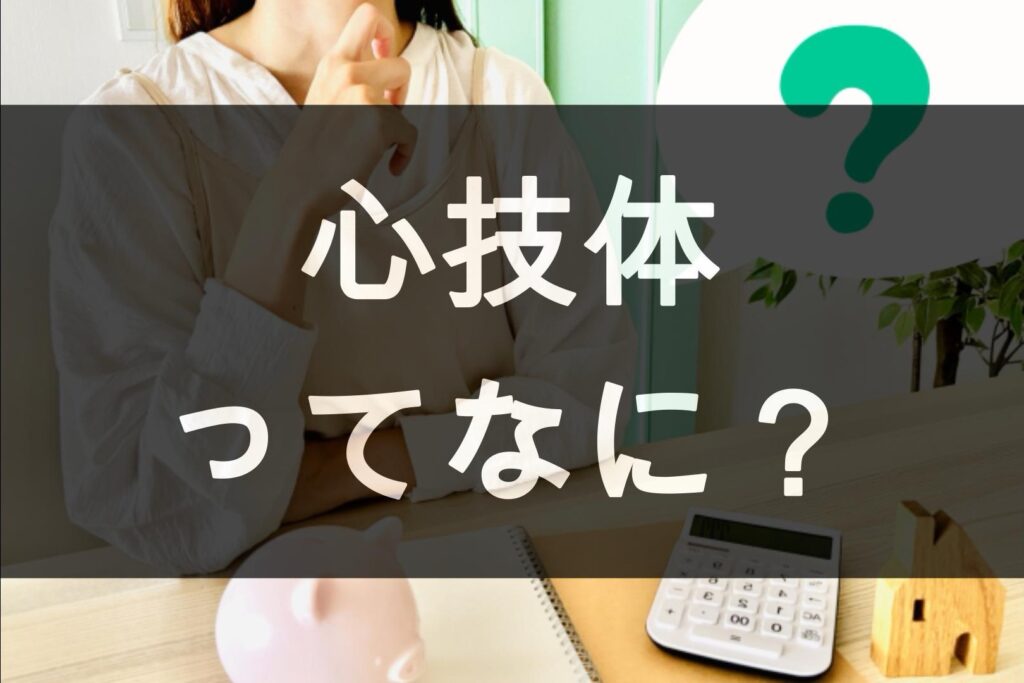
心技体とは文字通り心、技、体の3つの要素からなっていて、武道やスポーツをはじめ対人援助においても、これらの3要素がバランスよく発達している状態がより良いパフォーマンスを発揮できる状態と言えます。では対人援助における3要素とはどのようなものがあるのでしょうか?
①心
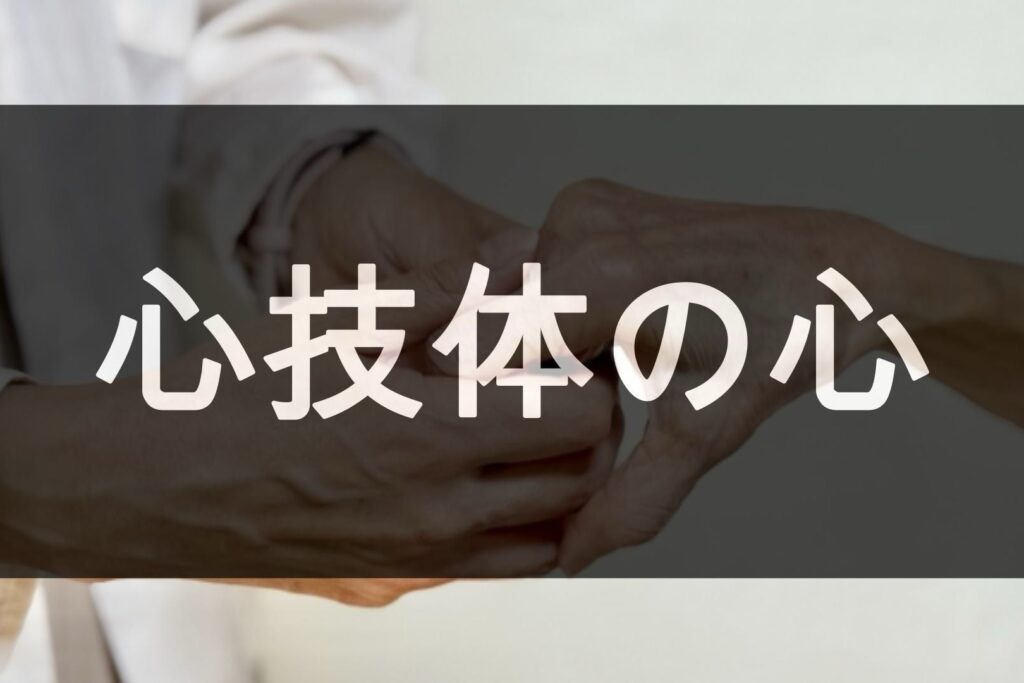
・相手を知ろうとする姿勢(興味関心)
・相手の話を聞く姿勢(傾聴)
・アンガーマネジメント(メンタルコントロール)
・倫理観の醸成
→自他の心の在り方と尊厳がテーマです。
②技
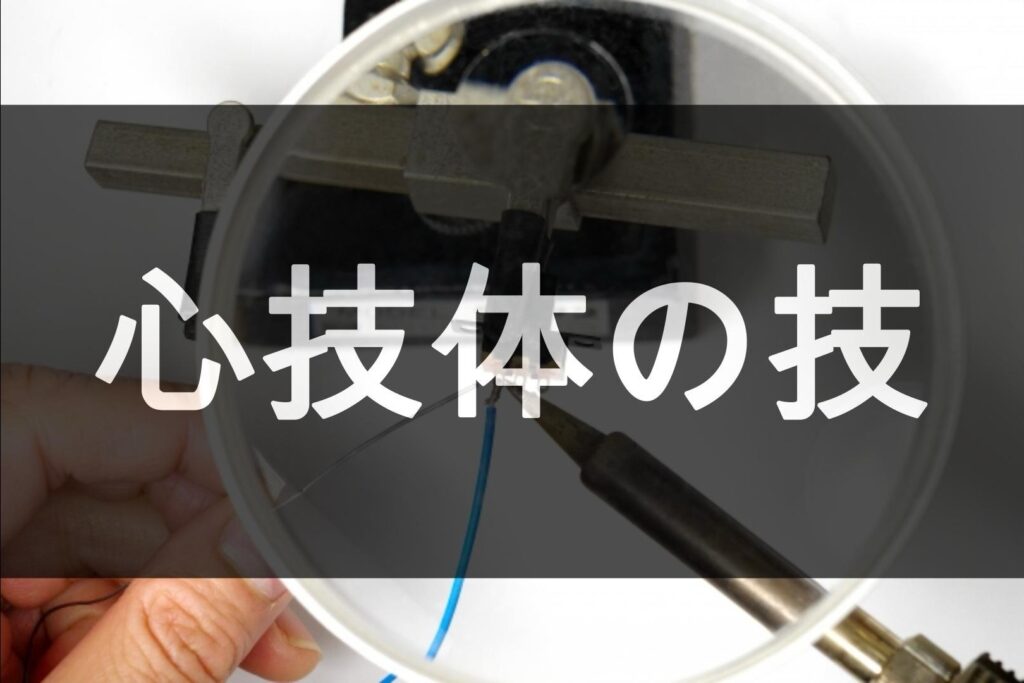
・制度の理解
・業務としてどこまでやってどこまでやらないかを明確する
→知識や技術を活かして課題を解消させることがテーマです。
③体

・介助技術(体の使い方)
・健康や体の機能の理解
・感染予防
→人間の体を知ることで、利用者に対してはいち早く体調の異変に気が付いたり、自身や他スタッフに対しては体を痛めないような工夫を施したりすることがテーマです。
以上が、対人援助における心技体それぞれの考え方でした。
では、具体的にこれらをどう実践で活かしていけばよいのでしょうか?
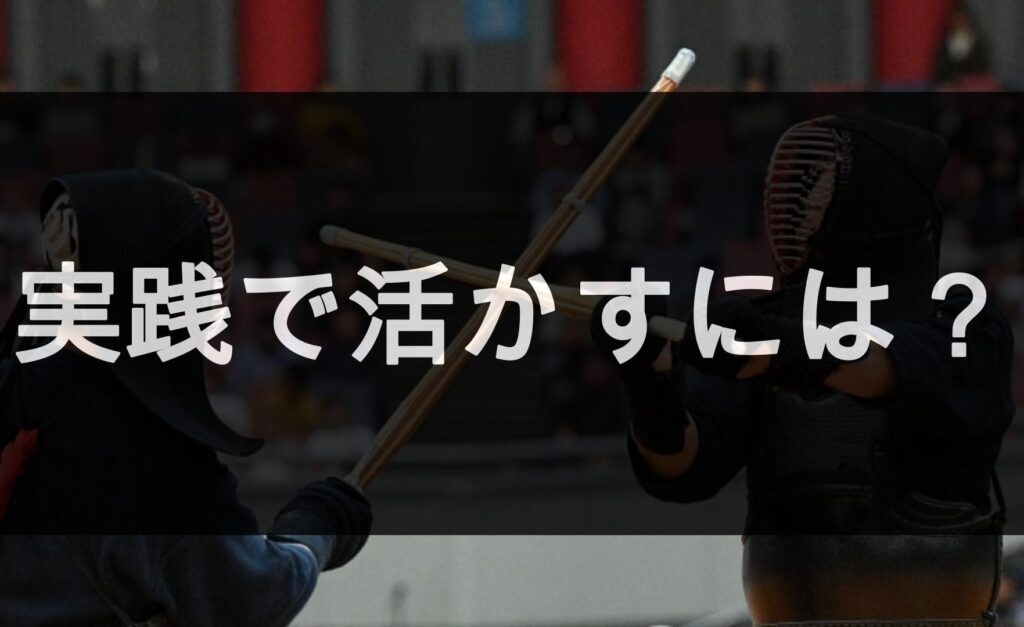
ここからが今回のテーマ、心技体の「体」についてです。まず「人間の体を知る」ということが大切です。生命活動をはじめ仕事や介助を行なっている自分自身の体、そして利用者の体を知るということが大切です。
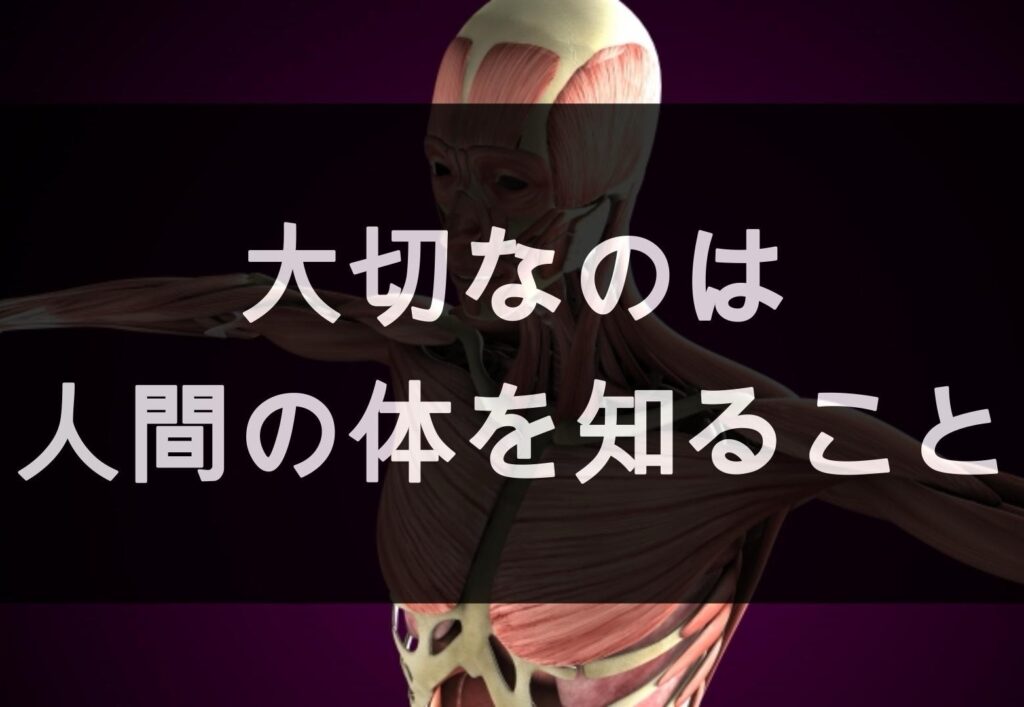
人間の体は骨、筋肉、内臓、皮膚などの器官や仕組みから成り、それぞれが連携して生命活動を維持しています。具体的には、脳からの命令で筋肉が関節を動かし、食べ物から取り入れた栄養と酸素でエネルギーを生み出し、心臓が全身に血液を送り出すといった複雑な機能を持っています。
体の構成要素
- 成分:
体は約60%が水分で、その他にタンパク質、脂質、ミネラルなどが含まれています。主要な元素は酸素、炭素、水素、窒素で、全体の95%を占めます。 - 器官・仕組み:
体は心臓、肺、胃などの「器官」や、骨や筋肉、神経、血管などの仕組みが集まってできています。 - 外観:
頭、首、胴体、両腕、両脚の「五体」に分けられ、それぞれが異なる役割を担っています。
体の機能
- エネルギー生産:
食事から摂った栄養分と呼吸で取り入れた酸素を使って、体内でエネルギーを作り出します。 - 運動と活動:
脳からの指令で筋肉が収縮し、関節を動かすことで手足が動き、運動することができます。 - 体温調節:
寒い時には筋肉の震えや血管の収縮によって熱を作り出し、体温を維持します。 - 血液循環:
心臓がポンプの役割を果たし、血液を全身に送り出すことで栄養や酸素を運び、二酸化炭素を回収します。 - 感覚と保護:
皮膚には外部からの刺激を感じ取るセンサーがあり、外部の刺激から体を保護する役割も担います。
体を維持するために
- 食事::体に必要な栄養を摂取し、エネルギーを生産します。
- 運動::筋肉を動かすことで骨が強くなり、全身の健康を維持します。
- 睡眠・休養::体や脳を休ませ、生命活動を維持するために不可欠です
介護や医療の現場においては、体を知るために行うバイタルチェックが大切です。
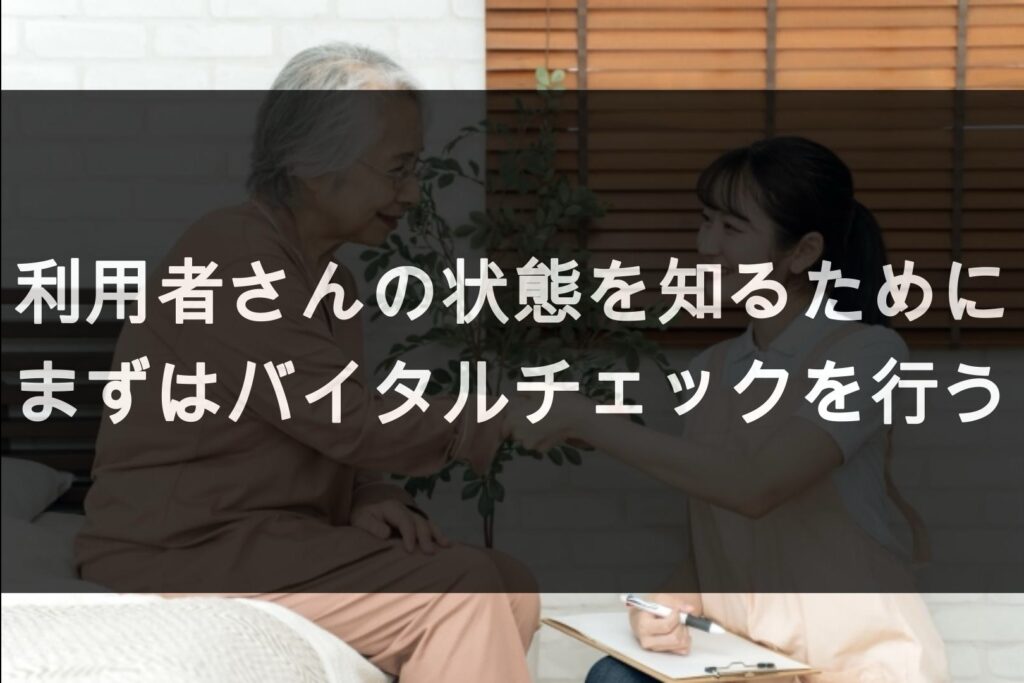
バイタルチェック(バイタルサイン測定)とは、体温、脈拍、呼吸、血圧、意識レベルなどの生命の兆候(バイタルサイン)を測定し、健康状態を客観的に把握する検査です。全身状態の変化や異常のサインを早期に発見し、適切な処置につなげる目的で行われます。特に高齢者など体調変化が自覚しにくい方にとって、病気の早期発見・早期治療に繋がり、重症化を防ぐ上で重要です。
バイタルサインの主な項目
- 体温(体温):最も一般的な測定項目です。
- 脈拍(みゃくはく):心臓の動きを測る指標です。
- 呼吸(こきゅう):呼吸の回数や深さを確認します。
- 血圧:心臓が血液を送り出す圧力です。
- 意識レベル:意識がはっきりしているか、ぼんやりしているかを確認します。
- SpO2(血中酸素飽和度):介護現場で測定されることもある項目で、血液中の酸素濃度を測ります。
バイタルチェックの目的と重要性
- 健康状態の把握:
客観的なデータをもとに、全身の健康状態を把握できます。 - 異常の早期発見:
測定値の変化を継続的に確認することで、体調の異変にいち早く気づくことができます。 - 病気の早期発見と治療:
異常が発見された場合は、速やかに医師に連絡し、適切な指示を仰ぐことで、病気の早期発見・早期治療に繋がります。 - 介護・医療サービスの安全な提供:
介護現場では、利用者様が安全に入浴や訓練などのサービスを受けられるかの判断材料となります。
実施される場面
- 医療現場:
病院では定期的に測定され、患者の状態変化の記録に利用されます。 - 介護現場:
高齢者の体調変化を早期に発見し、適切なケアを提供するために行われます。 - 訪問看護:
訪問介護の際に、利用者様の状態を確認し、医療との連携を図る上で重要な役割を果たします。
実施する際の注意点
- 利用者様に触れて測定するため、機器の取り扱いや測定方法について理解し、安心してもらえるように説明しながら行いましょう。
- 測定結果は記録し、変化があればかかりつけ医への連絡や指示を仰ぎます
おわりに
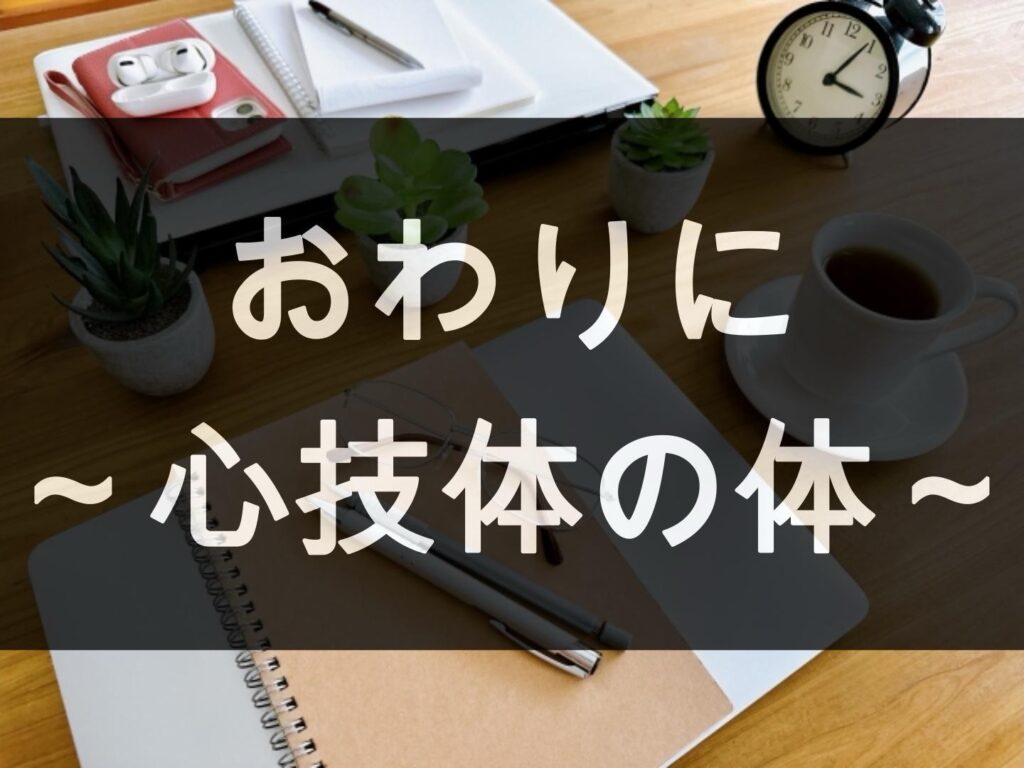
いかがでしたでしょうか?
今回は心技体の「体」について、まず「人間の体を知る」ということが大切だとお話ししてきました。利用者の体を知るということは、生命活動をはじめ仕事や介助を行なっている自分自身の体を知ることでもあります。
これらは利用者の安全安心を確保するために必要な知識ではありますが、その前に利用者のケアをする介助者がいなければなりません。介助者はなるべく負担を小さくし体を壊さないようにするといった工夫も大切です。
次回以降は利用者や介助者の体にまつわるお話しを小出しで出していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました!

