はじめに
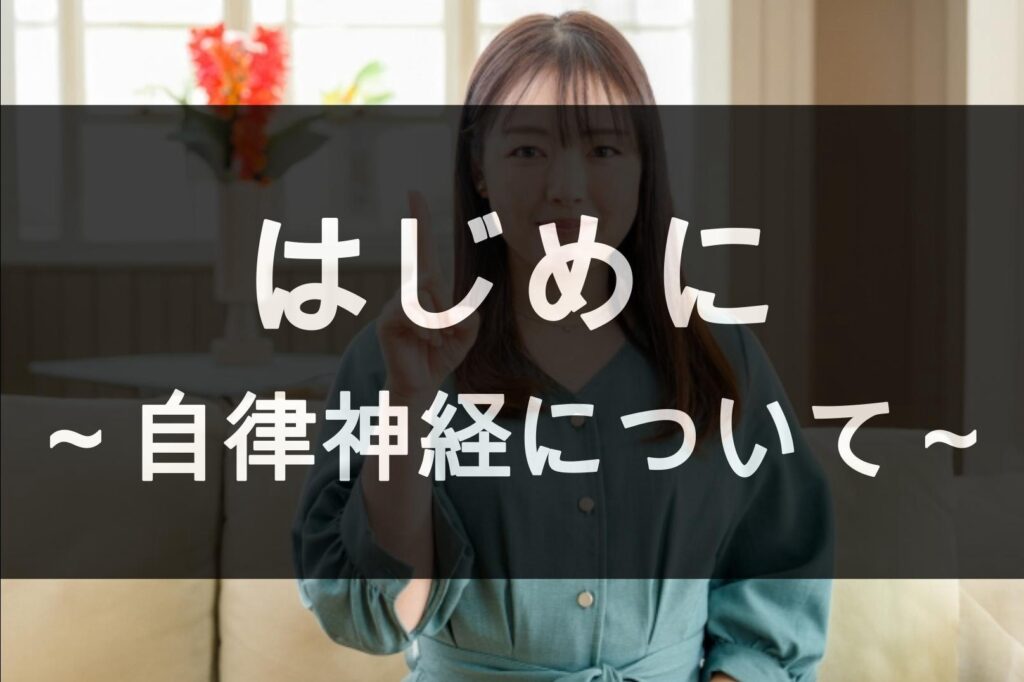
仕事や生活、そしてネットの中で、
「自律神経が乱れている」
「自律神経失調症」
「交感神経が高ぶっている」
などといった言葉を聞いたことはありませんか?
今回の記事は、日常生活に深く関わっている自律神経について、その用語の説明と日常の中での活かし方をお話ししていきたいと思います。
→自律神経の発展系であるポリヴェーガル理論について解説したこちらの記事も合わせて読むと理解が深まると思います。
自律神経とは?

ではそもそも、自律神経とはどのようなものなのでしょうか?
自律神経とは、私たちの意思とは関係なく、体を自動的に調整してくれる神経の仕組みです。
例えば、寝ているときでも心臓が止まらないのは、この自律神経が働いてくれているからです。
自律神経は、交感神経と副交感神経に大きく分けられます。
次に、この2つについての説明をしていきます。
交感神経とは?
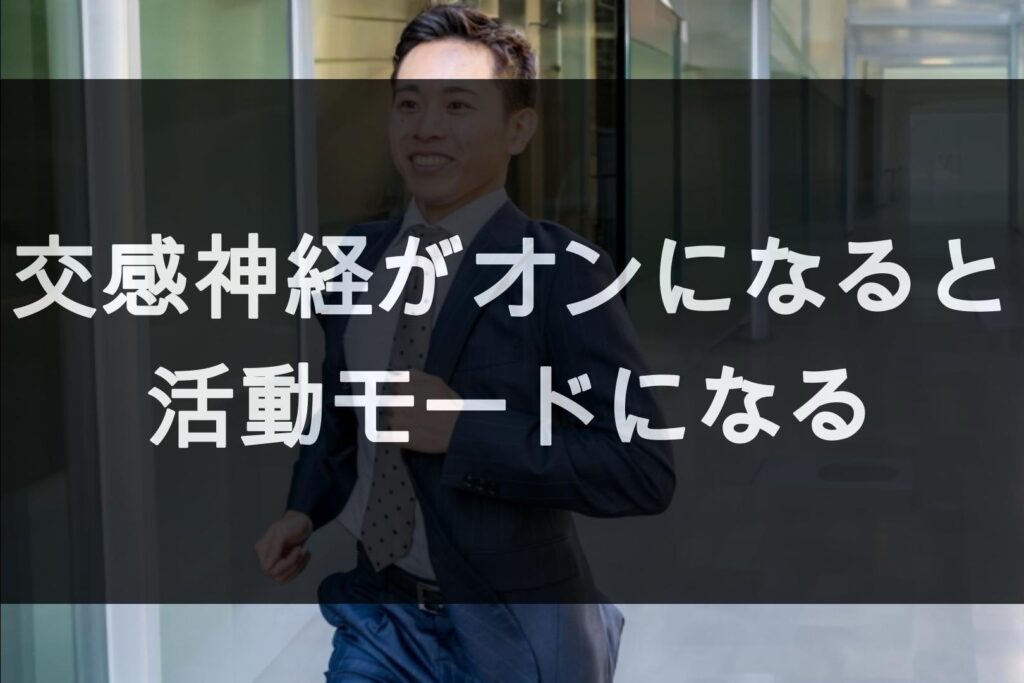
交感神経とは「活動のスイッチ」です。そして、交感神経のスイッチがオンになっているということは「活動モード」の状態です。
交感神経は、仕事をしたり、何か作業に集中して取り組んでいたり、身の危険を感じたり、ストレスを受けたりしているときに活発になります。
また、交感神経のスイッチがオンになっている時には、
・心拍数が上がる
・呼吸が速くなる
・呼吸が浅くなる。
・血圧が上がる
・体温が上がる
などといった働きをして、体を「活動モード」に切り替えます。
副交感神経とは?
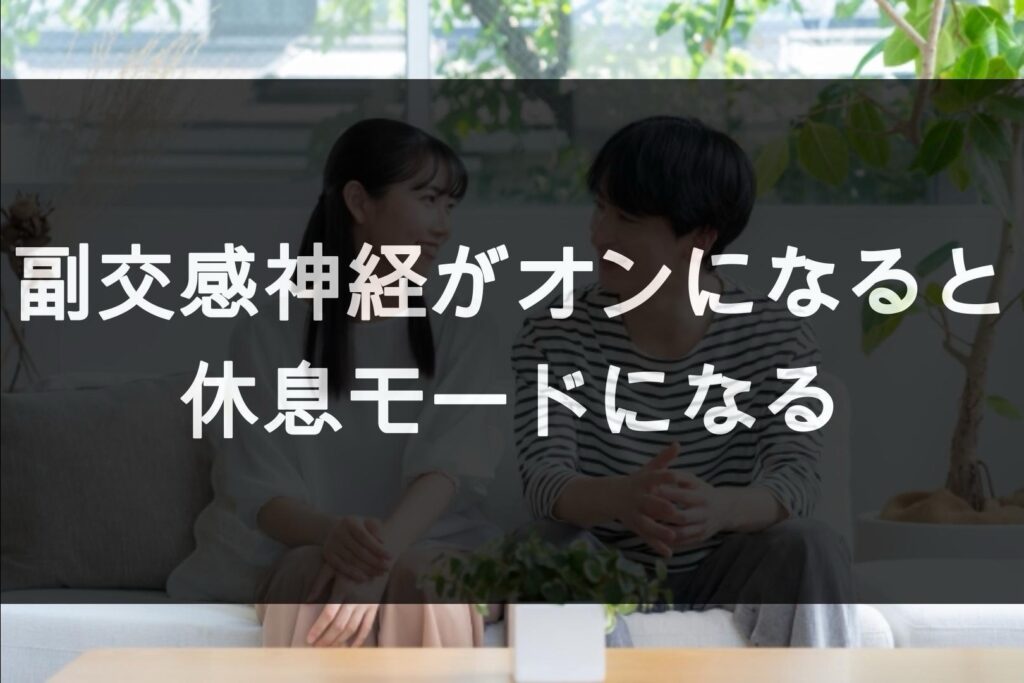
副交感神経とは「休息のスイッチ」です。そして、副交感神経が働いているということは「休息モード」の状態です。
副交感神経は、リラックスしているときや、眠っているとき、安心できる人と話しているときなどに活発になります。
また、副交感神経のスイッチがオンになっている時には、
・心拍数が下がる
・呼吸がゆっくりになる
・呼吸が深くなる。
・血圧が下がる
・体温が下がる
・消化が促される
などといった働きをして、体を「休息モード」に切り替えます。
バランスが大事
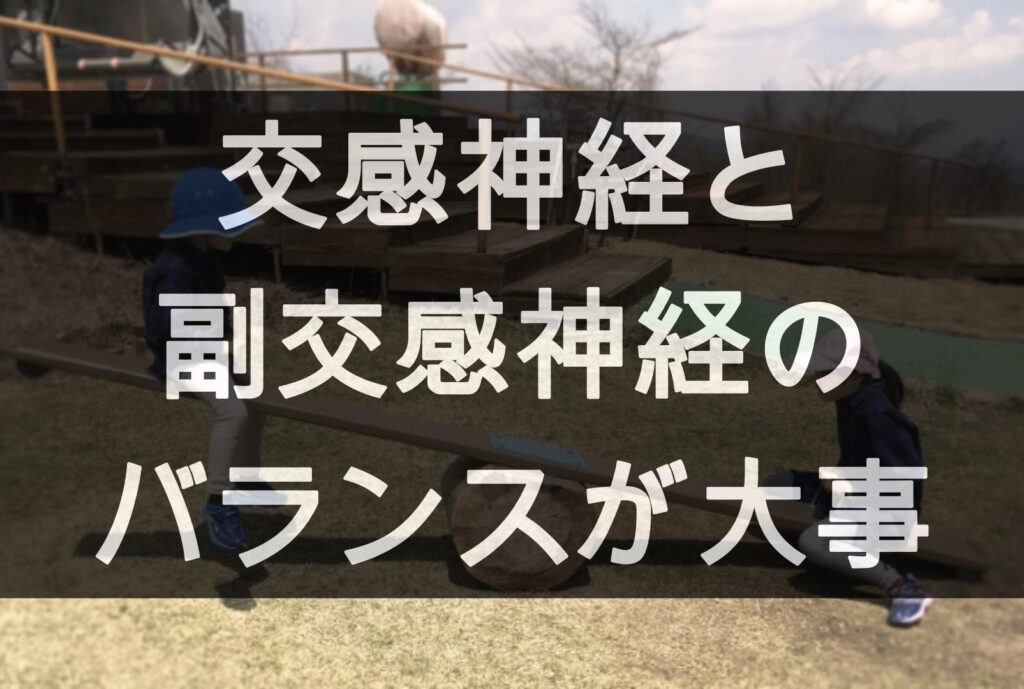
前節で自律神経、そしてその中の交感神経と副交感神経のお話しをしてきました。
さらに大切なこととして、交感神経と副交感神経はそれぞれバラバラに働いているものではなく、シーソーのように互いにバランスをとっていることで生命を維持させているのです。
どちらかに偏りすぎると、心身に不調が出やすくなります。
例えば、
交感神経が強く働きすぎると、眠れなくなったり動悸が起きたりといった緊張状態が続きます。
逆に、副交感神経が強く働きすぎると、やる気が出なかったり一日中眠かったりといった倦怠感に繋がります。
そして、これらのバランスが崩れていくと、自律神経失調症といった神経症や精神疾患などを引き起こすことにも繋がります。
ですので、交感神経と副交感神経をスムーズに切り替えていくこと、つまりは活動モードと休息モードを切り替えていくことがとても重要になっていきます。
次の章では、その切り替え方のコツについてのお話しをしていきたいと思います。
切り替え方のコツ
前の章では、交感神経と副交感神経をスムーズに切り替えていくこと、つまりは活動モードと休息モードを切り替えていくことがとても重要、というお話しをしてきました。
交感神経と副交感神経をスムーズに切り替えることは、自律神経を整えることに繋がります。
普段生活している中で自律神経系で問題や不調がなければ意識的に整えていく必要性をあまり感じないかもしれません。しかし、自律神経を整えていくと、仕事のパフォーマンスが上がったり、アンガーマネジメントが上手にでき良好な人間関係を作り出すことができたり、といった多くのメリットを生むことができます。
では、どのようにしたら自律神経を整えられるのでしょうか?
1. 呼吸法でリズムを整える

深呼吸(腹式呼吸):息を鼻からゆっくり吸って、お腹を膨らませ、口から長く吐き出す。1日数分でもOK。
4-7-8呼吸法:4秒吸う → 7秒止める → 8秒吐く。副交感神経を優位にしてリラックスできます。
2. 睡眠の質を高める
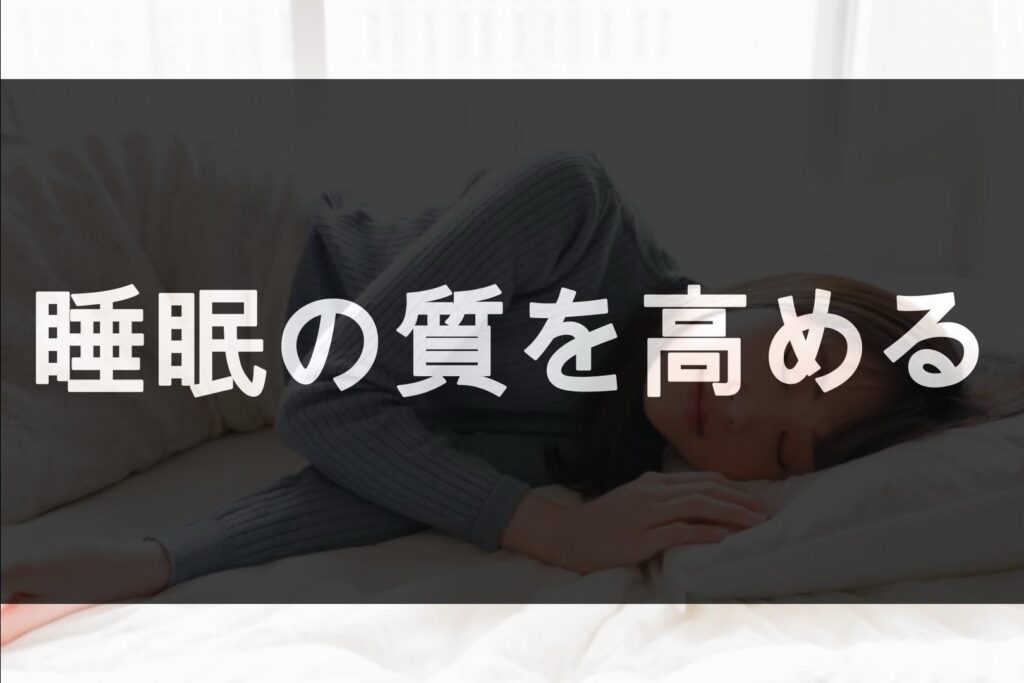
毎日できるだけ同じ時間に寝起きする。 就寝前のスマホ・PCは避けて、照明を少し落とす。 寝る前にストレッチや白湯で体を緩めるのも効果的です。
3. 食事の工夫
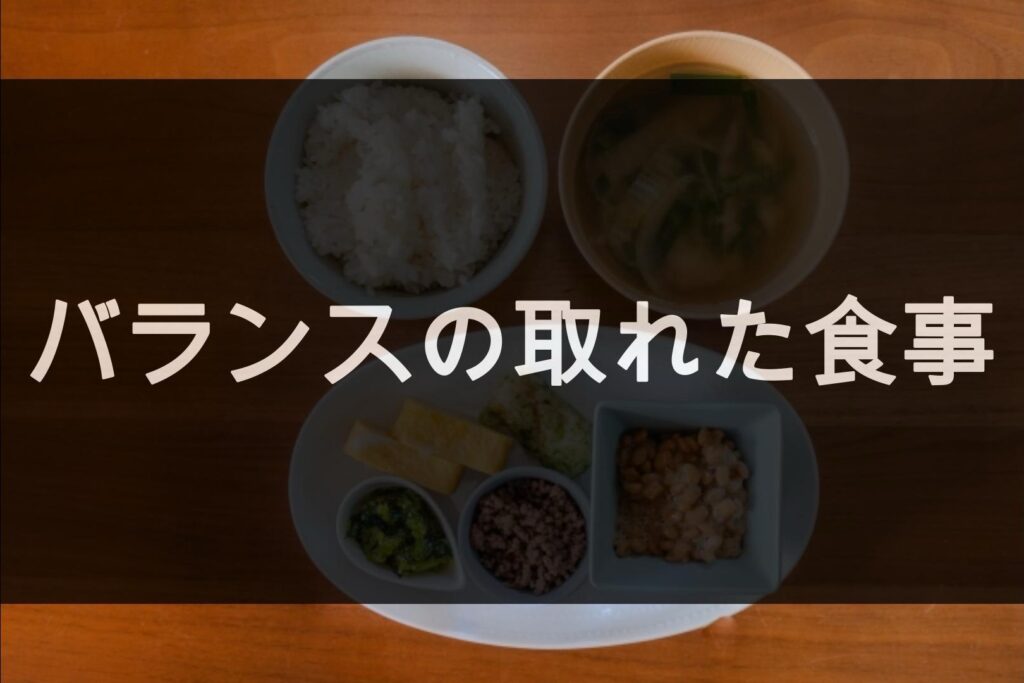
朝食でたんぱく質(卵・納豆・魚など)を摂ると、自律神経が活動モードに切り替わりやすくなる。 カフェインやアルコールの摂りすぎは避け、腸内環境を整える発酵食品や食物繊維を意識するとよいです。
4. 適度な運動とリズム
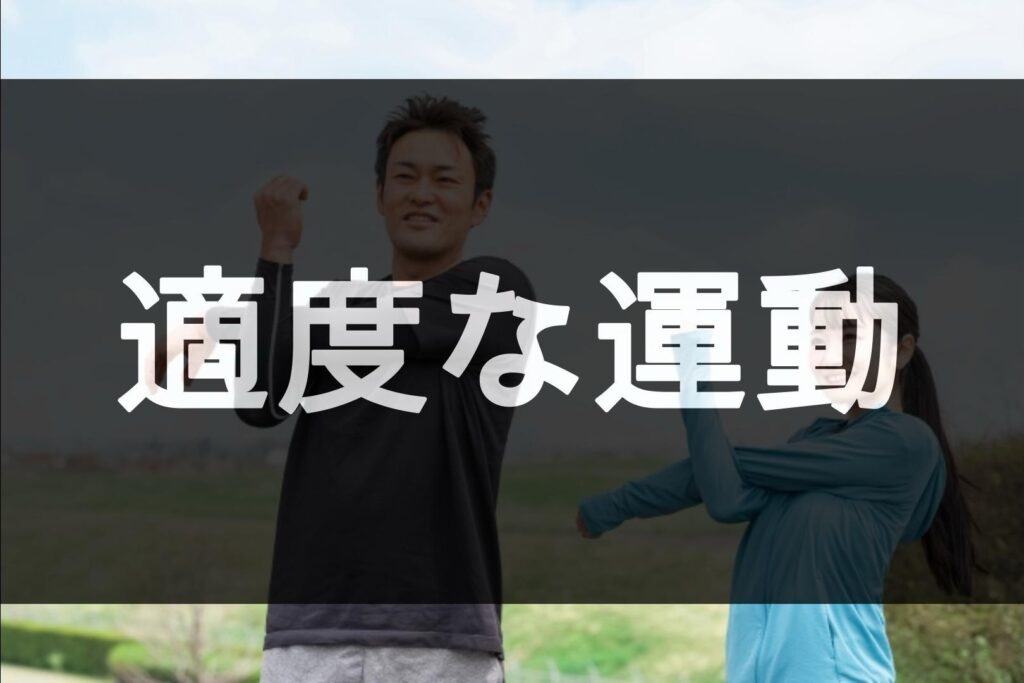
ウォーキングや軽いストレッチで血流を改善する。特に朝日を浴びながら歩くと体内時計も整います。 強い運動ではなく「心地よく続けられる運動」がベスト。
5. 心の整え方

短時間でも瞑想やマインドフルネスを取り入れる。 日記を書いたり、感謝リストを作るのも自律神経の安定に役立ちます。 怒りや不安を感じたらアンガーマネジメントの習慣も効果的です。
6. 環境づくり
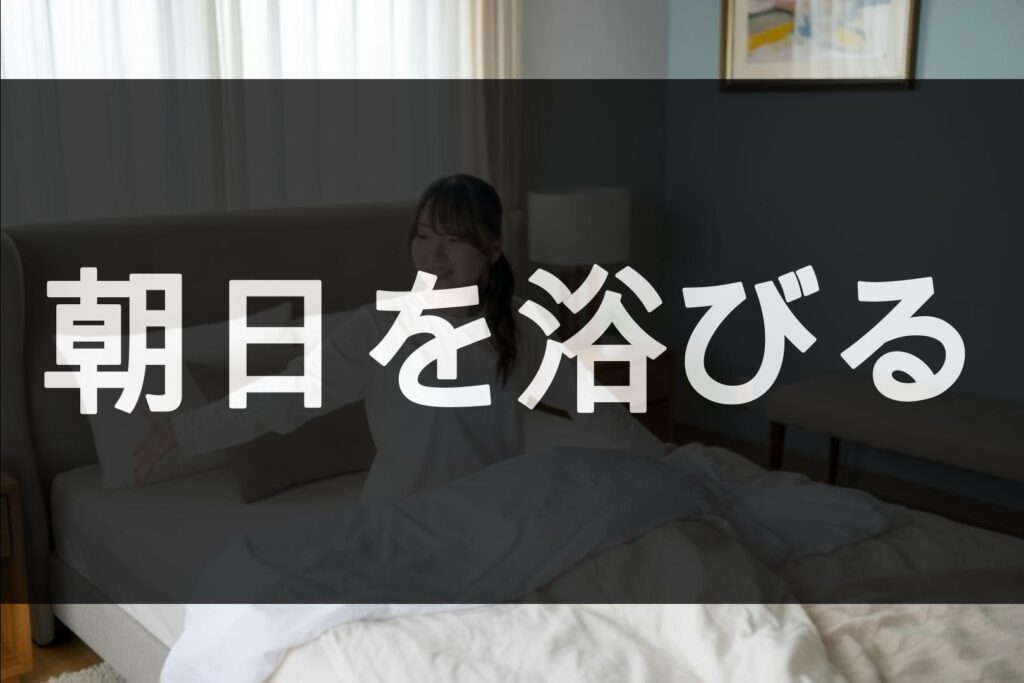
朝はカーテンを開けて自然光を浴びる。 部屋の温度や湿度を快適に保つ。 アロマ(ラベンダー、ベルガモットなど)や音楽を活用するのもおすすめです。
おわりに
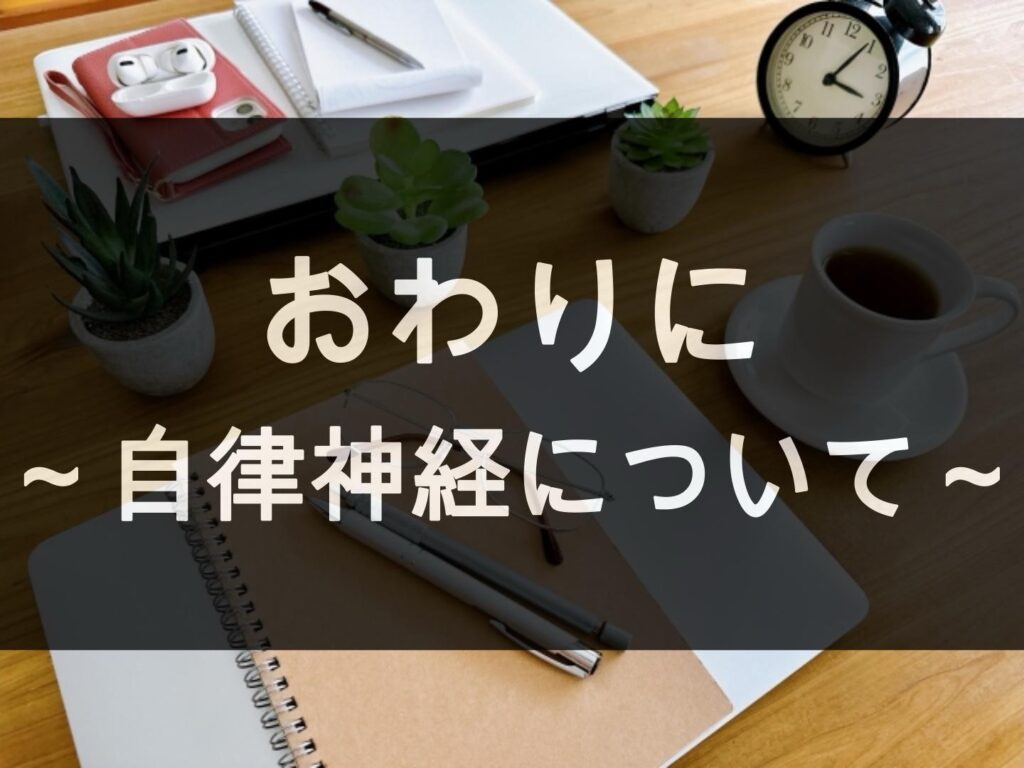
いかがだったでしょうか?
今回の記事はかなりニッチな内容を書いてきました。ですが、対人援助をはじめとした人と関わり合う立場においては、この自己マネジメント力がとても大切になってきます。そして、それと同時に、自己マネジメント力を個人だけに委ねるのではなく、チームや組織としてもこれを促せるような空気感を作っていくこともまた大切です。
自律神経は、私たちが意識しなくても体を守り、支えてくれる大切な仕組みです。交感神経と副交感神経はどちらも欠かせない存在であり、そのバランスがとれているからこそ心身は健やかに保たれます。
しかし、どちらかに偏りすぎると不調やストレスを招いてしまうこともあります。だからこそ、呼吸・睡眠・食事・運動・心の整え方・環境づくりといった日常の工夫を通して、自律神経を上手に整えていくことが大切です。
日々の小さな意識と習慣の積み重ねが、仕事のパフォーマンスや人間関係、そして自分自身の心地よい暮らしにつながっていきます。ぜひ今日から、自律神経を整えるための一歩を取り入れてみてください。

