最期に寄り添うとは何か。福祉現場で利用者の「別れ」と向き合う中で大切にしている視点やケアの在り方を、実体験をもとにやさしく綴ります。
もくじ
はじめに|最期に寄り添うとは何か──福祉現場で向き合う別れ
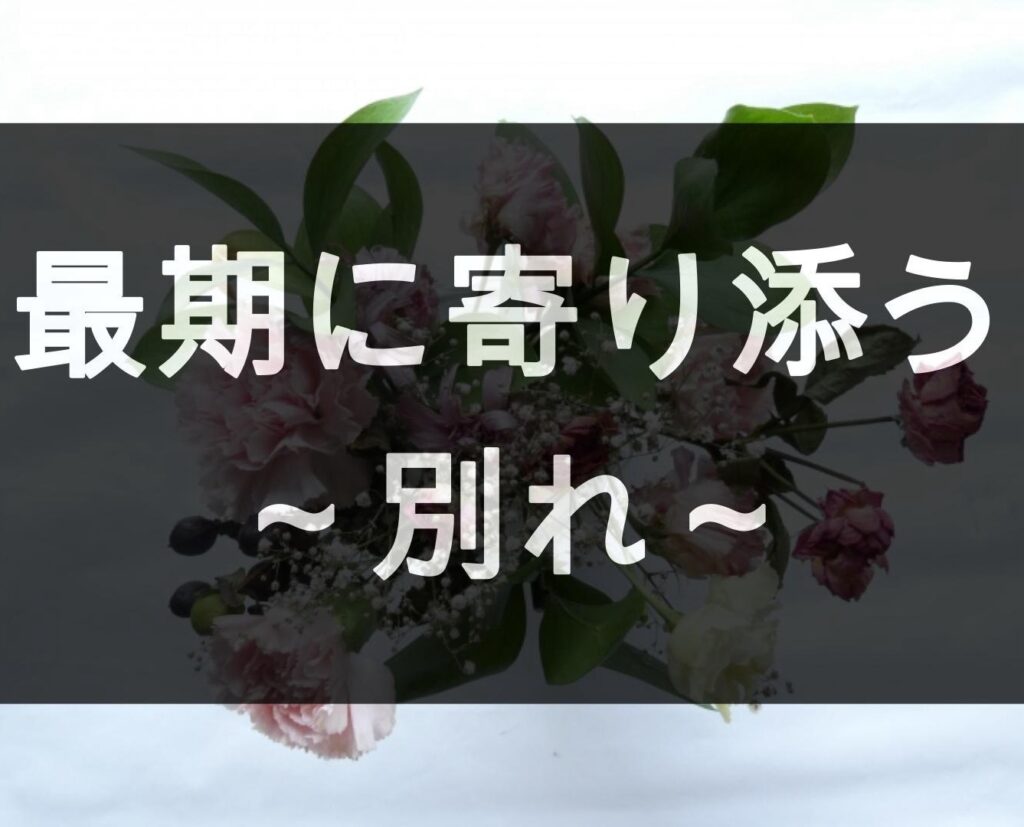
福祉の仕事をしていると、日々の暮らしの中でたくさんの出会いがあります。利用者さんとの何気ない会話や、ご家族とのやり取り、地域の方々との関わり。その一つひとつが積み重なっていくうちに、気がつけば仕事を超えて大切な絆になっていることがあります。
そして時に、その方の「最期」に立ち会うこともあります。仕事でありながら、同時に一人の人間として心を揺さぶられる瞬間に直面します。今回は、私自身の体験をもとに感じたことをお話ししたいと思います。
日常の積み重ねで育まれる絆|最期に寄り添う関係性の土台
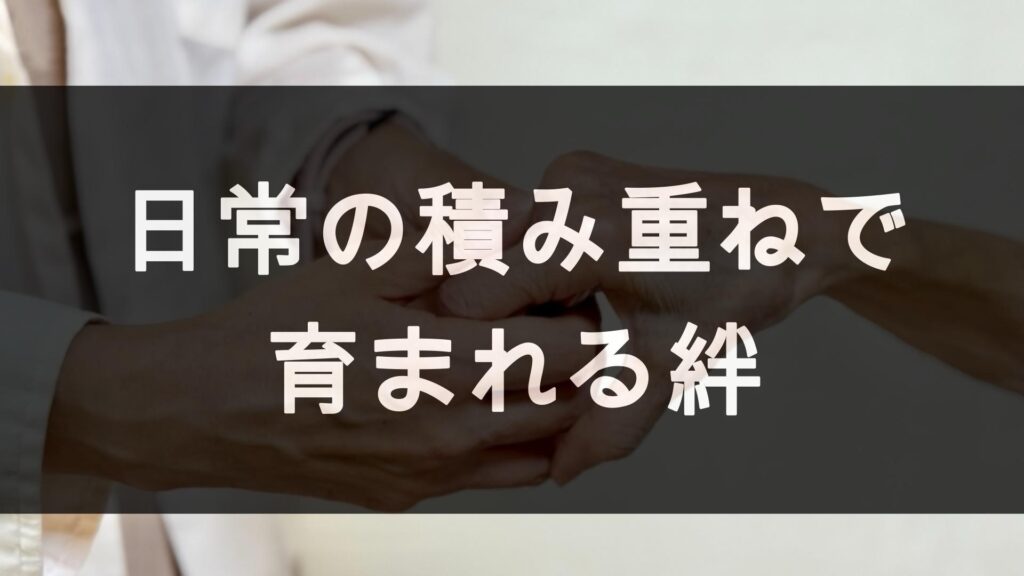
そういった時に不思議と思い出すのは、その方々と過ごした日常の風景です。
「おはようございます」
「こんにちは」
「いつもありがとうございます」
「また明日」
「おでかけ楽しみですね」
「忘れ物をしてしまい申し訳ありません」
「今日は調子が良さそうですね」
「あの時は申し訳ありません」
そういった日常の小さなやりとりの積み重ねが仕事を超えた温かい繋がりに変わっていきます。
最期に寄り添うとは|福祉現場で大切にされる関わり方
ギターが好きなAさん
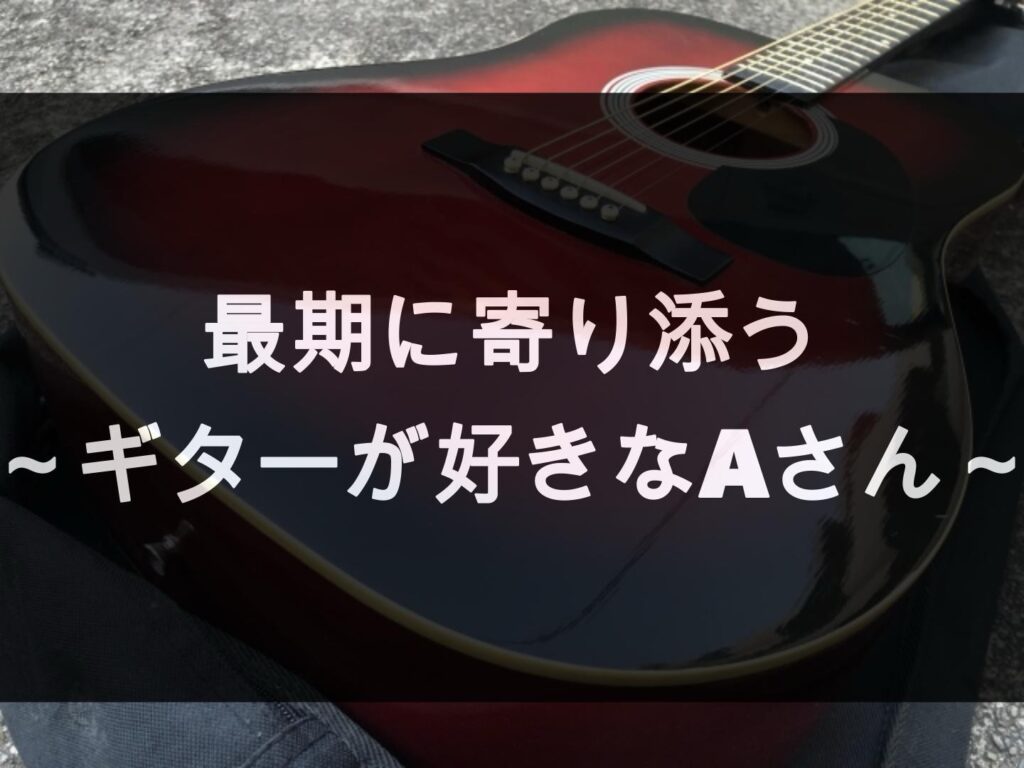
私が担当していた利用者さんの最期に寄り添った時のエピソードです。
彼とは、私が学生時代に施設にはじめてきた際に音楽を通じて知り合いました。彼はギター演奏が大好きで、私もギターを弾くのが好きだったため、ぐんと距離が縮まっていきました。それからは、音楽だけではなく日常の多くの時間を重ねて仲良くなっていきました。
彼の学校時代、「教室からいなくなったかと思えば音楽室にいた」というくらい音楽が大好きだったとの話をお母様から伺いました。
彼との時間を重ねていく中、大きく体調を崩し長期間入院されるようになりました。それに伴って、お会いする機会も減ってしまいました。
しばらくお会いしていなかった中で最期が近いというお話し来て、職員らで代わり代わり面会に行かせて頂きました。
利用者さんは、病室では眠っていることが多いとのことでしたが、面会の際はしっかりと起きていました。
そして、利用者さんご本人とお母様に、「施設に置いているギターをこれからも使ってもいいですか?」と尋ねた際に、病床に伏せ、体を重そうにしながらも右手を数十センチほど挙げられて、お決まりの「わかった」という返事をされていました。

それからほどなくしてご臨終の知らせが来ました。
告別式と出棺では、彼との思い出の曲である松田聖子の『青い珊瑚礁』を彼のギターとともに演奏し、皆さんで合唱してお見送りをしました。
そして告別式では、私が知っている方から知らない方まで大勢が参列されていました。彼と関わった時間は最期までのほんの数年間でしたが、告別式を通じて、彼やそのご家族の人生の一部を垣間見れた気がしました。最期の送り方は様々ですが、人生の集大成やフィナーレとも表現したいような言葉にはできない気持ちにさせられました。
責任感が強いBさん
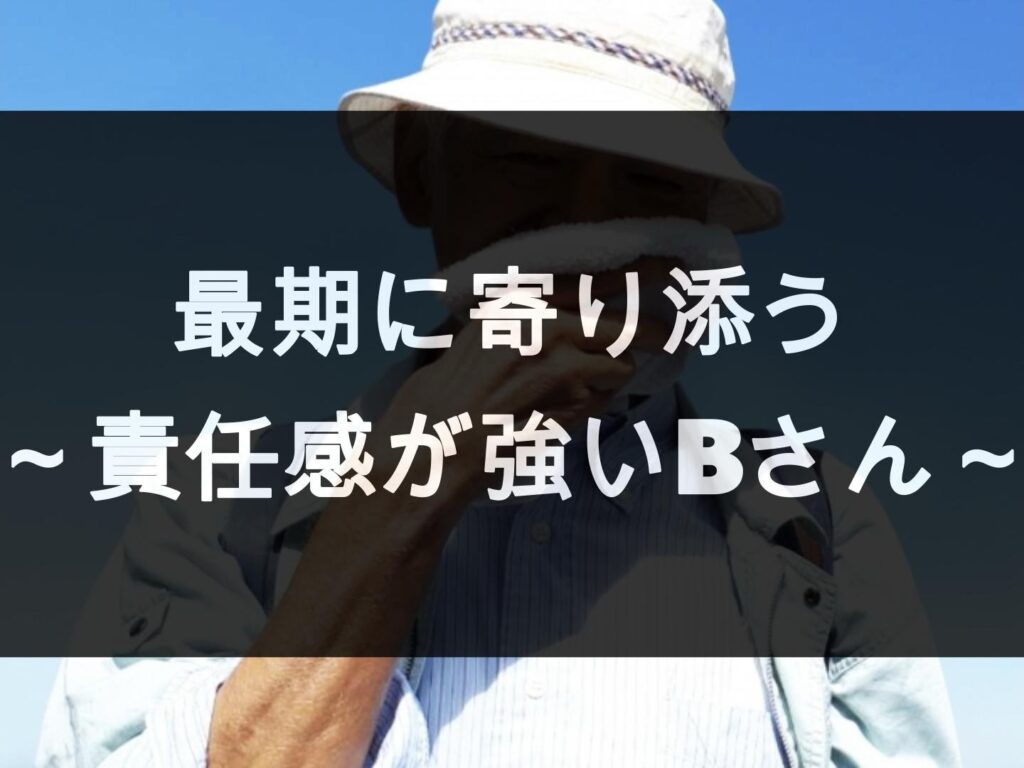
私が担当していた利用者さんのお父様の最期に寄り添った時のエピソードです。
私が担当するようになってほどなく、少しずつお父様の体調が悪くなっていきました。
そして、利用者さんが実家に帰る頻度が、毎週末、隔週、そして月に一回と、だんだんと少なくなっていきました。また、定期的に利用者さんの支援にまつわる面談を実施させて頂いていましたが、施設に来る体力もなくなっていきました。
そのため、利用者さんのご様子の報告とお父様の見守りを含め、隙間時間を見つけて定期的に電話をかけてお話しをするようにしていました。
お父様とお話ししている中で、
「家で見る自信がない」
「自分の弱い姿を見せたくない」
「毎朝ベッドから起きて体を動かすのが辛い」
「特に冬場は体が曲がらなくて辛い」
といったように、家族や周りにはあまり弱みを見せない一方で、電話越しでは弱音を吐くように話される時が多くありました。
入院期間中やリハビリ生活となっても考えは同じで、親族の面会は極力遠慮されていたようです。また、目標がないためリハビリにもあまり精が出ず、日々こなすような形になってしまっていたそうです。
そのような中、ご臨終の知らせが届きました。いつものように朝食を食べ終え、ヘルパーがお父様のもとを少しだけ離れた間に、だったとのことです。
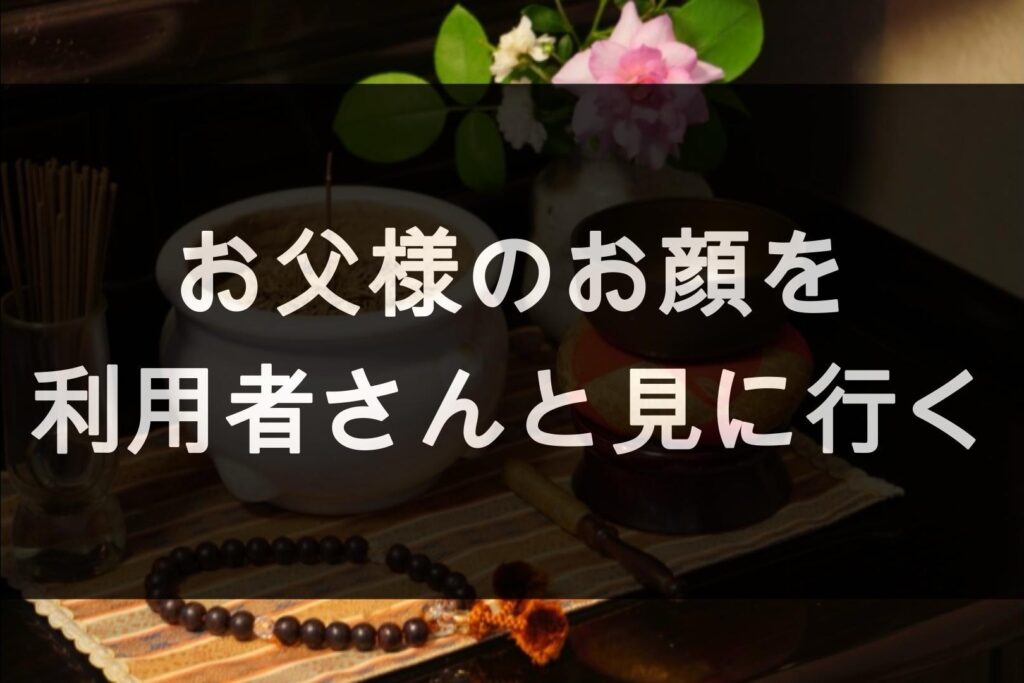
私は、利用者さんがお父様のお顔を見に行くため付き添いをさせて頂きましたが、生前意思の強かったお父様が決して見せなかったとても安らかな表情で眠られていました。
利用者さんは重い障害があり、双方向の言葉でのコミュニケーションは難しい部分がありますが、利用者さんのご家族がご臨終の際、利用者さんは別のところにいましたがそのタイミングで珍しく大きな声を出しながら泣かれていたとの報告が挙がっていました。
また、ご臨終の後、告別式や葬儀のことで利用者さんにお父様のことをお話ししたり、お気持ちを伺ったりした際に、決まってポロッと涙を流されていました。
利用者さんとお父様それぞれに大切にしている想いがあること、そして言葉を超えた繋がりがあることを強く感じさせられました。
おわりに|最期に寄り添う中で私たちが受け取ったもの
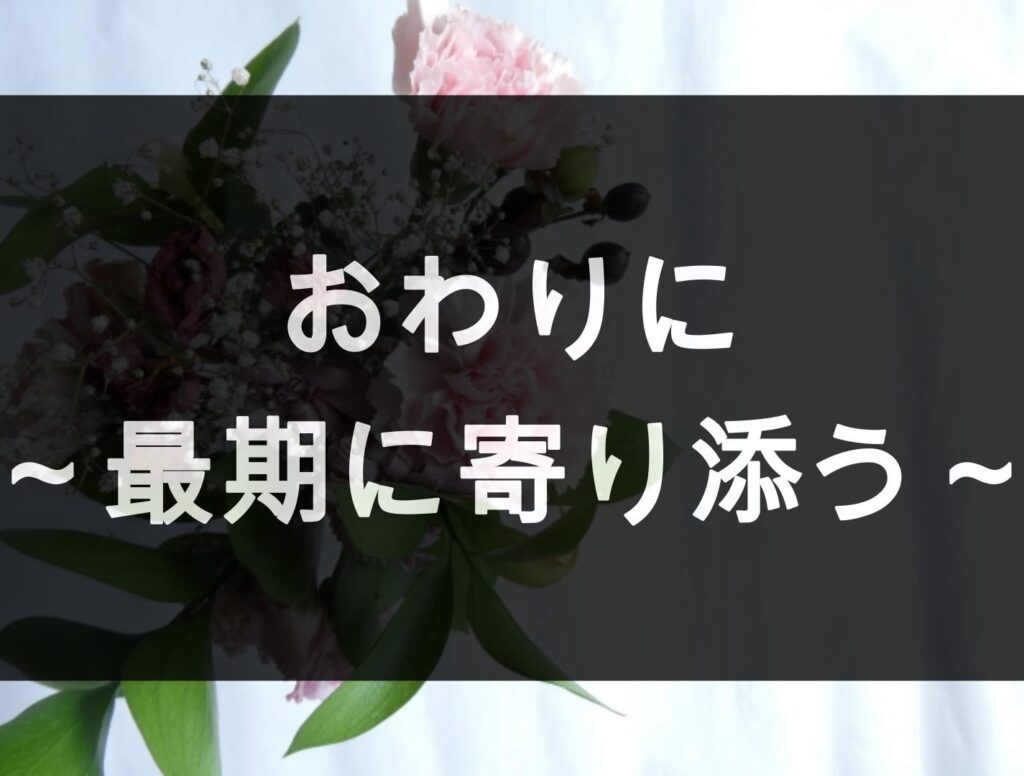
いかがだったでしょうか?
最期に寄り添うことは、悲しく、そして辛い出来事かもしれません。
しかし私は、これは対人援助職の最大の役割でもあると考えています。
最期に寄り添うことは、決して簡単なことではありませんが、その中に確かな絆と感謝があることを私はこれまでの経験から学びました。
そして、その根拠となるのが日々の小さな関わりの積み重ねです。
人生の最期に安心をもたらす力になる。そう信じて、これからも人としての繋がりを大切にしていきたいと思います。
あわせて読みたい関連記事
・延命治療とは? 知っておきたい基礎知識と後悔しないための考え方
