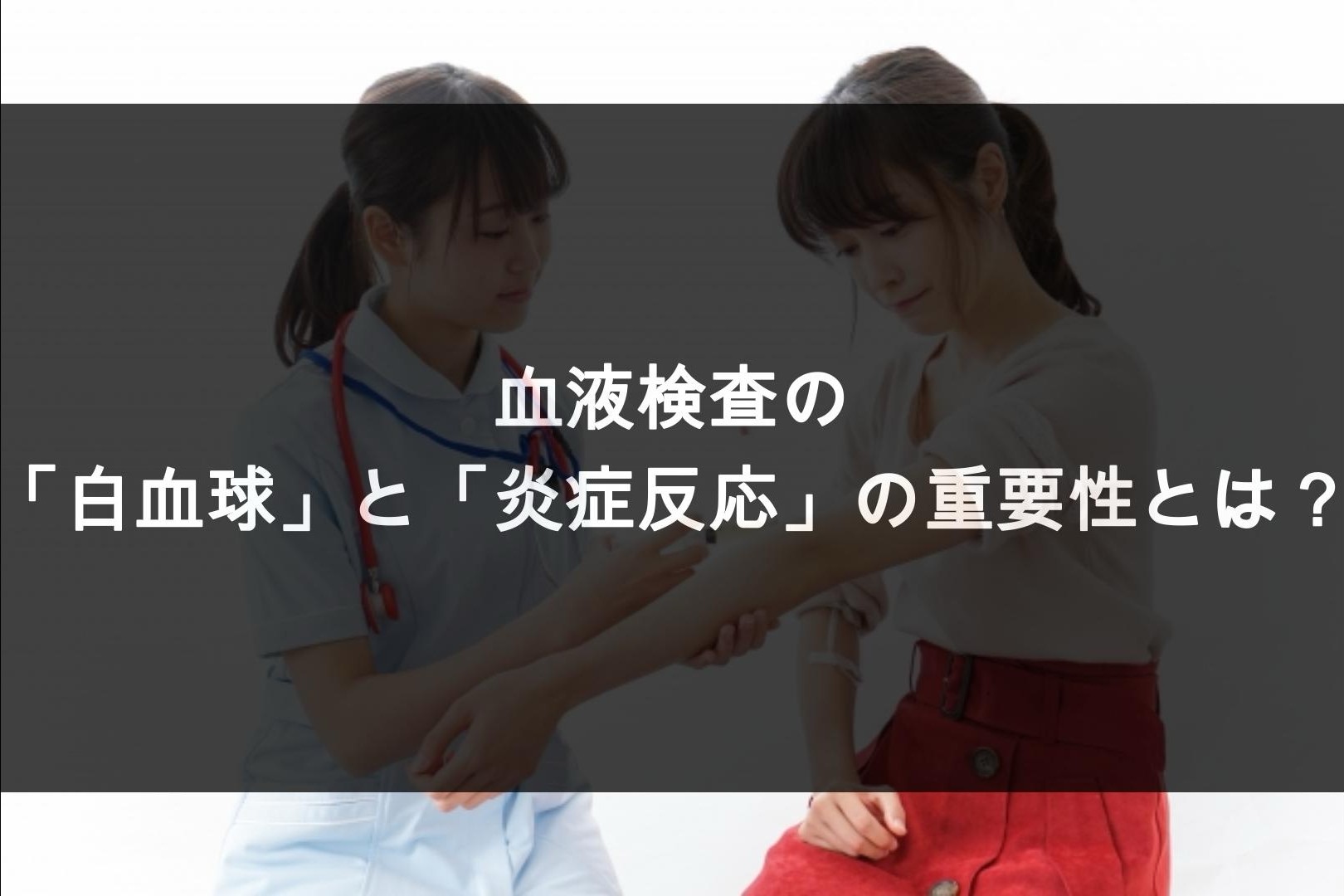はじめに
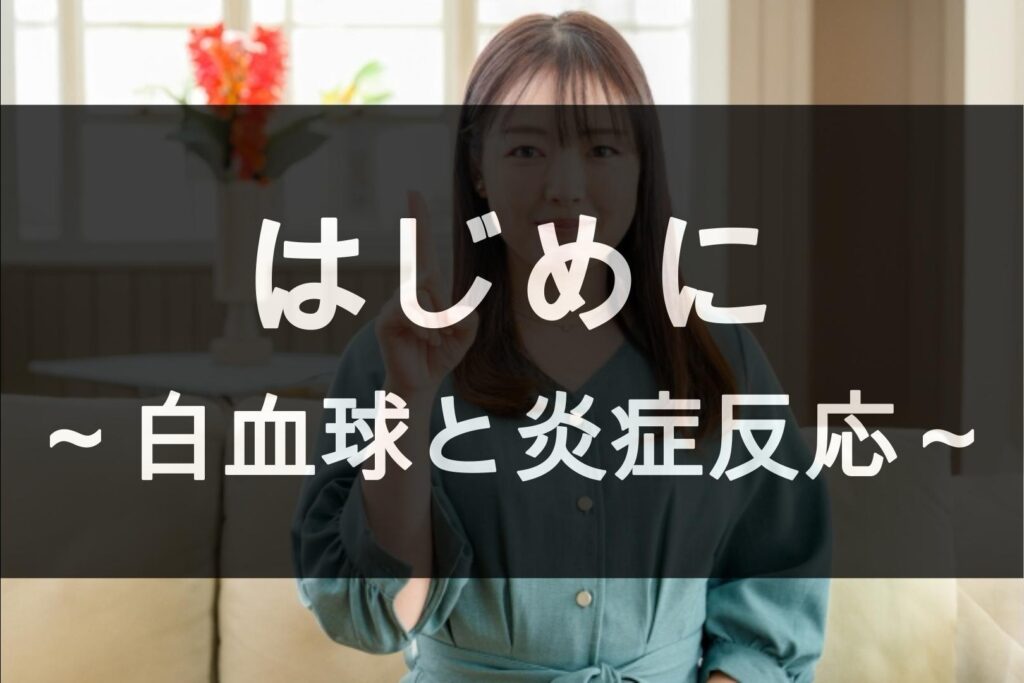
福祉の現場では、利用者さんの健康状態を日々観察することがとても大切です。その中でも、病院で行われる「血液検査」の結果を理解することは、体調変化にいち早く気づくための重要な手がかりになります。特に「白血球数(WBC)」と「炎症反応(CRP)」は、感染症や炎症を把握するうえでよくチェックされる項目です。
本稿では「白血球数(WBC)」と「炎症反応(CRP)」の概要と、福祉現場での活かし方、そして私が現場で経験した事例をご紹介したいと思います。
白血球数(WBC)とは?
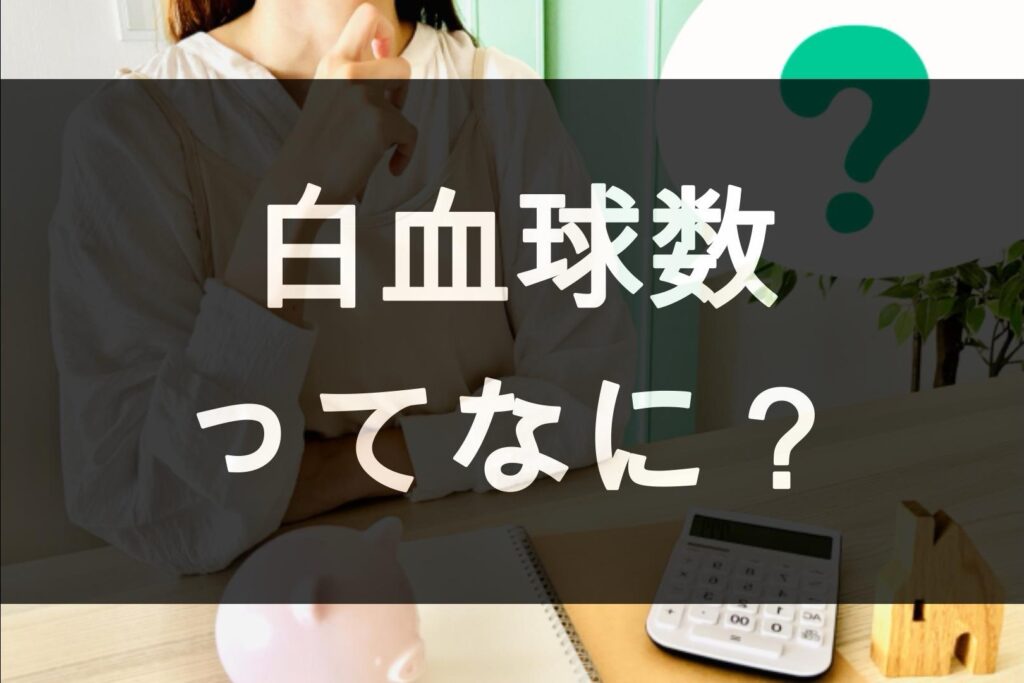
白血球数とは、体の中に侵入してきた細菌やウイルスを攻撃する「免疫の主役」であり、血液検査では WBC値(白血球数)を測定します。正常範囲より高ければ「感染や炎症の可能性」があり、低ければ「免疫力の低下」を示すことがあります。風邪や肺炎などの感染症では、CRP値(次の章で説明)が高くなるより前にWBC値から高くなる傾向にあります。これは、これから身体が細菌やウイルスと戦う準備をし始めているというサインでもあります。
炎症反応(CRP)とは?
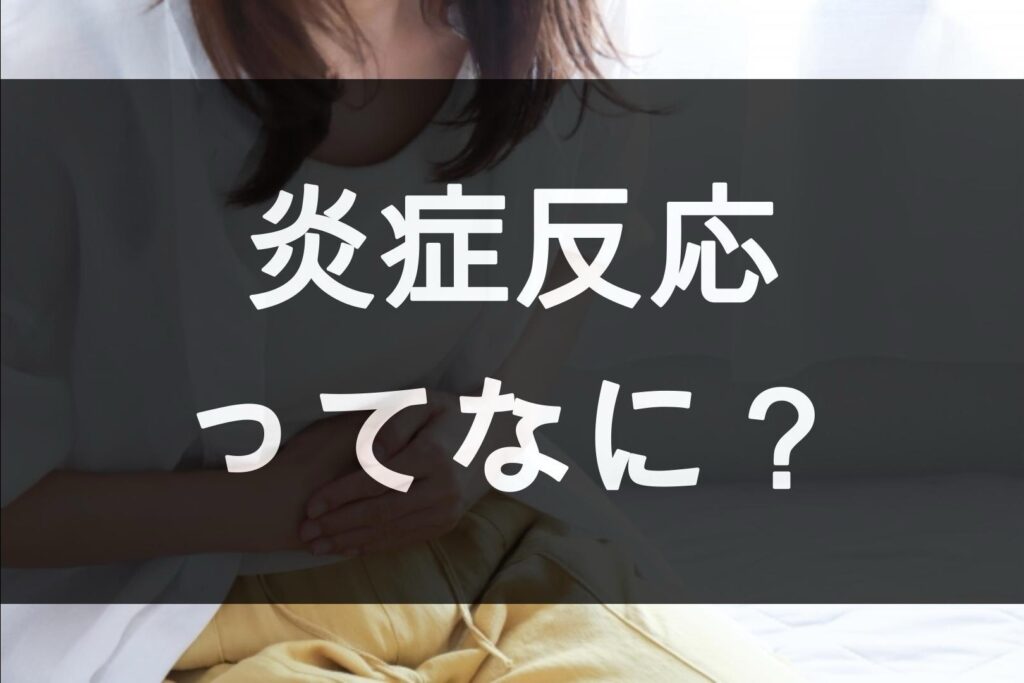
CRPは、体の中で炎症が起きたときに血液中に増える物質で、炎症の「程度」を数値で示すため、感染やケガの重症度を把握する指標となっています。
よくある事例:
・風邪の初期 → CRPはあまり上がらない(WBC値から先に上がる傾向にある)
・肺炎や尿路感染症など全身に影響する炎症 → CRPが大きく上昇
・風邪やインフルエンザなどのウイルス感染はCRPがやや上昇
福祉現場での活かし方
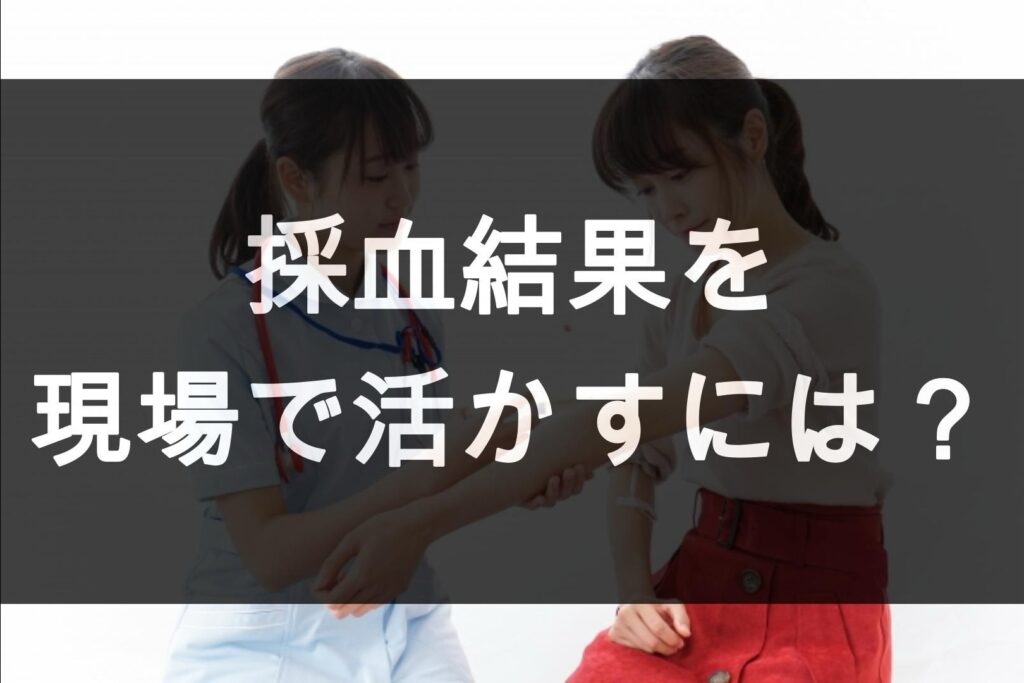
福祉職は医師や看護師ではありませんが、利用者の生活を支える立場として血液検査の意味を理解しておくことは役立ちます。
福祉支援員が出来そうなこと:
・発熱時にWBC・CRPの数値を把握することで「ただの風邪か」「重い感染か」を看護師や医師と共有できる。
・傾向として、医師が処方したものが抗生物質や点滴なら細菌感染を疑いとし、咳止めや痰切りであればウイルス感染を疑っている場合が多い。
・利用者さんやご家族に「数値が高いので注意が必要です」と説明する際の根拠になる。
・感染症が広がるのを早期に察知し、他の利用者への感染予防につなげられる、
利用者さんが尿路感染症になった時のエピソード
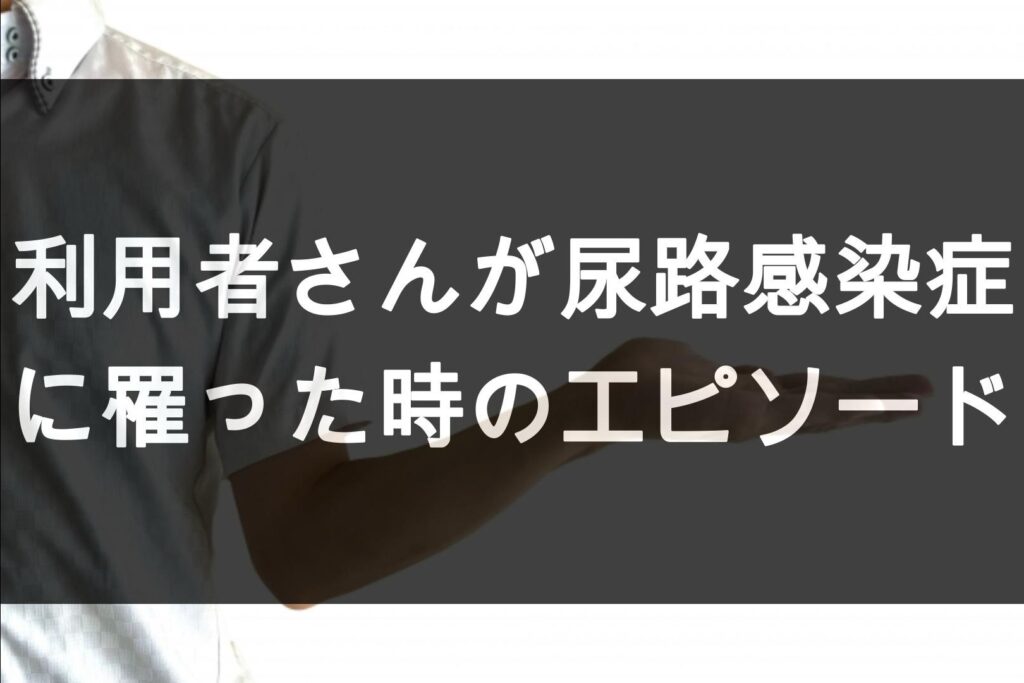
次は、私が担当していた利用者さん(50代男性)が尿路感染症になった時のことについてお話ししたいと思います。
まず尿路感染症とは、尿をつくる腎臓から尿道までの「尿路」に細菌が侵入して炎症を起こす病気です。最も多い原因菌は 大腸菌 で、尿道口から上にさかのぼって感染します。
ある時、利用者さんが高熱を出して気だるそうにされていました。すぐにかかりつけの病院を受診し、血液検査を行いました。すると、炎症反応(CRP)の値が19というとんでもなく高い数値を叩き出しており、そのほか検査を行い、医師からは尿路感染症と診断されました。
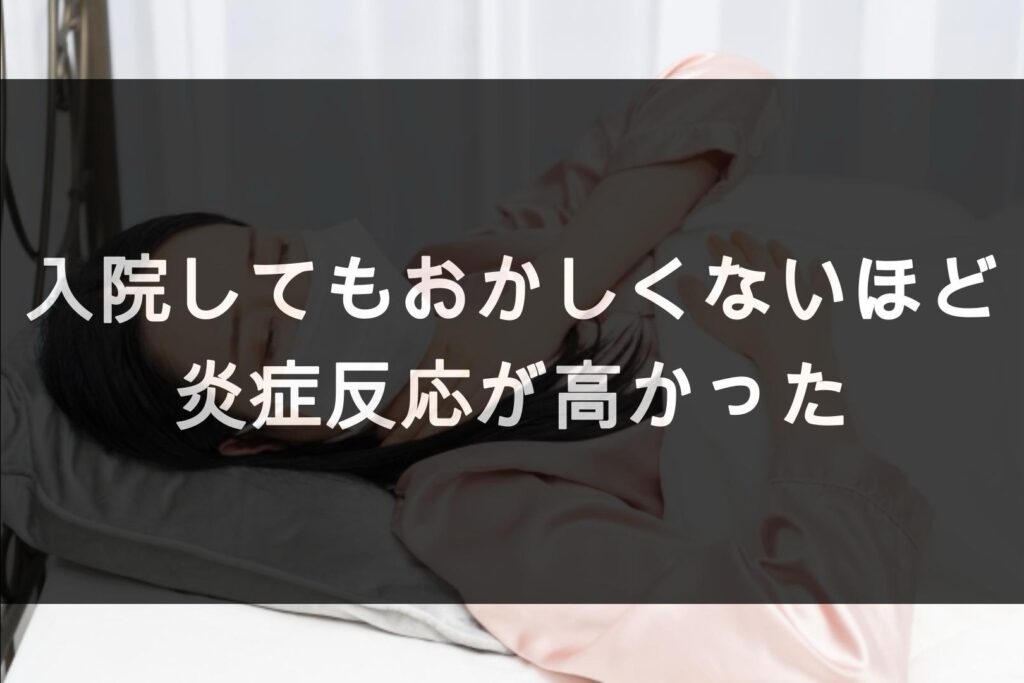
一般的にこのくらいの数値が出ていたら、入院レベルで、立っていることもままならないと言われるくらいです、ですが驚くことに、その時の利用者さんは、障害ゆえに言葉を話すことは出来ませんが、いつものように介助を受けながらトイレまで歩いていったりご飯を食べたりされていました。
そのような症状でしたので、通所はお休みし、しばらくはグループホームで静養することとなりました。その時の対応を私が行なっていました。

静養期間中のある日、利用者さんのご家族が訪問され、お見舞いと合わせて利用者さんの大好物のプリンを買ってきてくれていました。
利用者さんとご家族、私とテーブルを囲み、ご家族がその利用者さんの隣に座り声をかけると、本人はポロッと涙を流されていました。
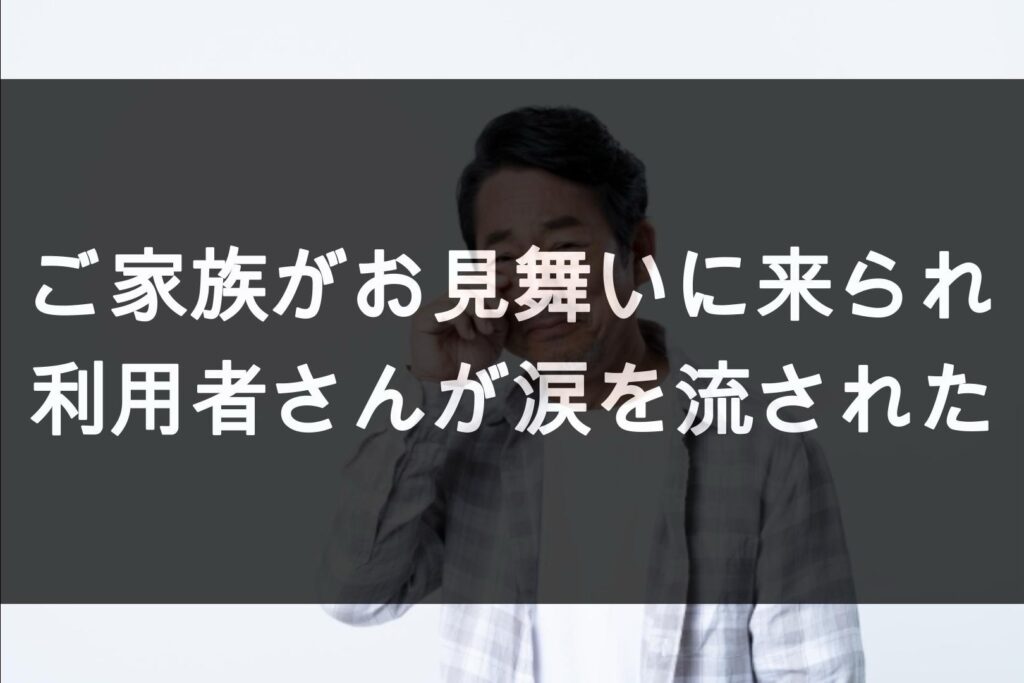
私はこの時はじめてその利用者さんが涙を流される様子を見ました。また、これまでの利用者さんの辛い経緯も少なからず見ていたので、利用者さんの心に触れた機会でもありました。
障害のある方は「今日は体調が悪い」「辛いんだ」「病院に行きたい」「休みたい」などと言葉や行動で気持ちを表現することが難しい部分があります。
ですが、だからこそ、いつも見ている人達が細かな様子の変化に気がつき、必要な対応を行い、日々寄り添っていくことが大切なのだと感じます。
おわりに
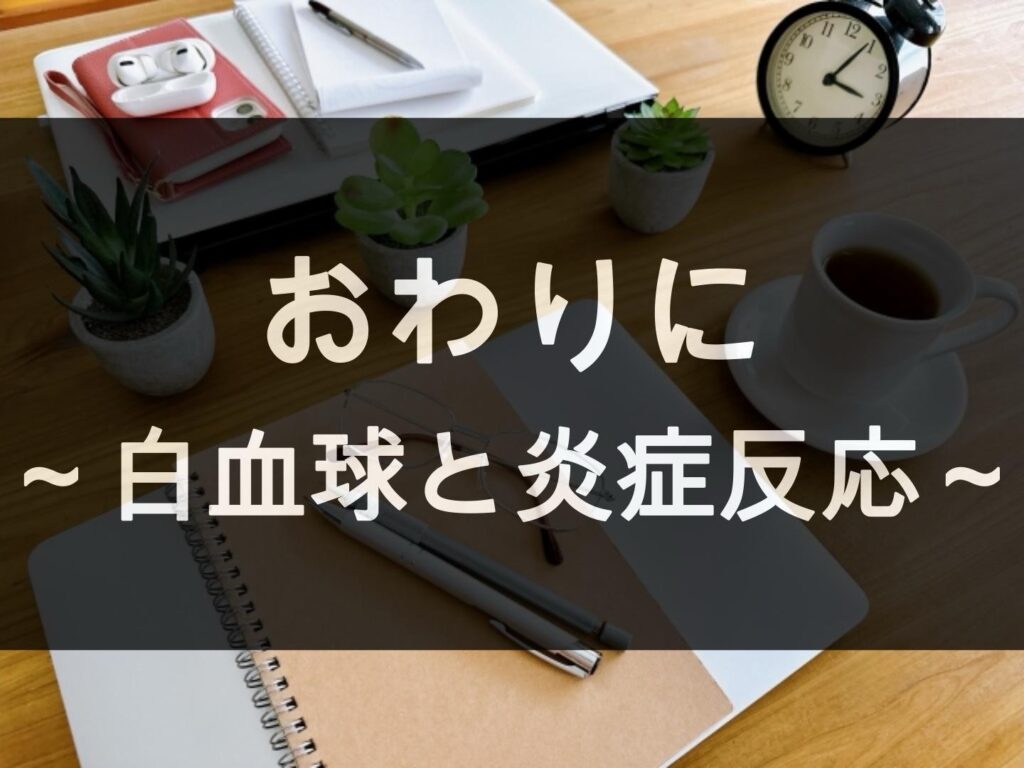
福祉の現場において、利用者さんの小さな体調変化に気づくことはとても重要です。その際に、医療現場で使われる白血球数(WBC)や炎症反応(CRP)の意味を理解しておくことは、大きな手がかりとなります。数値そのものを診断するのは医師の役割ですが、福祉職が基本的な見方を知っておくことで、医師や看護師との連携がスムーズになり、利用者さんへの支援もより安心・的確なものになります。
また、数値や症状をただ「情報」として受け取るのではなく、その背景にある利用者さんの想いにも目を向けることが大切です。体調の変化や行動の裏には、本人が言葉にできない「辛さ」や「安心したい気持ち」が隠れていることがあります。だからこそ、福祉職は医療的な知識と同時に、人として寄り添う姿勢を持ち続ける必要があります。
白血球数(WBC)や炎症反応(CRP)は単なる数値以上の意味を持ち、利用者さんの生活を支える私たちにとって「早期発見」と「安心の提供」をつなぐ架け橋となります。これからも医学的な知識を学びながら、日々の観察力と寄り添う心を大切にしていきたいです。