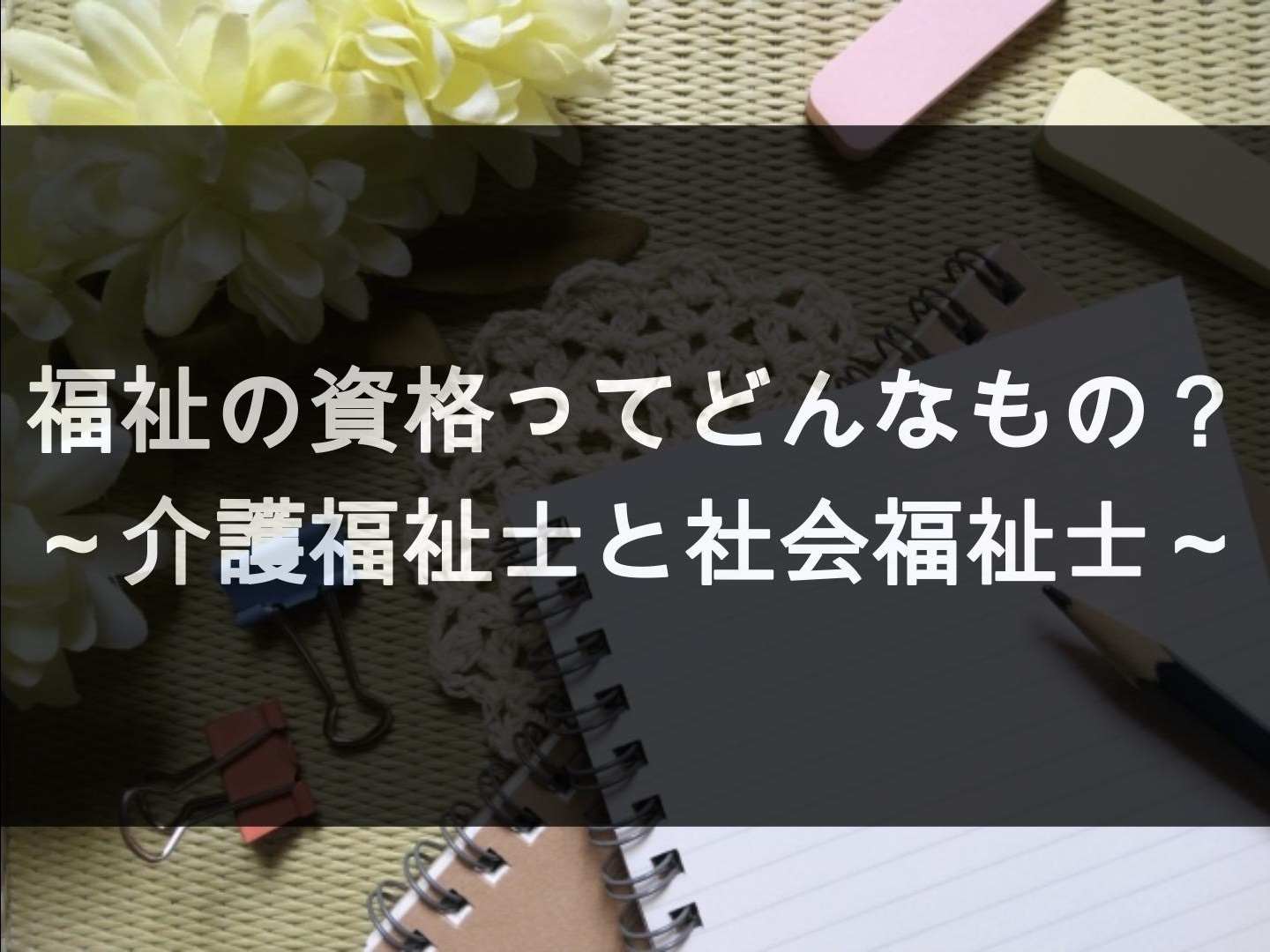はじめに
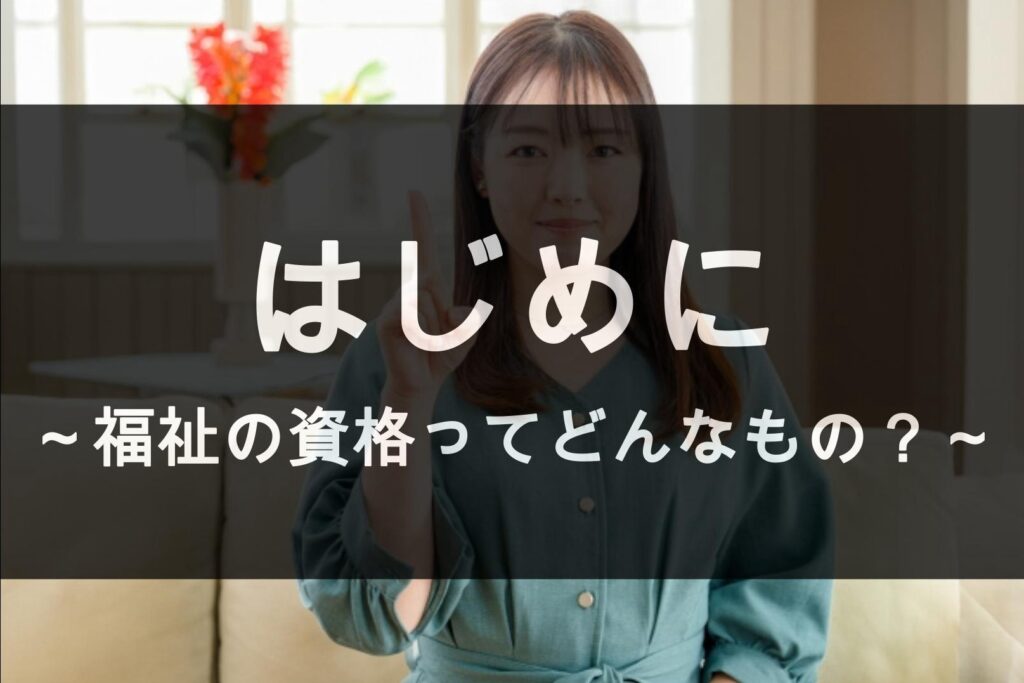
今回は福祉領域の代表的な資格としてよく言われる介護福祉士と社会福祉士についてお話ししていきたいと思います。
福祉の仕事をする上では、このような専門の資格を持っていると、採用の面で有利になるといったように社会的信用が高まったり、お給料に手当がついたり、資格取得を通して仕事をする上でも必要な知識や経験を育むことが出来たり、などといったメリットがあります。
その一方で、事業所や業務形態によっては必ずしも資格が必要というわけではないという部分もありますので、それぞれの役割を知っておくのは大事かなと思います。
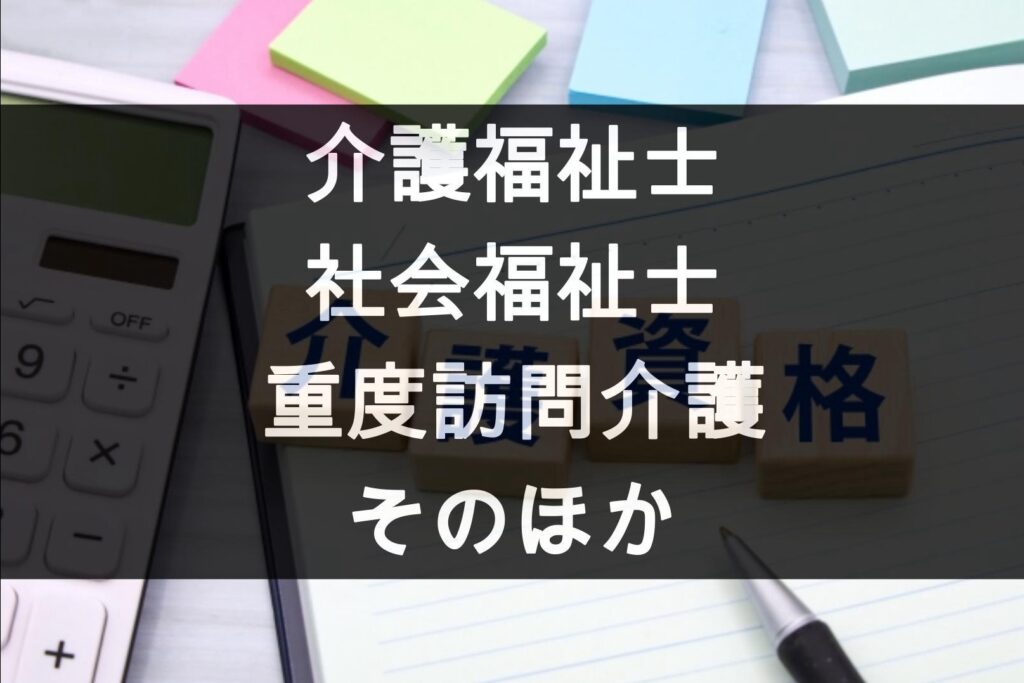
そのようなことがありましたので、かく言う私も生活介護事業所(形態は違いますがデイサービスと言うと分かりやすいかもしれません)に10年近く勤めていましたが、入職するにあたり、大学卒業はしていたものの、福祉の資格は持っていない状況からのスタートでした。また入職後、グループホームに住まわれている利用者さんの対応をする必要があり、それを機に重度訪問介護の資格を取得したという経緯はありました。
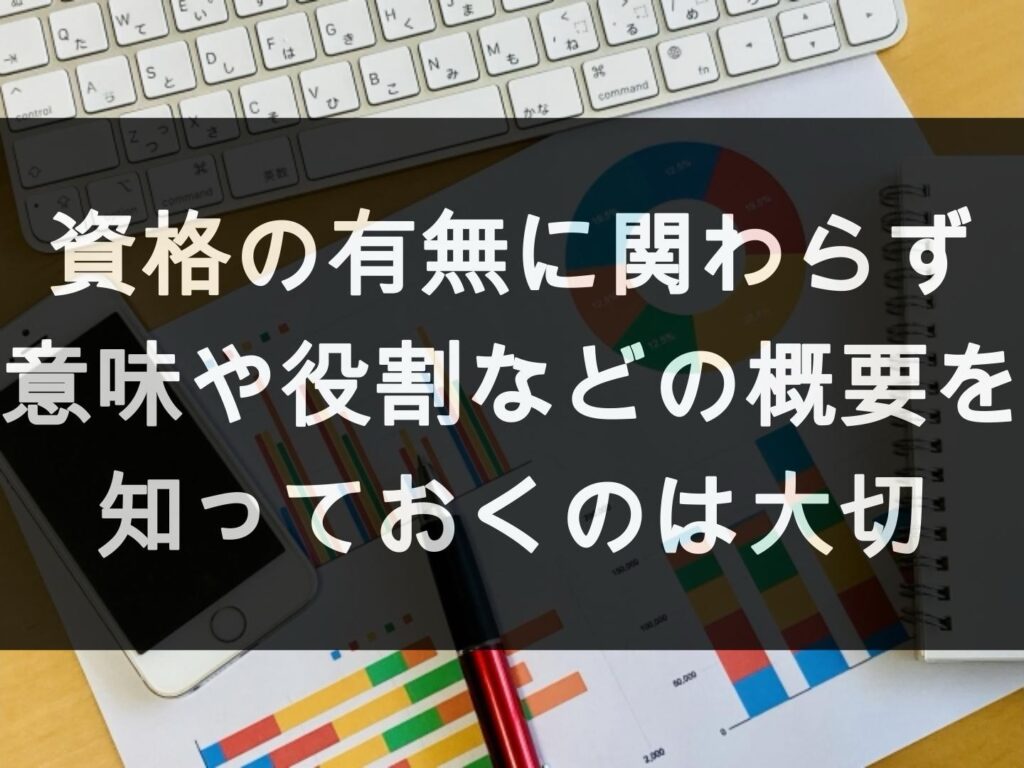
しかし、資格の有無に関わらず「介護福祉士」と「社会福祉士」に関しては、様々な場面で使われる言葉でもありますので、少なくともその言葉の意味と役割などの概要だけでも知っておくと便利だと思います。
実際に名前は聞いたことがあっても、実際にどのような役割があるのか、どんな仕事をしているのかは意外と知られていないケースもあります。そのため、今回はこの2つの資格を中心に福祉分野での専門資格についてご紹介していきたいと思います。
介護福祉士とは?
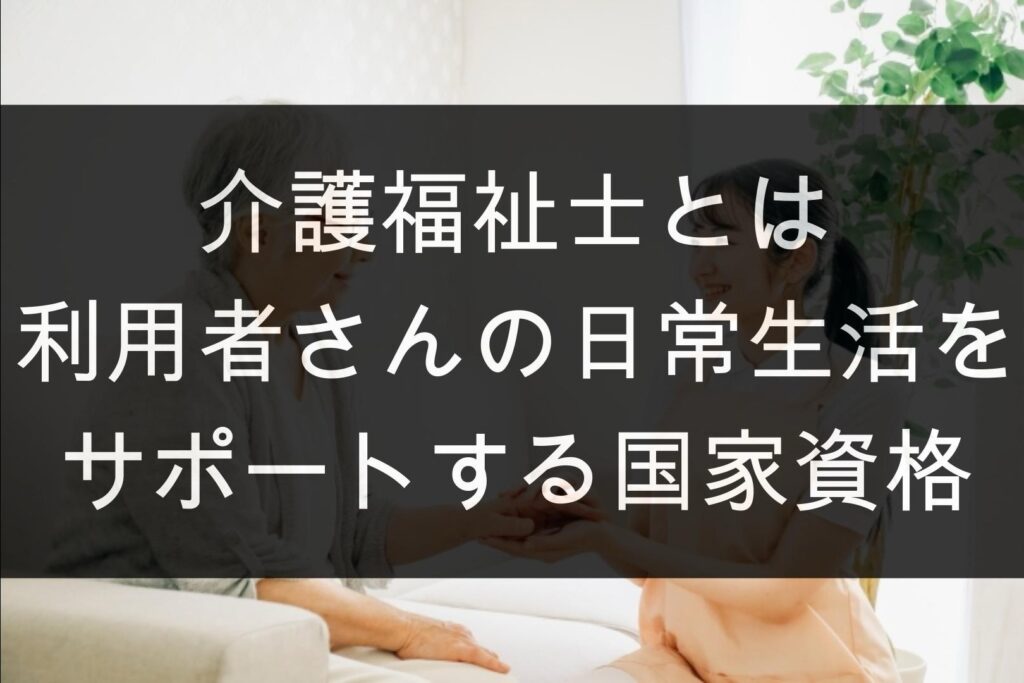
介護福祉士は、介護のプロフェッショナルとして高齢者や障害のある方の日常生活をサポートする国家資格です。食事、入浴、排せつ、衣類の着脱などの身体介護だけでなく、生活全般に関する助言や家族への支援も行います。
ヘルパーやパート、アルバイトなどとして一般的に「介護の仕事をしています」といった場合、介護福祉士の資格を持っている方である場合が多いです。必ずしも介護福祉士の資格を持っている訳ではありませんがこちらが大部分を占めている印象があります。
• 活躍の場:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、訪問介護など
• 取得方法:養成校での学習、または実務経験(3年以上+実務者研修)を経て国家試験に合格することで資格取得
• やりがい:利用者と直接関わり、「ありがとう」と感謝される場面が多く、人の生活を支える実感を得られる仕事です。
社会福祉士とは?
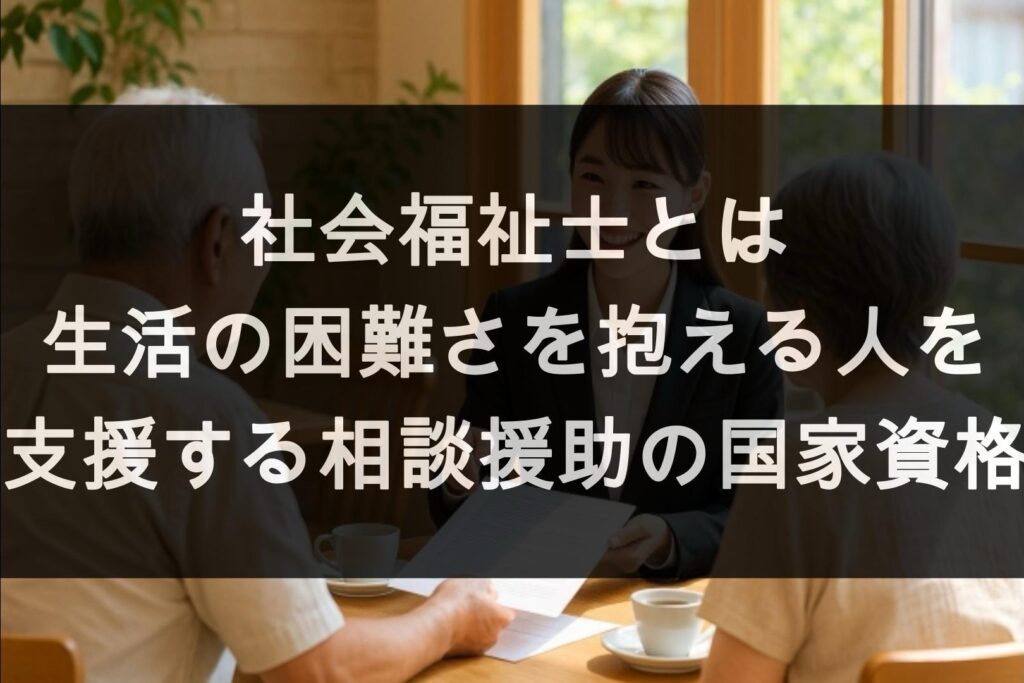
社会福祉士は、生活上の困難を抱える人を支援する相談援助の専門家です。経済的な問題、障害や病気、家族関係など、幅広い生活課題を抱える方に対して相談に乗り、制度やサービスの利用につなげる役割を担います。
社会福祉士は管理者や相談員など総合的なコミュニケーション能力が必要とされる立場の仕事です。また、資格取得の難易度が介護福祉士に比べて高いこともあり、介護福祉士のケースと比べてこの資格を持っている人は少ない印象です。しかし、「社会福祉士を持っている」と言えば一気に社会的信用が高まりますし、資格取得を通じて福祉で求められている倫理観を学ぶこともできますので、ご自身の将来像を描きながら目指してみるのも良いと思います。
• 活躍の場:福祉事務所、病院、障害者支援施設、高齢者施設、地域包括支援センターなど
• 取得方法:大学や養成施設で指定科目を修め、国家試験に合格することで資格取得
• やりがい:制度や地域資源を活用しながら、利用者の「自立した生活」を後押しできる点に魅力があります。
その他の代表的な福祉資格
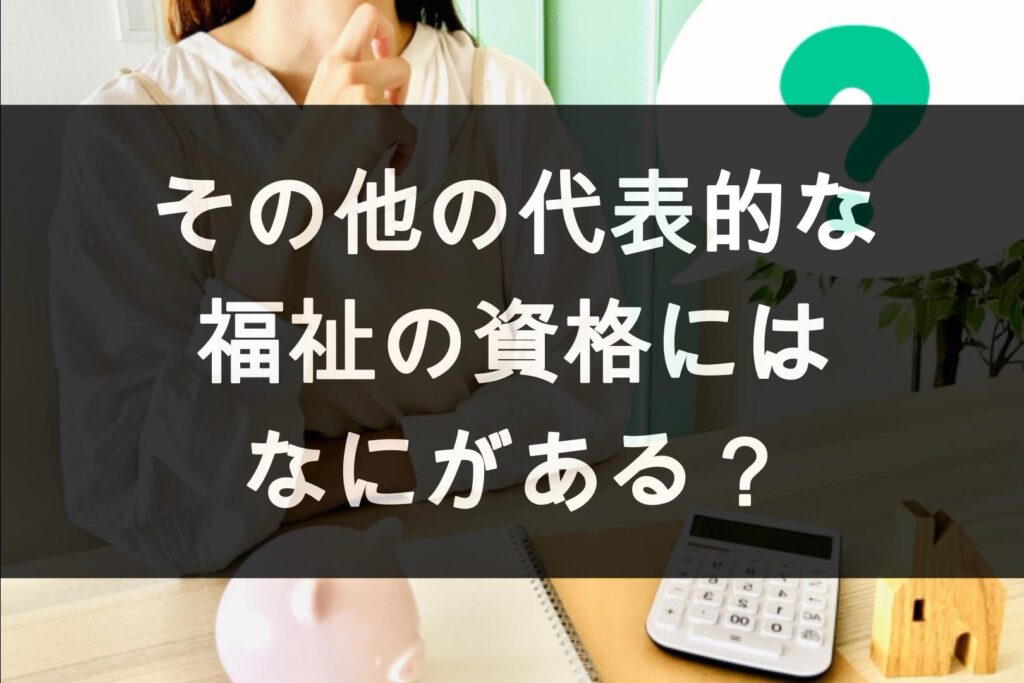
福祉分野には、介護福祉士や社会福祉士以外にも多様な資格があります。
• 精神保健福祉士:心の病を持つ方の生活支援を専門に行う国家資格
• 保育士:子どもの成長を支える専門職(こちらも国家資格)
• ケアマネジャー(介護支援専門員):介護サービス計画(ケアプラン)を作成する役割
それぞれの資格が、子どもから高齢者まで幅広い世代を支えています。
おわりに
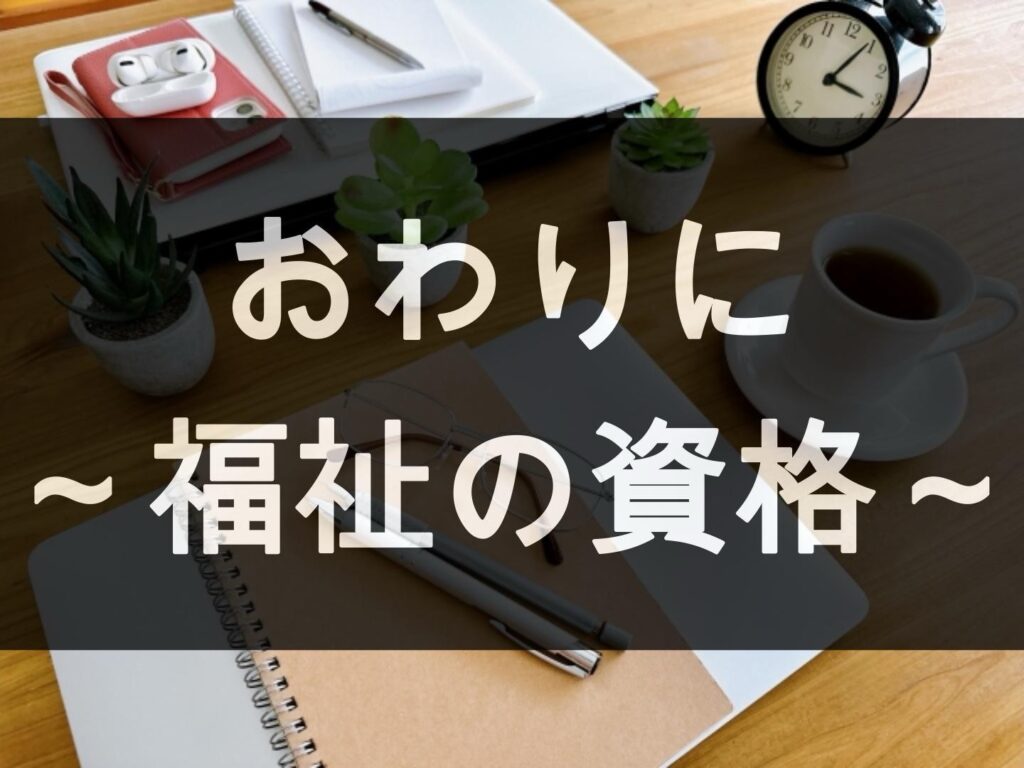
いかがだったでしょうか?
福祉の資格は、単なる肩書きではなく「人を支える力」を形にしたものです。
介護福祉士は、生活を直接支える専門職として、
社会福祉士は、生活課題を解決へと導く専門職として、
それぞれに大切な役割があります。
資格の有無に関わらず支援の現場に立つことはできますが、資格取得を通じて得られる知識や経験は、自分自身の成長や仕事への自信につながると考えます。これから福祉の仕事を目指す方にとっても、現在すでに現場に立っている方にとっても、自分の将来像を描きながら資格に挑戦してみる価値は大いにあるのではないかと思います。
少子高齢化が進む現代社会の中で、福祉の専門職の重要性はますます高まっています。人の暮らしを支える「力」を身につけて、一緒により良い未来をつくっていきましょう。