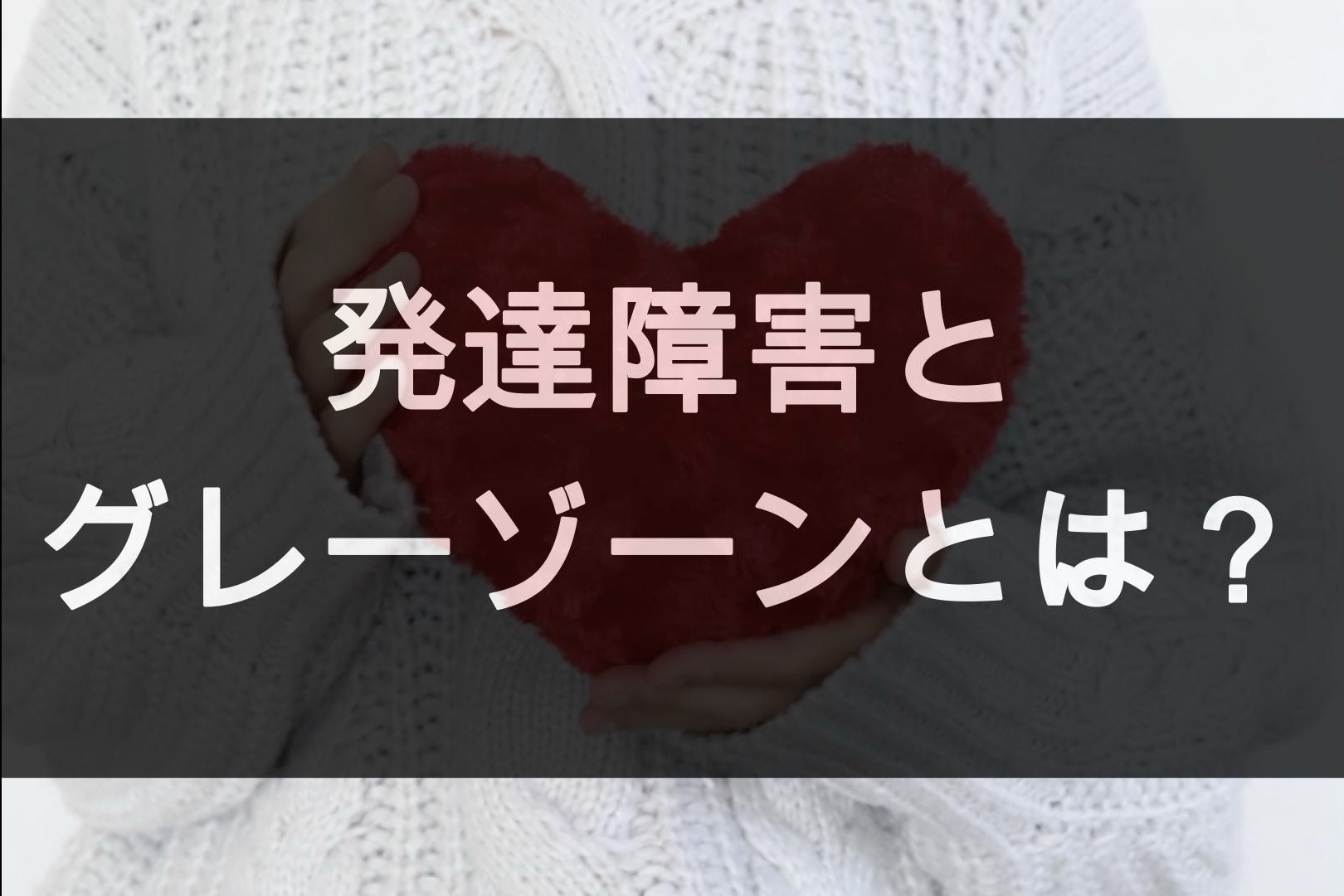はじめに
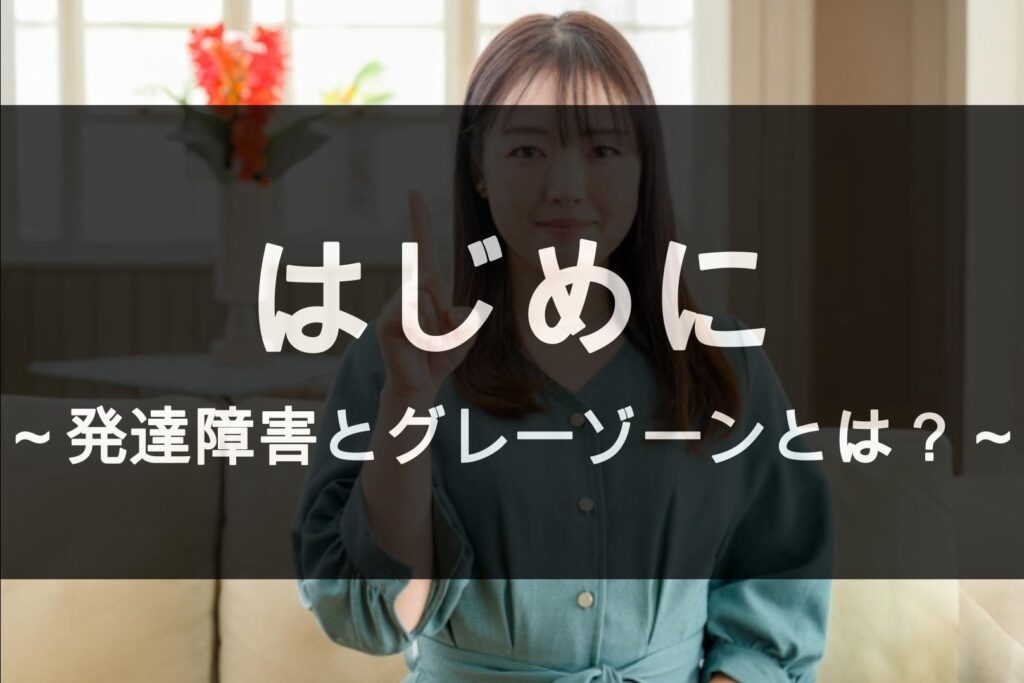
近年、発達障害やADHD、ASD(アスペルガー)、高機能自閉症、グレーゾーンといった言葉をよく聞くようになってきました。
これらは広義で発達障害と呼ばれいて、生まれつきの脳の発達の特性によって、社会生活やコミュニケーション、学習などに困難を感じやすい状態を指します。
障害にまつわる分野が広まっていく中で、「これまで自分が感じていた言葉に出来ないような生きづらさはADHDを持っていたからだったのか!」と気がつくといったように、一人ひとりがご自身の特性に目を向ける機会も社会的に増えてきているように感じます。
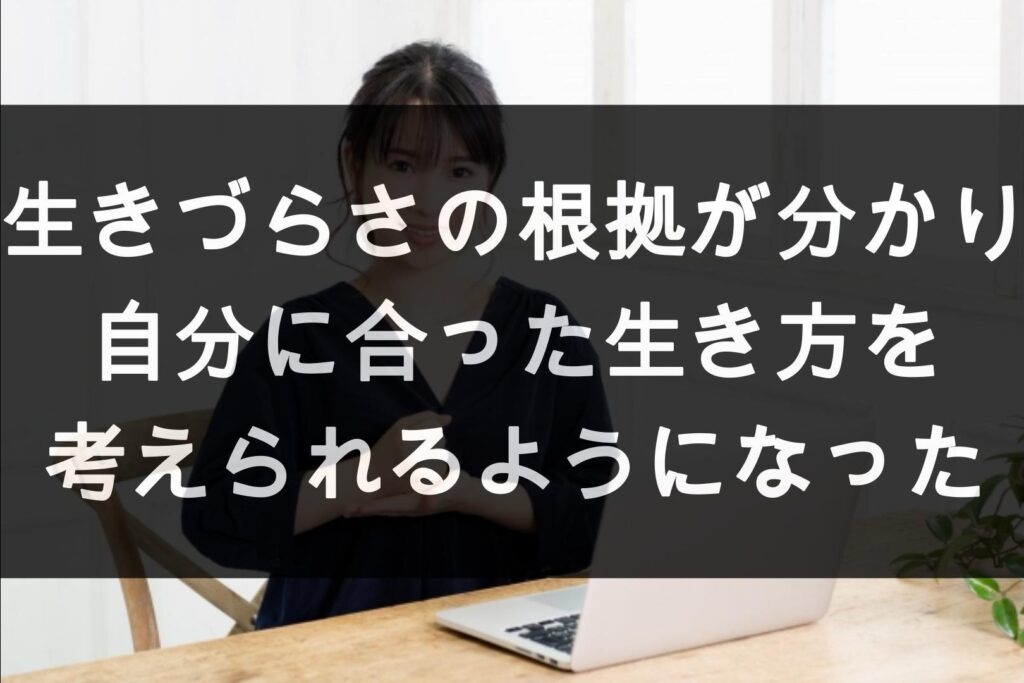
私の友人に、昔から悩んでいた自身の特性(人と会った後にスイッチが切れるようにどっと疲れる/注意散漫/過集中)が医師の診断もありADHDだったからだと知り、必要に応じて服薬治療をしたり物事の考え方を変えてみる実践をしたりすることで仕事を含めて社会生活が大きく改善していった方がいます。
単なる障害としてではなく、あくまで自他一人ひとりの特性(特徴)を知る指標として発達障害を知っておくことは、相手が大切にしている物事や世界観を知ることに繋がります。そういった指標を持つことで、思いやりや相手が困っていることの解決にも繋がると思います。
それでは、発達障害の具体的な内容に入っていきます。
発達障害の代表的なもの
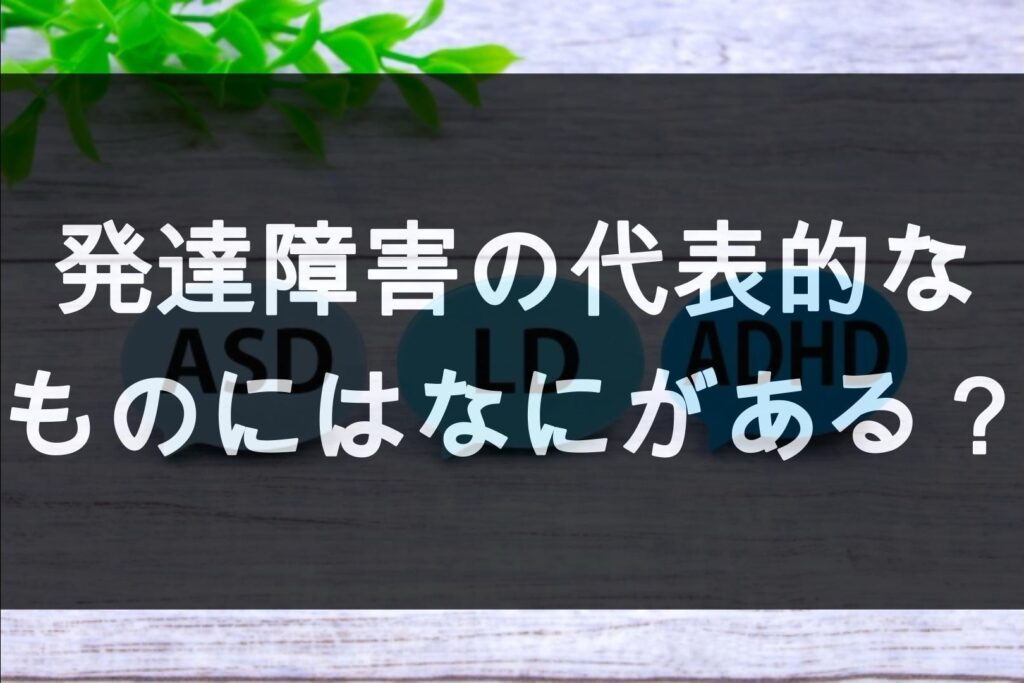
• 自閉スペクトラム症(ASD)
コミュニケーションや対人関係の難しさ、こだわりの強さが特徴。自閉症、アスペルガー(アスペと揶揄される時もある)などと言われることもあります。
• 学習障害(LD)
読む・書く・計算するなど、特定の学習分野に強い困難がある。
• 注意欠如・多動症(ADHD)
集中が続かない、不注意、衝動的な行動、多動といった傾向。
➡︎発達障害は「できる・できない」の問題ではなく、脳の特性の現れ方です。そのため、支援や環境の工夫によって本人の力を発揮できることが多くあります。
グレーゾーンとは?
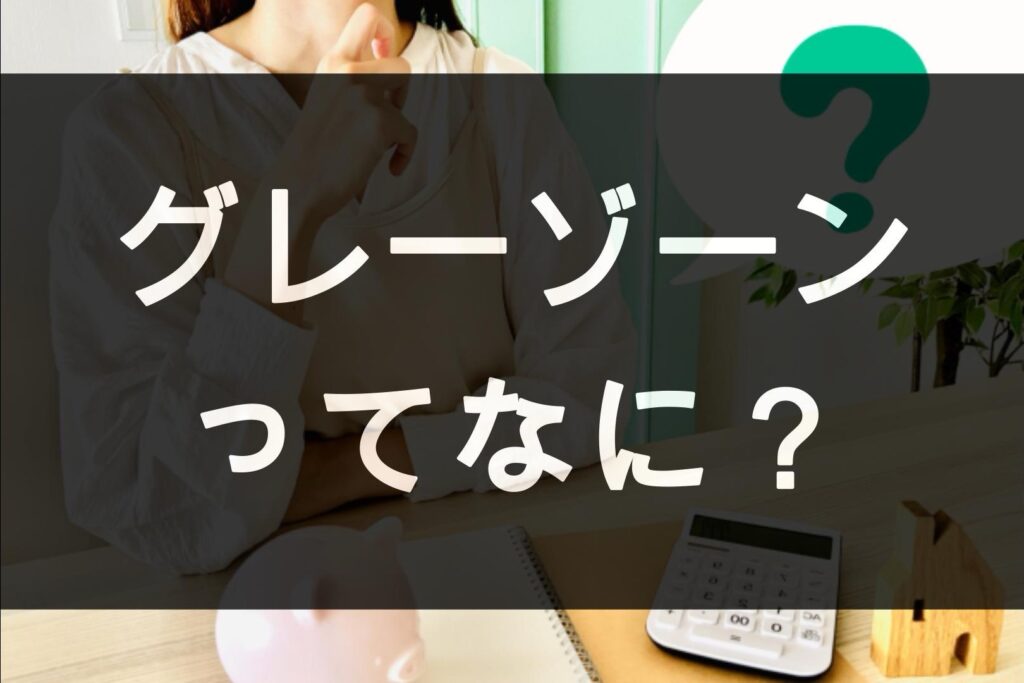
発達障害と診断されるほどではないものの、日常生活や学校・仕事で困りごとが多い状態を「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。
また、グレーゾーンはしばしば境界知能と表現され、知能指数(IQ)が70から85の範囲にある人を指していることもあります。
たとえば、
• テストでは良い点を取れるけれど、忘れ物が多く生活が乱れがち
• 人との会話はできるけれど、集団行動になると極端に疲れてしまう
• 「努力不足」と見られてしまいがちだが、実は特性の影響
といったケースです。
グレーゾーンの方は「診断がつかないから支援を受けにくい」という課題もあります。しかし、支援や配慮があれば大きく生活が改善されることも少なくありません。
誰もが過ごしやすい環境づくり
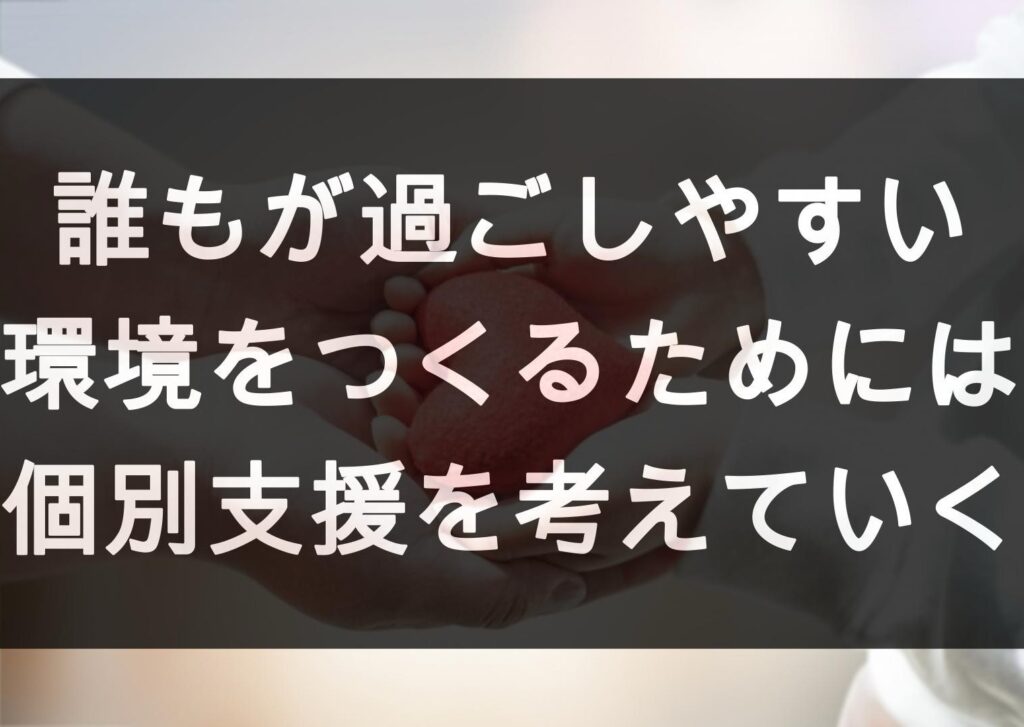
発達障害やグレーゾーンの有無にかかわらず、人はそれぞれ得意・不得意があります。大切なのは「困りごとを本人の努力不足にせず、環境の側で工夫すること」です。
• 学校では
→ 座る位置や学習方法を調整する
• 職場では
→ メモやスケジュール管理のツールを活用する
• 家庭では
→ 本人が安心できる生活リズムを一緒に整える
こうした小さな工夫が、その人の自信や可能性を大きく広げます。
まとめ
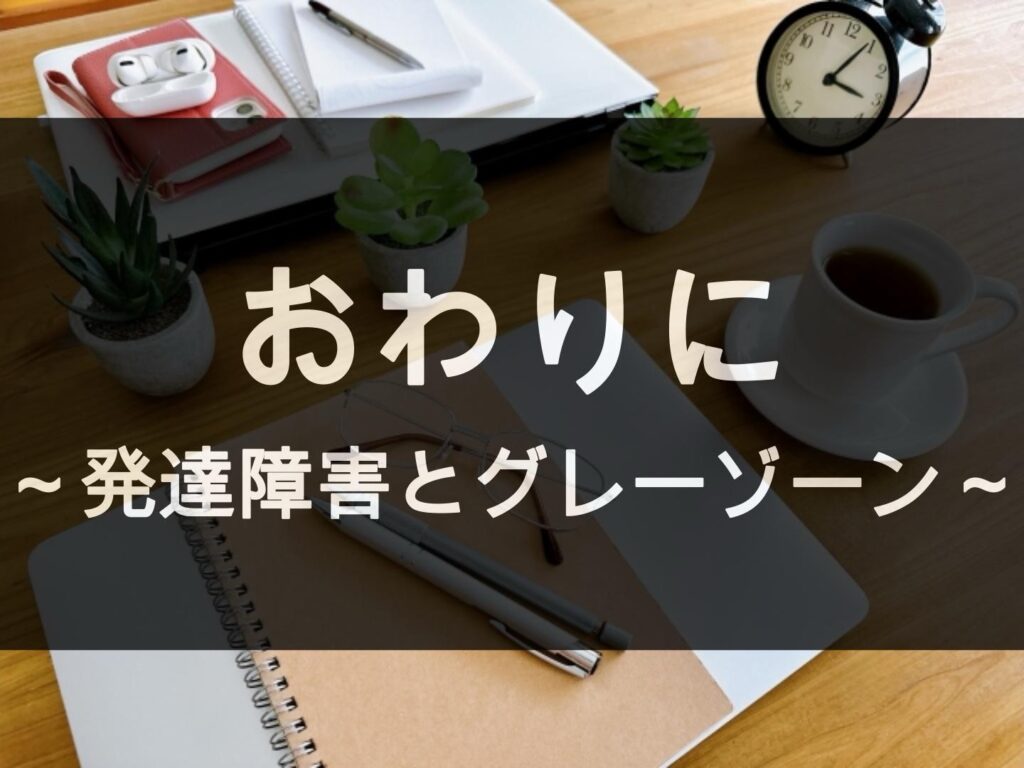
発達障害やグレーゾーンは「特別な人の問題」ではなく、多様な個性の一部です。社会全体が理解を深め、誰もが自分らしく生きられる環境を整えていくことが大切だと感じます。
一方で、ご自身の特性を障害だからと一括りにしてしまうといった後ろ向きな空気感がないとも言えません。
しかし、今回お話ししてきた内容が、単なる障害としてではなく、あくまで自他一人ひとりの特性(特徴)を知る指標として、自分や相手が大切にしている物事や世界観を知ることに繋がっていくと私は考えています。そういった指標を持つことで、思いやりや相手が困っていることの解決、そして自己理解にも繋がっていくと思います。
おまけ
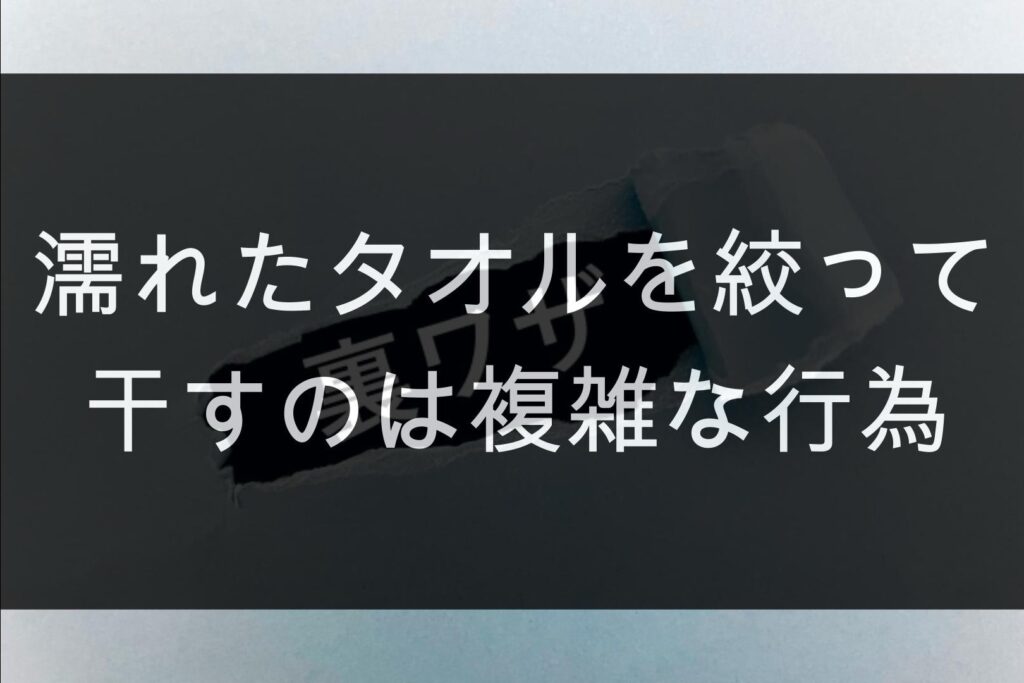
最後に、発達障害の程度を見分ける裏ワザをご紹介します。それは「濡れたタオルを絞って部屋に干す」という一連の動作から洞察できるということです。
これは一見なんの変哲もないことのように思えてしまうかもしれませんが、この一連の動作には多くの要素が複雑に絡み合っていて実はとても高度なことです。
まず、この動作を分解して捉えていきます。
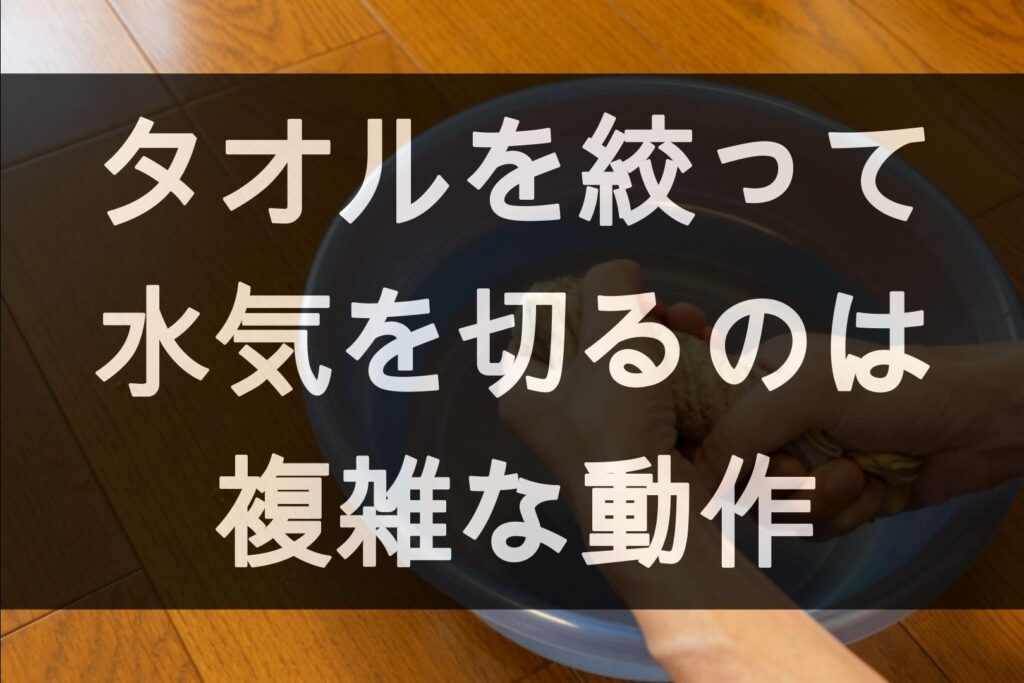
①濡れたタオルを絞って水気を取るには、左右の手指の力を複雑に使っていかなければなりません。タオルの先端の方だけ水気を切ってもダメで、全体的に水気を切っていけるよう力を使っていく必要があります。
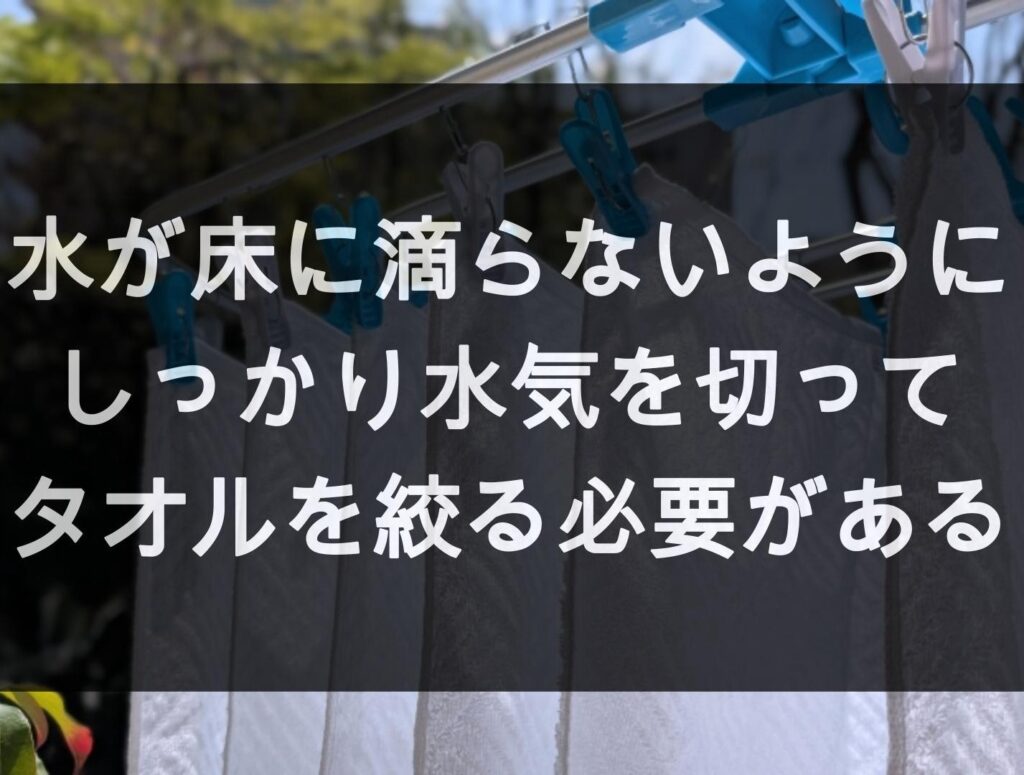
②そして、干すことを前提に水気を切っているので、干した後に水が床に滴らないよう水気の量に配慮しながら絞っていかなければなりません。
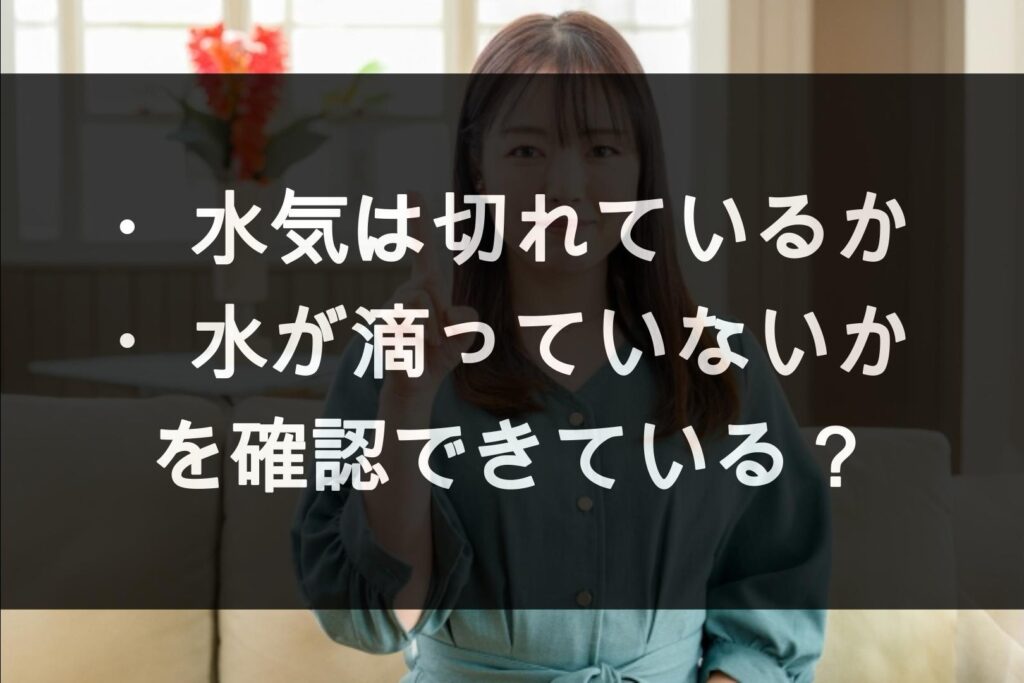
③まだ続きがあります。当事者が「確認」という行動をするかどうかが鍵です。水はタオルの下の方に流れていきますので、水気がうまく切れていなければ床を濡らしてしまいます。床に滴るかどうかも見据えて絞る必要があります。「濡れたタオルを絞って干す」という行為はここまでやって滞りなく完了です。
おわりに
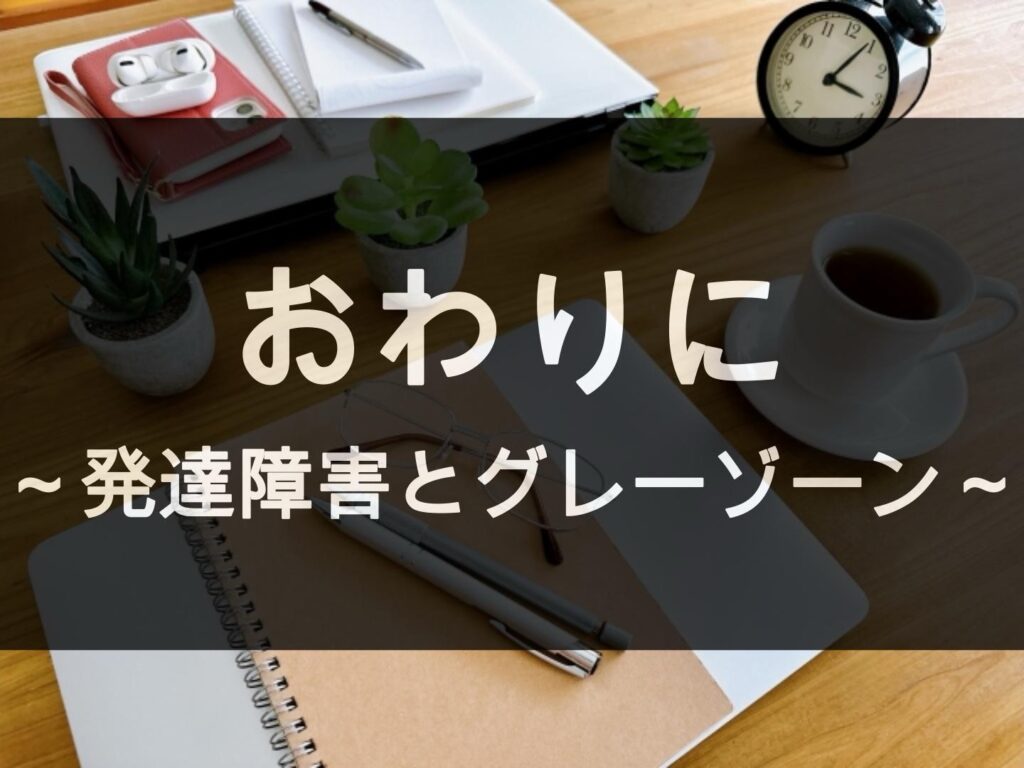
いかがだったでしょうか?
こういった日常の動作一つひとつに色んな意味合いを観察することができます。でも、出来たことや出来なかったことという目先のことが大事なのではなく、そういう背景を通じて、自他共にどう向き合えばよいのか、改善するためにはどうしたらいいのかなど広い視野で物事を考えていくことの方が大事です。
困りごとに直面している本人や家族にとっても、まずは「ひとりで抱え込まないこと」が第一歩です。学校や職場のか支援窓口、専門機関に相談することで、新しい解決の糸口が見つかるかもしれません。