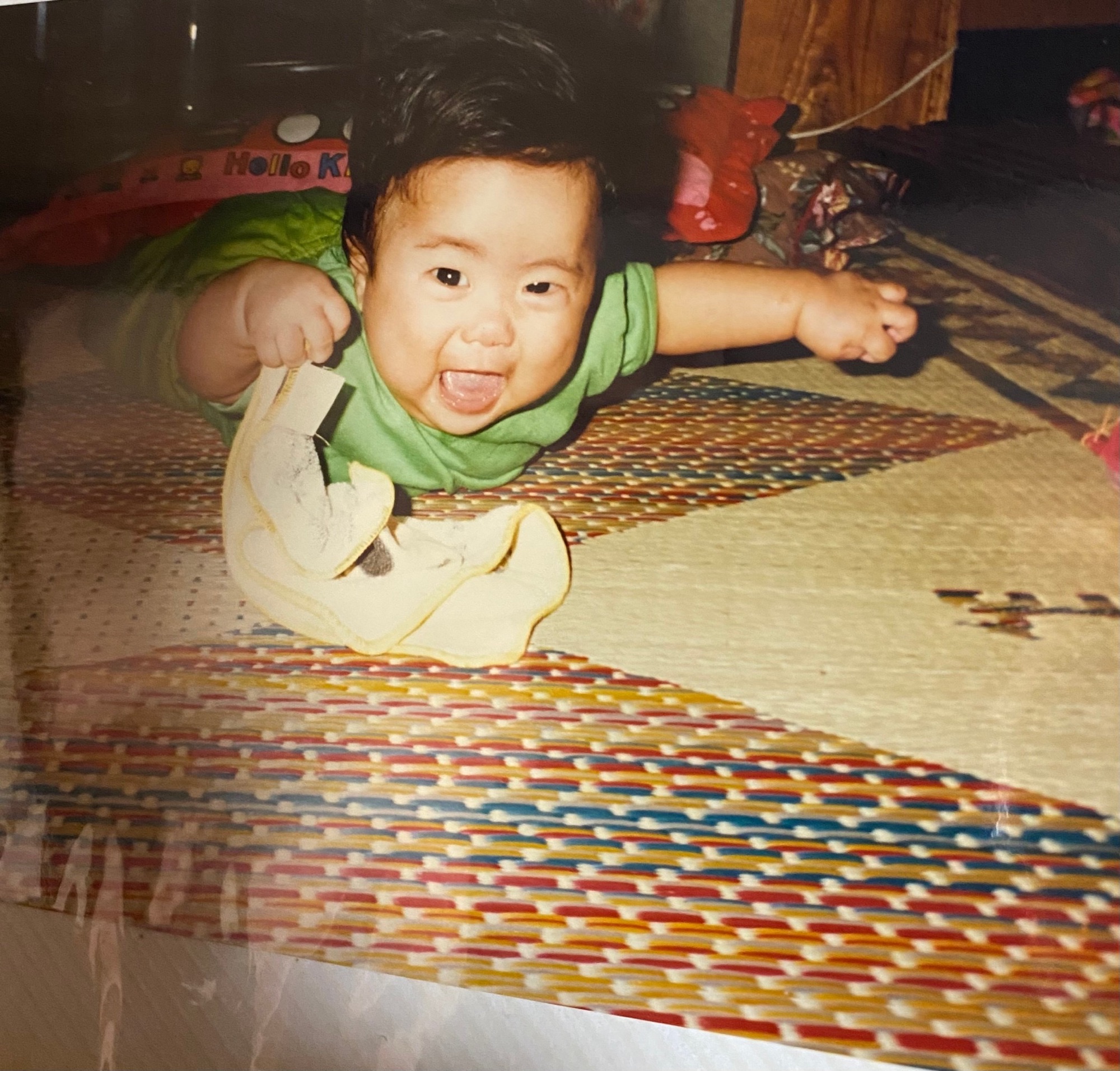はじめまして、対人援助が学べるバーチャル道場「福祉道」を運営している赤嶺圭一朗と申します。
このブログ運営の基盤にもなっていますが、私は20歳頃から10年ほど、横浜市にある社会福祉法人で福祉の仕事に従事していました。そこは、重度の肢体不自由と知的障害が重複している状態にある重症心身障害児(者)と呼ばれる方々が多く利用されています。重症心身障害児(者)の通所制度がまだ法律にない頃、この法人は全国で先駆けてそれを立ち上げたことで広く知られています。
また、私は普段は音楽家としても活動しています。実は、福祉の世界に入るきっかけはまさに音楽だったのですが、そのこともあり、私にとって福祉と音楽は切っても切り離せない強い繋がりを感じています。
今回の記事(自己紹介)は、私のルーツから現在までをお話しさせて頂ければと思います。
もくじ
生まれ 〜沖縄の地から〜

1996年2月28日、私は沖縄県(本島)で生まれました。
その前にまずは、私の父と母のルーツについてお話しさせて下さい。
父方のルーツ
父は、日本全国の中でも珍しい平仮名の地名「うるま市」の中の屋慶名(やけな)というところの出身です。屋慶名は、有名ミュージシャンのHY(=東屋慶名の略)のふるさと兼活動拠点でもあり、少し自慢なのは、知り合いの知り合いくらいには関係が近いことです。あとは、勝連城跡(かつれんじょうせき)というお城も有名です。また、父方の高祖父(ひーひーおじいちゃん)は、明治時代に屋慶名の土地を開拓・繁栄させることを役目とし、琉球王朝(首里)から派遣されて来たという話があります。高祖父が使っていたとされる三線(沖縄の三味線)が今も残っています。
母方のルーツ
母は、沖縄県最北端の伊平屋島(いへやじま)の出身です。伊平屋島には、沖縄県指定天然記念物の「念頭平松(ねんとうひらまつ)」という大きな松の木や、天の岩戸伝説の最南端とされる「クマヤ洞窟」などがあります。また、伊平屋島は、明治時代に琉球王国を統治した王家「第二尚氏」のルーツという言い伝えもあります。
父方の高祖父と、母の故郷伊平屋島にルーツがあるとされる第二尚氏の時代が明治ということもあり、「もしかしたらそこで2人は会ったことがあるのかな?」などとロマンを抱いてしまいます。
幼少期 〜福祉の世界は既にここから?〜
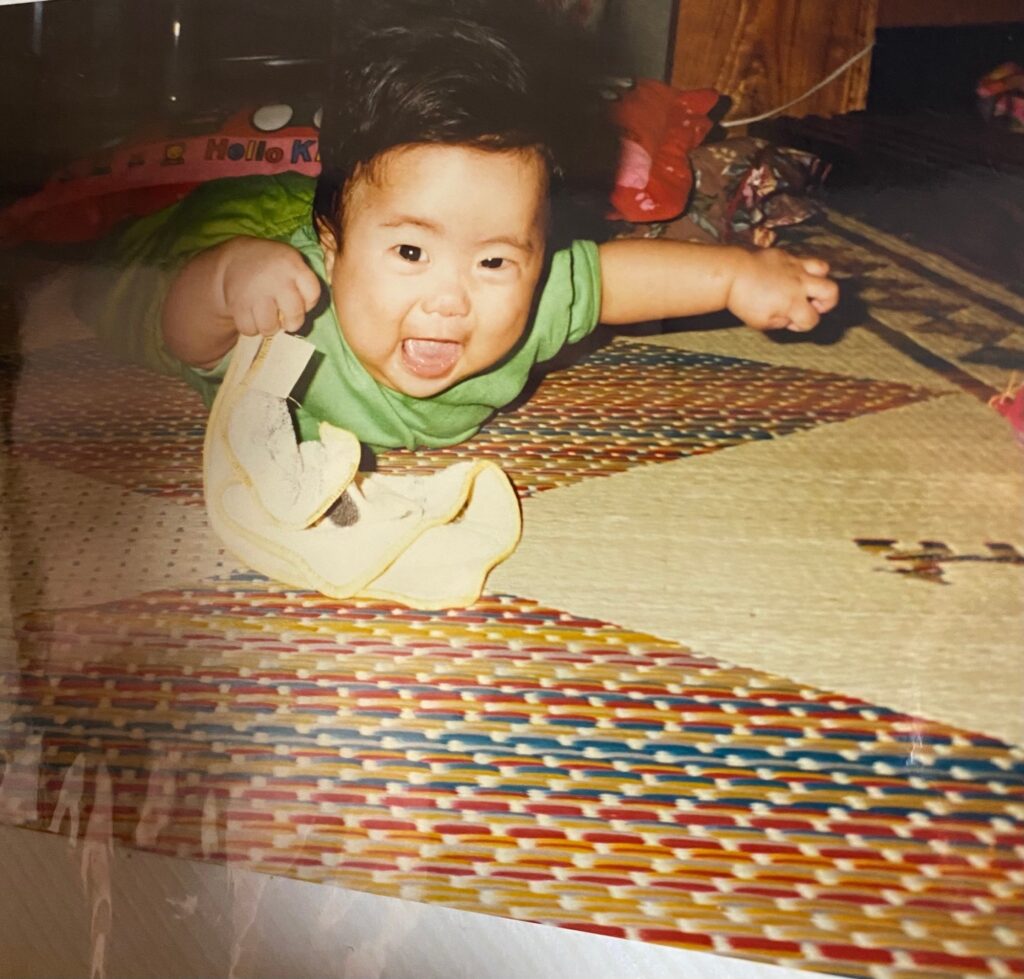
話は戻り、今度は私の生い立ちをお話ししたいと思います。
私は、1996年2月28日、沖縄県(本島)で生まれ、山内(やまうち)という土地で育ちました。山内保育園、山内幼稚園、山内小学校、山内中学校と、中学校までオール山内なのは少し自慢です。
小学生の時は書道、特に剣道とサッカーに打ち込み、サッカーは高校まで続けていました。文字通りのサッカー少年でした。
福祉とは縁遠い過ごしのように思えてしまいますが、当時を振り返ってみたり、近しい方からの話を聞いたりしていると、学校では発達障害を持っている同級生たちとも分け隔てなく遊び、また、困っている人がいたらすぐに歩み寄ろうとしていた子供だったとのことでした。意識はしていなくても、その頃から福祉への関心や理解があったのかもしれません。
高校から大学 〜哲学的に福祉を学び始める〜
高校時代
沖縄県立普天間高等学校に入学しました。普天間基地問題が昨今のニュースで取り上げられていましたが、本当に目の前に基地があり、毎日のように戦闘機やヘリコプター、そして当時話題だったオスプレイが上空を飛び回っていました。英語のリスニングのテスト中、ヘリコプターの音でテープから流れる声が全く聞こえず、仕切り直しになったのを今でも覚えています。情勢を物語っているなと感じました。
文武両道をスローガンにした高校だったこともあり、サッカーに勉強にと明け暮れていましたが、その頃より音楽に強く関心を示すようになりました。歌、ギター、バンド活動、曲作りも始めました。遊びに勉強に習い事にと、忙しくもありがたい経験を得られました。
大学時代

高校卒業後は、両親はじめ多くの方々の協力のもとで上京しました。東京都にある大学に入学し、文学部で一年次より哲学を専攻していました。大学のゼミでは生命倫理という生命の生き死にを深く考える分野を研究していました。その中で、国家指定難病にもなっているALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者さんや、重い身体障害と知的障害が重複した状態にある重症心身障害児(者)の方々と接し、福祉領域を哲学的な視点から深く考える機会となりました。
課題活動としては、学内ではクラシックギターアンサンブル部に入部し、真面目にギターとクラシックを学んでいました。学外では、バンド活動やソロでの弾き語り、曲作りなどと、音楽にどっぷり浸かっていました。
福祉施設にボランティアで行き始める

そんな中、大学3年生の時に、大学の教授から横浜にある福祉施設(のちに私が働くことになった施設)に「ギター演奏のボランティアに来てくれないか?」とのお誘いがあり、まずは施設の見学に行ってみることにしました。そこは、重度の肢体不自由と知的障害が重複している重症心身障害児(者)と呼ばれる状態にある方々が通所されている生活介護事業所でした。
見学の際、音楽プログラムを行っているところで、そこで私は少しだけギターを弾きました。そのとき、利用者さんが真剣にこちらを見たり、笑顔を見せてくださったことが強く心に残りました。
その後、施設の音楽活動に関わり、利用者さんや職員、地域の人々とともに結成したバンドでステージに立ち、パフォーマンスする機会もありました。
私は、それまで自分の音楽を自己表現のために用いることが多かったのですが、人に喜んでもらえる形で音楽を届けることに新たな意味を見いだしました。これが原体験となり、福祉の仕事を意識する大きなきっかけとなりました。
※大学時代に学んでいたことについて書いた論文もこちらに載せています。尚、プライバシーを守る観点から個人や大学、施設、地域、日付などは全て除外しておりますので、その点はご理解ください。
本格的に福祉の世界へ
アルバイト

そのような中でご縁を頂き、大学4年生の時に、そこでアルバイトを始めるようになりました。大学内では哲学を学び、生命倫理、障害、人の尊厳、意思決定、権利などについて深く考えていました。
当時の私は進路について迷っており、音楽を続けたいという思いが強く、就職を積極的に考えることができていませんでした。しかし、ボランティアやアルバイトを重ねる中で、この仕事なら今後もやってみたいと感じるようになりました。
就職

そのような経験を経て、そこに就職しました。仕事内容は、利用者さんの歩行や食事、移乗、トイレなどの介助に加え、日常生活の支援や関係機関との連携など多岐にわたります。
特に大切(やりがい)だと感じるのは、利用者さんが「何に喜びを感じているのか」「どのように暮らしていきたいのか」といった人生に寄り添うことです。長く関わる中で、最期に寄り添う経験することもありますが、それもまた「人生に寄り添う」ことの一部だと実感しています。
おわりに

福祉の仕事に従事していた中で、重度の知的障害ゆえに行動障害を伴う方々の支援に携わる機会が多くありました。行動障害は、その特性ゆえに、周囲から誤解されやすく虐待に繋がる可能性もあるため、現場で多くのことを感じ、考え、学ぶことが出来ました。
福祉に繋がりそうな資格と言えば、大学卒業と業務内で取得した重度訪問介護のみですが、大学で学んだ哲学的に物事を深く考察するスキルは現場の中ではとても活かすことが出来ました。なのでこの度は、そこで培った支援の知識とノウハウを、そして、成功体験から失敗体験までを、独自の視点で分かりやすくお伝え出来ればと思います!