ようこそ、対人援助が学べるバーチャル道場「福祉道」へ!
私は重症心身障害児(者)と呼ばれる重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している状態にある方々の支援に約10年間携わっていました。成功体験から失敗体験まで、そこで得た支援の知識とノウハウを独自の視点を交えて分かりやすくお伝え出来ればと思います。
詳しい自己紹介はこちらの記事に書きましたので合わせて読んで頂ければと思います!
また、ブログの概要はこちらの記事にまとめています。
今回は福祉道の心得についてお話しさせて頂きます。心得は以下の3つです。

以上の3つの心得について順番に概要をお話ししていきます。
①対人援助職である
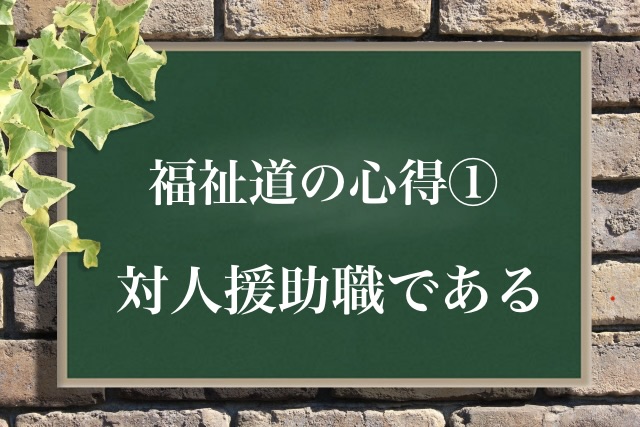
まず、福祉の仕事は対人援助職と呼ばれています。
対人援助職とは、福祉をはじめ医療や教育などの分野において人を支えている専門職のことです。具体的な仕事としては、介護士、社会福祉士、看護師、医師、保育士、教師、ソーシャルワーカー、カウンセラーなどが挙げられます。
また、社会基盤としてインフラという言葉がありますが、対人援助職は人間の生活を支えるインフラとも表現できます。
私が働いていた職場での研修では「福祉職は対人援助の専門職である」という言葉がよく出てきました。これは介護福祉士や社会福祉士など何か特定の資格を持ってはじめて専門職となるというものではなく、一人の人間や物事に対して看護師や医師などの様々な関係機関と連携(コミュニケーション)を図りながら所感や見立てを挙げていくという姿勢が求められています。この多角的な視点を持つことで物事を立体的に捉え、洞察力(正確性)を高めていくことに繋がっていきます。
※対人援助職についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
②エッセンシャルワーカーである

エッセンシャルワーカーという言葉に聞き馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんが、この言葉は新型コロナウイルスが世界的に流行している最中、感染リスクを負いながら現場で働く人たちに対してよく使われていました。
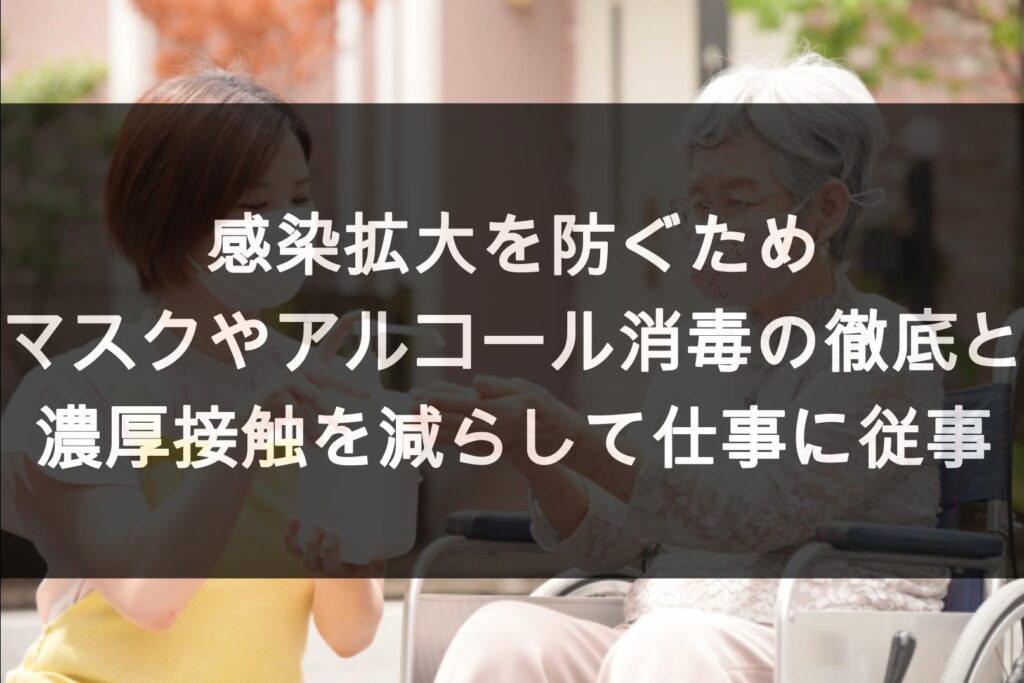
エッセンシャルワーカーは、福祉をはじめ医療や運送など日常生活を維持するうえで必要不可欠な仕事であり、対人援助職と同じく人間の生活を支えるインフラと表現できます。
2020年からの数年間は新型コロナウイルスが流行している状況ではありましたが、私自身もそのような仕事をしていましたので、感染対策をとって免疫力を維持しながら、2021年の緊急事態宣言の際も普段と変わらず電車で通勤をしていました。
私の職場は横浜市内にありました。いつもは駅のホームに学生やサラリーマンなどが行き交い、まさしく通勤ラッシュといった状況ではありました。
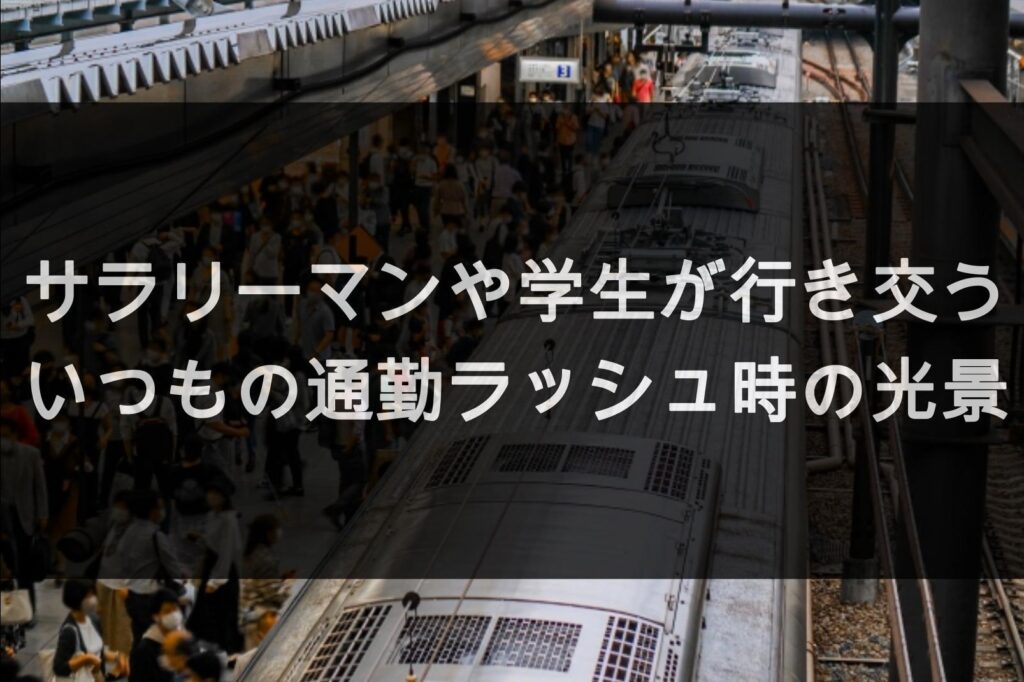
しかし、緊急事態宣言が出ている期間中は駅のホームも電車もガラガラで、まるで自分だけ違う世界に取り残されてしまったような虚無感がありました。
ですが、振り返ってみると、利用者さんやご家族、同じ職場で働くスタッフらをはじめ、自分のやっていることが社会から求められているという使命感もあいまって、社会との繋がりを意識することができ孤立せずにいることが出来たのだなと感じます。
エッセンシャルワーカーは、マクロで見ると社会機能を維持させる仕事で、ミクロで見ると人間活動を維持させるために必要不可欠な最前線の仕事です。人に向き合う仕事だからこそ私はそこに人間力が求められていくと考えています。
※エッセンシャルワーカーについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
③心技体の備わった人間力が大切である
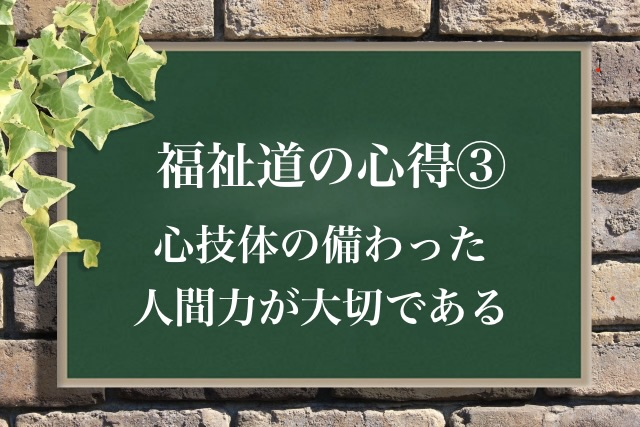
では、その人間力とは何かというと心技体の備わりといえます。
武道やスポーツなどで心技体という言葉を耳にするかと思います。心技体とは心、技、体の3つの要素を指し、何か特定の物事を成す時にそれぞれの要素を最大限引き出していくと、より良いパフォーマンスに繋がるという考え方です。
自己紹介の記事でも触れさせて頂きましたが、私は小学生の時は書道、剣道、サッカーに打ち込み、サッカーは高校2年の終わり頃まで続けていました。特に剣道では、剣道に向き合うための心意気、技(型)の練習、試合で相手に負けないための体作りといった点で心技体の考え方をたくさん学びました。
そして、これは福祉職においても同様だと考えます。相手に向き合うための心のマネジメント、多角的な視点で支援するために必要な知識(技)、介助をするための体の使い方といった点で現場では心技体の考え方が求められていました。
そのため私は、武道やスポーツなどと同様に、福祉職もこの心技体を整えた状態で臨んでいくことが求められる仕事だと考えています。
※心技体についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
おわりに

いかがだったでしょうか?
今回は福祉道の3つの心得についての概要をお話ししてきました。
福祉の現場で働く私たちは、常に「人」と向き合い続ける対人援助職であり、社会を支えるエッセンシャルワーカーでもあります。そして、その基盤となるのが心技体(心・技・体)を備えた人間力です。これら3つの心得を意識して取り組むことで、支援の質を高めるだけでなく、自分自身の成長ややりがいにもつながっていきます。
「福祉道」は、まさに日々の実践を通じて磨き続ける道です。これからの記事では、それぞれの心得をさらに深め、現場や日常生活に役立つヒントをお伝えしていきますので、ぜひ一緒に歩んでいきましょう。
次回は福祉道の心得の1つ目「対人援助職である」について深掘ってお話ししていきます。日常生活においても応用出来ますのでぜひお試しあれ!

